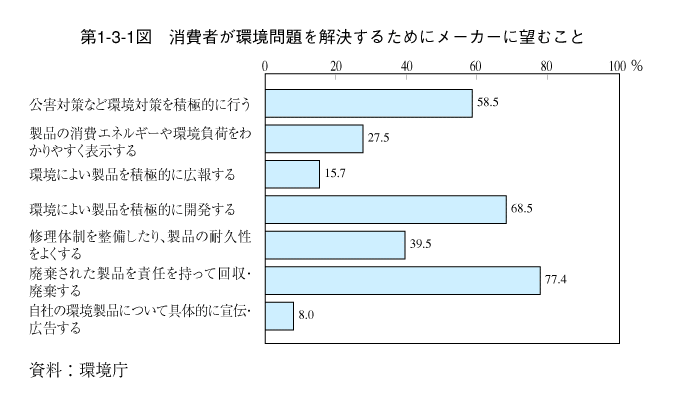
1 環境効率性の考え方
環境効率性とは、財やサービスの生産に伴って発生する環境への負荷に関わる概念であり、同じ機能・役割を果たす財やサービスの生産を比べた場合に、それに伴って発生する環境への負荷が小さければ、それだけ環境効率性が高いということとなる。このコンセプトは、1992年(平成4年)に設立された「持続可能な開発のための経済人会議」(BCSD)の宣言の中で生まれたものである。
こうした考え方は、持続可能な社会を実現するためには経済効率に偏重する現在の経済社会システムから、環境への配慮を織り込んだシステム、すなわち、財・サービスを生産・消費する際に環境への負荷を最大限削減するようにするというシステムへの変革が必要であるとの考え方から生まれている。
現在大きな問題となっている廃棄物問題を始めとする都市・生活型の環境問題は、これまでの経済社会システムでは、人間が環境への負荷による社会的コストを市場メカニズムに織り込むことなく、過剰にエネルギーや資源を消費し、廃棄物等の環境負荷を排出してきたことが原因の一つとなっている。
市場経済においては、財・サービスの提供者はできるだけコストを下げ、低廉な価格でより優秀な製品を作ることで競争に打ち勝たなくてはならない。市場における競争を通じて、社会全体として資源が効率的に使われ、最適な資源配分がもたらされるというのが、市場メカニズムの原理である。
財・サービスの原材料となる資源の採取の場、また汚染物質や廃棄物の排出の場としての大気、水、自然等の環境の使用への対価は、これまでは規制等によらなければ、特に支払われてこなかったが、何らかの形でその費用が社会的コストとして織り込まれれば、市場経済に環境汚染という外部不経済を削減していくインセンティブが働き、環境という資源を含めた形で、各種の資源が市場を通じて効率的に配分されていくことが可能になる。
そのためには、こうした資源は決して無尽蔵に存在するものではなく限りあるものであり、さらにそれらの使用に伴い、環境に負荷を与えるということを認識し、環境の使用という社会的コストを内部化することで、環境に配慮した持続可能な経済社会システムを構築することが必要である。環境負荷による社会的コストが適切に内部化されれば、財・サービスの生産・消費に伴って発生する環境への負荷をできるだけ削減することが、経済的なメリットに結びつくため、市場メカニズムを通じて、環境への負荷が削減されることとなる。
環境負荷による社会的コストが経済活動に内部化されるようになった例として、我が国がかつて経験した激甚な産業公害に対する規制によるものが挙げられる。このとき、企業は環境規制の強化に対応するために、技術開発とそれを応用する汚染防止装置への投資を行うというかたちで環境負荷による社会的コストを内部化し、産業公害を克服してきた。また、我が国が世界の国々の中でも早期に厳しい自動車排出ガス規制等を実施してきたことが、結果的に自動車の技術開発を大きく促進したことはよく知られているところである。そしてこのようなメリットに加えて、こうした環境規制に伴う環境負荷による社会的コストの内部化がマクロ経済に与えた影響については、長期的な経済成長の足枷にはならなかったことがOECDの日本の環境対策レビュー等によって示されている。ともすれば、環境と経済がトレードオフの関係にあるように考えられがちであるが、こうした考え方は、これまで我が国が歩んできた道を振り返ってみる時、必ずしも当てはまっているとは言えないことが理解できる。
国立環境研究所が行った「地球環境問題をめぐる消費者の意識と行動が企業戦略に及ぼす影響《消費者編》」のアンケート結果によれば、消費者は、企業が廃棄された製品を責任を持って回収・処分すること、環境によい製品を積極的に開発することを望んでおり(第1-3-1図)、また、企業が環境に配慮した行動をとるために、消費者が、環境に配慮している企業の製品や環境に配慮している店を選ぶことが有効だと認識している。今や企業は環境への配慮をした事業活動を行っていかなければ、消費者の支持を得られず、市場にとどまることが許されなくなってきているのである。こうした点からも、事業者は環境に配慮した事業活動、言い換えれば環境負荷による社会的コストを含めた「トータル・コスト」を効率的に削減し、環境負荷を最小化していく活動を行っていく必要があることが分かる。
例えば製造段階で環境に負荷を与える物質の排出量を少なくする装置に変えたり、使用物質の少ない設計を導入したりすることは、初期投資は必要となるが、経常的には投入する資源量を削減できるので、ランニングコストを削減できる。
前節までに見てきたように、循環型の経済社会システムを実現していくためには、静脈部分のみならず、財・サービスのための原料採取段階、生産段階にあるいわゆる動脈部分においても、この環境効率性の高い活動を行っていく必要がある。
動脈部分における環境効率性向上のための取組は、大きく二つに分類することができる。取組の一つは、製品の製造、使用、廃棄等のライフサイクルの各段階における環境負荷を低減させる取組である。こうした取組について製品のライフサイクルに沿って考えてみると、製品はそれぞれが原材料採掘・投入−製造−使用・消費−廃棄・リサイクルというプロセスを持ち、それぞれの段階で何がしかの環境負荷が発生している。したがって、各段階それぞれにおいて、またライフサイクル全体において、なるべく環境へ負荷を与えないように配慮していくことが期待される。経済社会システム全体でこうした活動を実現していくため、各段階ごとに具体的には、
? 投入する資源、エネルギーをなるべく少なくする
・ すべての原材料の在庫状況、使用状況の把握の徹底等
? 環境中に排出される環境負荷物質をなるべく少なくする
・ 無害の、より有害性の少ない原材料の使用、購入
・ 廃棄物の排出のない、少ない設備の導入 等
? 使用段階、廃棄段階における環境負荷をなるべく少なくする製品設計
・ 使用原材料の種類の少数化
・ 有害な原材料から無害なものへの代替 等
? 廃棄物の再資源化と生産段階における再生物の利用
・ 回収、再使用を容易にするための廃棄物の種別ごとの区分管理 等
といったことを念頭におきながら取り組んでいく必要がある
企業が通常の事業活動の中の各段階において、?〜?に挙げたような行動を織り込んで、環境効率性の高い経営を効果的に実践していくには、従来、事業活動の中で利用していた慣行や手法を環境に配慮したものに変えたり、環境への配慮を行った形で活用したりすることが重要となってくる。本節では、このようなライフサイクルの各段階において、環境効率性を高めるための取組を進めていく上で、助けとなると考えられる様々な手法について触れていくこととする。
もう一つの取組としては、同一の効用を実現するために財・サービスの提供方法を見直す取組がある。こうした取組の例としては、自動車などのリース業がある。消費者が求める「自動車による移動」というサービスのみをリースという販売方式で提供することで、同じ車を何人かの利用者が共有することで「自動車による移動」というニーズは満たしながら自動車の製造のために投入される資源を削減することが可能となるので、本体を売り切りするよりも環境負荷を低減することが可能となる。また、経済のサービス化により、経済活動に悪影響を与えずに環境負荷の削減が進められることが期待できよう。このようにニーズの実現をサービスの提供によって行うことで、環境効率性の向上が実現できるようにもなるのである。