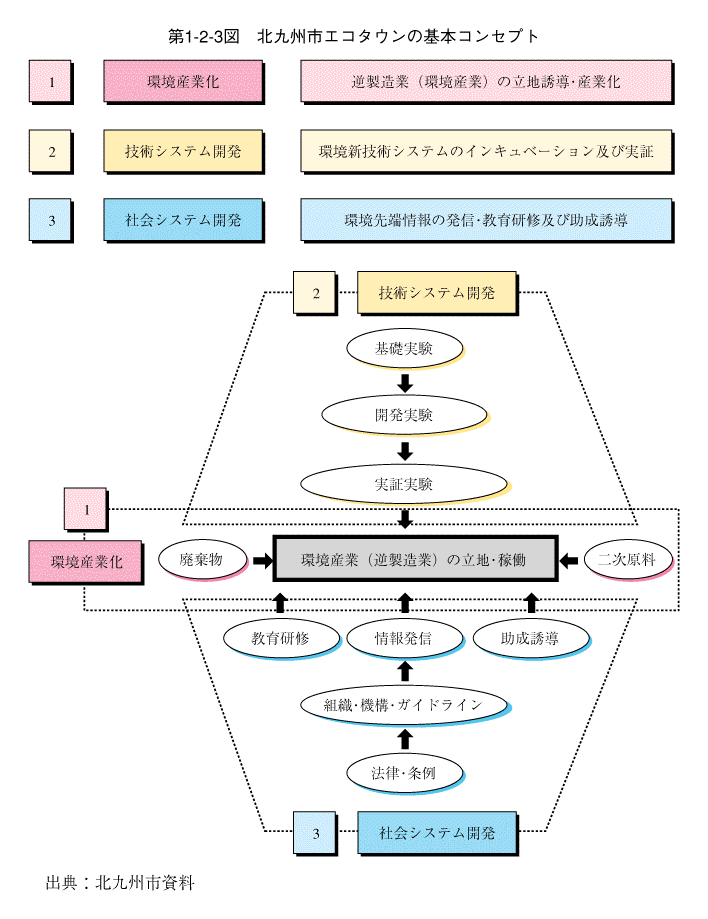
2 循環型産業システムのモデル提示−北九州市の取組−
(1) 循環型産業システム
ゼロエミッションを目指し、循環型経済社会を構築していくためには、廃棄物・リサイクル対策の新たな展開として、動脈産業に多くの力が注がれ、静脈産業にはあまり日を当てずにいた、今までの産業システムを、廃棄物処理・リサイクル産業の健全な組込によって動脈産業と静脈産業が適切な循環の輪において結合し一体化した新たな循環型の経済・産業システムへ転換していく必要がある。
そのためには、まず静脈部分の産業としての確立や健全な育成が必要となる。高度な技術に支えられた静脈産業は、動脈産業とも対等関係になり、処理・リサイクルコストや製品の設計開発、さらには再生物の利用等の面で動脈産業への提言も可能となるなど、動脈産業と静脈産業との間の適切な連携への道を開いていくと考えられる。
また、静脈産業における再生物の生産供給機能の強化を図り、従来の廃棄物処理業を再生物製造業に転換していくことは、廃棄物処理に対する国民のイメージを変えていく大きな一歩ともなり得る。
循環型経済社会を目指して、「生産・消費・廃棄」の一方通行型の経済・産業のシステムを転換していくためには、循環の輪をつくり・つなぎ・太くしていくことにより、廃棄物を再生資源として有効利用することを通じて、最終処分に係る環境負荷を低減するとともに、天然資源採取による環境負荷を適切に低減していくことが必要となる。
緒についたばかりの我が国におけるこの循環型経済社会へ転換の取組に対しモデルともなり、先駆的に転換を引っ張っていくような動きが、北九州市で展開され始めている。
(2) 環境産業都市づくりに向けた動き
北九州市は、工業都市として製鉄業をはじめとした重厚長大産業が次々に立地し繁栄してきた。と同時に、工業都市が抱える宿命として、いわゆる産業公害問題も深刻化し、昭和30年代から40年代にかけては、工場の煙突から放出される煙には様々な有害物質が含まれ「七色の煙」と呼ばれ、洞海湾は「死の海」と化していった。
このため、北九州市では、最大の行政課題の一つとして産業公害の克服に取り組み、この過程を通じて環境保全に必要な技術やノウハウが行政や地元企業に蓄積されていった。また、環境問題に対する研究体制の整備も着実に進められていった。
北九州市では、これらの基盤を活かし、「重厚長大産業都市」から「環境産業都市」に脱皮し、循環型経済社会づくりのモデルを全国に向けて提示するために、「環境産業振興のための技術開発、実証研究」を中心に、「教育・基礎研究基盤整備」と「環境国際協力の推進」を合わせた総合的な施策を展開し、地域の産業構造の資源循環型へのダイナミックな転換を目指している。
この北九州市のリサイクル産業を中心とした環境産業の拠点の構築による環境産業都市づくりの構想が、ゼロエミッション構想推進のために平成9年度に創設された通商産業省の「エコタウン事業」を受けて、北九州市における「エコタウンプラン」として平成9年7月に承認され、このプランに基づく施策等が着々と実施に移されつつある。
囲み1-2-2 エコタウン事業
通商産業省は、既存の処理施設・処分場の許容範囲を超えて年々増加し続ける廃棄物への対応策として、これまでコンセプトとして提唱されてきた「ゼロエミッション構想」を実際の地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想として位置付け、地域振興の機軸として推進することにより、既存の枠にとらわれない先進的な環境調和型まちづくりを支援するため、平成9年度より「エコタウン事業」を開始した。
この事業の目的は、個々の地域におけるこれまでの産業蓄積を活かした環境産業の振興を通じた地域振興、及び地域における資源循環型社会の構築を目指した産業、公共部門、消費者を含めた総合的な環境調和型システムの構築にある。
そのため、地方公共団体が推進計画(エコタウンプラン)を作成し同省の承認を受けた場合に、民間等の建設するリサイクル関連施設への助成や、環境産業見本市・技術展への助成、住民等に対する環境関連情報提供事業への助成などの中から、それぞれの地域の特性に応じて、総合的・多面的な支援を実施することとしている。
平成9年度は、長野県飯田市、川崎市、北九州市、岐阜県の推進計画が承認された。
(3) 北九州市のエコタウンプランを踏まえた取組及び今後の方向
北九州市は、環境産業都市づくりの取組を推進していく上での基本的なコンセプト(第1-2-3図)として、次の3点を掲げている。
第1は、「環境産業化」、すなわち、環境産業の立地の促進・誘導及び静脈産業の健全で成熟した産業としての確立である。
第2は、環境に関する新技術の開発とその実証を行う「技術システムの開発」である。
第3は、環境産業に関する先端情報の発信や啓発、支援などを通じてリサイクルシステムの創出を目指す「社会システム開発」である。
これらのコンセプトに基づく施策を展開する上で、環境産業の集積拠点を構築していく場として、市の北西部に位置する「響灘地区」の約2,000haに及ぶ臨海埋立地を活用することとしている。ここは、港湾に隣接し今後国際物流港の整備が図られることとなっているほか構内鉄道線など物流のための施設が充実し、船舶や鉄道による大量輸送が可能であるとともに、今後のアジアに向けた資源物流の国際展開にも対応できるといった特徴を持っている。また、この周辺部には、もともと鉄鋼業などの既存産業が集積しており、そこで蓄積された技術等を活かすことや豊富な水等の確保が可能であること、廃棄物の最終処分場が存在することといった利点もある。
この北九州市の取組の特色は、?環境産業・技術開発・実証研究拠点の整備を中核として、?教育・基礎研究基盤の整備、?環境国際協力の推進を併せて行っていくという、市民等の社会的受容性にも配慮した総合的な施策の展開にあるといえる。それぞれの事業内容は次のとおりである。
環境産業・技術開発・実証研究拠点の整備としては、「総合環境コンビナート」及び「実証研究センター」の構築を図ることとしている。
総合環境コンビナートでは、ペットボトルや自動車、家電等のリサイクル施設の集積を予定している。立地する施設は高度な技術に基づく高いリサイクル率を有するとともに、各施設が有機的に連携し廃棄物ゼロを目指し、コンビナート事業全体の最適化を追求する場としている。
実証研究センターは、環境技術に関する実証研究施設の集積拠点として、技術情報の発信、環境技術の展示機能、国内外の人材育成のための教育、研修機能を整備するものである。
さらに、環境事業団と連携して、市内の自動車解体業者や廃棄物処理業者が保有するこれまでの経験や蓄積等に基づく環境技術を活かしていくための「中小企業向けのリサイクル団地」や、建設廃材を対象とした「建設リサイクル団地」の設置も検討されている。
教育・基礎研究基盤の整備としては、基礎研究基盤や、人材育成・教育基盤の整備を図ることとしている。これは市内に建設が予定されている北九州学術・研究都市との連携などが考えられている。
環境国際協力の推進としては、北九州市が行っている環境国際協力を、従来の研修中心のものから、総合環境コンビナートや実証研究センターを積極的に活用したより実用的実践的な協力事業として発展させるための体制整備などを行うこととしている。
現在は、エコタウンプランを踏まえた施策事業の中核として、総合環境コンビナートの構築や実証研究センター構想の具体化が進められている。
ア 総合環境コンビナート
総合環境コンビナートは、九州全域や中国・四国地方までも含む広域地域を対象として想定し、ペットボトル、廃自動車、廃家電・OA機器、廃プラスチック、シュレッダーダストなどの適正な高度処理・リサイクルを行う環境産業を有機的に結びつけ、リサイクル率の向上はもとより、最終的にはゼロエミッションの産業システムの構築を目指すものである。
そのため、立地する施設は高度な適正処理・リサイクル技術を組み込んだものとしていくこととしている。また、収集運搬には陸上自動車輸送を極力減らし響灘地区の条件を活かした船舶や鉄道等の大量輸送機関の活用による広域的な物流システムを組み込んだ総合リサイクル事業の展開が考えられている。総合環境コンビナートのイメージは第1-2-4図のとおりで、既に構想への積極的な参加の意向を表明している企業等による調査研究も多数行われている。
総合環境コンビナートの最初のプロジェクトとして、平成9年4月に設立された(株)西日本ペットボトルリサイクル(第3セクター)が、平成10年度から操業を開始することとしている。
これは、容器包装リサイクル法を受けペットボトルの再商品化に対応する事業で、当初は4,000t/年の規模で実施されるが、最終的には北九州市はもとより九州全域、中国・四国地方までを対象範囲として営業を拡大し、8,000t/年の規模を目指している。
また、家電メーカー数社が総合環境コンビナート内で「廃家電リサイクル施設」の共同設置に向けた研究会を設立し、この施設ではコピー機などのOA機器のリサイクルもその対象とすることが検討されている。
その他にも廃自動車や、廃プラスチックのリサイクルなども関係企業等の間で連携を図りつつ検討が進められている。
これらの各事業におけるリサイクルに向かないものやシュレッダーダストなどを破砕選別、燃焼、溶融、熱回収・発電等により、適正処理・リサイクルし、コンビナート内のゼロエミッションを可能にする複合機能処理リサイクル施設の設置を検討しており、これを総合環境コンビナートにおける複合中核施設と位置付けている。
この複合中核施設は、個々のリサイクル施設単体では事業化を図れないものの受け皿機能を持つものでもある。さらに、この施設では燃焼時の熱利用やスーパー発電の併用を進めるとともに、焼却灰等の溶融後の溶融固化物を路盤材等の建設資材として活用していく計画も検討されている。
総合環境コンビナートは、廃棄物や再生資源を原料にして再生物を製造し販売するものであることから、それが事業として成立するためには、再生物の需要や市場の確保が課題となる。しかし、再生物は、初期段階から十分な需要を見込むことは容易でないため、当初はハイリスクに耐え得る大企業や優良企業の参入が必要である。北九州市におけるこの事業の場合、地元の大手企業が、当初からプロジェクトに参画し、そのことによって異業種の参加各企業間の有効かつ適切な連携が図られてきている。ペットボトルリサイクル事業においても、製鉄メーカー、総合商社、物流企業などの参画により、広域的な事業展開が検討されている。また、北九州市自らも、再生物の流通ルートや市場の確立に資することを目指し、職員の作業服にぺットボトル再生繊維を使用したものを積極的に採用することとしているほか、公共工事においても再生建設資材等を利用していくことを検討している。
イ 実証研究センター
実証研究センターでは、廃棄物の処理・リサイクル技術の有用性や安全性の確認、再生物化の実験や安全性の確認などの調査研究を行うこととしている。これらは、相互に密接に関連することから、センターでは、実証研究施設を集中し、広く共同利用できる研究・研修施設や情報処理施設を併設したものにしていくこととしている。
ここでは、環境産業に関する技術情報の発信や環境技術の実証研究・研修による国内外の人材育成を積極的に行うため、平成9年度文部省の「学術フロンティア推進事業」として選ばれた福岡大学の「資源循環・環境制御システム研究所」が実証研究センターの中核施設として既に建設され平成10年3月から研究がスタートしている。これは、廃棄物のリサイクルや埋立を中心とする安全処理システムに関する総合研究機関として、焼却灰から重金属を資源として回収する技術の研究開発やプラスチックのガス化・固体燃料技術の研究開発、最終処分場からの浸出水に関する調査研究などが予定されている。
また、隣接地では、民間企業によって、一般廃棄物の焼却灰を薬品処理によって重金属等が溶出しないように安定化させ、道路の下層路盤材として環境保全に配慮しつつ有効利用するための実証研究が行われている。その他にも、廃プラスチックのリサイクル実証施設、最終処分場の上部を屋根で覆ったクローズド型最終処分場の実証研究、最終処分場の遮水シートに関する実証研究などの参画が現在検討されており、今後は資源循環実証研究拠点として重要な役割を担うことが期待されている。
(4) 産学官連携による取組
北九州市が目指す環境産業都市の構築に向けた取組には、産業界、研究機関及び行政の適切な連携が必要不可欠である。
前節で述べた最終処分の規制強化など廃棄物処理・リサイクルをめぐる近年の新たな進展により、これまで埋立処分されていた廃棄物についても、処理コスト等の面からも高度処理による減量やリサイクルの組込を活発化させ、その最終処分量を削減させていく方向にあるといえる。こうした流れは、新たな環境保全の産業化の芽ともいえるものであり、この動きを事業化するためには、種々の実証研究の成果などを基にした環境政策の方向付けが重要な支援になると考えられる。このような行政施策等の積極的な展開により新たなビジネスチャンスを活かし定着させていくためには、地域内外の産業界の協力参画等により地域の産業構造をつくり変えていくことも必要になる。北九州市の取組においては、産学官の連携協力及び各種産業間の連携の下に循環型の産業システムの構築を図るとともに、環境産業の振興の拠点づくりやそれを梃子にした地域の産業構造の変革なども合せて、循環型経済社会の実現に向けた先駆けとなっていこうとしているといえる。
(5) 環境産業の推進に向けた視点
静脈産業を、資源としての再生物を生産する産業として位置付け、優良な民間企業により高度な技術を組み込み、地場産業とも連携して地域社会を経済的にも環境的にも良好なシステムに導くような環境産業として発展させることは、環境産業による地域振興につながるものである。
このような環境産業を創出し推進していくためには、以下の4つの視点が重要であるとされているが、北九州市の取組はこれらの視点を組み込んだものになっているといえる。
ア 広域性
現在は、他地域からの廃棄物や再生資源の持ち込みを拒否する地方自治体が多いが、廃棄物処理・リサイクルを一つの産業としてとらえた場合には市場を極度に限定することになるので適切ではなく、市町村や都道府県といった行政区画にこだわらず、環境産業の創出・推進に向けた広域的な廃棄物や再生資源等の流通を含めた協力協働体制をつくっていく「広域性」が重要である。
イ 実験性
既存の処理業者は、比較的小規模な企業が多く、技術開発への資金負担をすべて行うことは困難な状況にあることから、公的支援等の下での機器の実験や技術の実証を積極的に行っていくといった「実験性」の視点も重要となる。処理・リサイクル機器の製造企業と実際の処理・リサイクル業者が分かれていることから、両者の間をつなぎ独自のノウハウの交換や高度処理や多様なリサイクルの技術の情報管理等における提携の場づくりも必要である。
ウ 公開性
地域住民等による正しい理解も、環境産業の創造には欠かせない。適正な理解の促進のためには、情報の公開や話し合いの場づくりに努めることなどにより住民と環境産業の間をつなぐとともに、廃棄物・リサイクル指導行政や技術支援等の場を透明にする「公開性」が求められる。
エ 協働性
廃棄物リサイクル問題は、住民、企業及び行政の関係各者から見える状況にかなりの隔たりがあることが考えられるため、関係者間の協議の密接化等により他の立場を自身に置き換えることを通じた相互理解と協調を進めていけるような機会の確保を図りつつ、住民、企業及び行政が実際に可能なところから事業として協力協働していく「協働性」も必要である。
以上のような視点を合わせて、静脈産業を環境産業として確立発展させ、動脈産業と静脈産業の適切かつ緊密な連携により、再生物の生産・供給機能の強化を図るとともに、併せて再資源化物の生産等への利用の促進を図ることが、循環型産業システムを有効に機能させ、循環の輪をつなぎ・太くしていく上で重要な条件であると考えられる。