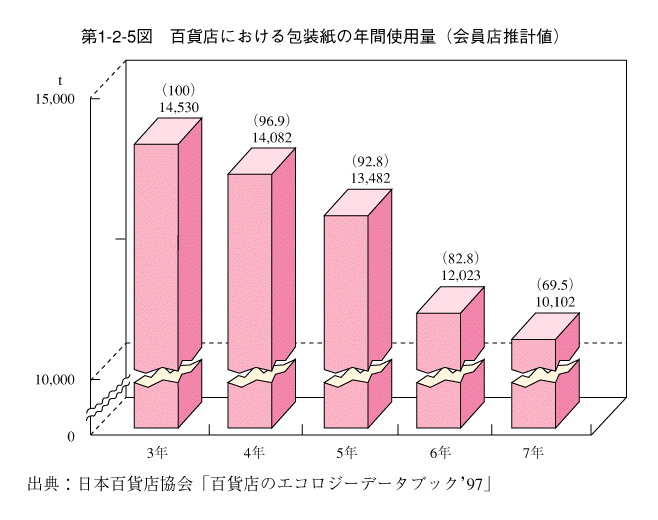
3 生産、流通、消費段階での新たな動き
循環型社会の輪をより太いものとするためには、生産段階の変化、流通段階の変化、そして消費者の対応の変化も合わせて重要になる。静脈産業の確立により循環の輪をつなげていった場合、各段階における廃棄物の排出抑制やリユースなどについて、より多様な方策の選択が可能になると考えられるが、ここでは、そのことにもつながっていくような現状での動きを概観してみたい。
(1) 生産段階の変化
生産(製造)者は、原材料の選択や設計段階からリサイクルしやすい製品づくりに変えていくこと、廃棄された際に有害な物質となるものの使用量を削減することが求められ、既に見た自動車や家電をはじめ一部の企業ではあるが具体的な取組が進められてきている。こうしたなか、製品が不要になった際に、自らが製品を回収し、そこから再使用できる部品を取り出し、生産ラインに組み込む取組も行われてきている。
OA機器のリースやレンタルは企業向けを中心に行われているが、リースされた製品は、期間が終了すれば企業により引き取られる場合が多い。引き取られた製品は、解体され部品の交換を行い再度組立て出荷することも可能となる。
また、使い捨て容器の見直しも行われてきている。使い捨て容器の今日の普及には、従来の販売店による配達・回収といった流通形態から自動販売機やコンビニエンスストア等による売り切り型への移行といった点も大きいが、消費者が返却の手間を嫌うといった利便性重視の意識やそれを支えるライフスタイルの問題も大きい。
リターナブル容器を定着させることは現状では困難も大きいが、新たな技術を活かし、利便性との両立を目指した商品開発が重要であると同時に、消費者の商品選択等で果たす役割も大きく、消費者の意識を変えていくことが重要になる。
囲み1-2-3 OA機器メーカーの取組
大手複写機メーカーでは、設立以来レンタルビジネスといった形態で事業展開を行っており、使用済みの複写機のほとんどが回収される仕組みになっている。回収した複写機は分解・洗浄され、再使用できる部品を取り出し、品質検査に適合した部品は再び生産ラインに投入され、新品部品とともに新たな複写機として生まれ変わる。この結果、生産ラインと直結した再生ラインの稼働が可能となっている。
より多くの部品を再使用できるようなシステムをつくるために、最初の複写機を設計する段階から、分解しやす設計、部品の共通化、材質表示などの項目について「商品リサイクル設計ガイドライン」を作成している。また、回収、分解等の各工程で得られた情報を設計部門にフィードバックすることにより、更に再使用できる部品を拡大するための製品設計に活かしている。
この生産システムでは、ユーザーは製品原料の供給者であり、製品の生産を工場の中だけでみるのでなく、製品回収まで含んで見直すことの重要性を示唆しているといえよう。
(2) 流通段階の変化
次に、流通段階では、平成8年度「百貨店の環境対策に関する定期調査」によると、包装紙の年間使用量の推移は第1-2-5図のとおりで、大幅に減少している。
また、製造者が製品を回収しリサイクルを実施するようなシステムの構築には、製品が不要になった際に消費者から回収するという点での流通業界の果たす役割は大きい。
さらに、流通業界では、リターナブル容器や詰め替え容器の採用、ばら売りや簡易包装の実施、中古品の更生と再販売、リサイクル品の販売などの取組も一部ではあるが新たに始まっており、これらの動きは関係する生産者に対しても影響を与えることができ、また、消費者の意識を変えそれを普及させることにも資すると考えられる。
(3) 消費者の対応の変化
消費の段階では、例えばフリーマーケットやバザー等を活用して、不要品を必要としている人に譲ることなどの動きもでてきているとともに、消費者相談やユーザーレポートなどを通じて、生産者や流通業者に対して廃棄物の発生を抑えた製品づくりを促していくような動きも見られ始めている。
また、消費者が製品を長期間使用するためには修理が欠かせないが、「修理には時間と費用がかかるため、新しく買い替えた方が得」というような生産流通システムが消費者の使い捨てを助長している面があることから、修理に対する不便さを解消し、消費者の修理意欲をサポートするために、家庭と製造メーカーを結ぶ宅配便ルートなどが現れてはじめている。このような修理業等の動きについては、第3章を参照のこと。
囲み1-2-4 百貨店の環境白書
日本百貨店協会環境委員会は、会員各店の環境に対する包括的な取組の実態を把握し、百貨店の総合的な環境対策に資するため、平成5年に「百貨店の環境対策に関する総合調査」を実施した。この調査結果に分析・評価・提言を加え、平成5年12月「百貨店の環境白書」を作成した。これによると、百貨店は環境問題を社会性、公共性を重視して取り組むべき問題としてとらえており、今後、業界として発展するためには、環境問題は決して避けられないものとしている。そして、今回の調査では、地域により意識や取組に差があること、商品面で取組や消費者に対する百貨店としての主体的な提案が進んでいないことなどが明らかとなり、これらへの対応として、マーケティング戦略を環境適合の観点から再構築することや、メーカーと消費者の間にあってモノを循環させる(製品を消費者に渡すだけでなく、不要品や廃棄物を消費者から回収しメーカーへ渡す)ための橋渡しを行っていくこと、消費者ニーズであるエコライフの推進を商品面からサポートしていくことなどを提言している。