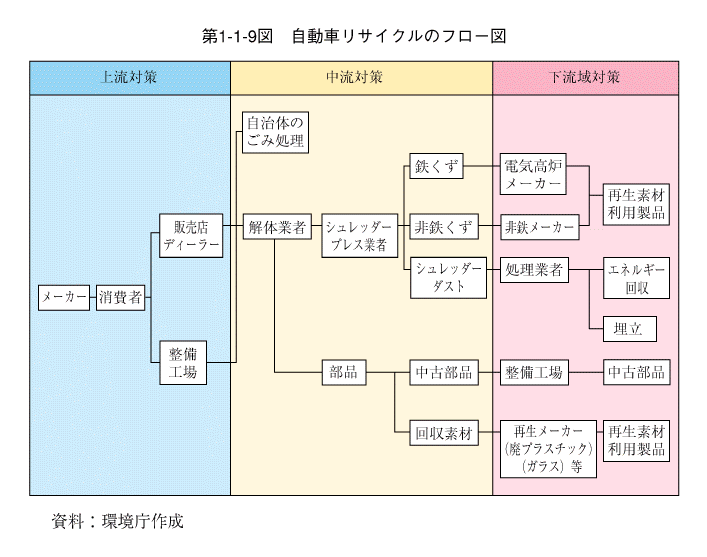
2 廃棄物処理に関する規制強化の動き
(1) 廃棄物処理対策の過去・現在
廃棄物の処理は、腐敗しやすい生ごみを市街地に放置しておくと伝染病まん延の原因となるため、公衆衛生上の観点からの行政による処理として始まっている。昭和29年には公衆衛生保持の観点から、汚物の衛生的処理を市町村の固有事務とした「清掃法」が制定された。その後、昭和45年には、公衆衛生保持のみでなく、生活環境保全の観点から廃棄物の適正な処理を確保するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定された。廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、一般廃棄物の処理は市町村の固有事務、産業廃棄物の処理は排出事業者に義務付けるといった新たな廃棄物処理の体系がつくりあげられた。
その後、廃棄物の排出量の増大や質の多様化、最終処分場の残余容量の逼迫、不法投棄や不適正処理の増加などの問題が生じ、これらに対応するため、平成3年に廃棄物処理法の改正が行われた。この改正により、それまで排出された廃棄物の処理に重点を置いてきた対策から、廃棄物の排出抑制と減量化の積極的な推進を含めた総合的な対策への方向転換が図られた。また、併せて資源の有効利用の確保を図ること等を目的とした「再生資源の利用の促進に関する法律」(再生資源利用促進法)が平成3年に制定された。
(2) シュレッダーダストの最終処分の規制強化
既に述べた豊島問題をはじめとして、シュレッダーダストの不適正な最終処分による有害物質等の環境汚染が各地で問題になった。シュレッダーダストの主な発生源は、廃自動車や廃家電などとされている。廃自動車については、一般的にディーラーを通じて、又は個人から直接自動車解体業者に渡される。解体業者は、部品として使用できるものを取り外し、残りをシュレッダー業者に渡す。シュレッダー業者は、さらに破砕機や磁力選別機により再利用できるものを回収する。この際に残るプラスチックや繊維、樹脂などがシュレッダーダストとして、最終処分場に持ち込まれている(第1-1-9図)。一方、廃家電製品は、市町村の回収ルートで回収される場合と家電販売店による引き取りルートがある。どちらで回収されても、破砕機や磁力選別機による処理を経た後に最終的に残るシュレッダーダストは、廃自動車と同様に、最終処分場に持ち込まれている。
このシュレッダーダストについては、これまで安定型最終処分場(性状が安定しており浸出水による地下水汚染など生活環境上の支障を及ぼすおそれが少ないと考えられる金属くず、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみを対象とする処分場)に埋立処分することが認められていた。近年、シュレッダーダストの埋立処分に伴う安定型最終処分場からの有害物質による地下水汚染等が問題となったため、最終処分場による環境汚染の防止を徹底する観点から、シュレッダーダストの最終処分の規制強化が図られた。すなわち、廃棄物処理法施行令の改正が行われ、平成7年4月から、シュレッダーダストは管理型の最終処分場(浸出水による地下水等の汚染を防止するため底部にシートを敷くなどの遮水工が講じられ、廃水処理施設等が設置されている処分場)に処分することが義務付けられた。
(3) 廃棄物処理法の改正
廃棄物の処理をめぐる様々な問題を踏まえ、国民の廃棄物処理に対する信頼性の回復と廃棄物の適正な処理の確保を図るため、「廃棄物の減量化・リサイクルの推進」、「廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上」及び「不法投棄対策」を3本柱として平成9年6月に廃棄物処理法の改正が行われた。
ア 廃棄物の減量化・リサイクルの推進対策
「廃棄物の減量化・リサイクルの推進」を図るため、多量の産業廃棄物を排出する事業者に対して都道府県知事が作成を指示することができる「産業廃棄物の処理計画」に「減量化に関する計画」を必ず盛り込まなければならないこととした。また、一定の廃棄物の再生利用について、生活環境の保全に十分配慮した上で、規制緩和を講ずることとし、厚生大臣の認定を受けた場合に廃棄物処理業や処理施設の設置に対する許可を不要とした。
イ 廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上対策
「廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上」を図るため、廃棄物処理施設の設置に際し、設置しようとする者は施設の設置による周辺地域の生活環境への影響について調査しなければならないこととされ、施設設置の許可基準に当該施設が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであることが加えられた。また、焼却施設と最終処分場に関しては、都道府県知事は許可申請書等を公衆に縦覧すること、施設設置に関し利害関係を有する者は都道府県知事に対し生活環境の保全上の観点から意見書を提出することができること、都道府県知事は施設設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村長及び生活環境保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこと、という手続きが定められた。
また、施設の維持管理の強化として、維持管理計画の策定、焼却施設及び最終処分場については維持管理状況の記録及び生活環境保全上の利害関係者への記録の閲覧並びに特定の最終処分場における埋立終了後の維持管理の適正な実施のために必要な費用を埋立期間中に維持管理積立金として環境事業団に積み立てることに関する規定が設けられた。さらに、処理業者の信頼性の回復を図るため処理業の許可に当たっての欠格要件の追加や許可業者が無許可業者に対し許可名義を貸す行為の禁止の規定が設けられた。
囲み1-1-5 廃棄物処理施設設置手続の流れ
今回の廃棄物処理法の改正により、施設の設置手続のフローは以下のとおりである。
ウ 不法投棄(及び不適正処理)対策−排出者責任の徹底−
「不法投棄対策」としては、不法投棄の未然の抑止効果をねらって、大幅な罰則の強化が図られた。
また、排出事業者が廃棄物の流れを管理し適正な処理を確保する産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度をすべての産業廃棄物に適用することにより、排出事業者の処理責任の実質的な明確化及び徹底が図られた。従来は産業廃棄物の処理を委託した場合、排出事業者は、特定の廃棄物以外は処分先や処分方法を確認する必要がなかった。このことが不法投棄を横行させる原因の一つとなっていた。今回の改正により、産業廃棄物の排出者は、自分が委託した産業廃棄物がきちんと運搬又は処分されていることを確認することができることになるとともに、確認をする義務も生じた。これは、適正処理処分を契約上の行為として担保するのみでなく、すべての産業廃棄物について、実際にマニフェストに沿って産業廃棄物の処理を排出事業者自らが確認することにより、適正処理を実質的に担保することが義務付けられたことになる。すなわち、排出事業者は産業廃棄物の処理を処理業者に委託すればそれで終わるのではなく、きちんとした処理が行われていることを確認してはじめて排出者としての処理責任を果たしたこととなる。
このことは、産業廃棄物の不法投棄が万一行われた場合、原状回復措置を命令できる対象として、マニフェストを交付しなかった者や虚偽のマニフェストを交付した者にも拡大したことにも表れている。
さらに、不法投棄を行った者が不明であったり、原状回復費用を負担するための十分な資金力がない場合には、原状回復を行う都道府県等に対し、産業廃棄物適正処理推進センターに産業界からの拠出等により設けられた基金から、資金協力等を行うことができる仕組みが設けられた。
今回の改正における排出者処理責任の実質的な強化徹底によって不法投棄や不適正処理の防止が図られていくことを通じて、廃棄物による生活環境への支障に対する住民の不安が解消される方向に進むことが期待される。
(4) ダイオキシン類に関する規制強化
廃棄物焼却施設から発生する排出ガス中のダイオキシン類を削減するため、環境庁では、平成9年6月の中央環境審議会答申「ダイオキシン類の排出抑制対策のあり方について(有害大気汚染物質対策に関する第四次答申)」を踏まえ、大気汚染防止法施行令の一部改正等を行い、ダイオキシン類を指定物質(その排出・飛散を早急に抑制しなければならない物質)に指定するとともに、廃棄物焼却炉等についてダイオキシン類の指定物質抑制基準を定め、厚生省では、廃棄物処理法施行令等の一部を改正し、許可の対象となる廃棄物焼却施設の裾切りを引き下げて規制範囲を拡大するとともに、廃棄物焼却施設の排ガス処理設備の基準の強化等の構造・維持管理基準の強化を行い、いずれも平成9年12月1日から施行した。
安定的な燃焼管理を行うためには、大型で24時間連続運転を行う全連続式焼却施設が望ましいことから、人口の少ない市町村にあっては、単独で廃棄物処理を実施するよりも行政区域を超えた範囲で協力・協働体制を組み、広域的な連携の下で廃棄物を収集し、適正な燃焼管理が可能な焼却施設等で処理を行っていくことが必要になってくる。
(5) 最終処分等の更なる規制強化
最終処分場に対する規制を強化することにより、廃棄物の最終処分をめぐる問題の軽減を図るため、中央環境審議会から平成9年11月に出された「廃棄物に係る環境負荷低減策の在り方について」の第1次答申を受け、最終処分基準の強化を図ることとし、平成9年12月廃棄物処理法施行令等の改正が行われた(施行は平成10年6月17日)。
改正では、安定型処分場に埋立られている安定型産業廃棄物のなかには、有機性汚濁の原因となる物質が含まれ溶出するおそれのあるもの、有害物質の溶出の観点からそれ自体問題があるもの、そのような汚染の原因となるような物質の付着や混入の可能性が高いものなどが含まれていたため、安定型産業廃棄物の範囲を見直し、安定型処分場に安定型産業廃棄物以外の廃棄物が入らないようにするための措置が強化された。
囲み1-1-6 廃棄物焼却施設の構造・維持管理基準の強化の主な内容
・主な構造基準の強化としては、
? 廃棄物を一定量ずつ継続的に供給できる装置を設置すること。
? 燃焼ガスの温度を800℃以上の状態で焼却できる燃焼室を設置すること。また、燃焼ガスの温度を速やかに800℃以上にし、これを保つための助燃装置を設置すること。
? 排出ガス処理装置の入口における排ガスの温度を概ね200℃以下に冷却できる排ガス冷却装置を設置すること。
? 燃焼温度、排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度を連続的に測定し、記録するための装置を設置すること。
・主な維持管理基準の強化としては、
? 廃棄物を均一に混合し焼却室に投入すること。
? 燃焼室の温度を800℃以上に保つこと。また、運転開始の際には助燃装置を作動させて速やかに炉の温度を上昇させ、運転停止の場合には、助燃装置を作動させながら炉の温度を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
? 排ガス処理装置の入口における排出ガスの温度を概ね200℃以下に冷却すること。
? 焼却施設の既設新設の別や処理能力に応じて設定された排ガス中のダイオキシン類濃度の基準以下とすること。
? 排ガス中のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し記録すること。
これにより、?プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る)、?ブラウン管(側面部に限る)、?鉛蓄電池の電極、?鉛製の管又は板、?石膏ボード及び?容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、処分までの間にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く)が、安定型産業廃棄物から除外され、管理型産業廃棄物への移行がなされた。
さらに、一定量以上の有害物質を含む汚泥等については、廃棄物の発生施設に関わりなく遮断型最終処分場に埋め立てることとすること、廃棄物処理法施行(昭和46年9月)以前の埋立地において公共用水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には必要な措置を講ずることなどが定められた。
最終処分以外では、廃棄物の保管場所からの飛散流出による水源や地下水などへの環境汚染のおそれが指摘されるとともに、産業廃棄物の積み上げ等が問題となっていたため、廃棄物の保管基準の強化が行われた。
(6) 規制強化と処理・リサイクルコスト
廃棄物の適正処理の確保のための規制の強化に伴い、生活環境の保全の観点からのより高度な廃棄物処理が求められてきているところであるが、このためには高度な施設や技術が必要になり、これにかかる費用も高くなる。例えば、一連の産業廃棄物の最終処分基準の強化により、比較的簡便な施設整備や管理が可能な安定型処分場に替えて、遮水工等生活環境保全上必要なより高度な構造が必要であるとともに排水処理などその管理も高度な管理型処分場に埋め立てることが必要となり、最終処分に係る費用の大幅な増加が見込まれる。
これらの費用は処理費用として排出事業者が支払うものであり、これに伴う排出事業者の意識の変化、すなわち事業活動によって排出される廃棄物の適正処理には多大なコストが掛かるという意識が、事業活動の見直しを促す契機の一つとなっていくとも考えられる。
また、廃棄物処理コスト意識の広がりは、適正処理を行う廃棄物処理業者への適正費用の還流につながることも考えられ、廃棄物処理・リサイクル業の「静脈産業」としての確立につながっていくことも期待される。高度なリサイクル技術と処理、処分技術に支えられた静脈産業の確立は、循環型産業システムの形成に当たっての一つの基礎となるものと考えられる。