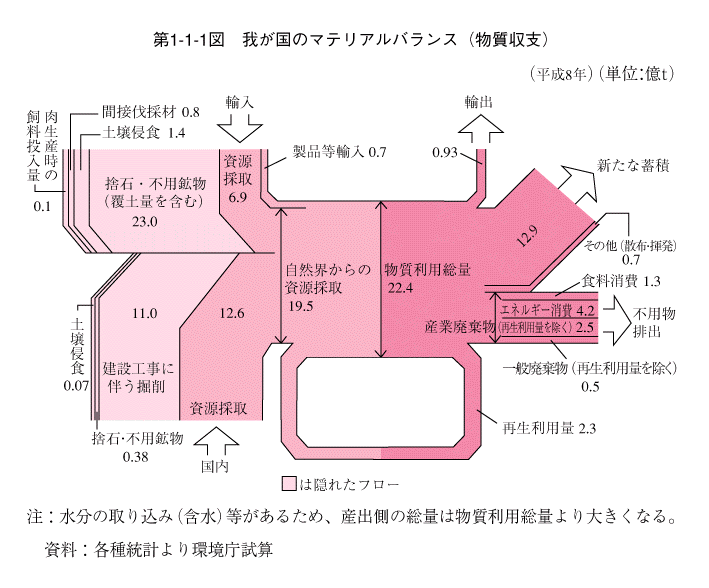
1 廃棄物処理をめぐる今日の問題状況
(1) マテリアルバランスにみる一方通行社会
我々の経済活動における物質の利用状況を、平成8年のマテリアルバランス(物質の収支)により概観してみよう。(第1-1-1図)
これによると、平成8年に自然界から資源採取した量は19.5億t(前年比1.0%増)で、そのうち海外から6.9億t輸入している。製品等の輸入量は0.7億tで、経済活動に投入された資源の量は20.1億tであった。資源として投入されたものの他に、建設工事に伴い掘削された土、鉱物採取の際の捨石・不用鉱物、耕作地等から浸食された土壌、また輸入資源の生産に際し発生する捨石・不用物、浸食された土壌、間接伐採された木材など(以下「隠れたフロー」という)がある。国内における「隠れたフロー」の量は11.5億t、海外における「隠れたフロー」の量は、25.3億tで、実際に投入された資源の量と「隠れたフロー」を合わせた国内総物質需要量は56.9億tであった。
また、平成8年において、新たに蓄積された量(建物や道路などの土木建築物を中心として家具や家電製品等の耐久消費財も含む)は12.9億t(前年比2.4%増)、不用物として排出された量は8.5億t(前年比1.2%増)で、再生利用された量は2.3億t(前年比9.5%増)であった。
国内の生産活動は、90%近くが国内外から採取された天然資源に依存しており、再生利用率は、10%のみである。国内におけるマテリアル・フローは循環性が低く、資源採取から廃棄に向かう一方通行の流れであることが分かる。まさに現状が「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済社会であることを視覚的にも表していると言えよう。このような我々の経済社会活動に伴い生じている環境負荷は、資源採取に伴うものと、不用物を廃棄物として排出することによるものがある。
マテリアルバランスの新たな蓄積は、耐用年数が経過すると建て替えられたり、作り直されたりする。今存在しているものは、その時点で廃棄物となると考えられることから廃棄物予備軍であるともいえる。
この現状のマテリアルバランスからは、この廃棄物予備軍が将来的に膨大な廃棄物となることが読み取り得るが、その時その多くの部分を再び資源として利用していくようなフローが成り立っていなければ、膨大な環境負荷が発生することになる。したがって、これらの再生利用の流れを今から太くしていくことが、このマテリアルバランスからも求められている。そのことが、現状で大きな環境負荷をもたらしていると考えられる天然資源採取における将来的な環境負荷の低減にもつながり、既に述べた資源と環境の両面から環境負荷を最小化する循環型経済社会の構築にもつながるものである。
(2) 廃棄物処理の現状
我が国では、平成元年度以降、毎年年間約5,000万tの一般廃棄物が排出されている。排出量の推移をみると第1-1-2図のとおりで、平成6年度には、総排出量5,054万t(東京ドーム136杯分、平成5年度5,030万t)、国民1人1日当たり1,106g(平成5年度1,103g/人・日)といった状況にある。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)においては、一般廃棄物は市町村で処理を行うこととなっており、市町村が一般廃棄物を直接又は間接的に収集し、中間処理を行い、最終処分することが一般的である。市町村は、収集した一般廃棄物を安定化させ、最終処分する量を極力少なくするために中間処理を行うが、この中間処理の中心が焼却処理である。処理方法の推移は第1-1-3図のとおりで、平成6年度は、市町村が行った中間処理のうち、直接焼却処理された量は37,485千t、約75.5%にのぼる。
さらに、この直接焼却以外にも粗大ごみを破砕等処理する施設を経由して焼却処理に回されるものなどで焼却処理されるものを合わせると、38,946千tが焼却処理されている(第1-1-4図)。
また、市町村や住民団体による資源ごみとしての回収や中間処理により再資源化される割合(リサイクル率)は平成6年度で9.1%(平成5年度8.0%)で年々増加している。
また、平成6年度に最終処分された量は14,142千tで、前年に比べ80万t減少したが、一般廃棄物の最終処分場の残余年数は、全国平均8.7年で逼迫している状況に変わりはない。
産業廃棄物の排出状況についてみると、平成2年度以降ほぼ横這いの状態で年間約4億tが排出されている。産業廃棄物の排出状況をみると第1-1-5図のとおりで、平成6年度には、総排出量約4億500万t(平成5年度約3億9,700万t)、種類別では汚泥、動物のふん尿、建設廃材が全体の約8割を占めているといった状況にある。業種別に見ると、建設業、農業、電気・ガス・熱供給・水道業がそれぞれ20%弱を占めている。
平成6年度の産業廃棄物の処理状況は第1-1-6図(産業廃棄物の種類別の内訳は第1-1-7図)のとおりで、総排出量のうち38%が再生利用され、最終処分された量は約8,000万t(平成5年度約8,400万t)で、産業廃棄物の最終処分場の残余年数は、全国平均2.6年で一般廃棄物の最終処分場以上に厳しい状況にある。
(3) 産業廃棄物処理の問題
前述したような膨大な量の廃棄物、特に産業廃棄物が最終処分されている状況は、量的な面だけでなく、近年の廃棄物の質の多様化に伴い有害物質を含んだ廃棄物の最終処分が広く行われるようになる中で、搬入不適物の混入等不適正な最終処分場への搬入埋立や処分場の不適切な維持管理等が目に付くようになり、これによる地下水や土壌の汚染等への周辺の住民等の不安が広がりかつ高まっている。その中で、豊島問題に象徴される一部の業者(排出事業者である場合や産業廃棄物処理業等の許可をもっていない場合など廃棄物処理業者ということは適切でない場合も多い)による最終処分とも絡んだ不適正処理による環境汚染の問題が社会的に大きくクローズアップされた。これと全国的に起こっている廃棄物の不法投棄の問題が相まって、産業廃棄物及びその処理に関するイメージの悪化を招き、それによる処理業者の立地や操業の困難化も一因となって、適正処理の確保の困難化がさらに進むなど、悪循環の様相を呈している。
囲み1-1-1 豊島問題
香川県豊島では、廃棄物処理業者がシュレッダーダスト(自動車や電気器具等を破砕し金属を選別回収した後の残滓で、プラスチック、ガラス、金属等を含むもの)等の不法投棄を行ったために、有害物質を含有している膨大な量の産業廃棄物が放置された状態となっている。平成5年、住民らが、公害紛争処理法に基づき、産業廃棄物処理業者、香川県、産業廃棄物を排出した事業者等を相手方として、産業廃棄物の完全撤廃を求める等の公害調停を申請した。公害等調整委員会において調停手続が進められた結果、平成9年7月、県が主体となって廃棄物及び汚染土壌を無害化処理し、できるだけ再生利用を図り、原状回復を目指すこと等で県と住民との間で中間合意がなされ、現在、県が設置した技術検討委員会において具体的な処理方法を検討している。また、平成10年3月までに一部の産業廃棄物を排出した事業者との間で、住民に対し解決金を支払うとの調停が成立している。
警察白書によると、平成8年の廃棄物処理法違反の状況は第1-1-1表のとおりで、全体の約76.4%が不法投棄事犯であった。さらに、産業廃棄物不法投棄事犯の投棄者別、動機別内訳は第1-1-2表のとおりで、「処理経費節減のため」といった経済的な動機が約65.3%を占めている。この二つの表を見比べると、産業廃棄物以外すなわち一般廃棄物の不法投棄による検挙件数が産業廃棄物のそれの4倍以上あることがわかる。ここで問題なのは、まず、排出事業者による不法投棄が全体の78.5%も占めている点である。さらに、それ以外の不法投棄事犯もその多くが無許可の者によるものであること、廃棄物処理法違反事件についても不法投棄以外の大半が委託基準違反=無許可処理業(一つの事件で排出事業者にとっては無許可業者に処理を委託したという委託基準違反、受託した側からは無許可で処理業を行ったという違反となるもの)であることと合わせて、排出事業者が責任においてイニシアチブをもつもの、すなわち排出事業者が適正に処理しようと思えば防げる違反事件といい得ることである。不法投棄をはじめとする(産業)廃棄物問題=産業廃棄物処理業者の問題といったイメージが強いが、実際には、経済的な理由からの排出事業者による不法投棄や排出事業者に責任のある不適正処理が多いことが注目される。このことからは、排出事業者において産業廃棄物処理には適正な経費を掛けなければならないといった考えが欠落しているか又ははなはだ弱い場合が多いことがうかがえる。すなわち、排出事業者の企業活動等における事業経費として廃棄物の処理コストが適正に組み込まれていないことに、産業廃棄物問題の根幹の一つがあると考えられる。
廃棄物処理法上、排出事業者は、産業廃棄物を自らの責任において適正に処理するか、又は産業廃棄物処理業者に処理を適正に委託しなければならないことになっているが、既に述べた排出事業者の処理コストに対する意識は、廃棄物処理業者に処理を委託する際にも現れている。すなわち、排出事業者においてはより安い処理料金ということのみに注目した業者の選定がなされる傾向にあり、その結果処理業者の間ではダンピングともいうべき取引が行われやすい状況にあるとも言われている。こうした状況は、悪質な業者等による不適正処理にもつながりかねないのみならず、適正処理を行おうとする処理業者の操業を困難にする重大な問題でもある。さらには、本来適正な処理コストが勘案された場合に排出事業者又は処理業者において経費的にも選択されたかもしれない高度処理やリサイクル等の方途を、あらかじめ閉め出すことにもなってしまう可能性もあることから、高度な処理技術やリサイクル技術の開発・普及に対する実質的な障壁になっていることも考えられる。
この排出事業者の適正処理のためのコスト負担意識の弱さは、その一つの背景として市民や事業者の間に「廃棄物は目の前からなくなればいい」という意識が根強くあることも考えられる一方、廃棄物というモノのあり方からくる面もあるとされている。すなわち、通常のモノやサービスは、需要者によってチェックされ、モノと貨幣は逆方向に流れ、質の悪いモノは売れなくなる。しかし、廃棄物は現状では負の価値財=いわゆるグッズ(GOODS)に対するバッズ(BADS)と考えられモノの流れと貨幣の流れが同方向になることから、排出者は廃棄物処理の質が低くても困ることはないため、何もなければ、廃棄物の処理状況を排出者がチェックするといったことは行われにくく、質の低い処理が淘汰され質の高い処理が残るといった状況にはなりにくいという問題がある。後で述べる廃棄物処理法の改正では、マニフェスト制度の徹底、すなわちすべての産業廃棄物の排出事業者にチェック義務を課すことにより、この問題の解決を図ろうとしているのである。
しかしながら、本来の処理責任者である排出事業者のコスト負担の弱さが、不適正処理による環境汚染や事後処理の必要を生じさせるなどの事態を招き、それに伴い膨大な社会的コストが発生しているとすれば、このコストの発生を事前に防止するために、廃棄物の処理コストを排出事業者の企業活動等に適正に組み込むことによって、市場のメカニズムを通じて、適正処理のためのコストが社会において適切に負担されるようにしていくことが、不法投棄や不適正処理の問題を解決していくための一つの鍵であると考えられる。後でも述べるが、廃棄物処理法等による適切な規制等もこのような効果をもたらすことが期待される。
さらに、社会において適正な廃棄物処理コストが負担されることは、廃棄物処理業者への適正な費用の支払いの確保による優良な業者のビジネスチャンスを意味するとともに、廃棄物処理業の産業化や高度化、さらにはこれまでのような安易な最終処分の道が狭まることによる様々なリサイクルの可能性がコスト的にも生まれてくることにもつながり、リサイクル産業を組み込んだ適切な静脈産業としての発展への道を開く一つの鍵にもなると考えられる。
囲み1-1-2 情報公開と住民理解の重要性−福岡県八女市の事例−
廃棄物の処理は、各地で起きている最終処分場をはじめとした処理施設の設置に対する住民等の反対やその運動を基盤にしたいくつかの市町村での住民投票の実施にみられるように、住民の理解が得られず行き場を見失っている状況にある。これには情報公開の不十分さなどにより住民が過度に廃棄物処理やそれを担う処理業者等に対して不安感不信感を持っている点も否めない。
適正な廃棄物処理・リサイクルの推進のためにも、地域住民の理解は欠かせない。そのため、廃棄物処理・リサイクルに携わる処理業者等や市町村は、積極的に情報を公開し、住民の合意を得つつ適正な廃棄物処理を展開することが必要であり、そのような事例の積み重ねが、住民の不信感を解消する地道な方途であろう。住民は、公開された情報をもとに、自らも当事者として処理事業の安全性や環境保全対策の妥当性、社会生活におけるその事業の必要性などを十分検討すべきである。このような観点からも以下の事例に注目したい。
福岡県の八女市においては、市内の産業廃棄物最終処分場の拡張計画に対して、地元住民などからの激しい反対運動が行われる中で、市は「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に基づき福岡県と協議しつつ、処理業者等と話し合いを行い、住民への情報公開に努め不信感等を解消しつつ、環境保全の確保を図るため、業者との間で「環境の保全に関する協定」を締結した。この協定は、住民や処理業者と半年以上に及ぶ検討を重ねた末に、?最終処分場への持ち込み品目の限定、?持ち込み区域の限定、?排水基準の設定と処理業者による水質検査の義務付け、?市職員の立ち入り調査権の確保、?市が任命した監視人の設置、?工事の段階的な施工、の6項目を盛り込んで、平成6年3月に市と処理業者との間で締結するに至ったものである。現在も、この協定に基づく水質検査や監視が行われ、その結果も公表されている。
この八女市の事例は、産業廃棄物処理施設への地元市町村としての対応の一つのあり方として、市が責任を持って環境保全の確保を図りつつ、処理業者と住民の合意形成を図るという注目すべき手法と考えられる。同様の手法は、他の自治体でも追求され一定の成果を見ている。このような地道な努力の積み重ねが、草の根から廃棄物処理や処理業者のレベルを上げていくとともに、そのイメージの転換にも寄与していくと考えられるが、そのためにも協定の環境保全項目を完全に守れるだけの適正な処理コストが処理業者に流れることを確保するなど、静脈産業を適正に機能させ確立させることが必要である。
(4) 廃棄物処理とダイオキシン問題
近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による環境汚染が全国的に大きな問題となっている。ダイオキシン類は、塩素が存在する状態で有機物を燃焼させた時などに非意図的に発生する有害な有機塩素化合物で、平成9年2月に世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)が、これまでの評価を変更しダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDについて人体に対して発がん性があるとの評価を行ったものである。我が国におけるダイオキシン類の総排出量の9割以上は廃棄物焼却施設から排出されているという推計もあり、特に高温での完全燃焼が行いにくい構造の焼却炉等において排出が多くなるといわれている。
厚生省では、平成8年度に市町村等が設置している焼却施設について、焼却の際に発生する排ガス中のダイオキシン類濃度の状況を調査した結果、平成9年9月末現在で、1,641施設(平成9年5月末現在の全焼却施設数)のうち107施設で緊急対策の判断基準(これを超える施設においては、燃焼管理の適正化、間欠運転から連続運転への変更、施設の改造や休廃止等を至急検討することされた)である80ng(10億分の1)-TEQ/m
3
Nを超過していた。このため、11施設では焼却処理を休止し、6施設では施設そのものを廃止した。さらに今後2施設が廃止を予定しているといった状況にある。また、文部省では、学校におけるごみ焼却炉についてダイオキシン類等の有害物質の排出に対する安全性の確認がなされない限りは原則として廃止するよう、平成9年10月に各都道府県教育委員会等に対して通知により指導した。これらの一般廃棄物の焼却処理施設等の問題は、産業廃棄物の焼却処理施設にも共通する問題であり、廃棄物の中間処理として最も広く行われている焼却処理について、適正な処理の確保の観点からの改善等が必要であるとともに、新たな処理技術の開発が進められてきているところである。
囲み1-1-3 ダイオキシン類
ダイオキシン類とは、有機塩素化合物で、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)とポリ塩化ジベンゾーパラージオキシオン(PCDDs)の総称で、物の燃焼過程等で非意図的に生成されるものである。
ダイオキシン類のなかでも最も毒性の強い2,3,7,8ーTCDD(四塩化ジベンゾーパラージオキシン、構造式で2,3,7,8の位置に塩素がついたもの)については、人に対する発がん性が確認されている。
ダイオキシン類の濃度は、環境庁が実施した一般環境大気中の測定結果(平成8年度)によると、工業地域近傍の住宅地域の平均値は、1.00pgーTEQ/m
3
(0.38〜1.67)、大都市地域の平均値は1.02pgーTEQ/m
3
(0.30〜1.65)、中小都市地域の平均値は0.82pgーTEQ/m
3
(0.05〜1.56)、バックグラウンド地域の平均値は0.07pgーTEQ/m
3
(0.05〜0.10)であった。これに対して、ダイオキシン類の大気環境指針として、年平均値0.8pgーTEQ/m
3
以下とすることが、平成9年9月に定められている。
ダイオキシン類の構造式
(参考)
1pg:1兆分の1g
TEQ:毒性を評価する際の単位。
ダイオキシン類の量を2,3,7,8ーTCDDの量に換算した量として表記する際の符号。
(5) 最終処分の状況
既に述べたように、産業廃棄物の不適正な最終処分による環境汚染の問題が注目され、後述するような最終処分の規制強化が行われるとともに、最終処分場の残余容量の逼迫化と相まって、排出事業者においても、また処理業者においても、さらには上流に遡って製品の生産者においても、最終処分量を減らそうという動きが出始めている。一方、市町村が実施している一般廃棄物の焼却灰の最終処分の状況についても、厚生省の調査によると、平成9年12月末現在、1,901ある最終処分場のうち、遮水工又は浸出水処理施設を有しない施設が538施設(28%)(処分場から排出される浸出水の処理を必要としない廃棄物のみを処理している処分場を除く)あった。このことは、焼却処理後の焼却灰は、地下水等への影響を考慮し、遮水工や浸出水処理設備を持つ最終処分場に埋め立てる必要があるとされていることからみても、環境保全上の問題を引き起こす可能性があり、放置できない問題である。このため、厚生省では、遮水工や浸出水処理設備を有しない処分場においては浸出水の処理が必要な廃棄物の受け入れの停止、新たに施設の構造基準や維持管理基準に適合した最終処分場の整備、複数市町村による広域的な最終処分場の確保について検討などの方針の下、平成10年3月に都道府県を通じて市町村に対する指導の徹底を図った。併せて、538施設の周辺地下水の水質検査の実施と汚染拡散防止対策を検討・実施するよう指導した。
このような最終処分場の逼迫と不適正な処理という最終処分の状況は、これまでの廃棄物処理システムが抱える問題を改めて示すとともに、廃棄物の無害化、再資源化等の技術開発の促進の必要性を高めることとなり、これらの技術の普及の契機になっていくものとも考えられる。
(6) 市町村の処理経費の問題
我々が日常生活で使用する製品等の多様化に伴なって、廃棄物の質も多様化してきたため、大型ごみの破砕等の処理や生活環境保全上の様々な措置の必要が生じ、市町村はそのための設備等を設けなければならなくなった。同様に、最終処分に際しても、最終処分場としての埋立地の安全性を確保するための構造や付帯設備等が必要となった。これらによって、廃棄物処理施設の建設や維持管理には多額の経費と人と技術を要することとなり、市町村の負担は極めて重いものとなってきている。処理経費の推移をみると第1-1-8図のとおりで、平成6年度には2兆1,665億円を要し、国民1人当たり年間に約17,300円、4人家族では年間に約6万9千円を要したことになる。
このようにみてくると、一般廃棄物の処理は無料でなく、住民が事実上処理費用を負担しているのであるが、税金による負担であるため、廃棄物の排出をできるだけ少なくしている者も、まったく意識していない者も同様の金額を負担していることになる。この不公平を是正することも含めて、一部自治体では一般廃棄物処理の有料化を実施している。有料化の実施は、特に従量制の料金設定の場合には家庭等からの廃棄物の排出を抑制する効果があることがこれまでの実施自治体の経験から言われているが、導入に当たっては、廃棄物処理の実態を住民に公表しその問題状況を理解してもらうことにより、費用負担と排出抑制の必要性について、合意形成に努めていくことが重要である。このような有料化に向けた論議の中で、日常生活における廃棄物の発生要因に目を向け、その量や質をめぐって消費のあり方を見直していく契機となることも期待し得る。
例えば、使い捨て容器について、リターナブル容器との比較において考えてみよう。生産段階での選択基準は、機能が同じであれば、その生産に係る経費が安いかどうかであるから、廃棄物になったときの処理コストを市町村がすべて負担していれば、生産側にとって回収に掛かるコストが不要との意味で経費が安いことから使い捨て容器を選択し生産することになる。流通側も回収に掛かる経費が不要な使い捨て容器を販売することになる。消費側は、環境保全上の観点が意識にない場合には値段と利便性が判断の基準となるため、仮に同じ料金であっても、利便性をどう考えるかの価値観の問題が入り得るが、回収への手間の掛からない使い捨て容器が現状では選択されているようである。このように、各段階で使い捨て容器の方が選択されることになっているが、ここでは、処理に掛かる経費は市町村が負担していることにより各段階で処理経費が無視し得ることから、このような選択になったとも考えられ、処理コストが各段階で負担されていれば、その多寡にもよるが異なった選択が取られることも考えられる。このことからも、廃棄物の処理経費が適正に考慮されていない現在の生産、流通、消費の在り方の問題性をかいま見ることができる。
廃棄物処理の有料化に関する論議は、現在の使い捨て社会に対する問題提起でもあるといえる。
囲み1-1-4 廃棄物問題と住民意識
毎日のように廃棄物問題に関する報道が流れ、その内容も不法投棄による周辺環境への悪影響や、不適正処理による地下水汚染や大気汚染等の廃棄物処理施設周辺での環境問題など、廃棄物や廃棄物処理に関しマイナスのものが多く、その影響もあり国民は、廃棄物の処理及びそのための施設は自分たちの社会生活にとって必要なものであるにもかかわらず、廃棄物は怖いもの、廃棄物を処理する施設は危険で迷惑な施設といったイメージを持つようになっている。
このことから、廃棄物を適正に処理する施設でさえ、「自分の裏庭でなければいい」(NIMBY:NotIn My Back Yard)という意識が広がってしまい、その立地が困難になっている状況にある。
廃棄物は、我々が生活している限り、又は産業活動が継続する限り必ず発生する。生活とは関係のない企業の廃棄物と意識される場合の多い産業廃棄物についても、日常生活で日々使っているモノの生産やそれに何らかの関連を有する生産等に関わる廃棄物である。したがって、廃棄物の問題は、我々の社会生活に密接に関わるものである。