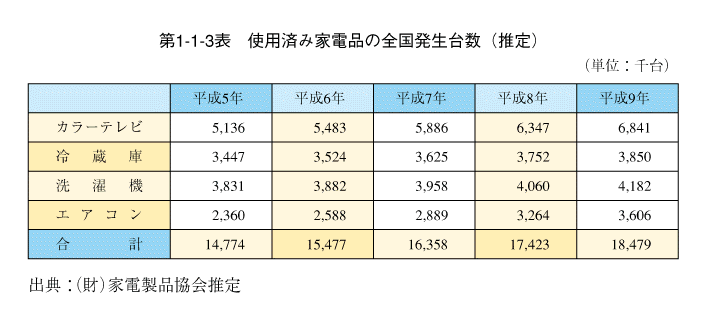
3 循環の輪をつくり・つなぐ動き−循環型社会へ向けた取組−
新たな制度の整備や事業者、地域社会等における取組において、循環の輪をつくり、つなぐ動きの端緒となるようなものが見られ始めている。また、廃棄物の処理・処分においても、従来の焼却中間処理−焼却灰埋立最終処分という処理システムをこのまま継続していくことが困難になりつつある状況を踏まえ、中間処理を高度化しリサイクルを組み込むことにより焼却量、さらには最終処分量を極力減らしていこうとする取組が広がり始めている。このような中から、官民連携、広域連携などの模索も含めて重要と考えられるいくつかの取組に視点を当てていきたい。
なお、このような廃棄物処理・リサイクルの取組を進める上で、これが環境負荷を低減していく上で最も望ましい形で進められることが重要である。環境基本計画においては、廃棄物・リサイクル対策の基本的な考え方として、第1に発生抑制、第2に使用済製品の再使用(リユース)、第3に、回収されたものを原材料として利用するリサイクル(マテリアルリサイクル)を行い、それが技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合、環境保全対策に万全を期しつつ、エネルギーとしての利用を推進し、最後に発生した廃棄物について適正な処理を行うこととしており、このような考え方に沿った取組が進められることが必要である。また、リサイクルを進める上で、カスケードリサイクルの考え方(再生物の質の劣化の程度に応じた適切なリサイクルを行うこと。例えば、上質紙として再生可能な古紙であるにも関わらずトイレットペーパーに再生する、といったことを避ける等)や、セメントや路盤材など環境と直接接触するような形で利用される再生物についての環境配慮なども必要であろう。さらに、リサイクルの推進に当たり、廃棄物に混入した塩化ビニル類等が以下に述べるような各種の取組を進める上での支障になっている等の問題点も指摘されているところである。
(1) 事業者によるリサイクルの義務付け等の制度の整備
ア 容器包装廃棄物
既に述べたとおり、一般廃棄物の最終処分の残余年数は9年弱となっており、その残余容量は逼迫している。これを受け、一般廃棄物のうち、容積比にして約6割を占める缶、びん、プラスチック容器などの容器や紙などの包装が廃棄物となったもの(容器包装廃棄物)について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化(リサイクル)を促進することにより、この減量化を図るとともに、再生資源としての利用を確保するため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が平成7年に制定され、平成9年から本格施行された(平成12年4月に完全施行)。なお、容器包装のリサイクルの状況については、第4章第4節を参照のこと。
イ 廃家電等
近年、電気製品は我々の生活においてますます需要が増え、特にテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった家電製品は生活必需品となっている。また、これらの製品は年々大型化が進むとともに、その機能も高度化・多様化が進んでいる。さらに、これらの製品には鉛やフロンなどの環境に負荷を与える物質が使われているものもある。
財団法人家電製品協会の推計によれば、家電主要4品目の廃棄量は年々増加する傾向にある(第1-1-3表)。これらの廃家電は、約8割が買い換え時に販売店が引き取り、残りは市町村が粗大ごみとして引き取っており、最終的には約6割が小売店の委託を受けた処理業者により、約4割が市町村により処理されている(第1-1-10図)。現在、廃家電の処理は、破砕された後に鉄やアルミニウムなどの金属の回収を行っているのみのリサイクルに留まっているほか、破砕施設をもたない市町村においてはそのまま埋め立てられている場合も多い。
このような状況を踏まえ、市町村における廃棄物の処理技術や施設では高度なリサイクルが困難なものについて、小売業者による収集及び運搬と製造業者等による再商品化等を義務付けることにより、廃家電等の適切なリサイクル・処理を確保するため、政府は、平成10年3月に「特定家庭用機器再商品化法案」を閣議決定し、国会に提出した。
(2) 動脈産業による廃棄物のリサイクル
ア 製鉄産業の動き−廃プラスチックの高炉の還元剤としての活用−
国内で排出される廃プラスチックの処理状況は、第1-1-11図のとおりで、約70%以上が焼却や埋立てられている。プラスチックは軽く、腐食せず、加工しやすいといったメリットをもつため、我々の生活用品に深く関係している。しかし、?埋め立てられる廃プラスチックの中に中空の状態等のものが含まれる場合には埋立地の安定性を損ない跡地利用の支障となるおそれがある、?リサイクルの可能性のあるプラスチックまでもが廃棄物として排出され埋立てられている、などの問題点が指摘されている。
製鉄産業では、この廃プラスチックを製鉄の過程における高炉での鉄鉱石の還元剤として利用することに取り組み始めている。通常高炉では鉄鉱石の還元剤としてコークスを用いているが、このシステムは、コークスの替わりに廃プラスチックを使用し、廃プラスチックを破砕・造粒し還元剤として高炉に吹き込むものである。既に、産業廃棄物の中間処理リサイクル施設として稼働しているものもあり、今後は、家庭から排出される廃プラスチックのリサイクルについても検討が開始されている。
廃プラスチックを高炉の還元剤として活用することで、最終処分に回され埋め立てられる廃プラスチックの量を削減することができ、最終処分に伴う環境負荷が低減できるとともに、還元剤として使用しているコークスの量も同時に削減できるため、資源採取に伴う環境負荷の低減も期待し得る。さらに、この工程を採用することによりコークスを使用する場合に比較して、CO2の発生が約2割削減できると言われている。
イ セメント産業の動き
セメント産業は、使用する原料や燃料に幅がある(弾力性がある)という特性を活かし、火力発電所から排出される石炭灰、自動車の古タイヤ、鉄鋼業から排出されるスラグ、廃プラスチック、さらに廃パチンコ台など産業廃棄物として排出される多くのものを、原料や燃料として利用してきている。平成8年度に生産されたセメント量は約99,267,000tで、それに使用された産業廃棄物・副産物の状況は第1-1-4表のとおりで、高炉スラグ、石炭灰、副産石こうが70%以上を占めている。
セメント製造工程では、原料を1,450℃前後の高温で焼成するため、ダイオキシン類の発生も抑制することが可能であり、2次処理すべき残さもほとんど残らない。(第1-1-12図)
セメント産業では、原料や燃料としての受け入れ方針として、?原料の運搬・貯蔵・処理工程で粉塵や悪臭等新たな環境問題を発生させないこと、?セメントの品質に悪影響を及ぼさないこと、?原料や燃料として、質、量ともに安定供給が確保されること、などとしている。
セメントの品質を低下させたり、製造装置を腐食させるものとして、塩素がある。現在は、原料として使用される焼却灰などに含まれる塩素を除去するための研究が行われている。
また、セメント産業等では、最終処分の対象でしかなかった一般廃棄物の焼却灰や下水汚泥を原料としたセメント生産技術の研究開発も進められている。
このようなセメント産業等の動きは、最終処分として埋め立てていた廃棄物を、原料や燃料として大量に使用することで、最終処分にかかる環境負荷の大幅な低減を図ることを可能にするとともに、併せてセメント原料としての天然資源の採取に伴う環境負荷の低減を図ることも可能とするものであり、今後、取組の一層の拡充が期待されている。
ウ 自動車産業の動き
社団法人日本自動車工業会では、使用済み自動車のリサイクルの促進やシュレッダーダストの削減を主要課題の一つとして取り組んできた。また、各自動車メーカーも同様の取組みを進めてきているが、こうした動きに一層拍車をかけるため、平成10年1月に日本自動車工業会として?新型車のリサイクル率の向上、?有害な物質の使用の削減への努力、?関連事業者が行うリサイクルの促進・シュレッダーダストの発生削減などを盛り込んだ自主行動計画を策定した。各自動車メーカーはこの自主行動計画を基に各社独自の目標を掲げ、自動車のリサイクルや有害な物質の削減等の取組を始めている。このような自動車産業の動きは、関連産業の多さやその広がりから、多方面におけるリサイクルの進展等の面で大きな期待が寄せられている。
囲み1-1-7 シュレッダーダストのリサイクル
大手自動車メーカーでは、シュレッダーダストとして最終処分場に埋め立てる量を減量化するためのプラント建設を開始した。
プラントでは、シュレッダーダストを12の素材に大別し、さらに再資源化工程を経て純度の高い素材を抽出する。この工程で生まれた再資源化(再生)物は、新車用の防音材や建築用タイルの強化材などとして利用されている。
さらに、リサイクル性に優れた素材の開発や取り外しやすい部品設計、有害物質の低減なども行われ、解体により得られた情報を生産工程に反映させるシステムも稼働し始めている。
(3) 地域社会における新たな取組
市町村における廃棄物処理をはじめ同様の方法を採る産業廃棄物処理などの現場においては、既に見てきたようにダイオキシン類対策などによる焼却方法の適正化や適正な最終処分の確保などが最近の大きな課題となってきている。例えば、焼却の際に発生するダイオキシン類を極力抑制するためには、ごみの排出抑制やリサイクルによって焼却量を減らすことがまず重要であるが、焼却時には適正な温度管理が必要であり、そのためには24時間連続運転の焼却処理が有効な手段となる。一度焼却炉の温度を適正温度まで上昇させたら、できるだけ長時間その状態を保つ必要があるため、小規模のごみ焼却施設をできるだけ集約化して、連続運転が可能な大型のごみ焼却施設に転換する必要が生じてくる。このようなダイオキシン類対策では、高度な焼却処理技術が要求されていることから、小規模市町村が単独で処理施設を運営する場合などでは、財政的にも技術的また人的にも困難な状況となることも予想される。
ダイオキシン類対策に加え、焼却の際に発生する熱を有効利用する観点からも、ごみ焼却施設を全連続式とすることが必要である。これによりごみ発電等の余熱利用を効率的に実施することができ、一次エネルギーの代替を図るとともに、地球温暖化の防止にも資することができる。さらに、公共事業コストの縮減の観点からも小規模なごみ焼却施設を多数整備するよりも、可能な限りごみ焼却施設を集約化することの方が望ましい。
これらのことから、今後の廃棄物処理は、市町村域を超えた広域処理により行う必要がある。
産業廃棄物の場合においては、処理の高度化やリサイクルの組み込みを進めるに当たって、廃棄物(要処理物)、再生資源や再資源化(再生)物の広域流通が適切に確保されることが、産業としての原料調達や市場の確保拡大の観点からも必要な前提と考えられる。
また、ダイオキシン類をはじめとした有害な物質の発生排出を抑制するようなより安全かつ高度な技術を活用した処理や重金属の再生等のリサイクルの組み込みには、民間企業との連携等が必要かつ有効なものとなることが考えられる。
さらに、先に述べた最終処分の規制強化や市町村による最終処分状況の見直しなどを受け、最終処分の適正化のみならず、中間処理の高度化やリサイクルの組み込みを徹底していくことによる最終処分量の削減・最小化へ向かう動きが強まり広がっていくことが考えられる。
ア 廃棄物固形燃料化の採用
生ごみや廃プラスチックなどのリサイクルの一つの方法として、廃棄物固形燃料(RefuseDerived Fuel:RDF)化が注目されている。廃棄物をRDFにすることで、臭いも抑えられ、圧縮・成形することにより容量が大幅に削減され運搬等が容易になる。また、乾燥により水分を減少させ、粉砕して均質化することにより品質が安定するため、長期間の保存が可能になるとともに、焼却時の熱効率も高くなる(発熱量は生ごみの7倍で安定している)。このため、効率的な処理が可能になるとともに、廃棄物をそのまま焼却し熱回収するよりもより効率的な熱回収が可能になる。また、高温による完全燃焼を行いやすく、適正な設備で燃焼管理を行えば、ダイオキシン類の排出抑制対策にも資するものと考えられている。したがって、適正な条件の下でRDFを活用していくことが期待されることから、RDFが燃料として一般に利用される場合にも適正な設備整備と燃焼管理が行われる必要があり、その推進に当たっては、RDFの製造方法や使用用途・方法等について適切に検討していく必要がある。併せて、RDFの性状の均一化、組成の違いによる環境負荷についての技術評価等を進めていく必要がある。
既に、一部の自治体ではRDF施設の導入に取り組みはじめており、製造されたRDFの多くは、地域の公共施設や民間企業の熱源として利用されている。また、RDF発電の構想を県レベルで計画しているところもある。(第1-1-13図)
例えば、大分県津久見市では、清掃センターの焼却処理施設の更新に当たり、ダイオキシン類対策等を検討する中で、同市にあるセメント工場からの「廃棄物の固形燃料化により工場での燃料としての利用が可能」との申し出を受け、ダイオキシン類等の環境負荷の低減とともに併せて最終処分場の延命化の観点も含め、廃棄物を固形燃料化した上でセメント工場で利用することとし、平成9年1月から、従来の廃棄物焼却処理施設に替えて新たに固形燃料化施設を稼働した。この施設で生産されたRDFは、市内のセメント工場で燃料として利用され、利用後の焼却灰もセメントの原料として活用されている。同市のこの取組は、廃棄物の処理・リサイクル対策を、民間企業との適切に連携の下に行うことにより、環境負荷の低減とともに資源の有効活用が併せて図れることの一例を示している。
イ 処理技術の高度化−溶融固化、ガス化溶融等の導入−
焼却処理における燃焼過程の高度化や焼却灰の減量化等に向けた技術開発が進みつつあり、単純な焼却中間処理−焼却灰埋立最終処分というこれまでの廃棄物処理システムの変化を受けた技術の開発・普及が進みつつある。溶融固化の技術がその代表的な一つである。
溶融固化とは焼却灰等の廃棄物を加熱し、概ね1200℃以上の高温条件下で有機物を燃焼させるとともに、無機物を溶融した後冷却しガラス質の固化物(溶融固化物)にする技術であり、重金属の溶出防止及びダイオキシン類の分解・削減に有効であるとされている。
さらに、焼却と溶融を総合し一体化した新たな技術としてガス化溶融が注目されている。このガス化溶融は、廃棄物をいったん熱分解し、熱分解ガスと固定炭素(チャー)を含んだ無機物に分離し、熱分解ガスとチャーの燃焼熱を利用して無機物を溶融し溶融固化物化する方法で、これを行うガス化溶融炉はごみを蒸し焼きにするガス化炉と溶融炉が一体のものとして構成されている。このガス化溶融の溶融固化に追加すべき利点は、?廃棄物の熱分解に必要な温度は300〜350℃であり、可燃ガスそのものの生成には高温を必要としないため、アルミの溶融や鉄、銅の酸化などを回避でき、これらの金属を有利な条件で回収することが可能となる、?排ガス量をより少なくできる、?高温排ガスからの熱回収により高効率発電が可能になる、などである。
溶融固化物の有効利用を進めることは、最終処分量の削減やそれによる最終処分場の延命化の観点から、環境保全上有効な取組であり、その品質が確保されれば道路路盤材やセメント骨材等の土木建築資材などへの利用が可能であるが、特に路盤材など環境に直接接触する形で利用する際には有害物質の溶出等の環境汚染への配慮が必要となる。したがって、環境と直接接触する形での再生物の有効利用を進めるに当たっては、このような環境への影響の評価を行う必要があると考えられる。
厚生省では、平成10年3月に、溶融固化物に係る有害物質溶出の目標基準を含め生活環境保全の観点から溶融固化の実施に当たり遵守することが望ましい事項を「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」として定め、地方公共団体に通知することにより、溶融固化物の環境保全に十分留意した適正な利用の促進に資することとした。
ウ 複合機能廃棄物処理・リサイクル施設−札幌市リサイクル団地−
排出事業者等によるリサイクルの取組が強化されつつあるとともに、いくつかの市町村においても新たな廃棄物の高度処理・リサイクル施設の導入等の動きが出始める中で、産業廃棄物と事業所等から排出される事業系一般廃棄物の適正処理やリサイクルを、行政と事業者が協力して展開している「札幌市リサイクル団地」の事例が改めて注目されている。
この札幌市のリサイクル団地は、事業系の廃棄物の中でも特に建設系の産業廃棄物を中心とした各種の処理・リサイクルを総合的に推進する施設の集合体として計画され、それぞれの施設を有機的に関連させて効率性等の向上を図ろうとしている。特にこの団地は「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき厚生大臣等の認定を受けており、これにより無利子融資等の優遇措置を活用した産業廃棄物処理施設の整備が図られ、さらに緑地、野球場等の公共施設を併設することにより地域に密着したリサイクル施設を目指していることが注目される。平成8年1月に第1号施設が稼働して以来、現在までに7つの施設が稼働しているが、リサイクル団地の建設に当たって、廃棄物処理・リサイクルの経済性からみて、?採算性が完全に見込めるものは民間企業が行い、?採算性の見込みはないがリサイクルの必要性が高いものは市が行い、?採算性において??以外のものは第3セクターが行う、という3つに区分して施設立地等を計画し、複合的に事業展開を図っていこうとしている。(第1-1-14図)
現在、団地内では事業系生ごみを脱水・乾燥、プレス、脱油といった処理を経て粉末化する民間業者によるリサイクル施設が稼働している。この粉末化されたものは、養殖魚の飼料の原材料として利用されている。また、第3セクターが運営している建設系廃棄物リサイクルセンターでは、建設物の解体に伴う建設系混合廃棄物の選別が行われ、金属類は売却、可燃物は市のRDF製造施設に持ち込まれた後、熱供給公社に燃料として供給されている。
札幌市では、札幌市リサイクル団地を、市内の各種廃棄物を再利用や再資源化していくための中核施設として位置付け、今後も積極的に新たな施設の立地を推進していくこととしている。
これらの事例にもそれに向けた動きが見られるように、処理の過程でリサイクルを最大限組み込んでいくためには、民間企業との連携等を含めより効率的かつ高度な廃棄物処理・リサイクルシステムの構築が求められている。さらには、ドイツやデンマークなど海外の事例における有害な廃棄物の適正な処理管理とリサイクル可能廃棄物の市場原理を導入した効率的経済的な処理・リサイクルとを両立させた手法なども踏まえ、新たな高度処理・リサイクルのシステム化等のあり方などについて、企業や市民も含め幅広い観点から検討していくことが必要となってきているといえる。
(4) 循環型経済社会の形成に向けて
これまで述べてきたとおり、廃棄物の問題は、資源採取から廃棄に至る社会全体の問題であり、それぞれの段階での主体の問題でもある。我が国においても、廃棄物の適正処理の確保のための規制等の強化・充実や、リサイクルの促進に向けた新たな制度の整備、各主体の創意工夫を活かした新たな取組などが進みつつあるが、このような問題への対応を「廃棄物処理」という形で最下流にしわ寄せするシステムには限界がある。例えば、ドイツを始め欧米の先進的な諸外国を中心として,廃棄物処理とリサイクルを一体として捉え,全体として廃棄物に係る環境への負荷を低減していくための枠組みを整備するとともに、OECD等において拡大生産者責任(製造物に関する廃棄・処分に至るまでの環境負荷の低減に関する責任を生産者等に課すという考え方)など、新たな考え方について議論が行われている最中である。
今後は、モノの流れの全体を国内外を含めて捉え、上流から下流に至る関係者の適切な役割分担の下、モノの利用から廃棄に伴う環境負荷を総合的に低減するための循環型社会を形成していく時期に来ているのではないだろうか。廃棄物をめぐる問題は我々一人ひとりの生活や経済活動と切り離せない問題であり、今後、広範な国民的議論を進めていく必要がある。
囲み1-1-8 中央環境審議会「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について」第1次答申
廃棄物に係る環境負荷を低減するため、環境との直接の接点である最終処分の在り方を基点として総合的かつ体系的な廃棄物対策について検討する必要があるとの認識の下、平成8年11月、環境庁長官は、中央環境審議会に対し、廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について諮問を行った。これを受け、平成9年11月、中央環境審議会から第1次答申が出され、その中で、最終処分の基準等の一部改定や有害物質を含む使用済み製品に起因する環境負荷削減対策のほか、環境保全のための総合的な廃棄物削減・物質循環促進が行われる物質循環社会の形成について提言がなされた。