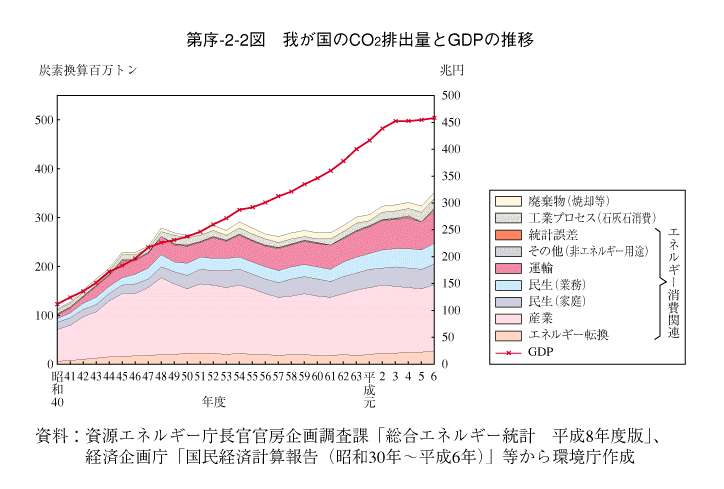
2 変革の方向性
経済社会システムを循環と共生を基本に据えたものに変革するためには、何を行う必要があるのだろうか。
かつての産業公害問題について、我が国では「技術」と「制度」を変革することによって対処した。まず、この「技術」と「制度」による変革について考察することにする。
(1) 技術の変革
技術の変化は社会に様々な影響を与えているが、環境への影響もその一つである。技術革新によって生み出されたものが、例えば公害という形で人の健康被害を招いた場合もあれば、新たな生産技術が結果的に環境に大きな負荷を与えた場合もあった。しかし、これは技術革新自体の罪というより、そのような健康被害や環境負荷を与える技術を生み出し、また使ってしまった人間や社会の側の問題というべきだろう。
現在では、むしろ様々な環境保全のための技術が開発されている。後に触れる低公害車の開発などはそのいい例であり、技術革新こそ環境保全の切り札であるという考え方をする向きもあるだろう。しかし、その際留意しなければならないのは、環境の一側面を画期的に改善するものであっても、他の側面を大きく悪化させるような技術は不適当であるということである。例えば、CFC(クロロフルオロカーボン:いわゆるフロンの一種)は、それ自体は人の健康に無害なものとして開発され、また、化学的不活性、不燃性等の観点から優れた特性を有し、冷媒、洗浄剤、発泡剤等として普及が進んだが、後にオゾン層を破壊することが判明し、地球規模の環境問題が発生することが新たに分かったので、世界規模で生産規制が順次行われ、先進国においては生産が全廃されるに至った。同様に、例えば二酸化炭素の排出を減少させる技術であっても、それが他の環境負荷を大きく増すものであれば不適当であるだろうし、廃棄物を全くゼロにする技術であってもそれに伴い大量のエネルギー消費を伴うものがあればこれも適当とは言えないだろう。
このように、技術による変革は重要な要素であるが、実は技術を求める側である我々社会の側の価値観や制度も同時に変わることによって、環境の方向に向いた技術の開発が行われるのである。
(2) 制度の変革
技術とともに経済社会システムの変革のための手段として必要なのは、制度の変革である。ここでは、規制や経済的手法等の行政が定める「制度」とともに、通信システム、電気システム、交通システムなどの公的又は準公的なインフラ設備についても「制度」として取り上げる。
ア 規制
規制は、法律等に基づいて社会に強制力を及ぼし、環境汚染物質の排出量などを確実にコントロールしうる最も基本的な制度である。これは、かつての激甚な公害問題などのように、原因と被害との因果関係が明確であり、汚染源が特定され補捉が可能である場合には非常に有効であり、自動車排出ガス規制のように技術の変革をもたらすという効果を有することもある。
最近注目されている規制の実例としては、米国カリフォルニア州における電気自動車など排出ガスを出さない車(ゼロエミッションビークル)の導入(販売)規制がある。これは、同州で自動車を販売するためには、2003年から同州での販売台数の10%をゼロエミッションビークルにしなければならないというものである。このように将来の規制を明示することは、規制のクリアのための技術的進歩に大きな効果があると考えられる。
イ 経済的手法
経済的手法とは、市場メカニズムを通じ経済的な誘因を与えることにより、各経済主体が環境保全に適合した行動をとるよう促そうとするものである。経済的手法には、補助金、融資、税制上の特例措置といった経済的助成措置や環境に係る税、課徴金、排出権取引、デポジット・リファンド制度などの経済的負担を課す措置がある。経済的負担を課す措置については、多数の日常的な行為から生ずる環境への負荷を低減させるという点で有効性が期待される。
経済的手法のポイントは、市場経済の価格メカニズムを活用すること、すなわち、市場メカニズムを通じた各主体の自主的かつ合理的な選択に依拠したものであり、資源の効率的配分にも資すると考えられている。
ウ インフラ等の整備
インフラは社会の基盤となる制度・システムである。インフラには、鉄道や道路等の交通インフラ、水道・電気・ガス・通信等の産業インフラ等があるが、我々のライフスタイルはこれらのインフラがその一面を規定していると言っても過言ではなく、循環型の経済社会システムへの変革を進めるためには、環境保全を踏まえたインフラ整備が行われる必要がある。
例えば、中長距離の地域間幹線輸送において、トラック輸送からエネルギー効率が良く二酸化炭素排出量の少ない輸送機関である鉄道及びRORO船等の海運への誘導を推進するためのインフラ整備を重視するとともに、トラック輸送についても物流拠点、物流情報システムの整備等のインフラ整備を進めていく必要がある。
(3) 価値観の変革
かつての産業公害のように加害者が企業や事業者のように特定される場合には、上記の「技術」「制度」を変えていき、問題となる部分について対処すれば克服することができた。しかし、地球温暖化問題のような我々の日常の生活や事業活動自体が原因となっている問題については、「技術」「制度」だけで対処することは不可能であり、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムを形成する根本となっている我々の意識、「価値観」が変わる必要がある。技術や制度を開発しあるいは作り出していく主体である我々の意識、価値観が変わるならば、それが技術や制度をさらに変えていくきっかけとなるであろう。
例えば、今所有しているものをレンタルで済まないか見直してみたらどうだろうか。自動車も買うのが当たり前と思うのではなく、公共交通機関やレンタカーを使う。あるいは、数世帯単位で共用の自動車を所有するようにする。その方が環境への負荷が少なくなるばかりでなく、総費用で見た場合安く済む場合が多いのではないだろうか。そのような考え方をする人が多くなれば、より利用しやすくするための様々な制度が提案されてくるだろう。また、冷蔵庫も所有することにこだわらなければ、外気をうまく利用し、長期間の使用に耐える、家具のような家に備付けの冷蔵庫を利用することによって環境への負荷を大幅に減らすという構想が既に提案されている。
では、その価値観の変革はどのようにして進められるものなのだろうか。世界中の人々の価値観を強制的に変えるということは、およそ不可能なことであると思われる。しかし、先に述べたとおり地球環境が有限なものであり、現在の成長を続けることが不可能であることが認識できれば、物質的な欲望を中心とした価値観をそのままにできないということも認識できるのではないだろうか、と考えることもできる。そのような地球的な視野での思考を助ける一つの道具として、インターネットをはじめとする情報システムの活用が期待される。
また、価値観の変革には、我々の経済社会システムの基盤となっている技術や制度の支援が不可欠であると思われる。一般に、個々人は社会の制度や技術の水準に受け身である場合が多い。したがって、新しい価値観がさらに広く人々に共有されるようになるためには、価値観の変革を支える様々な制度や技術の変革、例えば教育の充実やライフスタイル変更の基礎となる技術開発などを並行的に進めていくことが求められる。
(4) 変革と経済成長
上記のような変革を進め、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムから脱却しようとした場合、経済成長が減速し、不況が恒常的に続くことを懸念するむきがある。例えば、地球温暖化防止京都会議では、途上国に温室効果ガスの排出抑制の取組を求めた際、途上国側は「温室効果ガスの排出量を抑制すれば経済成長に悪影響を及ぼす」として反対し、結局途上国の温室効果ガス排出抑制については何ら規定できなかったということがあった。
しかし、このような変革を進めつつ、経済成長を果たすことは十分可能なことである。例えば、我が国においては、これまでの経済成長の過程、特に1973年(昭和48年)の第1次石油ショック以降、1980年代半ばまでの期間は、技術開発をはじめ様々な省エネのための試みが行われたことにより、経済が成長する一方で二酸化炭素の排出抑制に成功している(第序-2-2図)。また、昭和50年代前半に自動車の排出ガス規制の大幅な強化が実施された際、我が国では官民挙げて低公害化の取組を行ったことにより達成したが、これによって我が国自動車産業は公害防止のためばかりではなく、燃焼制御技術の進展や品質管理法の改善といった副次的、波及的な技術開発をももたらし、圧倒的な競争力を得ることにつながった。このような例から見て、上記の変革を進める場合にも、経済成長を阻害せずに行う可能性は十分にあるものと考えられる。
経済成長と変革とを両立させる一つの鍵は、エコビジネス(環境保全に関する事業活動)の推進である。エコビジネスは、環境への負荷の少ない製品やサービスを提供することや、環境保全に資する技術やサービスを提供しこれまでの製品の生産過程等をより環境への負荷の少ないものに変えるといったビジネスを指す。エコビジネスが産業として成長し利益を上げつつ、大量生産・大量消費・大量廃棄からの脱却の原動力を担うことができれば、経済成長の中身を環境保全的なものに変えることを通して、変革を行いつつ経済成長を果たすことが十分可能となるであろう。
平成9年5月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」(同年12月に第1回フォローアップを実施)では、今後成長が期待される産業分野として環境関連産業が採り上げられている。同行動計画では、環境関連産業として具体的に、エコマテリアル、低公害車等の環境調和型製品製造業、廃棄物処理・リサイクル産業、公害防止装置、廃棄物処理・リサイクル装置、環境分析装置等の環境関連装置産業、土壌浄化、水質浄化、都市緑化等の環境修復・創造産業等が挙げられている。その雇用規模、市場規模については、環境関連産業の範囲は一般的に定まったものではないため、一つの見通しではあるが、現状それぞれ約64万人、約15兆円であるところ、2010年には140万人程度、37兆円程度まで拡大するものと予測されている。
そのうちの廃棄物処理や再利用、リサイクルといったいわゆる静脈産業は、従来、製品を生産するいわゆる動脈産業の陰に隠れた存在であったが、廃棄物処理の規制強化や再利用、リサイクルが推進されることにより、この分野の市場規模は拡大しつつある。今後、先に述べたような循環型経済社会システムを構築する際、この静脈産業が産業として成立し、廃棄物の高度処理、再利用やリサイクルを推進する原動力となれば、経済社会システムの変革を行いつつ経済成長が進むことが期待できる。
モノの生産により経済成長を図るのではなく、エネルギーや資源の大量消費を伴わないサービスを中心に経済成長を図るということも一つの有力な考え方である。例えば、コンピューターソフト産業などはこれに該当するであろう。
しかしながら、このような変革により成長する産業がある一方で、従来型の大量生産・大量消費・大量廃棄により成長ないし維持できていた産業が衰退することによる悪影響が生じるのではないか、という懸念も考えられよう。従来型の産業が永遠に維持できるのであればその懸念ももっともなものと言えるが、先に述べたとおり、地球温暖化問題や資源の制約等の要因によりそれが不可能であるからこそ、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムを変革しなければならないのである。この変革は短期的にみれば、有利になる産業と不利になる産業、つまり勝者と敗者が生じることにより、雇用や設備投資にミスマッチが一時的に生じうる。しかし、このような変革が不可避であることが明確になれば、雇用や設備投資を先行してシフトさせることにより、変革による経済への影響・ミスマッチは最小限に留められるのではないだろうか。
もとより、経済社会システムは時代とともに大きく変化するものであり、過去我が国の経済成長はその変化を先取りしてきた者によって支えられてきた。先の京都会議で採択された京都議定書は、人間活動に伴い生じる二酸化炭素を大きく減少させなければならないということを明確にしたという点で、我が国をはじめとした先進国の将来の経済社会システムの変化の方向を示す重要なマイルストーンであるとも言える。
(5) 環境国際貢献の充実〜途上国支援を中心に〜
循環と共生を基本に据えた経済社会システムへの変革は、地球規模での環境への影響が問題になっていることからみても、当然、我が国や先進諸国に限定して行えばよいという性質のものではない。これから経済成長を目指している途上国が我が国や他の先進諸国のような大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムを築き上げた場合、それによる環境負荷は膨大なものになることが容易に想像できる。仮に途上国を含む世界全体が米国並みのエネルギー消費を行ったとすると、世界のエネルギー消費量は現在の6倍に達することになるが、これはエネルギー供給能力や資源埋蔵量からいっておよそ実現が困難であると思われる。そのため、現在行われている途上国への援助も、循環と共生を基本に据えた経済社会システムを念頭に置き、その実現を目指すというビジョンを描いて行われるべきであろう。
また、このような変革の実現を図るためには、地域間の協力や政府の政策調整が円滑に進められることも必要であるが、このためには国や社会セクター間の利害を超えた立場で、各国の政府・自治体・国際機関等の政策や企業・NGO等の行動に具体化される戦略づくりを如何に支援するかが重要となってくる。平成9年(1997年)6月開催された国連環境開発特別総会(UNGASS)において、我が国は橋本総理大臣により「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」を表明した。これはODAを中心とした環境協力の更なる充実を図っていくため、我が国の環境協力の基本理念と今後の協力の柱となる行動計画を取りまとめたものであるが、この中で、上記の戦略づくりを行うための政策的・実践的な機関としての「地球環境戦略研究機関」による戦略研究の国際的なネットワークづくりを進めることを明らかにした。さらに、9年12月には京都において「地球環境戦略研究機関設立憲章」の採択・署名会合が開催され、中国など10カ国の政府、4の国際機関及び18の研究機関が署名を行った。この設立憲章に基づき、10年3月31日には我が国の民法法人たる「地球環境戦略研究機関」が神奈川県(湘南国際村)に設立され、平成10年度より研究事業を開始した。