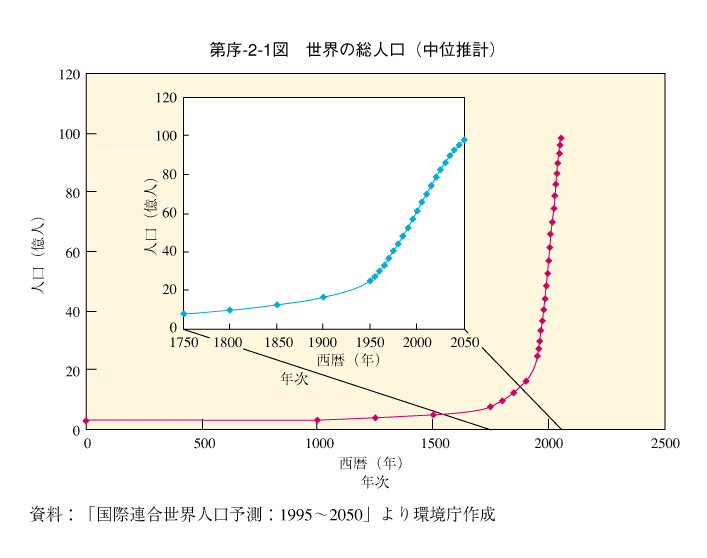
1 巨大な環境負荷を招く先進国社会の限界
(1) 人類の活動拡大と環境への影響
人類の活動は、古くは他の動物と同じように、生態系の中では微々たる存在であり、むしろその厳しい自然の中でいかに生き残るかが問題であった。しかし、人類が様々な道具を用い、集団で大規模な活動を行うようになるとともに、人類の活動が環境に影響を及ぼすことが多くなってきた。
平成7年版環境白書においては、古代文明が環境に影響を与える活動を行うことにより、環境を一定の限度を超えて損なう場合にはそれが一因となって文明の基盤そのものが失われ、文明が衰退していった例を見てきた。例えば、紀元前2000年の初め頃から発達したクレタ島のミノア文明は、豊富な森林資源をもとに、森林を燃料として土器や青銅器を作り、また船を造り木材や土器、青銅器を輸出することによって繁栄した。一度大地震に逢い宮殿が崩壊したときも、見事にこれを再建した。しかし、文明が発展し人口が急増していくうちに森林資源は次第に枯渇し始め、火山の大噴火とそれに伴う大津波に逢って再び宮殿が崩壊したときには、もう宮殿を再建するだけの森林資源は失われてしまった。加えて、森林破壊によって土壌が劣化、穀物の収穫量が減少し、土器や青銅器を焼く燃料にも事欠くようになってしまい、ついにミノア文明は滅亡するに至ったのである。
しかしながら、ある文明が衰退した場合でも、他の地域に別の文明が生まれ発展していくことにより、文明人としての人類の歴史は脈々と続いてきていた。例えば、ミノア文明が森林資源の枯渇によって滅亡に瀕しているとき、代わって繁栄したのは、やはり森林資源に恵まれたペロポネソス半島のミケーネ文明であった。このようにして、文明は時と場所を変えながら、繁栄を続けてきたのである。
ところが、時を経て西ヨーロッパにおいて発展した文明は、大航海時代とも言われる15世紀以降、世界各地に通商活動を大々的に行いはじめ、西ヨーロッパ以外の地域から資源を求めるようになり、通商活動を地球規模で拡大していった。それを更に押し進めたのが産業革命である。これは、化石燃料による動力機関が発明されたことを契機に、工場制の協業と社会的な分業が進められることによって生産性が飛躍的に向上し、自然の制約の中にあった従来からの農業生産社会の限界を脱したものである。この産業革命による工業化の進展が、大量生産・大量消費を可能にし、現在の世界の経済社会システムの基礎を作ったのである。
産業革命により人間活動の規模は画期的に拡大した。例えば世界の人口をみると、20世紀になり爆発的に増加したことがわかる。20世紀はじめには約16億5,000万人であった世界の人口が、現在はおよそ3.5倍の約60億人にまで増加した。国連の推計によれば、今後2015年には75億人、2050年には98億人にも達するとされている(第序-2-1図)。
このような大量生産・大量消費・大量廃棄を可能とする経済社会システムへの移行や人口増加等に伴い、二酸化炭素等の温室効果ガスが気候に影響を及ぼし、地球温暖化を招くほどまで増加しつつあることについては、既に第1節において述べた。さらにこれ以外にも、人間活動の規模の拡大に伴い食糧や水資源、森林資源、生物種に大きな影響を与えつつあることが指摘されている。例えば、これまでの穀物等の国際需給についてみると、需要は毎年増加する世界人口と経済成長に伴う食生活の向上により増加してきているのに対し、供給面では主要輸出国あるいは大消費国における作柄変動等があったことから、過剰とひっ迫を繰り返してきている。また、世界の水の消費量は今世紀半ばから3倍に増え、なおも増加し続けており、一部の国では既に灌漑用水の不足のために穀物輸入を増加させているともいわれている。森林資源については、今世紀半ば以来木材消費量は3倍、紙消費量は6倍になっており、この1世紀の間に世界中の原生林の半分近くが失われた。生物種についても、地球上に生息する約1万種の鳥類のうちの1,000種以上、約4,400種の哺乳類のうちの約1,100種が絶滅のおそれがあり、また魚類についても淡水魚と海水魚を含む全ての魚種のうち3分の1が絶滅のおそれがあるとされている。
以上で見たように、現代の経済社会システムは、古代文明と同様、一定の限度を超えて環境を損ないつつあると考えられる。古代文明の滅亡は地球全体からみれば一部の地域のものに過ぎなかったし、新しい土地でやり直しができた。しかし、地球規模に拡大した現代文明は、このようなやり直しはできないのである。
(2) 「循環」と「共生」の経済社会システムへ
それでは、現代の大量生産・大量消費・大量廃棄の経済社会システムが上記のように地球規模で環境に大きな影響を与えてしまった原因は何であろうか。
人間は自然界から得た物質を使って生産活動を行い、それを消費した結果生ずる廃棄物をまた自然界に戻しているが、従来は主に太陽からのエネルギーの供給を受けて生育した森林や食物などを使って生産活動を行い、廃棄物も様々な生物の生産活動に使われるという物質循環がきちんと成り立っていた。しかし、現代の経済社会システムでは、過去何億年、あるいは何十億年という歳月を経て蓄積されてきた化石燃料や資源を大量に使いつつあり、それは決して短時間で戻されるものではない。また、自然生態系の中で分解できる量をはるかに超えた大量の廃棄物があふれ、それが環境への負荷を与え様々な環境問題を引き起こしている。廃棄物の量的増加・質的多様化に伴う処理処分における有害物質による環境汚染の問題や、化石燃料の大量消費の結果生じる二酸化炭素等の増加による地球温暖化の問題も、このような環境問題の一つの例といえるであろう。
これを避けるためには、まず第一に人間の活動によって生じる物質を自然界の中でうまく循環できるようにし、環境への負荷を少なくしていくことが必要であり、さらに第二には、人間活動が上記のように自然からの恵みを受けた上で初めて行われることを踏まえ、自然界のメカニズムを理解して、自然との共生が図れるよう、人間活動を自然と調和させることが必要である。
我が国は、このような視点を踏まえ、我が国の社会を環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会へ変革し、物質循環と自然との共生を確保する経済社会システムへの転換を図ることを目指して、平成5年に環境基本法を制定、平成6年にこれに基づく環境基本計画を策定して様々な施策を推進してきた。その中で少しずつではあるが経済社会システム転換の芽は出始めてきている。しかし、地球温暖化防止に関連して第1節にも述べたとおり、経済社会システム転換の芽を根付かせ、大きく育てていかなければ、この危機は乗り越えられないのである。
地球規模で環境に大きな影響を与える現代文明、経済社会システムを変えずにこの危機をしのごうとした場合、仮に我々の世代は可能であっても、次の世代においてはかなりの困難が予想される。例えば、二酸化炭素の排出削減についてみると、第1節にも触れたように、地球温暖化の進行を抑えるためには、世界の人口が大幅に増加し、途上国が大幅な経済成長を図ろうとする中で、21世紀末には現在の二酸化炭素排出量と同レベル以下にしなければならないが、我々の世代がこのままのペースで二酸化炭素の排出量増加を続けた場合、地球温暖化の進行を同様に止めるため21世紀末に必要な二酸化炭素の排出レベルは、さらに達成困難なものになることが明らかであろう。また、大気への温室効果ガスの蓄積、森林資源や生物種の減少等は、確実に我々の子孫の世代(将来世代)のために残す資源を食いつぶしてしまい、将来世代はそのことによる不利益を一身に受けることになる。
将来世代は、地球温暖化防止やその他の資源の減少の問題のような自らの生活にかかる問題について、我々の世代が行う意思決定に参加することはできない。その際、将来世代の生存可能性を低くし、取りうる対策について選択の幅を狭めることをしてはならないよう、我々の世代は責任を持つべきであり、将来世代の生存権を奪ってまで我々の世代が現在の大量生産・大量消費・大量廃棄を招く生活をする権利はない、という考え方は一定の妥当性を有するものと考えられる。
我々の世代が将来世代の生存権を奪うことを避けるためには、変革を先延ばしにすることはできない。今こそ、経済社会システムを大量生産・大量消費・大量廃棄型から、物質循環を確保し、かつ自然のメカニズムを踏まえ自然との共生を確保した、「循環」と「共生」を基本に据えたものに変えるため行動する必要がある。