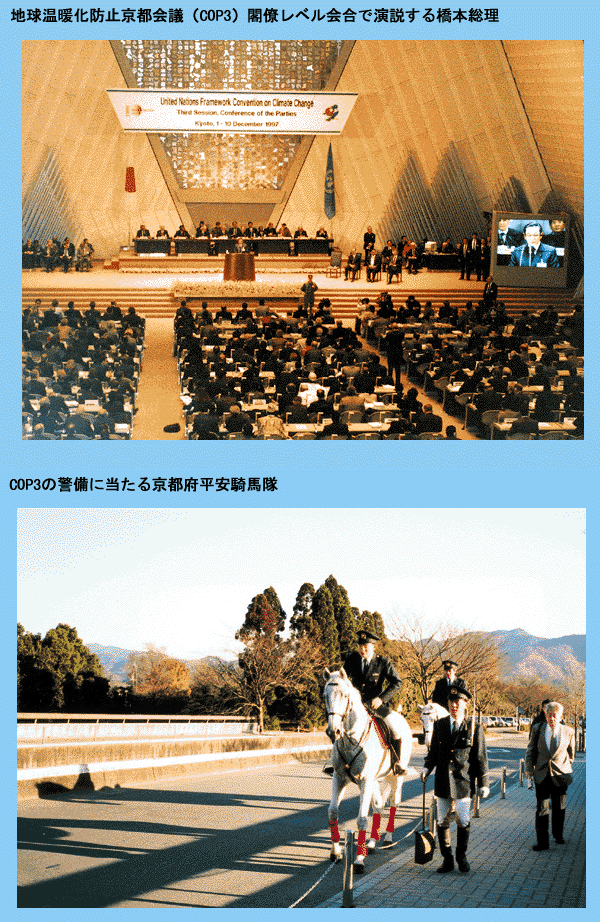
2 京都会議の開催
1997年(平成9年)12月1日、京都国際会館においてCOP3(地球温暖化防止京都会議)が開幕した。COP3参加のため京都に集まった158カ国の締約国政府代表団及び6カ国のオブザーバー代表団に加え、各国から集まったNGO及び報道関係者を含めると、参加者が計10,000人にも上る大規模な会議となった。
まず、冒頭に開催された本会議において、我が国の大木環境庁長官が議長に選出された。また、本会議の下に議定書の内容について検討を行う全体委員会が設置され、実務的な協議はこの全体委員会において行われた。全体委員会では、AGBM会合に引き続きエストラーダ在中国アルゼンチン大使(当時)が議長を務め、また委員会での協議と並行して別途詳細な協議が必要と判断される主要案件について非公式協議グループをつくり、その結果を全体委員会に報告するという議事進行形式がとられた。
第1週は各国の事務レベルによる協議が行われた。大きな論点となったのは、森林などの吸収源の扱い、HFC等の扱い、EUバブルの扱い、政策措置の規定、排出割当量の取引及び共同実施などの柔軟性のある措置、途上国の取組等である。当初は第1週において事務レベルで合意可能な事項をできる限り合意に持ち込み、数値目標の具体的数値などの重要交渉案件のみを第2週の各国閣僚などを含むハイレベルの代表団による交渉に委ねることが予想されていたが、第1週の交渉でも各国の意見の対立は解けず、第2週のハイレベルでの交渉に解決が持ち越された。
第2週は、第1週に引き続き、事務レベルによる全体委員会及び各種非公式会議のほか、閣僚などによるハイレベルの交渉が3日間にわたって行われ、これまでの2年余りの国際交渉に終止符を打つべく、公式・非公式の協議が精力的に行われた。協議は長引き、ようやく協議が終了し議定書の採択の機会となる最終の全体委員会が開催されたのは、本来の会期最終日である10日を過ぎた11日午前1時過ぎであった。
この全体委員会では、議長作成の議定書案をもとに、これまでの10日間の交渉でまとまったところを採択していく方式がとられた。しかし、途中、排出割当量の取引と、途上国の自発的な取組の2カ所で途上国側から反対があり、協議が大いに長引いた。一時は、議定書の採択を悲観視する見方も出たほどであった。
しかし、エストラーダ議長の采配もあり、何とかこれらの問題を乗り越え、11日午前10時、全体委員会において「京都議定書」の案が取りまとめられ、引き続き午後1時からの本会議において議定書が正式に採択された。