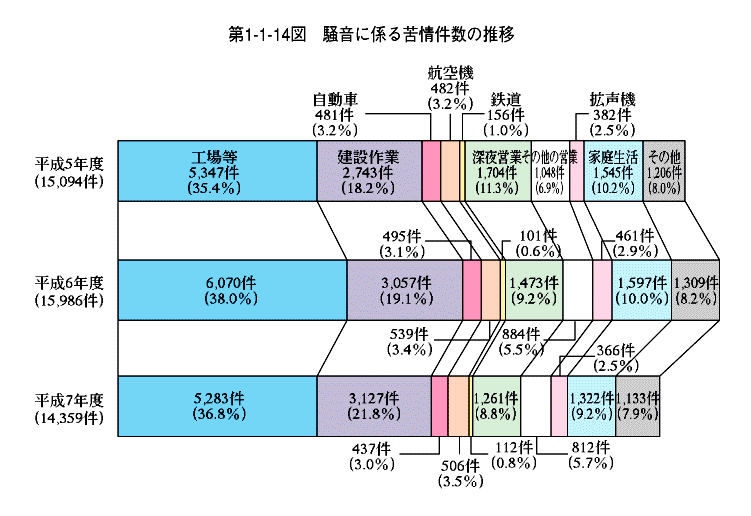
5 地域の生活環境に係る問題への対策
(1) 騒音・振動対策
ア 総説
(ア) 騒音・振動の現況
騒音は、各種公害の中でも日常生活に関係の深い問題であり、また、その発生源も多種多様であることから、例年、その苦情件数は公害に関する苦情件数のうちで最も多くを占めている。
騒音発生源の種類ごとに苦情件数をみると、工場・事業場騒音が最も多く、建設作業騒音、営業騒音、家庭生活騒音がそれに次いでいる(第1-1-14図)。
騒音苦情の件数は、平成6年度は前年度に比べ増加したが、ここ10年位は減少傾向にある。そのうち、建設作業騒音に対する苦情件数は、平成7年度はわずかながら増加した。
一方、振動は、各種公害の中で騒音と並んで日常生活に関係の深い問題である。苦情件数の推移をみると、ここ数年減少傾向にあったが、平成6年度及び平成7年度は前年度に比べ増加しており、平成7年度は2,742件であった。
その内訳をみると、建設作業振動に対する苦情件数が最も多く、工場、事業場振動に係るものがそれに次いでおり、苦情原因として依然大きな割合を占めている(第1-1-15図)。
(イ) 騒音に係る環境基準
環境基本法第16条の規定に基づき、「騒音に係る環境基準」が定められている。同基準では基準値を、一般地域及び道路に面する地域の2つに分け、それぞれにおいて地域の類型・区分及び時間の区分ごとに設定している。
基準値は、一般地域については「とくに静穏を要する地域」における「夜間」の「35デシベル以下」から「相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域」における「昼間」の「60デシベル以下」の間で、道路に面する地域についても「45デシベル以下」から「65デシベル以下」の間で、それぞれ地域の類型・区分及び時間の区分ごとに設定されている。都道府県知事は、類型を当てはめる地域の指定を行うこととなっており、平成7年度末現在で47都道府県において、605市、886町、100村、23特別区について地域指定が行われている。
また、現行の騒音環境基準では、騒音評価手法として騒音レベルの中央値(L50)を用いているが、その後、騒音測定技術が向上し、近年では国際的に等価騒音レベル(LAeq)が採用されつつあること等の動向を踏まえ、平成8年7月に中央環境審議会に対し「騒音の評価手法等の在り方について」が諮問され、同審議会騒音振動部会に設置された騒音評価手法等専門委員会において、最新の科学的知見の状況等に基づき、騒音環境基準の在り方及びこれに関連して再検討が必要となる基準値等の在り方について審議が行われている。
平成8年11月に同専門委員会の中間報告がとりまとめられ、同中間報告においては、騒音の評価手法としてこれまでの騒音レベルの中央値(L50)から等価騒音レベル(LAeq)に変更することが適当であること等が示されている。
(ウ) 騒音規制法による規制等
「騒音規制法」では、騒音を防止することにより生活環境を保全すべき地域を都道府県知事(指定都市・中核市にあってはその長に委任)が指定し、この指定地域内にある工場・事業場における事業活動と建設作業に伴って発生する相当範囲にわたる騒音を規制するとともに、自動車から発生する騒音の許容限度を環境庁長官が定め、さらに、都道府県知事は、都道府県公安委員会等に対して道路交通に起因する自動車騒音について対策の要請等ができることとされている。
都道府県知事(指定都市・中核市にあってはその長に委任)による地域指定は、平成7年度末現在で、47都道府県において、661市、1,240町、177村、23特別区について行われており、全市区町村数の64.5%である。
(エ) 振動規制法による規制等
「振動規制法」では、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を都道府県知事(指定都市・中核市にあってはその長に委任)が指定し、この指定地域内において工場及び事業場における事業活動並びに建設作業に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動について都道府県公安委員会等に対する要請を行うよう定めている。
都道府県知事(指定都市・中核市にあってはその長に委任)による地域指定は平成7年度末現在で、47都道府県において651市、869町、100村、23特別区について行われており、全市区町村数の50.5%である。
イ 工場・事業場及び建設作業による騒音・振動対策
(ア) 工場・事業場及び建設作業による騒音・振動の現況
騒音については、騒音規制法の指定地域内にあって金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(以下「特定工場等」という。)が規制の対象となるが、指定地域内の特定工場等の総数は平成7年度末現在で20万6,548である。
指定地域内において行われる建設作業であって政令で定めるくい打作業等の特定建設作業が規制対象となるが、平成7年度の特定建設作業実施の届出件数は4万304件である。
振動については、振動規制法の指定地域内にあって、金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場及び事業場(以下「特定工場等」という。)が規制の対象となるが、指定地域内の特定工場等の総数は平成7年度末現在で11万7,076である。
指定地域内において行われる建設作業であって政令で定めるくい打作業等の特定建設作業が規制対象となるが、平成7年度の特定建設作業実施の届出件数は、2万7,637件である。
(イ) 対策
a 工場・事業場
騒音については、指定地域内の特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(市町村長に委任。以下同じ。)は、特定工場等から発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合に、計画変更勧告や改善勧告、さらに改善命令を行うことができる。平成7年度中には、改善勧告が7件行われた。また、これらの騒音規制法に基づく報告徴収等の調査後における騒音防止に関する行政指導が1,035件行われた。
また、近年の苦情等の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るため、未規制施設等について騒音実態調査等を行うとともに、平成8年12月20日付で騒音規制法施行令を一部改正し、騒音規制法の規制対象となる特定施設として切断機(といしを用いるものに限る)を追加した(平成9年10月1日より施行)。
一方、振動については、指定地域内の特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(市町村長に委任。以下同じ。)は、規制基準に適合しない振動を発生することにより周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、計画変更勧告や改善勧告及び改善命令を行うことができる。平成7年度中においては、改善勧告、改善命令ともに行われなかった。なお、苦情に基づく報告徴収等の調査後における振動防止に関する行政指導が233件行われた。
また、振動に係る苦情のうち、法規制対象外の施設や建設作業を発生源とするものの割合が半数以上を占めている。そのため、振動公害対策に係る調査検討を行った。
なお、住工混在の土地利用により、現に騒音・振動公害が発生し、問題となっている地域では、遮音壁や振動防止施設の設置等の騒音・振動防止対策、当該地域からの工場・事業場の移転等が公害対策の重要な手段となっている。しかし、騒音・振動が問題となる工場・事業場の多くは中小規模であり、資金的な面等から移転が困難な場合が多いので、中小企業金融公庫等による工場移転についての融資、環境事業団による集団設置建物の建設が行われている。
b 建設作業
都道府県知事は、特定建設作業に伴い発生する騒音が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれると認める場合においては、騒音の防止の方法等に関し改善勧告又は改善命令の措置を行うことができる。平成7年度においては、改善勧告、改善命令ともに行われなかった。また、苦情に基づく報告徴収等の調査後における騒音防止に関する行政指導が713件行われた。
都道府県知事は、特定建設作業に伴い発生する振動が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれると認める場合においては、振動の防止の方法等に関し改善勧告又は改善命令の措置を行うことができる。平成7年度中においては、改善勧告等は行われなかった。なお、苦情に基づく報告徴収等の調査後における振動防止に関する行政指導が316件行われた。
建設作業の騒音・振動については、低騒音型建設機械・低振動型建設機械の開発・普及が進められている。
なお、建設作業に伴う騒音については、近年の苦情等の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るため、未規制の建設作業についても騒音実態調査等を行うとともに、平成8年12月20日付で騒音規制法施行令を一部改正し、騒音規制法の規制対象となる特定建設作業としてバックホウ、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業を追加した(平成9年10月1日より施行)。
また、振動については、振動苦情の実態に対応した規制を行うため、平成8年度より所要の調査検討を開始した。
ウ 自動車交通騒音・振動対策
(ア) 自動車交通騒音の現状
自動車騒音について、「当該地域の騒音を代表すると思われる地点」又は「騒音に係る問題を生じ易い地点」において、平成7年中に全国の自治体(都道府県、市町村及び特別区)の測定した結果を見ると、第1-1-16図のとおりである。騒音に係る環境基準については、全国の測定地点(環境基本法に基づく環境基準の類型指定区域内4,380地点)のうち4時間帯(朝、昼間、夕、夜間)で環境基準が達成されたのは555地点であった。また、騒音規制法に基づく要請限度については、全国の測定地点(騒音規制法に基づく指定地域内4,795地点)のうち4時間帯すべて又は4時間帯のいずれかで要請限度を超過したのは1,503地点であった。
また、測定期日・時間が年によって必ずしも一致していないため、単純に比較することはできないが、平成2年から5年間継続して同一地点で測定している1,708測定地点で見ると、第1-1-17図のとおりであり、7年に4時間帯すべてで環境基準が達成された地点は189地点と、引き続き低い水準で推移している。
さらに、環境基準の達成状況について、大都市域(東京都23区及び12政令指定都市)とそれ以外の地域で見ると、4時間帯のすべてにおいて環境基準が達成された測定地点の割合は、大都市域が5.3%(640測定地点中34地点)であり、それ以外の地域の13.9%(3,746地点中521地点)に比べて低くなっており(第1-1-18図)、また、道路の種類別に見ると、4時間帯すべてで環境基準が達成された測定地点の割合は、高速自動車国道が最も高く、逆に都市内高速道路が最も低くなっている(第1-1-19図)。
(イ) 対策
自動車本体からの騒音は、エンジン、吸排気系、駆動系、タイヤ等から発生するが、沿道においては、自動車本体から発生する騒音に、交通量、通行車種、速度、道路構造、沿道土地利用等の各種の要因が複雑に絡み合って自動車騒音として問題となっている。また、道路周辺における振動についても、自動車重量、走行条件及び路面の平坦性、舗装構造、路床条件等の道路構造等の要因もあいまって道路交通振動問題となっている。これらの騒音・振動間題を抜本的に解決するため、自動車構造の改善による騒音の低減に加え、走行状態の改善等の発生源対策、交通流対策、道路構造の改善、沿道対策等の諸施策を総合的に推進している(第1-1-20図)。
なお、自動車騒音に関して道路管理者等に対して意見陳述を行った件数は、平成7年度は24件であった(第1-1-17表)。また、交通振動に対する要請は、ここ数年においては、平成3年度及び平成5年度にそれぞれ1件ずつ行われた。
a 自動車構造の改善
自動車構造の改善により、自動車単体から発生する騒音の大きさそのものを減らす発生源対策として、自動車騒音規制が実施されている。
騒音規制としては、市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音、一定の速度で走行する際の騒音である定常走行騒音、使用過程車の街頭での取締りなどに適した近接排気騒音の3種類について規制を実施している。
新車に対しては、加速走行騒音規制が開始された昭和46年以降、数次にわたる規制の強化が行われ、最新規制は、46年規制と比較して6〜11デシベルの大幅な規制強化となっている。
また、街頭における測定が容易である近接排気騒音規制が、昭和61年6月から使用過程車も含めて実施され、不正改造車等の取締りに対して効果をあげているところであり、これらの措置は、騒音防止上重要な役割を果たしてきている。特に、暴走族の深夜、住宅地等における爆音暴走が多発し、大きな社会問題となってきたことから、消音器不備、近接排気騒音、空ぶかし運転等の取締りを強化している。平成8年中の暴走族の消音器不備等に係る取締り件数は10,671件であった。
しかし、これまでの規制強化にもかかわらず、自動車交通量の増加等により幹線道路の沿道地域を中心に環境基準の達成率は依然として低く、一層の騒音低減が必要であるため、平成3年6月、中央公害対策審議会に対して、「今後の自動車騒音低減対策の在り方について」を諮問し、平成4年11月、加速走行騒音を1〜3デシベル低減する目標値の設定を中心とした中間答申がなされ、さらに平成7年2月、定常走行騒音を1〜6.1デシベル、近接排気騒音を3〜11デシベル低減する目標値の設定を中心とした答申がなされた。これらの答申に盛り込まれた目標値は、世界的に見ても最も厳しいものであり、環境庁としては、平成7年6月より自動車騒音低減技術評価検討会を開催して継続的に技術評価を行うことにより技術開発を促進し、目標値の早期達成を図ることとしている。
これまでの評価の結果、答申に示された目標値のうち、平成10年頃までに達成すべきとされたすべての車種、すなわち、大型バス、乗車定員6人以下の乗用車、軽二輪自動車及び第一種原動機付自転車については、目標値達成の技術的目途が立ったことから、平成8年12月に規制強化のための告示改正を行ったところである。
b 総合的施策
総合的な道路交通騒音対策の推進として、平成7年3月の中央環境審議会答申等に示された方針に沿い、地域の状況に応じて、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の各種対策の推進を図るため、地方自治体による計画の策定等の取組の指導支援を実施している。
また、国道43号・阪神高速神戸線の道路騒音等について国の責任を認めた「国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件」の最高裁判所判決(平成7年7月7日)を関係省庁は重く受け止め、道路交通公害対策関係省庁連絡会議(警察庁、環境庁、通商産業省、運輸省及び建設省)において、平成7年8月30日に「国道43号及び阪神高速神戸線に係る道路交通騒音対策について」を取りまとめ、同地域における対策の枠組みを示した。
さらに、全国的に見ても道路交通騒音の環境基準の非達成測定点が多く存在し、特に都市部幹線道路沿道においては多くの測定地点において騒音規制法に基づく要請限度をも超過する等道路交通騒音が深刻な状況が続いており、周辺の土地利用、交通特性から見て国道43号沿線地域と同様に対策の早期実施が求められる地域が存在している。このため、関係省庁においては、前記連絡会議において、平成7年12月1日に「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針」を取りまとめ、関係省庁連名にて全国の都道府県等に地域レベルにおける関係行政主体一体となった対策の推進を要請した。この通知を受け、平成8年度には都道府県等で関係行政機関参加による道路交通騒音対策のための協議会等が相次いで開催され、道路交通騒音の深刻な地域における問題の早急な解決に向けて総合的な対策の検討が開始された。
c 道路構造の改善
道路構造の面からの対策としては、環境施設帯や遮音壁等の整備、道路緑化を推進している。また、高架裏面吸音板、低騒音舗装の試験的な導入等を推進しているほか、低騒音舗装の騒音低減効果の持続性の向上を図るための技術開発等を行った。
d 物流の効率化等
中長距離の幹線輸送においては、鉄道・海運の積極的活用を通じた適切な輸送機関の利用を促進する等の施策を推進する。また、トラック輸送においては、営業用トラックへの転換、積合せ輸送、共同輸配送の推進、情報化による帰り荷の確保等により輸送効率の向上を図っている。
さらに、主要な物流拠点とのアクセス道路の整備、倉庫、トラックターミナル等の物流拠点の集約化・適正配置等を積極的に進め、効果的な物流システムの構築を図っている。
e 交通流対策
交通流対策としては、バイパス、環状道路を始めとする道路網の体系的整備により道路交通を分散、円滑化すると共に、交通管制システムの整備、旅行時間計測提供システムを始めとする交通情報収集・提供機能の拡充による交通流の集中の抑制、駐車場・駐車場案内システムの整備、交差点の改良及び信号機制御の高度化等による交差点等での交通渋滞の解消等により交通混雑を緩和し、環境への負荷の軽減を図っている。さらに、道路交通情報を車載機へリアルタイムに提供する「VICS(道路交通情報通信システム)」については、平成8年4月の首都圏及び東名・名神高速道路等に続いて、同年12月には大阪地区においてもサービスが開始され、全国への展開に向けて積極的な取組がなされたことにより、交通流の集中の抑制が期待される。
また、高速走行に起因する騒音の防止のための高速走行抑止システムの整備や、大型車の中央より車線通行指定のほか、最高速度規制、大型車の夜間通行止め規制等の交通規制等を実施すると共に、住居系地区等への通過交通の進入を抑制するために、交通規制とコミュニティ道路等の面的整備を組み合わせたコミュニティ・ゾーンの形成等を推進している。
さらに、都市内における円滑な交通流を阻害している違法駐車を排除するため、違法駐車抑止システム、駐車誘導システム等の整備、悪質・危険性、迷惑性の高い駐車違反に重点を置いた取締り等を推進している。
過積載運転に対しては、荷主等の背後責任追及を積極的に実施するなど、取締りを一層強化している。警察による平成8年中の過積載に係る取締り件数は50,812件、道路管理者による平成7年度の車両制限令違反車両に係る指導取締り回数は8,377回であった。
f 沿道環境の整備
沿道対策としては、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路が、平成7年度末現在で7路線延べ約112km指定されている。このうち環状7号線20地区を始めとして、27地区、65.0kmについて沿道整備計画が決定され、その実現を支援するため、緩衝建築物の建築費の負担、防音工事の助成、市町村の土地買入れ資金の無利子貸付けを実施している。
さらに、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道において、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとする等の沿道整備計画の拡充及びそれに伴う沿道地区計画への改正、適正かつ合理的な土地利用を促進するための土地に関する権利の移転等を市町村の定める計画によって一体的に行う制度の創設、市町村が沿道整備推進機構に対し緩衝建築物用地等の取得費用の無利子貸付けを行う場合における、国による当該市町村に対する無利子貸付に係る規定の整備等を内容とする「幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律」が平成8年5月に公布され、同年11月に施行された。
なお、高速自動車国道等の周辺の住宅で騒音による影響が著しいものに対して、緊急的措置として防音工事の助成等を行っており、平成7年度末までに実施した戸数は約49,700戸である。
また、昭和60年度より発足した道路開発資金制度において、沿道環境の向上に資する建築物の建築等に対する長期の低利融資を実施している。
g その他の対策
自動車NOx法に基づく総量規制計画に盛られた施策は、NOx削減効果と併せて自動車騒音低減効果をも有するため、関係都府県を指導し、その円滑な実施を図ったほか、環境負荷の少ない自動車の使用法等の普及啓発活動を行った。
(第1章1節3項 大都市圏等への負荷の集積による問題への対策参照)
エ 航空機騒音対策
航空機のジェット化の進展等は交通利便の飛躍的増大をもたらした反面、空港周辺地域において航空機騒音問題を引き起こした。特に空港周辺の市街化とあいまって、民間空港2港及び防衛施設4飛行場においては、夜間の発着禁止、損害賠償等を求める訴訟が提起された。このような航空機騒音問題を防止するため、発生源対策、空港周辺対策等の諸対策を推進している。
(ア) 環境基準及びその達成状況
航空機騒音公害防止のための諸施策の目標となる「航空機騒音に係る環境基準」(昭和48年12月27日)については、地域類型の当てはめに従い、WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル)の値を専ら住居の用に供される地域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域については75以下になるようにすることとされている。
航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、環境基準制定当時に比べて騒音の状況は全般的に改善の傾向にあり、平成7年度において約69%である(第1-1-21図)。なお、地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととなっており、平成7年度末現在で、33都道府県、61飛行場周辺において行われている。
また、コミューター空港、ヘリポート等については、環境基準が適用されない小規模なものが多く、これらの騒音問題の発生の未然防止を図るため必要な環境保全上の指針を平成2年9月に制定している。
(イ) 発生源対策
発生源対策は、航空機の騒音をその発生源である航空機の段階で極力低減させるもので、騒音対策上、最も基本的かつ効果的な施策である。これまで、低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等の発生源対策を推進することにより、航空輸送量の増大に対応しつつ、騒音の及ぶ地域を縮小してきた。
a 低騒音型機の導入等
一定の基準以上の騒音を発生する航空機の運航を禁止する騒音基準適合証明制度については、昭和50年に制度化され、昭和53年には騒音基準の強化が行われた。この結果、騒音問題の深刻な大阪国際空港を始めとする主要空港を中心として、高騒音機であるB707、DC8等は、昭和63年1月以降我が国における運行が原則として禁止された。さらに、主要空港以外の空港についても、平成6年の航空法の改正により、昭和53年に強化された騒音基準に適合しない航空機の運航については、平成7年4月1日以降段階的に運行を制限し、平成14年4月1日以降その運航を禁止することとされた。
また、平成8年5月の航空法の改正により、騒音基準適合証明が耐空証明に一本化されるとともに、騒音基準に適合している航空機について型式証明を行うこととされ、さらにヘリコプター及びプロペラ飛行機に係る規制が新たに導入された。
b 発着規制
緊急時等を除き、新東京国際空港及び東京国際空港については午後11時から午前6時までの間、大阪国際空港については午後10時から午前7時までの間、ジェット機の発着を禁止している。さらに、大阪国際空港においては、午後9時以降定期便のダイヤを設定しないこととしている。
c 騒音軽減運航方式
各空港の立地条件等に応じて、優先滑走路方式、優先飛行経路方式、急上昇方式、カットバック上昇方式、低フラップ角着陸方式及びディレイドフラップ進入方式が採用されている。
(ウ) 空港周辺対策
発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」等に基づき周辺対策を行っている。同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際、大阪国際、福岡等15空港であり、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備、テレビ受信料の助成等を行っている(第1-1-18表)。
また、大阪国際空港及び福岡空港については、周辺地域が市街化されているため、同法により計画的周辺整備が必要である周辺整備空港に指定され、国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された空港周辺整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画に基づき、上記施策に加えて、これまでに再開発整備事業、代替地造成事業等を実施している。
周辺対策事業を推進してきた結果、住宅防音工事は昭和60年度に概ね完了し、「航空機騒音に係る環境基準」の目標に定める屋内環境が保持されることとなった。一方、移転跡地を活用しつつ、空港と周辺地域との調和ある発展を図っていく必要があるため、次の施策を講じている。
? 大阪国際空港周辺については、運輸省及び2府県が緑地の計画的な整備を順次進めている。
? 函館、仙台、新潟、大阪国際、名古屋、松山、高知、福岡及び宮崎空港においては、地方公共団体が住宅の移転跡地等を利用して行う公園、緑道等の周辺環境基盤施設の整備に対して補助が行われている。
また、「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、新東京国際空港では、空港と調和のとれた土地利用を図るため、昭和57年千葉県知事により航空機騒音対策基本方針が決定され、これに基づき航空機騒音障害防止地区等に関する都市計画の策定が進められている。
(エ) 防衛施設周辺における航空機騒音対策
自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、音源対策、運航対策としては、消音装置の使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっている。この場合の駐留米軍における音源対策、運航対策については、日米合同委員会等の場を通じて協力を要請している。これまでに、厚木及び横田の両飛行場における航空機の騒音規制措置について、日米合同委員会において合意されており、さらに、平成8年3月には嘉手納及び普天間の両飛行場における騒音規制措置についても合意されたところである。
自衛隊等の使用する飛行場に係る周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買入れ、緑地帯等の整備、テレビ受信料に対する助成等の各種施策が実施されている(第1-1-19表)。
なお、平成8年度末現在26飛行場周辺について同法に基づく第1種区域等が指定されており、住宅防音工事の助成等が実施されている。
オ 新幹線鉄道騒音・振動対策
新幹線鉄道は、昭和39年の東海道新幹線開業以来、大量高速輸送機関として発展してきたが、一部の沿線地域において騒音・振動が環境保全上大きな問題となった。
このうち名古屋地区においては、昭和49年3月に東海道新幹線に係る騒音・振動公害の差止め及び損害賠償を求める訴訟が提起されたが、昭和61年4月、発生源対策の一層の推進等を内容とする和解が成立している。
(ア) 環境基準の設定とその達成状況
a 環境基準
新幹線鉄道騒音対策の目標となる「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」(昭和50年7月29日)は、地域の類型に応じ、主として住居の用に供される地域については70デシベル以下、商工業の用に供される地域等については75デシベル以下としており、これが達成され、又は維持されるよう努めるものとしている。地域の類型当てはめは、都道府県知事が行うこととなっており、新幹線鉄道の運行している21都府県のすべてにおいて行われている。
なお、新幹線鉄道振動については、昭和51年3月に環境庁長官から運輸大臣に対し、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」が勧告されている。
b 環境基準等の達成状況
騒音については、東海道・山陽・東北及び上越新幹線について、それぞれ環境基準の達成目標期間の最終年の経過後において、その達成状況ははかばかしくなかったことから、東海道・山陽新幹線にあっては住宅密集地域が連続する地域、東北・上越新幹線にあっては住宅集合地域を対象として、当面の対策として75デシベル以下となるよう対策を講じてきた(いわゆる「第1次75ホン対策」)。平成6年度の環境庁による達成状況調査の結果、この当面の目標については概ね達成された。
現在、引き続き環境基準の達成に向け騒音対策を一層推進するため、平成8年度末を目途に、東海道・山陽新幹線にあっては住宅集合地域、東北・上越新幹線にあっては、住宅集合地域に準じる地域にそれぞれ対象地域を拡大し、「第2次75ホン対策」を講じるよう関係機関に要請しているところである。
振動については、環境庁長官の勧告(昭和51年3月)に基づく振動対策指針値(70デシベル)の達成状況について、昭和61〜62年度の環境庁による調査の結果、概ね達成されており、また、指針値を超過した地点については、関係機関に対し振動対策を一層推進するよう要請しているところである。
(イ) 対策の実施
東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社は、「国鉄改革後における新幹線鉄道騒音対策の推進について」(昭和62年3月閣議了解)及び環境庁長官の勧告(昭和51年3月)等に基づく運輸大臣の通達を受けて、音源対策、振動対策及び障害防止対策を実施した。
a 音源・振動対策
前述の「第1次75ホン対策」に引き続き、平成4年度から「第2次75ホン対策」として、第1次75ホン対策と同様に防音壁のかさあげ、改良型防音壁の設置、レール削正の深度化、バラストマットの敷設、低騒音型車両の開発等各種の音源・振動対策を実施している。
b 障害防止対策
騒音レベルが75デシベルを超える区域に所在する住宅及び70デシベルを超える区域に所在する学校、病院等に対し従来から防音工事の助成等を実施し、申出のあった対象家屋についてはすべて対策を講じている。
また、東海道・山陽新幹線において、振動レベルが70デシベルを超える区域に所在する住宅等の防振工事の助成及び移転補償等を実施しており、申出のあった対象家屋についてはすべて対策を講じている。
(ウ) 騒音・振動防止技術の研究開発
音源対策及び障害防止対策をより効果的に実施するため、国鉄の試験研究に関する業務を承継した財団法人鉄道総合技術研究所を中心として、引き続き有効な騒音防止対策の開発等を推進している。
カ 在来鉄道騒音・振動対策
新幹線以外のいわゆる在来鉄道については、新設又は高架化等のように環境が急変する場合の騒音問題を未然に防止する必要があるとの観点から、平成7年12月、新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針(第1-1-20表)を定め、騒音対策の適切かつ円滑な実施について、関係機関に対して協力を求めた。
キ 近隣騒音対策(良好な音環境の保全)
近年、深夜等の営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の4割近くを占めており、重要な対策課題となっている。
このため、都市における快適な環境(アメニティ)の向上の一環として住民等の生活騒音防止活動を積極的に支援する観点から、サウンドスケープ的手法をとり入れたモデル事業(音環境モデル都市事業)や各種の啓発普及活動を行った。
また、近隣騒音対策は、国民一人一人のマナーやモラルに期待するところが大きい。このため、各地域における地方公共団体や住民等の良好な音環境を保全しようとする取組を支援するため、「残したい“日本の音風景100選”」を選定し(第1-1-22図)、身近な音環境に関する意識の啓発を図っている。
なお、騒音規制法では、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が必要な措置を講ずるようにしなければならないとされており、平成7年度末現在、深夜営業騒音については42都道府県・指定都市、また拡声機騒音についても45都道府県・指定都市で条例による規制がなされている。
ク 低周波音(低周波空気振動)対策
人の耳には聞き取りにくい低い周波数の音(空気振動)がガラス窓や戸、障子等を振動させたり、人体に影響を及ぼしたりするとして、平成7年度は全国で23件程度の苦情が発生した。
この現象は、低周波音又は低周波空気振動と呼ばれており、これまでの調査研究では、一般環境中に存在するレベルでは人体に及ぼす影響を証明しうるデータは得られていない。
(2) 悪臭対策
ア 悪臭の現状
悪臭苦情の件数は昭和47年をピークに概ね減少傾向にあり、平成7年度は11,276件で、前年度に比べ5.6%減少した。発生源別では、畜産農業に係る苦情の割合は減少、各種製造工場に係る苦情はほぼ横ばいとなっており、「サービス業・その他」等いわゆる都市・生活型に分類される苦情の割合が増加する傾向にある(第1-1-23図)。
イ 悪臭防止対策
(ア) 「悪臭防止法」による規制の実施
悪臭防止法では、都道府県知事(政令市においてはその長)が規制地域の指定及び規制基準の設定を行うこととしており、平成7年度末現在、全国の51.6%に当たる1,680市区町村(613市、919町、125村、23特別区)で規制地域が指定されている。
都道府県知事(市町村長に委任)は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について、特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準に適合せず、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認められるときは、事業者に対して悪臭防止の措置を講ずるよう改善勧告、改善命令を発することができる。平成7年度中は改善勧告が7件で、改善命令に至ったものはなかった。このほか、規制地域内の悪臭発生事業場に対して5,014件の行政指導が行われた。
(イ) 悪臭防止対策の充実
特定悪臭物質(政令で指定するアンモニア、メチルメルカプタン等22物質)濃度による従来の規制では対処が難しい複合臭や生活起因の悪臭などの問題に対処するため、平成7年4月に悪臭防止法が改正され、人間の嗅覚を用いた悪臭の測定法(嗅覚測定法)による「臭気指数」を用いた規制基準を導入できることとされ、併せて、国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関する国民の責務等が設けられた。
この改正法の施行を受け、嗅覚測定法による臭気指数の規制の円滑な施行を図るため、地方公共団体に対する臭気指数規制の導入に係る費用の助成、地方公共団体職員を対象とした嗅覚測定技術の研修を行った。また、地方公共団体から委託を受けて臭気指数の測定を行う者として新たに創設された国家資格である臭気判定士試験を実施した(平成8年11月16日に指定機関である(社)臭気対策研究協会が実施)。受験者総数は688人、合格者数は244人であった。
また、悪臭防止法に基づく臭気指数に係る規制基準のうち、煙突等の気体排出口及び排出水に係る規制基準については未だ設定されていないため、これらの基準を速やかに設定するための検討を行っている。
(ウ) におい環境保全総合対策
良好なにおい環境の保全のため、においマップの作成などを通じて街のにおい環境の大切さへの認識を高め、都市生活に伴う悪臭を減らすために、市民をはじめとする各主体の具体的な行動を喚起することを目標としたかおり環境都市モデル事業(クリーンアロマ推進計画)を実施している。また、一般環境大気におけるにおいに関する目標設定のための調査検討を行っている。
(エ) 悪臭防止技術の改善
各地方公共団体の担当者が、臭気指数規制の導入により新たに悪臭防止対策が必要とされる事業場等に対し、発生源の種類、周辺状況に応じ適切な改善措置を指導できるようにするため、有効な悪臭防止技術に関する知見を収集し、その全国的な普及を図る事業を行っている。
(3) その他大気に係る生活環境対策
? 日々の生活において国民がさわやかで澄んだ空気等より良い大気環境を享受するためには、健康に直接影響する大気汚染物質の削減等を推進することはもとより、「光害」等の新たな問題も視野に入れつつ、生活環境の保全の観点から良好な大気環境の確保を図ってゆくことが今後重要となる。このため、良好な大気生活環境の在り方とその実現方策等に関する調査検討を行っている。
また、ヘール・ボップすい星の接近に伴い、光害等の大気生活環境保全に関する意識の啓発に資することを目的として、へール・ボップすい星ライトダウンキャンペーンを始めとする啓発事業を展開した。
? 大気汚染地域等の公立義務教育諸学校の児童生徒の学習能率向上と積極的な心身の健康促進を図るため、学校環境緑化促進事業を、児童生徒の健康増進特別事業(平成8年度予算額9億1,875万円)のメニューの一つとして実施した。
また、騒音等の公害により著しく不適当な教育環境となっている公立学校の公害防止工事に要する経費について補助を行い、平成8年度には10億9,300万円を計上した。また、私立学校の公害防止事業に対しては、日本私学振興財団が行う貸付事業において、平成8年度は貸付計画額5億円を計上した。