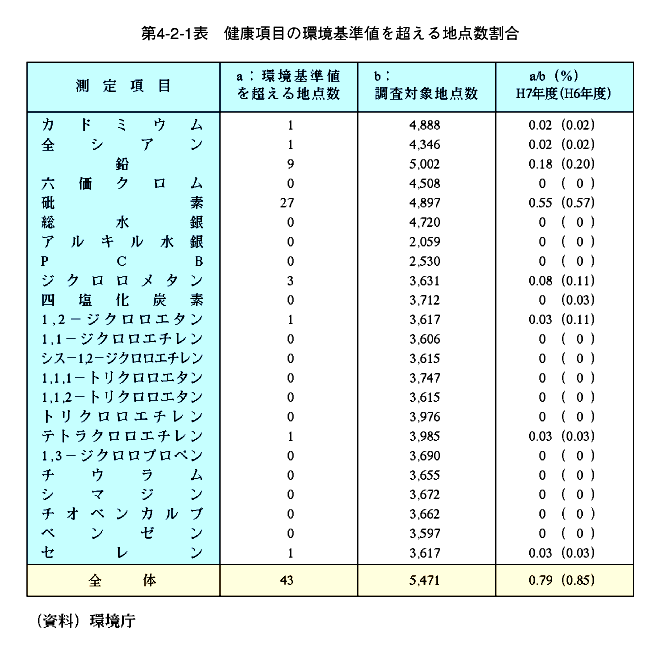
水環境の保全対策は、水質汚濁の防止、水辺空間の利用の観点からの対策が中心であったが、我々が水環境から享受する様々な恵沢を考えると、水質だけでなく、水量、水生生物、水辺地等の様々な要素があり、それらを包括的かつ総合的にとらえ、水環境の保全対策を推進していくことが必要である。また、水は雨となって地上に降り注ぎ、森林や土壌、地下水に保水され、川を下り、海に注ぎ、蒸発して再び雨となるという自然の循環過程の中にあることから、水循環を保全するためには、流域全体を視野に入れた環境保全上健全な水循環の確保の視点が重要である。
水質汚濁は、下流への影響や内海の汚染に見られるように広域的な影響をもたらす問題であるとともに、有害化学物質により数十年後に健康被害が生ずる場合もあるなど長期的な影響をもたらす問題である。また、一旦被害が生ずるとその回復は極めて困難であり、不可逆な影響をもたらす問題でもある。
我が国の水質汚濁の状況は、環境基準の設定されている有害物質については、前年度に引続きほぼ環境基準を達成している。また、有機汚濁については、なお全体の約3割の水域で環境基準が達成されておらず、特に、湖沼や内海内湾等の閉鎖性水域及び都市内河川の中には、依然として水質汚濁の著しいものがある。地下水については、有機塩素系化合物の検出が続いている。また、都市化の進展などによって各地で良好な水辺環境が失われつつある。
(1) 重金属・有害化学物質等
水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域の水質について達成し、維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の二つからなる。健康項目はカドミウム、シアンなど23項目からなり、生活環境項目はBOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)など9項目からなる。なお、BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中の微生物によって消費される酸素量のことで、水中の微生物によって分解可能な有機物の量を示す指標であり、COD(化学的酸素要求量)とは、一定の酸化剤によって消費される酸素量のことで、水中の有機物の量を示す指標である。
健康項目については、平成7年度の調査では、環境基準を超える測定地点は、第4-2-1表のとおりであり、非達成率は前年度に比べやや減少しているが、これは、自然由来の砒素による影響が大きいと考えられている。
また、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした平成7年度化学物質環境調査結果によると、水系環境中に残留していると予測される30物質のうち、1-ブタノール、2-ブタノン、2-ブトキシエタノール等の6物質が水質から検出されたものの、検出濃度等から見て直ちに問題を示唆するものはないと考えられる。また継続的に行っている水質のモニタリング調査結果によると、平成7年度は、調査対象物質20物質のうち、o-ジクロロベンゼン、BHT、リン酸トリブチル等の5物質が検出された。
農薬による水質汚濁の状況については、平成7年度のゴルフ場で使用される農薬の水質調査結果によると、平成2年5月に定められた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」に示された指針値を超過したものは、約10万9千検体中1検体のみであり、暫定指導指針設定以降着実に改善されている。
(2) 有機汚濁等
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)としては、有機汚濁等に係るものがある。(第4-2-2表)。これらの生活環境項目については、水域ごとに利水状況などを踏まえた類型を指定しており、これにより、各水域の特性を考慮した環境基準となっている。
水域の生活環境は、有機汚濁により最も大きな影響を受けることから、代表的な有機汚濁の指標であるBOD(河川)及びCOD(湖沼・海域)などの項目について、環境基準の達成率の評価を行っている。
平成7年度の生活環境項目(BOD又はCOD)の環境基準達成率は、第4-2-1図で示すとおり、全体で72.1%(平成6年度68.9%)、河川で72.3%(同67.9%)、湖沼で39.5%(同40.6%)、海域で78.6%(同79.2%)であった。
河川については、渇水の影響で低下した平成6年度から、今年度は回復している。また、都市内河川の汚濁状況は、近年改善傾向にあるものの、一部では依然として汚濁の著しい河川がある。これは都市域の拡大による生活系排水等の増加によって河川への負荷が大きくなっているためであるが、下水道及び地域の実情に応じた合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備などの生活排水対策や、河川等の直接浄化事業等が行われている(第4-2-2図)。一方、平成7年度の調査で、環境基準満足度の高かった河川は第4-2-3表のとおりとなっており、ほとんどが北海道に集中している。
湖沼・内海・内湾等の閉鎖性水域では、外部との水の交換が行われにくく汚濁物質が蓄積しやすいため水質の改善や維持が難しい。このうち、湖沼については、生活環境項目の環境基準達成率は近年横ばいないしやや改善の傾向が見られていたが、平成7年度には39.5%まで低下し、全窒素及び全燐の環境基準達成率は、平成6年度が41.7%に対し平成7年度では35.4%とさらに低下し、いずれも40%を割り込んだ。湖沼は、富栄養化の進行により、水道水の異臭味、漁業への影響、透明度の低下等の問題が生じており、環境基準の達成率も低いことから、水質改善対策が急務となっている。また、湖沼に流入するCOD汚濁負荷の発生源は生活系、産業系、畜産系などの多岐にわたっており、どの発生源が最も大きな影響を与えているかは湖沼流域の土地利用や産業構造によって異なる。特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要がある湖沼については、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼に指定しており、当該湖沼において策定された湖沼水質保全計画に基づき、他の公共用水域より厳しい排水規制に加え、下水道等の整備や蓄積した汚濁物質の除去対策などのきめ細かな対策を実施中であるが、各指定湖沼の水質改善状況は、全般的にははかばかしくない(第4-2-3図)。
また、海域の生活環境項目の達成率については、河川や湖沼と比べ高い達成率となっており、一定の水質改善効果は現れていると判断されるが達成率の向上には至っていない(第4-2-4図)。このため、平成8年4月に内閣総理大臣により3海域に係る総量削減基本方針が策定されるとともに、平成8年7月には関係都府県知事により総量削減計画が策定され、第四次の総量規制が開始されている。
(3) 海洋
海洋は、陸上の汚染が水の働きにより移されて蓄積するなど汚染物質が最終的に行き着く場所となることが多く、広大ではあるものの人間の活動に伴い、汚染が世界的に確認されるに至っている。
平成8年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は754件で、平成7年に比べ57件(約7%)の減少であった(第4-2-5図)。このうち油による汚染は370件と全体の約5割と高い割合を占め、油以外のもの(廃棄物、有害液体物質(ケミカル)、工場排水等)による汚染は294件、赤潮は90件であった。油による汚染は船舶からのものが約8割を占め、原因別に見ると取り扱い不注意によるものが最も多く、ついで故意、海難と続いている。
また、浮遊性廃棄物についても、環境庁が実施する海洋環境保全調査においてプラスチック類等調査を実施している。平成7年度の調査においては、表層におけるプラスチック類等の分布個数は、東京湾、伊勢湾では湾口部が最も多く、大阪湾では、湾奥部が多くなっている。その組成を見ると、自然物、塊状の石油化学製品の占める割合が多くなっている(第4-2-6図)。
底層では、湾奥部でプラスチック類や自然物のほか、金属やガラス類が多く見られ、その現存量は約1,000〜5,000g/haの範囲であった。一方、湾口から沖合域では膜状プラスチック及び自然物が多くなり、その現存量は最大約500g/haであった。
放射性廃棄物の海洋投棄問題については、1993年(平成5年)4月、ロシア政府が公表した白書により、旧ソ連・ロシアが1959年(昭和34年)から1992年(平成4年)にわたって北方海域及び極東海域において放射性廃棄物の海洋投棄を行ってきた事実が明らかになった。また、1993年(平成5年)10月にロシア太平洋艦隊が日本海において放射性廃棄物の海洋投棄を実施したために、国内で大きな問題となった。
このような事態に対し、我が国では、厳重な抗議を申し入れるとともに、さらなるロシアの海洋投棄を防止するために日露核兵器廃棄協力委員会の資金の一部を利用して低レベル液体放射性廃棄物処理施設の建設のための協力を進め、1996年(平成8年)1月に同施設の建設に係る契約が結ばれた。
(4) 底質
河川や湖沼及び海域の底質には、様々な経路からもたらされる多くの種類の汚染物質が蓄積している可能性がある。我が国では、かつての著しい産業公害の過程で、水銀やPCBを含むヘドロの汚染などが明らかになった。このため平成8年度末までに、有害物質等の除去を目的として、全国で合計約3,325万m
3
に及ぶ底質のしゅんせつが行われた。
一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした底質に関する平成7年度の化学物質環境調査では、調査対象24物質のうち15物質が検出され、アジピン酸ビス及びトリクロサンの検出頻度がやや高く、今後一定の期間をおいて環境調査を行いその推移を監視することが必要と考えられるが、その他は検出濃度から見て直ちに問題となる物質はなかった。
また、ダイオキシン類は燃焼過程や化学物質の合成過程などで意図せずに生成される化学物質である。ダイオキシン類などの非意図的に生成される化学物質について環境庁が行った実態によると、平成7年度の調査結果は、ダイオキシン類による一般環境の汚染状況は、前年度までの調査結果と比較して大きく変化したとは認められないが、底質を中心に広範囲に検出されているため、今後とも引続きその汚染状況の推移を追跡して監視する必要がある状況にある(第4-2-4表)。さらに、近年、廃棄物の焼却等に伴い発生するダイオキシン類による汚染が大きな社会問題となっていることから、ダイオキシン類による被害の未然防止を図るため、環境庁では、平成8年5月より有識者で構成する検討会を随時開催し、ダイオキシン類のリスク評価及び排出抑制対策のあり方について総合的な検討を行っている。平成8年12月の中間とりまとめにおいては、ダイオキシン類に係る健康リスク評価指針値(5pg/kg/日)が示されるとともに、ダイオキシンによる健康リスクをより小さくする観点から環境中のダイオキシン濃度の低減を図る必要があること及びダイオキシン排出抑制対策についての基本的考え方が示されたところであり、引き続き検討会において検討が進められている。
(5) 地下水
地下水は、温度変化が少なく、一般に水質が良好である等の特徴を有するため、我が国の水の使用量の約7分の1、生活用水などの都市用水の約3分の1を占めるなど、身近にある重要な水資源として広く活用されている。また、災害時の水源としても重要な役割を有するなど河川、湖沼等の公共用水域と同様に重要な水資源となっている。しかしながら、昭和50年代後半より、トリクロロエチレンを始めとする有機塩素系化合物等による地下水汚染が顕在化した。これらは、多くの場合有害物質やこれらを含む排水、廃棄物の不適切な管理が原因と考えられる。
平成元年度の「水質汚濁防止法」の一部改正により、都道府県知事は地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなくてはならないこととなっている。
地下水は、流速が極めて緩慢であり、希釈拡散も期待できないなどの物理的特性を有しており、一旦汚染されるとその自然回復が非常に困難である。このため、地下水の水質の保全のためには、平成元年に措置された未然防止策に加えて、汚染された地下水を浄化するための事後的な対応を講じる必要があることから、平成8年6月、汚染された地下水について、人の健康の保護のため必要があるときは、都道府県知事が汚染原因者に対して地下水の水質浄化のための措置を命ずることができることとすることなどを内容とする水質汚濁防止法の改正がなされた。
平成7年度の地下水の水質に係る調査の結果は第4-2-5表のとおりとなっており、依然として新たに設定された環境基準に照らして基準を超える物質の検出が見られる。こういった地下水汚染が発見された場合には、周辺井戸の調査を行うとともに、井戸の使用方法の指導や有害物質を使用している事業場に対する指導等を行っている。
硝酸性窒素による地下水汚染は、多肥集約農業に伴う大量の窒素肥料の使用により1960年代の欧米で顕在化した問題であるが、近年国内においても、硝酸性窒素による地下水汚染が明らかになり始めており、平成7年度に355自治体が行った調査によれば、6.3%の井戸で硝酸性窒素濃度が要監視項目としての指針値(10mg/l)を超えていた。一般的に、硝酸性窒素による地下水汚染の原因としては肥料、畜産廃棄物、生活排水等が考えられる。硝酸性窒素は乳幼児への健康影響が報告されているため、看過できない問題であり、実態の把握を含め汚染地域における調査対策が必要となっている。
(6) 水辺環境
河川や水路などの水辺環境は水辺の生物や水生生物の生息地としてだけではなく、多様な動物の繁殖地や生息地である様々な緑地をつなぐ移動ルートであるため、連続した水辺環境が必要である。また、湖岸、河岸には、陸側から水辺に向けて、水辺林、湿性植物、抽水植物、浮葉植物、沈水植物まで、狭い場所に様々な植物の群生が見られる。このような水辺の移行帯はエコトーンと呼ばれ、独特の生態系を形成している。
Box37 全国水生生物調査
環境庁では、カゲロウ、サワガニ等の水生生物を調査することによって水質を判定する全国水生生物調査を毎年行っている。カゲロウなどの水生生物は水質汚濁等の影響を受けるので、こうした生物を調査することでその水域の水質が把握できる。しかも、こうした調査方法は、一般の人にもわかりやすく、参加しやすいので、調査を通じて自然に接することのできるよい機会となっている。
結果を見てみると、関東及び近畿地方できたない水の割合が多く、北海道・東北地方できれいな水の割合が多くなっていることがよくわかる(図)。
しかしながら、人々の生活や社会経済活動との関わりの深い河川や海域などにおいては、都市化の進展などによって埋立等の人工的な改変が行われ、水辺の生き物の生息環境が損なわれたり、過度の森林伐採により土壌の保水能力が減退し、河川の流量の安定が損なわれるなど、良好な水辺環境が失われつつある。
また、都市内部では身近な湧水の枯渇や水量が低下する事例が発生しており、湧水を水源とする中小河川の流量が減少する傾向にある。平成4年の東京都の地下水実態調査報告書によると、東京の都心部では、明治期より平成2年の調査時点までに枯渇あるいは消滅した湧水が約180ヶ所以上になるとされ、市街地の中小河川や水路では、平常時の水量が著しく減少し、降雨時以外は水流が消滅したものもある。