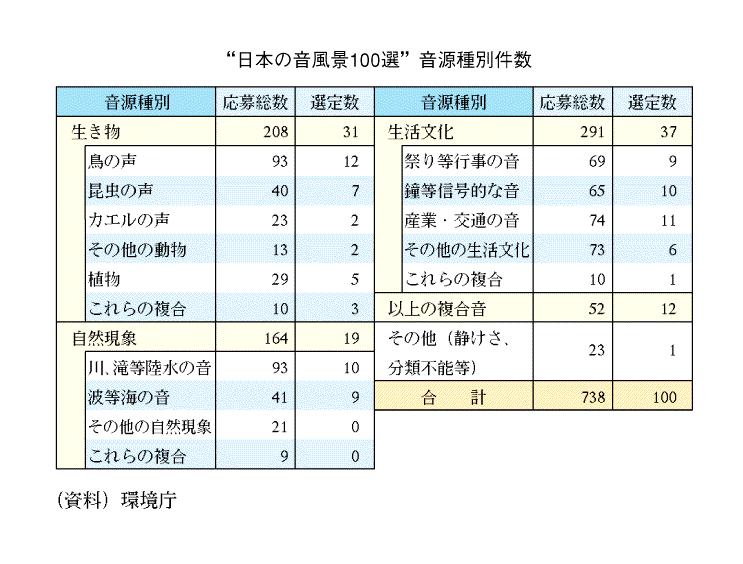
5 地域における生活環境に係る問題
生活環境を保全する上では、大気汚染のほか、主に人の感覚に関わる問題である騒音・振動・悪臭が重要課題となっている。騒音・振動・悪臭は、苦情件数は減少傾向にあるものの、各種公害苦情件数の中では大きな比重を占めており(第4-1-23図)、発生源も多様化している。
(1) 騒音・振動
騒音は日常生活に関係の深い問題であり、騒音に係る苦情件数は地方公共団体に寄せられる各種公害苦情件数の中で最も多い。平成7年度は14,359件で、前年度と比べ約10.2%減少した。苦情件数の内訳を見ると、工場・事業場騒音が最も多く36.8%、次いで建設作業騒音21.8%、営業騒音14.5%、生活騒音9.2%等であった。
騒音については、一般居住環境、自動車交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音のそれぞれに対して、地域の土地利用状況や時間帯等に応じて類型分けされた環境基準が定められるとともに、工場・事業場及び建設作業や自動車単体の騒音について規制基準等が定められている。
ア 一般居住環境及び自動車騒音
平成7年度においては、一般居住環境については、地域の騒音状況をマクロに把握するための地点においては、環境基準の適合率は69.2%、騒音に係る問題を生じやすい地点等においては、適合率は70.8%であった。自動車騒音については、環境基準や、都道府県知事が都道府県公安委員会に対し、「騒音規制法」に基づき所要の措置を要請する際の基準となる要請限度が定められているが、平成7年には、全国測定地点4,380地点のうち、環境基準を達成できなかった地点は3,825地点(87.3%)に及んでいる。また、要請限度を超過した地点は、全国測定地点4,795地点のうち、1,503地点(31.3%)にのぼっている(第4-1-24図)。さらに、5年継続測定地点で見ると、環境基準を達成できなかった地点の割合は、88.9%と引き続き高い水準で推移しており、自動車交通騒音は依然として厳しい状況にある(第4-1-25図)。
また最近では、拡声機、カラオケ、ピアノ、ペットの鳴き声、自動車の空ぶかしなどの都市生活等による騒音も大きな問題となっている。
Box35 日本の音風景100選
環境庁では、音環境保全対策の一環として、残したい“日本の音風景100選”事業を行った。これは、「日常生活のなかで耳を澄ませば聞こえてくる様々な音について再発見を促す」こと、「良好な音環境を保全するための地域に根ざした取組を支援する」ことを目的として行われたものである。738件の応募の中から音環境を保全する上で特に意義があると認められるもの100件程度を“日本の音風景100選”として認定した。音源種別で見た件数の分布は表のとおりである。
イ 航空機騒音及び新幹線騒音
航空機騒音については、低騒音型機材の導入・空港周辺の整備等の対策が行われており、東京・大阪・福岡等の代表的な空港周辺では環境基準制定当時に比べると全般的に改善傾向にある。
新幹線に起因する騒音については、環境基準未達成の地域が多く残されているものの、東海道・山陽新幹線沿線は住宅密集地が連続する地域等、東北・上越新幹線沿線は住宅が集合する地域等において、75デシベルを超える地域について特に対策が講じられている。この結果75デシベル以下という暫定目標は概ね達成できた。また、在来鉄道については個別に対策が講じられているが、環境庁では、在来鉄道の新設又は大規模改良(高架化、複線化等)に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上で目標となる当面の指針を定めている。
(2) 悪臭
悪臭は、人に不快感を与えるにおいの原因となる物質が大気中に混じることにより感じられ、騒音・振動と同様、感覚公害であるため、我々の生活に密着した問題である。現在、「悪臭防止法」により、規制が行われている。
悪臭苦情件数は、ピークであった昭和47年から年々減少し、平成7年度ではピーク時の半分程度となっており、前年度に比べ5.6%の減少である(第4-1-26図)。悪臭は、典型7公害に係る苦情件数のうち騒音についで多い。発生源別には、「サービス業・その他」(2,930件)が最も多く、次いで「畜産農業」(1,824件)、「個人住宅・アパート・寮」(1,481件)の順となっており、いわゆる都市・生活型に分類される悪臭苦情件数の割合が増加する傾向にある。
こうした状況に対処するため、悪臭防止法の一部改正が平成7年4月に行われ、複合臭等が問題で従来の特定悪臭物質ごとの排出濃度の規制によっては対応が困難な区域については、これに代えて、人の嗅覚を用いた悪臭の測定法(嗅覚測定法)による「臭気指数」を用いた規制基準を導入できることとされ、併せて、国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関する国民の責務等が設けられた。この改正法は平成8年4月より施行されている。
Box36 「におい環境」アンケート調査
環境庁では、平成8年6月に「におい環境」についてのアンケートを行った。このアンケートの結果によると、日常生活において不快なにおいを「感じる」とする回答は72.6%、心地よいにおいを「感じる」とする回答は62.5%であり、不快なにおい、心地よいにおいのどちらも関心が高いことを示している(図)。屋外で感じる不快なにおいとしては、自動車の排気ガス、公衆トイレ、ゴミ集積所・収集車などが上位を占めており、また、家庭調理の排気や排水などが工場や飲食店・食料品店などを上回っている。
一方、心地よいにおいとしては、「草花」、「樹木」に多くの回答が集中しており、植物の発するにおいは、多くの人が心地よいにおいと感じていることがわかる。また、「海」、「日光」、「風」なども多くの人が挙げており、かおりを通じて私達が身の回りの様々な環境と結びついていることを示している(図)。