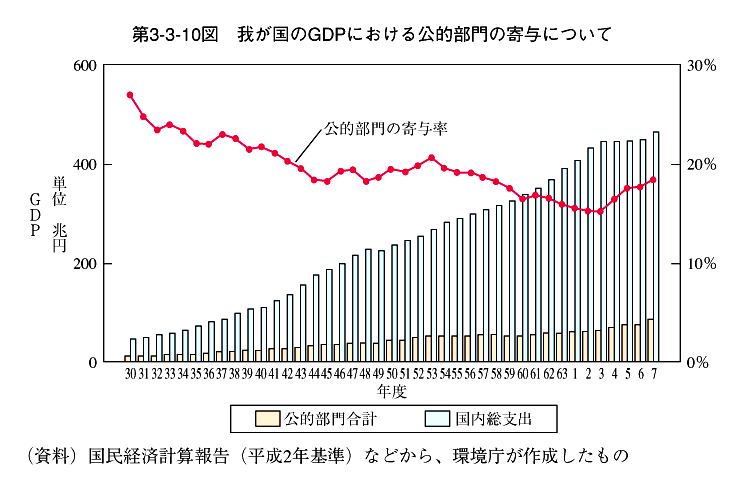
2 国・地方公共団体の率先的な取組について
(1) 国の率先的な取組
ア 率先実行計画の背景と概要
国・地方公共団体は、様々な政策や事業を行うという主体としての役割のほか、民間企業と同様に、各種の製品やサービスの購入・使用や、建築物の建築・維持管理など、事業者や消費者としての経済活動を行っており、経済活動全体のうち公的部門の占める部分は極めて大きい。我が国の平成7年度のGDP(国内総生産)は466.9兆円であるが、そのうち国と地方公共団体の総寄与分は86.5兆円(政府最終消費支出、公的資本形成、公的在庫増加の合計)に及び、全体の約18.5%を占めている(第3-3-10図)。このうち、国の最終消費支出部分は、GDPの約2.3%となっている。したがって、国がその経済活動に際して環境保全に配慮した行動を行えば環境への負荷を大きく低減することが期待できる。
こうした国自らの活動に伴う環境への負荷を自主的・積極的に削減するため、政府は、環境基本計画に基づき、平成7年6月に各省庁に共通した実行計画として、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」(以下「率先実行計画」)を閣議決定し、併せてこの計画を実施するための各省庁の取組の具体的な例を環境基本計画推進関係省庁会議で申し合わせた。
率先実行計画は、11の数値目標を含む具体的な目標を掲げており、?財やサービスの購入・使用に当たっての環境保全への配慮、?建築物の建築、管理等に当たっての環境保全への配慮、?その他行政事務に当たっての環境保全への配慮、?環境保全に関する職員に対する研修等の実施、?計画の推進体制の整備と実施状況の点検の5つに分類している。
また、率先実行計画に掲げた各省庁に共通した取組のうち、検討課題とされた事項については、「環境負荷の少ない物品等の仕様、材質等に関する推奨リスト」の作成や「共同購入の方策」、「率先実行計画の監査の在り方」などについて、検討を進めているところである。
イ 率先実行計画の実施状況について
率先実行計画に基づく取組の実施状況については、各省庁の部局単位又は必要に応じて出先機関単位等適切な単位で把握し、環境基本計画推進関係省庁会議において、毎年、関係省庁の成果を取りまとめた上、環境白書等適切な方法を通じ公表することとされている。
昨年12月に、平成7年度における各省庁における率先実行計画の実施状況として、数値目標のある項目の実績のほか、各省庁の具体的な取組内容をとりまとめ、公表したところである。
このうち、数値目標に関する政府全体の実績数値については、第3-3-1表のとおりである。
なお、各省庁の取組の詳細については第2部「環境保全に関して講じた施策」第3章第2節を参照されたい。
ウ 率先実行計画の効果
率先実行計画に関しては、平成7年度の実績が初めての公表結果であり、本調査以前との比較は難しいが、用紙類の使用量や電気使用量等、入手可能なデータで率先実行計画の導入以前との比較を行ってみる。
(ア) 用紙類
まず、用紙類の使用量について環境庁本庁(合同庁舎5号館内)の例をみると、用紙類の使用量を平成4年度から平成6年度の平均と平成7年度の実績を単純に比較して、約15%減少した(第3-3-2表)。これの一つの要因として、環境庁本庁での用紙類の使用量の90%以上を占めるコピー用紙について、両面コピーの励行やミスコピーの削減を行った結果によるものと思われる。しかし、減少したといえ平成7年度の実績から推計すると職員一人当たりでは約3万6千枚/年(A4用紙に換算)ものコピー用紙を使用している計算になり、引き続き削減の努力が必要であろう。なお、平成8年度から環境庁行政情報システム(LAN)が確立し、電子掲示板機能等によるペーパーレス化が本格的に推進できる体制が稼働したことから、情報文書の電子化等により、一層の削減が期待できると考えられる。
(イ) 電気使用量
事務所の単位面積当たりの電気使用量については、(財)日本エネルギー経済研究所が行った平成7年の一般業務部門電力使用量の推計と比較すると、政府の単位面積当たりの電力使用量の方が約13.7%少ないことがわかる(第3-3-11図)。率先実行計画では、事務所の単位面積当たりの電気使用量を平成12年度までに概ね90%以下にすることに向けて努めるとしており、さらなる省エネに努めることが必要である。
このように、数値によって進捗状況の把握を行うことは、率先実行計画の適切な実施を図る上で重要な意味を有する。
なお、低公害車に関しては、第1章第2節第4項を参照されたい。
(ウ) 今後の課題
率先実行計画の推進に当たっては、今後、毎年の取組の実施状況を踏まえ、その中の効果的な取組等を分析し、有効に活用していく必要がある。各省庁がより効果的な取組方法を選択できれば、国の消費・事業活動による環境への負荷はさらに減少させることができるであろう。このため、率先実行計画の検討課題として掲げられた率先実行計画の監査に関して、その内容や具体的な実施方法及び実施体制について、検討を進めていく必要がある。このような仕組みは、政府全体の環境マネジメントシステムの構築につながっていくものである。
また、このような国の率先的な取組を広く地方公共団体、国民、事業者等に普及させることは、これらの主体の環境保全意識を高め、ひいては環境保全型製品等のエコビジネスの市場形成の一助となり、これによって環境保全型製品の経済全体に占める割合が拡大することも期待される。エコビジネスの市場が拡大すれば、環境保全型製品の価格低下にもつながり、国や事業者にとっては率先的な取組が行いやすくなるとともに、副次的な効果として経費の節減にもなるだろう。このため、国は様々な機会を捉えて率先実行計画で得た経験や情報等を国民や事業者に広く普及させていくことが必要である。
(2) 地方公共団体の率先的な取組
持続可能な社会の基礎は地域の環境の保全であり、地方公共団体の役割は大きい。また、国と同様に地方公共団体も消費者・事業者としての経済活動に及ぼす影響は大きく、環境保全に関する行動を率先的に実行することが環境基本計画でも明記されている。ここでは、地方公共団体による環境保全に関する率先的な取組を紹介する。
平成9年1月に北九州市において「政令指定都市環境サミット'97」が行われた。この会議では、政令指定都市の市長が環境会議としては初めて一堂に会し、21世紀における環境保全のための大都市の変革に向けた理念と方向性を明らかにするための議論が行われた。
政令指定都市は通常の都市と比べて人口や産業の集積が進んでおり、そのための環境への負荷は大きく、過去においても多くの激甚な公害問題を経験してきた。各政令指定都市はこの経験を活かし、今日の地球環境問題や都市生活型環境問題の解決に向けて何をすべきかについて議論を行い、会議の結果「政令指定都市環境宣言」を策定した。
これとほぼ時を同じくして、「20%クラブ国際環境ワークショップ」が神奈川県で開催され、世界の地方公共団体が共同して環境保全に積極的に取り組むことを目指す「持続可能な都市のための20%クラブ」が設立された。この20%クラブは、概ね5年以内に環境負荷要因の20%削減と環境改善に効果的なものを20%増加させるという数値目標を掲げており、目標の種類・数については拘束されないが、国の率先実行計画と方向性を同じくするとともに、地方公共団体間の環境活動の相互強化が期待されている。
北海道では、道が行う事業において環境への負荷の低減を図るため、環境配慮指針のオフィス編と公共事業編を策定した。このうち、公共事業編は「豊かな自然環境の保全」と「地球環境問題等の対応」を基本方針とし、?野生生物、?自然景観、?大気環境等、?水環境、?省資源・省エネルギー、?廃棄物の減量化とリサイクル、の6つの視点に沿って、「多様な緑地等の保全」や「修景等の緑化」など17の配慮事項を盛り込んでいる。また、指針のフォローアップとして、事業担当者の研修会や環境情報のシステムの推進を掲げている。
また、東京都の板橋区は平成8年度に「率先実行計画」を策定し、平成12年度までの主要課題としてフロン等の削減対策や省エネルギー対策等の8項目を掲げたほか、この率先実行計画の実施体制の整備、実施結果の評価体制の確立等を行う仕組みとして「板橋区環境管理・監査システム」を構築している。同システムは平成9年度から本格的に運用が開始されることとなっている(第3-3-12図)。
(3) 諸外国の率先実行の事例(政府のグリーン化:政府の活動を環境配慮型にすること)
我が国だけでなく、諸外国においても「政府のグリーン化」は世界的な潮流となりつつある。
ア OECDの取組
1996年(平成8年)2月のOECD環境大臣会合に併せて開催されたOECD理事会は、加盟国が政府の運営や各種施設のすべての側面に環境配慮を組み込むことによって、政府の環境保全の取組を継続的に向上させるための戦略を策定し、政府の関連する意思決定過程に適用することを勧告した。
また、理事会はOECD環境政策委員会に対し、加盟国が政府の運営や施設における環境保全の取組を向上させる努力を、加盟国の「ベストプラクティス」の収集及び情報提供を中心に、支援することを勧告した。この勧告に基づき1997年(平成9年)2月に「政府調達に関する国際会議」がスイスにおいて行われ、各国の率先的な政府調達に関する取組が発表された。
イ 各国の取組
オランダでは、1989年(平成元年)に国家環境政策計画(NEPP)を策定し、その中で、?すべての省庁における環境マネジメントシステムの確立、?政府調達における環境配慮の重視、の2つの行動が盛り込まれた。その結果、現在ではすべての省庁が環境マネジメントシステムを整備し、各省庁毎に環境を配慮した政府調達を行っている。しかし、政府調達の仕組みは各省庁毎に異なっているため、政府全体としての取組を困難にしており、今後は各省庁間の調整メカニズムが課題とされている。
アメリカでは、1993年(平成5年)以降、環境に配慮した政府調達について一連の大統領令が公布されている。1993年4月に、?オゾン層破壊物質に関する政府調達と要件、?連邦政府による代替燃料自動車の使用、?エネルギー効率の高いコンピューター機器の購入の3つの大統領令が公布され、それ以降、?知る権利法及び汚染未然防止要件の連邦政府としての遵守(93年8月)、?連邦政府の調達、リサイクル及び廃棄物抑制(93年10月)、?連邦施設におけるエネルギー効率と節水(94年3月)、?連邦政府調達及び地域社会の知る権利(95年8月)についての一連の大統領令が順次公布された。
EPA(環境保護庁)では、こうした大統領令に加えて、省エネルギー、省資源、有害物質対策等に関する率先的な取組を行っており、こうした取組は、州政府や地方自治体が費用効果的・革新的取組を行う上で、適用することができるとしている。
デンマークでは、環境・エネルギー省が、1994年(平成6年)8月に「持続可能な政府調達の政策に関する行動計画」を策定した。この行動計画は、「1991年の持続可能な政府調達の政策に関する戦略」を踏まえて策定されたものである。
この計画の重点分野としては、事務機器、電子機器、事務用家具、清掃用品、ぺンキ、調理器具、照明、交通機器、食料品等があげられているが、これ以外の取組を排除するものではなく、例えば、コピー用紙、タイプ用紙、電線などが追加される見通しである。
1995年(平成7年)の春には、政府機関の調達担当者向けに「調達を通じた環境改善」というマニュアルが作成された。このマニュアルは、製品サービスの購入に当たっての環境配慮について、一般的なアドバイスや指針が盛り込まれている。さらに、1995年12月には、リサイクル・クリーナーテクノロジー評議会によって、各種製品を環境面から評価したデータシートを作成するためのプロジェクトが開始されている。
このように、国際的にも政府による率先的な取組が進められており、我が国においても、諸外国の事例等を参考にしつつ、引き続き積極的な取組を行っていく必要がある。また、我が国の率先実行計画で設定されている政府全体の数値目標は諸外国の事例に見られないものであり、我が国にとってリーダーシップが発揮できる分野であるといえ、この分野での国際的な貢献が期待されている。