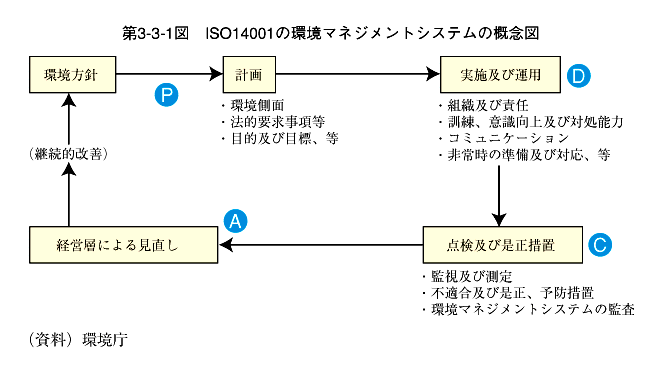
1 企業の自主的取組について
事業活動と環境は深いかかわりを有している。事業者の生産活動の結果である製品に着目すると、第2章第1節で見たとおり、原材料の採取段階から始まり、製品の生産、輸送、使用、廃棄段階にいたるまで、環境に対して何らかの負荷が発生している。したがって、事業者は製品の「ゆりかごから墓場まで(ライフサイクル)」を考慮し、自らの事業活動が環境に及ぼす影響をできるだけ定量的かつ総合的に判断し、自主的、積極的に環境への負荷を可能な限り小さくしていくことが必要である。
(1) 事業目的と環境保全の関係
事業者の相当部分を企業が占めているが、企業の本来的な目的は利益をあげることであり、その利益をできる限り大きくすることである。従来、この企業利益を大きくするという目的は、環境保全のための積極的な取組とは両立しないと考えられがちであった。
しかし、このような通念は、根本的に問い直さなければならない時にきている。今日の環境問題は人類の生存基盤そのものをおびやかす問題であり、企業にとっても、その存続の基盤そのものをおびやかす問題になっている。したがって、自ら積極的に取り組むことによって健全な環境を維持していかなければ、自らの存続自体があり得なくなっているのである。
また、企業は株主や従業員だけではなく、消費者、地域住民、同業者等多くの利害関係者と関わっている。従来から地域住民は企業に対し環境への配慮を求めていたが、近年の地球環境の悪化を背景として消費者の環境意識が高まっており、特に欧米等で顕著になっている。このような環境意識の高まりから、消費者は企業に対して環境配慮や環境にやさしい商品を要求し始めている。
このような周囲の状況を考えると、環境保全に対する取組において社会の信頼と尊敬を得られなければ、企業は存続することはできない。したがって、短期的な利益の確保のみならず、環境への配慮を行うことが企業の存続の条件となってきているのである。このような状況において、環境保全への取組は企業の目的として成り立つのであり、事業目的の中に環境保全を織り込んでいくことがマネジメントの主要な問題となってくる。
(2) 環境管理と環境マネジメントシステム
ア 環境管理と組織
環境保全を企業の目的として有効に機能させるためには、環境保全を経営方針に掲げ、その上で組織の管理者が下部組織や構成員に対する調整を行わなければならない。単に経営方針に掲げるだけでは、組織全体で体系的な取組を行うことはできない。
組織論の始祖といわれているチェスター.I.バーナード(アメリカ、1886〜1961)は主著「経営者の役割」の中で、組織を構成する上で不可欠な要素として、組織の目的、構成員の協働意志、コミュニケーションの3要素をあげている。この考えにしたがえば環境保全を目的化するだけでは十分ではなく、管理者はコミュニケーションシステムによって環境保全に関する目的を下部組織や構成員に伝達し調整する必要がある。また、構成員に対して、環境保全に積極的になるための誘因を供与し、説得を行い、教育を行うことも重要である。その上で、管理者は最終的に目的と実績の比較及び検討を行い、継続的な改善努力を図っていく必要がある。
このような環境保全に関する目的を組織内において体系化する手法を環境管理といい、そのための組織内システムを「環境マネジメントシステム」と呼んでいる。
イ 統一的な規格作り
環境管理もしくは環境マネジメントシステムは、個々の先駆的な企業で行われてきた。まず、その先駆けとなったのは、1992年(平成4年)1月にイギリスの規格協会が策定した規格(BS7750)である。また、EUでは、環境監査を中心に検討が進められていたが、BS7750の影響を受け、1993年(平成5年)7月に企業の自主的な取組としての「環境管理監査規則」(EMAS)が発行し、1995年(平成7年)4月から実施適用されている。
世界共通の環境マネジメントシステム規格としては、国際的な非政府機関である国際標準化機構(ISO)において国際規格の制定についての作業が行われ、1996年(平成8年)9月に国際規格として「ISO14001」が発行した。
ISO14001は、基本的にはBS7750を継承しつつ、Plan(環境保全に関する方針、目標、計画の制定)、Do(実施及び運用)、Check(点検及び是正措置)、Action(経営者による見直し)といういわゆるPDCAサイクルで組み立てられている(第3-3-1図)。
ISO14001規格では、環境保全に関する方針は対外的に公表が義務づけられている。
また、点検及び是正措置を実施する段階において、環境マネジメントシステムの内部監査が行われる。環境マネジメントシステムの監査手順については、1996年(平成8年)10月から「ISO14010, ISO14011 , ISO14012」として既に発行されている。
環境マネジメントシステムは、企業をはじめとする事業者の組織が自主的に環境保全への取組を行う場合、環境目標の体系的な管理手段として、極めて有効なツールとなるものであり、その規格の統一化は、環境マネジメントシステムを有効に機能させる上で重要な役割を果たすであろう。
Box32 ISOとISO14000シリーズ
○ ISO(国際標準化機構)について
ISOは、1947年(昭和22年)に設立された国際的な非政府機関であり、物質及びサービスの国際貿易を容易にし、知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力を助長するために世界的な標準化とその関連活動の発展を図ることを目的としている。
ISOでは設立以来、機械、鉄鋼、自動車、化学、包装類など様々な分野において、10,000以上の規格の制定を行っており、例えば、「ISO400」と表示される写真フィルムの感度などが良く知られている。
ISOへの加盟は、個々の事業者ではなく、各国の代表的な標準化機関1つに限られている。我が国からは、1952年(昭和27年)の閣議了解に基づき、日本工業標準調査会(工業標準化法に基づき通商産業省工業技術院内に設置された組織)が加入している。
○ ISO14000シリーズ
ISO14000シリーズは、環境マネジメントに関する規格の総称であり、環境マネジメントシステム、環境監査、環境ラベル、環境パフォーマンス評価、LCA、用語と定義の6つの規格に大別されている。現在、発行されている国際規格のうち、環境マネジメントシステム(ISO14001)だけが認証の対象であり、一方、発行された国際規格のうち、その他の規格は利用可能な指針であるため、認証を必要とされるものではない。
ウ 我が国の取組
我が国においては、ISO規格に対応するために、平成8年10月にISO14001規格を工業標準化法に基づくJIS規格(日本工業規格Q14001)として制定した。工業標準化法は鉱工業を対象としているが、ISO規定は鉱工業にとどまらない広く事業者一般が自主的に採用することができる規格であることから、環境庁は平成8年11月、ISOの環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたこと、JIS制定及びその内容等について告示を行い、広く周知を図った。
企業が構築している環境マネジメントシステムがISO14001規格として認定されるためには、認証を得ることが必要とされる。この認証を行う機関は「審査登録機関」と呼ばれ、また、この審査登録機関が適正かどうかを認定する機関は「認定機関」と呼ばれる。なお、認証及び認定事業は欧米諸国と同様に民間機関により実施されている。
平成8年12月現在で、我が国の審査登録機関は、海外で認定されたものも含めると、既に12団体にのぼっている。また、ISO14001の認証を取得している事業所数は平成9年3月末現在で200事業所を上回っている。
環境庁が上場企業と従業員500人以上の非上場企業に対して実施した平成8年度の「環境にやさしい企業行動調査」によれば、ISO14001規格の認証を取得又は取得予定の企業は500社以上あり、今後、各企業における環境管理の積極的な取組が期待される(第3-3-2図)。
エ 環境活動評価プログラム事業
我が国では、中小企業の比率が大きな割合を占め、事業者全体の90%以上を占める。この700万近い幅広い事業者(学校、病院等を含む。)の大多数は、環境保全活動への意欲はあったとしても、自らの事業活動と環境とのかかわりや行動の方法等についての情報が十分ではなく、どこから手をつけていいのかもわからないというのが現状である。また、ISO14001の認証を取得するにも、認証だけで数百万円の経費がかかり、中小企業にとっては負担が大きいと言われている。
環境にやさしい企業行動調査でも、上場企業に比べ非上場企業の方がISOの認証取得への対応は遅れていることがわかる(第3-3-2図)。
こうした状況を踏まえ、環境庁では平成8年9月に、中小企業等のより幅広い事業者の環境活動を推進するために「環境活動評価プログラム」を開始した。
環境活動評価プログラムは、こうした大多数の事業者が、簡単な方法により、自主的に「環境とのかかわりに気づき、目標を持ち、行動する」という地球市民としての役割を果たし、具体的な環境活動が展開できるようにするためのものである。具体的には、事業活動に伴う環境への負荷の簡易な把握の方法や、環境保全のための事業者に期待される具体的な取組のチェックリストを示し、その実行のための計画づくりと取組の推進を支援するものである(第3-3-3図)。
このプログラムに参加することによって知識と経験を身につけた事業者は、それを活かして、国際規格に沿った環境マネジメントシステムの構築へと進んでいくことが期待される。
オ 中小企業事業団の情報提供事業
中小企業事業団では、ISO規格の発行に合わせ、中小企業者に対し、環境管理・監査制度の概要について周知するため、各県の中小企業情報センターと協力し、ISO規格に関する情報提供を行っている。
(3) 事業者団体による自主的取組の推進
我が国では、事業者団体や経済団体を通じて環境保全に関する自主的な取組を行っている例も多い。また、業種毎の環境保全行動計画を策定しているところもある。
ア 経団連の取組
経済団体連合会(以下、経団連)においては、環境問題について自主的取組の推進を図るため、平成3年に「経団連地球環境憲章」を定め、環境問題への取組が企業の存在と活動の必須の条件であるとした基本理念と、今後企業が行っていくべき環境保全行動のための行動指針を明らかにした。ついで平成8年7月には「経団連環境アピール」として環境保全に向けた経済界の自主行動宣言を発表した。このアピールでは、?地球温暖化対策、?循環型経済社会の構築、?環境管理システムの構築と環境監査、?海外事業展開にあたっての環境配慮の4つを自主的取組の重点項目として掲げている。平成8年12月にはこのアピールをさらに具体的な行動に結び付けるために、各産業における行動計画として「産業毎の環境自主行動計画」を策定した。この計画には29業種・131団体(経団連全体の約13%)が参加しており、今後さらに参加する業種・団体が増加することが期待されている。
イ 事業者団体の取組
このような経済団体の取組とならんで、各事業者団体でも様々な取組が行われている。
製紙産業では、日本製紙連合会が中心となり環境保全に向けた自主行動計画を策定している。資源の再利用については、古紙利用率を1994年(平成6年)の53%から2000年までには56%にすることを数値目標として掲げている。日本の紙・板紙の国内消費量は今後も拡大すると見込まれており、通産省の試算では2000年の紙・板紙国内消費量は3,292万トンとなり、94年対比では410万トンの増加と予想されている。したがって、2000年に古紙利用率が56%になると、現状のままのケース(53%)と比較して、約100万トンのバージン・パルプ節減が可能となるのである。また、古紙を利用すると木材からパルプを作る1/3のエネルギー消費量で古紙パルプを生産することができるので省エネルギー対策にもなっている。
これらの古紙対策のほかにも、エネルギー多消費型産業としての省エネルギー対策、植林等の森林対策、廃棄物・公害対策などを積極的に行うことを目標としている。製紙産業は元来、水資源、森林資源、エネルギー資源の多消費型産業であるが、これらの取組を積極的に行うことによって、低負荷型のリサイクル産業となることが期待されている。
また、化学業界でも、第2章第3節でも述べたように「レスポンシブル・ケア」活動を行っている。
このような経済団体や事業者団体による自主的行動計画の策定は、環境保全に関するノウハウや技術情報の共有化を促進し、システムや制度を共用できるだけでなく、個々の企業の環境意識を高める効果も期待できる。
(4) 環境保全経費の把握と環境会計
ア 環境保全経費の把握の意義
企業が自主的取組を行うとき、その費用がどれぐらいかかるかを把握することは非常に重要である。費用を適切に把握しておくことは、効率的で効果的な取組を行うための基礎となるものである。
また、環境担当の管理者が環境保全に関する目標を達成するための行動計画を立てるとき、その全体費用が明らかにならなければ、その計画が実行可能なものかどうかを判断できないだろうし、他の部局からの支持も得られないであろう。環境保全のための活動や費用負担の中には、省エネ投資のように、環境保全のみならず経済効率性を直接向上させる効果を持つものもあり、費用対効果を見る上でも、費用の把握は必要である。
イ 環境保全経費の範囲
費用を把握する上で問題となってくるのが、何が環境保全のための費用なのかというところである。今のところ、環境保全支出の標準的な定義は無いが、WBCSD(世界環境経済人会議)の報告書「ファイナンシャル・チェインジ」によれば、概ね、設備投資、経常費用、汚染浄化措置費用、研究・開発費の四つに分類できるとしている。
設備投資には、従来のエンド・オブ・パイプ処理設備に対する投資だけでなく、省エネルギー設備やクリーンな技術に対する投資が含まれるが、そのうち環境に関する部分だけを抽出することは簡単ではない。
経常費用には、廃棄物の処理の費用や環境関連装置の維持費用、減価償却費、人件費などが含まれる。クリーンな技術を用いた装置なら、廃棄物の排出が少ないので経常費用は少なくなるだろう。
汚染浄化措置費用は、工場の敷地や水源の汚染を浄化するための費用である。アメリカでは、1980年に土壌汚染の原因企業に対し浄化費用の負担を義務づけるスーパーファンド法が成立した。同法では、責任者を土地所有者や管理者だけに限定するのではなく、有害物質の輸送者や融資を行った銀行までも責任の当事者としているので、多くの企業が汚染浄化措置費用を計上している。我が国でも、平成8年5月水質汚濁防止法が改正され、都道府県知事が地下水汚染の原因企業に浄化を命ずることができるようになったため、汚染浄化措置費用を負担する企業が出てくる可能性がある。
研究開発費は、環境保全型の商品や技術の開発のための経費である。
ウ 環境会計の適用事例
企業の中には、自社の基準で環境に関する投資・費用について把握し、投資及び費用負担の意思決定を行っているところがある。電機メーカーA社は、環境設備投資を行う際に投資額と経常費用を計算し、収益改善効果と環境改善効果との比較を行った上で投資に関する意思決定を行っている。第3-3-4図、第3-3-5図はA社の「水溶性切削油の油水分離装置の導入」に対する説明書と投資利益計算書である。この投資利益率計算書では投資額のほかに、投資前の経常費用と投資後の経常費用が比較されており、投資後の経常費用の改善を投資利益として表している。この投資利益率計算書によれば、約5年で投資額を回収できることがわかる。
このように、クリーンな技術に対する投資は経常費用を削減することがあり、費用と利益と環境改善効果が明らかになれば、企業の予算計画時において他の部署に対する合理的な説得材料にもなり、環境保全投資が行いやすくなる。
エ 環境会計の方向性
環境にやさしい企業行動調査によると、上場企業の約25.3%が環境保全支出を集計しており、そのうちの約半数が投資と経費に区別して把握している。しかしながら、上場企業の約68.7%は全く環境保全支出を把握しておらず、非上場企業では約78.0%に達している。また、同調査によると、環境保全支出の集計を行う上での問題点として、「環境保全支出の定義や集計方法が不明」としているのが全体の約45.8%を占めており、何らかの指針等が必要とされている。
上で述べたように、企業の活動において会計手法は大きな役割を果たしており、環境に関する自主的取組を行う際にもその経費の把握は不可欠である。また、企業の中には、自社の環境報告書の中で、環境保全支出を示しているところもあるが、基準がなければ比較しようがないという意見もある。このように意思決定のツールとしての管理会計的要求と利害関係者に対する情報の提供としての財務会計的要求が併存しているが、いずれにせよ環境保全支出の把握や環境会計の指針の活用は自主的取組の推進にとって有効な手法といえるだろう。
Box33 環境報告書とは?
環境報告書は、事業者が当年に行った環境に関する事項を一般に公表する資料のことを言う。近年、ヨーロッパを中心に、環境報告書を作成し、公表する企業が増えている。
報告書に記載する内容については、環境保全に関する方針、個別分野毎の目標及びその達成状況、実際に行った環境保全活動、環境保全に関する経費明細、環境関連設備投資額など企業によって様々である。
平成8年度の環境にやさしい企業行動調査によると、環境報告書を作成している企業は上場企業で25.0%であった。
(5) 自主的取組の意味
各事業者、各企業による環境保全のための自主的取組は、これまで述べてきたように、今日の環境問題を解決する上で重要な役割を果たしている。事業者の自主的取組なくして、今日の環境問題は決して解決されることはないと言って過言ではなかろう。
一方、自主的取組は、次のような性格を持っていることも忘れてはならない。
その第一は、自主的取組だけでは必ずしも社会的に望ましい水準まで環境対策が行われるとは限らないということである。我が国では、かつて深刻な産業公害を経験したが、その原因は、当時規制が全くなかったか、あるいはあったとしても緩いものであったため原因企業が自らできる範囲の対策しか取らなかったことにある。他の企業との競争下にある個々の企業の自発的意思だけでは厳しい対策は困難である。また、個々の企業が自主的に拠出できる資金にも限りがある。こうしたことから、自主的な取組は社会全体として見た場合不足しがちである。
環境にやさしい企業行動調査では、上場企業の85.0%が規制の遵守以上に環境への配慮を心がけており、また低負荷型の生産技術など長期的には企業の利益につながる環境対策もあるので、自主性に委ねていても今後もっと多くの取組がなされると思われる。しかし、同じ調査では、「業績にかかわらず環境保全のための負担を行う」と回答した企業は上場企業でわずか7.4%にとどまっている。
第二は「フリーライド」の問題である。環境が良好な状態であることは誰にとっても利益になるが、そのために自ら費用を負担したり環境保全活動をすると、自分にとっても良好な環境が享受できるメリットはあるが、全く負担しない第三者も同じ利益を得ることができる。つまり、何も負担しない者も他人の自主的な行為にいわば「ただ乗り」することができるため、自ら負担をしようするインセンティブが失われてしまうことになる。このように、他人の行為に「ただ乗り」する「フリーライド」問題が生じ、対策を講じた企業が経済的にはむしろ不利になってしまう状況が起こりうる。
これらの特徴があるとしても、自主的取組の重要性はいささかも減じられることはない。今日の環境問題を解決するためには、事業者、国民の自主的な取組を踏まえ、問題の性質に応じて、規制的手法や経済的手法、環境影響評価、社会資本の整備等多様な手法を適切に活用していくことにより、経済社会システムの在り方や行動様式を見直していくことが必要である。
(6) エコビジネス(環境関連産業)の推進
ア エコビジネスの状況
環境基本計画では、「環境保全に関する事業活動(エコビジネス)の発展は、環境への負荷の少ない持続可能な社会を形成する上で重要であり、積極的な取組が期待される」としている。また、平成8年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のためのプログラム」では成長が期待される産業分野として環境関連産業がとり上げられている。
エコビジネスとは、環境への負荷が少ない商品・サービスや環境保全に資する技術やシステムを提供するビジネスのことをいい、あらゆる産業にまたがった横断的な商品・サービスを提供する産業である。
エコビジネスは今まで述べてきた費用負担を伴う環境保全活動とちがい、それ自体ビジネスであり、利益をあげうるものである。したがって、エコビジネスは企業が利益を追求する過程で自然発生的に生じた産業であり、利潤を上げるための企業の戦略的行動といえる。しかし、その前提となったのは環境保全のための法規制であり、自主的取組の増加である。
イ 経済構造の変革と創造のためのプログラムにおける環境関連産業
平成8年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のためのプログラム」では、環境関連産業として具体的に、エコマテリアル、低公害車等の環境調和型製品製造業、廃棄物処理・リサイクル産業、公害防止装置、廃棄物処理・リサイクル装置、環境分析装置等の環境関連装置産業、土壌浄化、水質浄化、都市緑化等の環境修復・創造産業等が挙げられている。その雇用規模、市場規模については、環境関連産業の範囲は一般的に定まったものではないため、一つの見通しではあるが、現状それぞれ約64万人、約15兆円であるところ、2010年には140万人程度、37兆円程度まで拡大するものと予測されている。
また、環境関連産業の健全な発展のための基盤整備を行うことが重要であり、具体的には、?地球温暖化への対応、?リサイクル施設・廃棄物処理施設等の整備や廃棄物の広域処理の促進といった社会システムの整備、?環境への負荷の低減に資する環境関連技術の開発・普及の促進、?事業者・消費者の環境マインドの醸成やこれをリードする人材の育成、?事業者の環境配慮を促す制度等の構築・改善、?環境関連産業の創業利益水準を確保するに足る市場の創造、?途上国への環境協力の促進等を図ることが重要であるとされている。
ウ 多様なエコビジネス
環境庁の調査によれば、エコビジネスの市場規模は1995年(平成7年)では約9兆円であったが、2000年には約13兆円、2010年には26兆円になると予測され、将来有望な市場である。環境にやさしい企業行動調査では、上場企業の約30.8%、従業員500人以上の非上場企業の11.3%がエコビジネスの事業化を既に行っており、また、上場企業の約3割、非上場企業の約2割が参入を予定又は検討している(第3-3-6図)。
エコビジネスは、概ね?環境への負荷を低減する装置、?環境への負荷の少ない製品、?環境保全に資するサービス、?社会基盤の整備、の4分野に分類することができる。このうち、環境への負荷を低減する装置の中の一部である環境装置産業は我が国が激甚な産業公害に直面したことを契機に大きな市場として成立し、平成7年度における市場規模は約1兆4千億円にのぼっている(第3-3-7図)。今後は、環境アセスメント制度の確立、容器包装リサイクル法の施行、ISO規格の発行などにより、環境アセスメント、リサイクル・省資源、環境コンサルティングなど、様々なエコビジネス分野の発展が見込まれている。
エ エコビジネスの課題
企業はもともと状況の変化、不確実性、リスクといったものをビジネスチャンスとして捉えてきた。環境保全も個々の企業にとっては新たな負担となるかもしれないが、そのような状況の変化はエコビジネスという新しい産業を生み、企業の積極的な環境保全活動が期待される状況においては、エコビジネスの一層の発展が見込まれている。
しかしながら、エコビジネスはビジネスであるがゆえに、採算がとれなくなると、それがたとえ環境にやさしい事業であって、社会的にも求められていたとしても、継続は困難となる。実際、古紙回収業等のリサイクル産業や環境への負荷が少ない商品・サービスなどは、バージン原料や環境への配慮を行っていない通常商品と常に価格競争を行っている。バージン原料の価格が下落すると、古紙回収業等は成り立ちにくくなり、また、環境保全型製品は社会的コストを負担しているため、通常商品より価格が高い可能性がある。このように、エコビジネスは常に環境配慮を行っていない商品やサービスと競合している(第3-3-8図)。
このような状況において、エコビジネス市場を育てていくためには、需要側、つまり消費者の環境意識の向上が必要である。そのためにも、国・地方公共団体等は、消費者の環境意識を高めるための普及啓発事業を行うだけでなく、自ら消費者として環境保全型製品の購入を率先的に行っていく必要がある(本節第2項参照)。また、企業は生産者と同時に消費者でもあり、低環境負荷型技術の導入や環境保全型製品の購入を積極的に行うことは、エコビジネスの発展に効果的であろう。
こうした状況を受けて、平成8年2月に、企業、地方公共団体、民間団体、学識経験者等の共同の取組として「グリーン購入ネットワーク」が結成された(第2章第4節参照)。グリーン購入ネットワークはグリーン購入の在り方を検討したうえで、積極的に環境保全型商品・サービスを購入していくという需要側の取組といえよう。
オ 地方公共団体との協力
地方公共団体と地元の事業者とが連携したエコビジネス推進のための取組がなされている。北九州市では、平成4年に「北九州環境研究会」が設立され、同研究会の協力の下平成8年3月に「北九州産業環境技術要覧」を公表し、北九州地域における環境関連技術の紹介を行っている。 また、北九州市では市の北側に位置する響灘に環境産業団地の整備を計画している(第3-3-9図)。この計画では、事業対象エリアを九州全域、中国、四国を含む幅広い地域を想定し、広域的なリサイクルシステムの構築を目指しているほか、収集・運搬システムについても、自動車による輸送を極力排除し、海上輸送、JRコンテナ輸送等環境への負荷の少ない効率的な大量輸送システムを構築することとしている。この事業では、道路、上下水道、港湾施設等のインフラ整備は市が中心に行うが、リサイクル事業については、地元の大手鉄鋼メーカーを中心に地場の中小企業や業界団体等が事業主体となっている。
この事業で特徴的なことは、単独ではエコビジネスとして成立しにくい分野に対し、地方公共団体、地元有力企業、地場の中小企業、業界団体等が、お互いに情報提供、技術協力、事業協力などを行い、採算性、公益性、継続性を考慮して事業を進めているところである。この事業は、エコビジネスを地域の産業構造の中に取り込み、地域経済全体が環境への負荷が少ないものとなることを目指しているのである。
エコビジネスは本来事業者の事業分野の一つであるが、採算がとれないエコビジネスの中には将来的に有望であるが初期段階での立ち上がりに苦慮する事業者もある。そのようなエコビジネスには環境保全の観点から国、地方公共団体が情報提供の場を作ったり、積極的にエコビジネスの需要者となるなど何らかの支援や協力を行う必要がある。このような公的部門の取組はエコビジネスの市場形成を促し、ひいては政府の活動や経済全体が環境配慮型になることにもつながっていくのである。