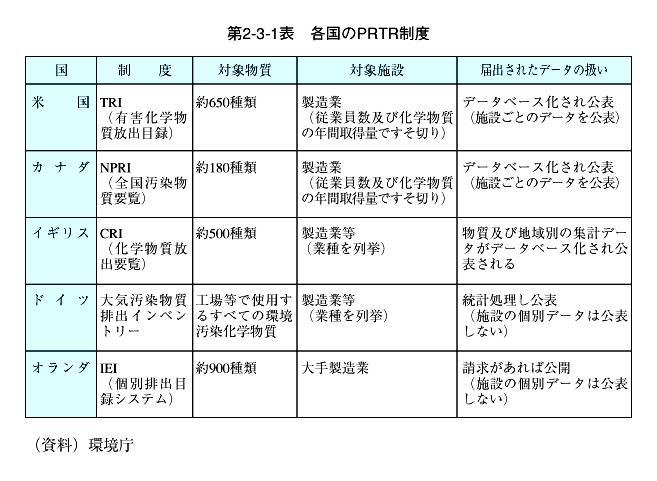
3 PRTR制度の構築に向けた取組
化学物質は、様々な用途に有用性を持ち、広範に用いられているが、その中には、生産、使用、廃棄等の仕方によっては人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがある。こうした化学物質による環境リスクを低減させるには、?環境への放出を抑制し、?汚染された環境からの暴露を防止し、?汚染された環境を浄化することが必要である。
このうち、「環境への放出を抑制」するという観点については、従来、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれについての知見の充実を図りつつ、大気汚染防止法や水質汚濁防止法に基づき対象物質を定め、環境への放出を規制してきたが、化学物質の数は余りに多く、この方式で環境中へ排出されている化学物質の大部分に対応することは非常に困難となる。
このような多数の化学物質に係る環境リスクについて、これを適切に管理していく新たなアプローチが求められている。このため、OECDが加盟各国に「環境汚染物質排出・移動登録」(PRTR=PollutantRelease and Transfer Register)制度の導入を勧告しており、OECD諸国のみならず、数多くの国でその導入が試みられている。
(1) PRTRの仕組み
PRTRとは、OECDによれば、「様々な排出源から排出又は移動される潜在的に有害な化学物質の目録又は登録簿」とされている。PRTRのシステムは、事業者が、規制・未規制を含む潜在的に有害な幅広い物質について環境媒体(大気、水、土壌)別の排出量と廃棄物としての移動量を自ら把握し、これを透明かつ客観的なシステムの下、何らかの形で集計し、公表するものである。
OECDは、PRTRの実施を検討している政府を対象にマニュアルを作成し、先の勧告においてマニュアルに記載された原則、情報を基礎として利用しつつ、各国において適切なPRTRの導入に取り組むことを勧告している。
まず、このPRTRには、環境汚染物質の大気、水、土壌への排出や移動に関する情報のほか、処理施設に運ばれる廃棄物についての情報も含まれる。また、登録簿は、ベンゼンなど、物質ごとについての報告であるので、国内の必要性に合わせたPRTRの作成と実施は、政府が経時的に様々な汚染物質の発生、排出、処理を追跡する手段となる。
また、このシステムは、?規制、未規制の化学物質を含み得る潜在的に有害な化学物質を対象とし、環境媒体(大気、水、土壌)別に排出を把握する、?報告された情報を分かりやすく、利用しやすい形で公表する、?公表された情報は関係各主体の化学物質の環境リスク対策の基礎として活用される、?報告情報の質を確保するとともに、企業秘密が不当に侵害されることがないように配慮する、というものである。
さらに、このようなPRTRには、
? 政府にとっては、環境汚染物質を排出・移動している主体はどこで、どのような物質が排出・移動され、地理的にどのように分布しているのかを把握することが可能となり、地域の各主体の汚染の改善又は環境汚染物質対策への取組を評価し、時間的な傾向を確認することができる。そして、国は、環境政策の進展の評価及び環境目標の達成状況と達成可能性の評価に役立て、
? 事業者にとっては、業種全体の排出、移動情報を得ることが可能となる。また、どれだけの貴重な物質資源が汚染物質として排出され無駄になっているかを知ることができる。さらに、このような情報を使って排出・移動量を削減することでコスト削減、効率向上、環境悪化の緩和を同時に行うことができる、
? 国民にとっては、環境リスクに対する理解が進み、適切な情報と理解の上に立った行政や企業との対話や、国民自らの環境リスクの低減行動が可能となる、
といった利点があるとされている。
Box25 PRTRと他の化学物質安全管理手法との連携
PRTRのほかにも、化学物質安全管理手法として、従来提案され、実施されているものがある。これらの手法とPRTRは共に包括的な管理を相互補完的に推進していくものである。
化学物質安全性データシート(MSDS)
MSDSは化学物質ごとに有害性をはじめとする物質性状やその安全な取扱方法等をまとめたもので、化学品のメーカーが作成し、ユーザー企業に伝達される。PRTRにおいて対象となる環境汚染物質ごとに排出量・移動量を把握するためには、ユーザー企業が自らが使用する化学品の成分を知ることが必要であるので、MSDSが実施されることで、PRTR対象物質の成分情報が末端ユーザーまで提供されるようになる。
化学物質の地域管理
地域における化学物質の総合的な環境安全性を確保するため、事業者による自主管理の徹底を基本とする化学物質の地域管理への取組がなされている。PRTRは、環境リスクの定量的把握に必要な暴露情報の系統的な把握の手段となるため、自主管理の促進やその実施状況の評価を可能にする。
レスポンシブル・ケア
レスポンシブル・ケアとは、化学物質を扱うそれぞれの企業が化学物質の開発から廃棄に至るすべての過程において、自主的に安全・健康・環境面の対策を行う活動である。PRTRに関する取組としては、このレスポンシブル・ケアの一環で化学物質排出量調査が実施されている。
環境管理・監査
環境管理・監査の重要な要素となり得る環境汚染物質の排出・移動量の客観的な点検・把握、自主的削減目標の設定等に際して、PRTRの情報は有効である。
(2) 各国における取組
PRTR制度は、既に米国、カナダ、オランダ、イギリスなどの国で導入されており、EU全体としては、主要な環境汚染物質について、データ収集・公表のためのシステムの導入が検討され、更にOECD諸国に限らず多くの国で導入の検討が行われている。主な国の実施例は、第2-3-1表に示すとおりである。
このように世界の国々において導入され始めているPRTR制度は、いずれも官民の取組促進のための基礎的情報の把握という点で共通している。また一方で、米国、カナダのように、住民への情報公開に主眼を置き、各事業者から届け出された施設ごとのデータがそのまま公表される制度や、オランダ、イギリスといった欧州型のように、排出抑制に主眼が置かれ、生データは集計等の処理を経て公表されるため、個々の施設ごとのデータはPRTR制度としては基本的には公表されない制度などそれぞれ特徴がある。
我が国でも、平成6年度から環境庁において包括的な化学物質対策の検討を進めており、平成8年6月に検討の取りまとめが行われ、?系統的な情報の収集と環境リスク評価の充実、?化学物質の包括的な管理、?情報の提供と各主体の取組の促進の三つを化学物質リスク管理の課題とした上で、PRTRをこの解決のための中心的方策として位置付けている。また、社団法人日本化学工業協会でも、PRTRに関する取組として、レスポンシブル・ケアの一環で化学物質排出量調査を実施し、その結果を化学品審議会で報告した。
(3) 国際機関における取組
PRTRは、1992年(平成4年)の国連環境開発会議(地球サミット)で採択されたアジェンダ21において、その意義が確認され、各国政府にその導入を推奨している。
また、OECDは、国際化学物質安全計画(IPCS)のPRTRに関するガイドライン作成依頼を受け、1996年(平成8年)2月、各国がPRTR制度を導入するに当たってのガイダンス文書を取りまとめた。そして、同月、OECD理事会は、「OECD域内のPRTRの実施に係る理事会勧告」を行い、加盟各国に対して「OECD作成のPRTRのための政府マニュアルに記された原則、情報を利用しつつ、PRTR制度を適切に構築し、実施し、公衆に利用可能なものとするよう取り組むこと」を勧告するとともに、OECD環境政策委員会に対し「加盟国の取組を本勧告の日から3年後(1999年(平成11年)2月)に理事会に報告すること」を指示した。
(4) PRTRの意義
様々な国々で取り入れられているPRTR制度は、先に述べたように、十分なリスク評価結果に基づき速やかに対策を講じることが困難な環境汚染物質を、その対象に多く含んでいる。このため、従来の環境中への化学物質排出規制制度とは、排出量の把握方法の考え方について大きく異なっている点がある。
それは従来の考え方ではリスク評価をはじめとして可能な限り厳密性を要求しているところであるが、PRTRにおいては、公平性や公正さの客観性の確保には留意するものの、環境汚染物質を排出する者の負担を軽減する観点から、排出量の把握等において簡便な推計が可能となるよう工夫がなされていることである。その結果得られたデータは、各種規制制度に基づく報告等のデータと比較すると科学的厳密性の観点からは劣るものの、それ以上の意義・効果をもたらしている。つまり、PRTRにおいては、実際にその結果を企業秘密等に配慮しつつ公表することにより、関係者がそれぞれ自主的に評価し、削減に取り組むこととなり、結果として、環境汚染の未然防止を図っていこうというものであり、これまでの規制的手法では対応できなかった問題に、新しい手法で対応していこうという意義を有しているということである。
こうした前提があるものの、PRTRにより得られたデータはこれまで全く把握がされていなかったものであり、このため、こうしたデータが把握されるということは、以下のような意義を有していると言える。
第一に、PRTRは、厳密なリスク評価に必要な情報がない潜在的に有害な物質まで含め、排出・移動量を把握し、その情報を収集・提供するシステムである。このため、人への健康影響、生態系への影響が懸念される潜在的に有害な環境汚染物質等を幅広く対象とすることが可能である。
第二に、PRTRにより、化学物質の排出量の把握及び情報提供を通じ、事業者の化学物質の自主管理を促進する。
第三に、PRTRにより、行政における環境リスク対策の立案、推進、対策効果の追跡、地域レベルでの環境リスク評価に用いられるなど、化学物質の包括的管理対策としての効果を発揮するとともに、他の有害な物質の管理手法の推進にも寄与する。
第四に、PRTRは、国、地方公共団体、事業者、国民、民間団体に対し、有害な物質の発生源と環境リスクに関する適切な情報を与えるシステムであり、これにより、各主体が理解、協力しつつ、適切な役割分担に応じた化学物質対策を講じることが可能となる。
以上のような意義を持つPRTRのシステムの導入を、我が国としても積極的に検討していくことが重要である。
(5) PRTRに関する合意形成
PRTR導入の検討に当たっては、前述のOECDのガイダンス文書が参考になる(第2-3-1図)。
このガイダンス文書では、PRTRの枠組みを示しつつも、その具体的内容については選択肢を示し、各国で導入されるべきシステムは、政府、産業界、国民、NGO等の関係者間の合意形成により形づくられるべきであるとしている。また、PRTRは、多くの物質を対象とし、多くの関係者を巻き込むものであるため、システムが適切に運用されるよう、本格的な実施の前に、特定地域等での試行を行うことを推奨している。
これに沿って、我が国においても、その導入に当たって、国、地方公共団体、事業者、国民、民間団体等の間で合意形成を図っていくことが不可欠である。
また、地域的なパイロット事業の実施に取り組むことも必要であり、現在、環境庁では地方公共団体等と協力しつつ、そのための準備を行っている。一方、PRTRに関する取組の産業界における体制整備を進めるため、現在、社団法人経済団体連合会において、準備に着手している。