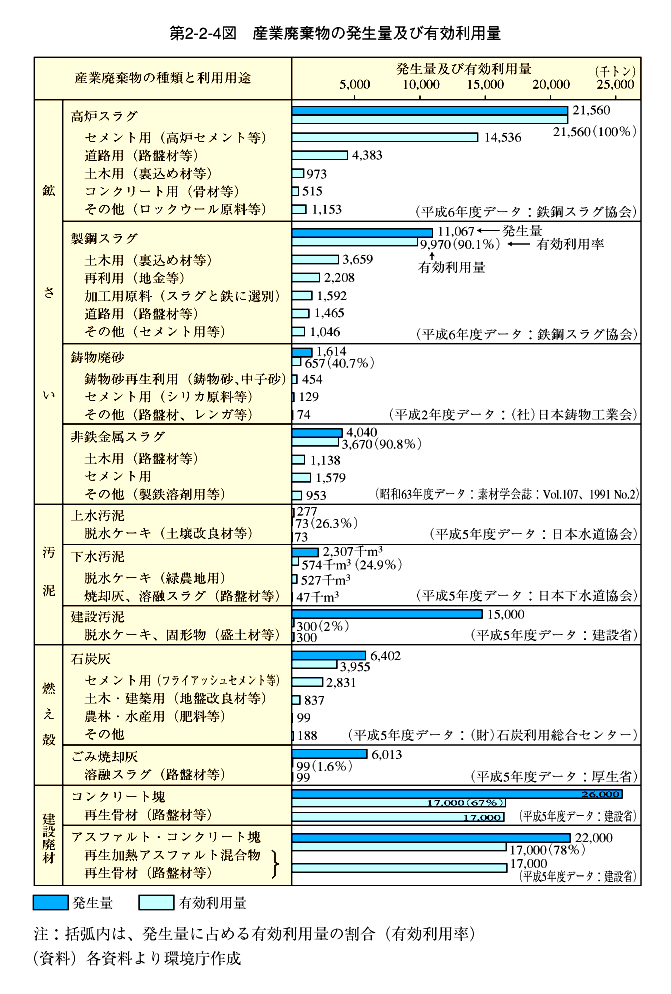
4 適正なリサイクルの推進
(1) リサイクルの推進の考え方
マテリアル・リサイクルは、廃棄物を回収し製品の原材料として再生利用するものであり、資源やエネルギーの消費を抑制するとともに、天然資源から原材料を生産する場合と比べて、環境への負荷が少ないケースが多い。また、マテリアル・リサイクルが行われたものは、再び原材料として利用されるため、マテリアル・リサイクルに伴って生じる処理残さが焼却処理されるならば、廃棄物をエネルギーとして利用する場合より、最終処分される廃棄物の排出量を少なくし得る。さらに、マテリアル・リサイクルは、廃棄物焼却施設からの排出物質をめぐる問題に対処する方策の一つともなる。
したがって、環境への負荷が総合的に見て少ない場合には、マテリアル・リサイクルが、廃棄物のエネルギーとしての利用よりも可能な限り優先されるべきであり、それが技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適当ではない場合には、環境保全対策に万全を期した上で、廃棄物のエネルギーとしての利用を推進すべきである。
(2) リサイクルの実施状況
ア 分別収集の状況
リサイクルを進めていくためには、排出時にその素材によって適正に分別することが必要である。これには、廃棄物対策のサイクルの中に排出者がかかわり、廃棄物の発生を抑制する必要性とその手法についての意識を高める必要がある。実際に、マテリアル・リサイクルが可能な廃棄物を再び生産過程に戻すためには、最終消費者が廃棄物を分別しなければならない。
ごみについて、再生利用の前提となる分別収集の状況を見てみると、平成7年9月現在で、市町村のうち65.0%が何らかの資源ごみの分別収集を行っており、平成5年6月時点の約42%に比べ大きく伸びている。
イ ごみ・産業廃棄物のリサイクルの実施状況
ごみについては、市町村における資源化と集団回収を合わせたリサイクル率(再生利用のための回収率)が平成5年度で8.0%(平成4年度は7.3%)にとどまっており、年々上昇しているものの、低いレベルにある。
産業廃棄物については、同一の排出過程から単一の性状で継続的に大量に排出されることが多いため、利用者から見れば原材料が安定的に供給されるという側面を有しており、リサイクル率は平成5年度で39%(平成4年度は40%)となっている。産業廃棄物の種類別の発生量及び利用用途別の有効利用量について見てみると、第2-2-4図のとおりであり、種類によっては、発生量の大半についてリサイクルが実現している。
一方、リサイクルされる量の増大に伴い、有害廃棄物等のリサイクルによる環境汚染を未然に防止するため、リサイクルを実施するに当たって環境配慮を行うことが必要となっている。
ウ 種類別のリサイクルの実施状況
有償で引き取られることが多いスチール缶・アルミ缶、ガラスびんについては、分別収集率・再資源化率共に高い水準にある。
スチール缶・アルミ缶のマテリアル・リサイクルの状況について見てみると、平成7年のスチール缶の生産量は142.1万tであり、再資源化量は104.8万tで、再資源化率は73.8%となっている(第2-2-5図)。アルミ缶については、平成7年度の国内総販売重量は26.5万t、再資源化量は17.4万tで、再資源化率は65.7%となっている(第2-2-6図)。
また、ガラスびんについて見てみると、平成7年のガラスびんの生産量は223.3万tであり、そのうち原料として使用されたカレット(使用済びんを細かく砕いたもの)の量は136.9万tで、カレット利用率は61.3%となっている(第2-2-7図)。
一方で、ペットボトル等のプラスチック類は、有償で引き取られることが少ないため、分別収集率は低い割合になっている。
(3) リサイクルを妨げる要因
このようにリサイクルは年々進められてはいるものの、再生資源の取引は、再生資源事業者によって経済的に成り立つ範囲に行われるにとどまり、ごみについては市町村がコストを負担しなければ業者が引き取らないという逆有償(廃棄時に有償で引き取られること)の問題も生じており、分別収集・リサイクルの普及促進の障害となっている。
例えば、第2-2-8図は、東京都内の再生資源の末端での引取価格の推移を示したものであるが、価格は一時的な上昇はあるものの、近年では低い水準で推移している。古紙、金属くず、古繊維等は、元々民間の事業としてリサイクルされてきたものであるが、例えば、新聞について見てみると、昭和55年3月には20円/kgとされていた引取価格が最近では0円かあるいは「設定できず」(0円でも引き取られず、引取りに際しては何らかの助成金が必要である状態)となってきている。
この背景としては、?再生資源・リサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品よりも需要が大きくなりにくいこと、?リサイクルを実現するための費用は廃棄物の最終処分費用に比べて高くなりがちであるが、その費用が各主体により適切に負担されていないこと等が考えられ、このように取引が逆有償化しているものの多くについては、リサイクルされずに最終処分されることになる。
このため、様々な製品の製造、流通、消費等の過程において、公平な役割分担の下で、ごみの排出抑制や再生利用のインセンティブを生じさせるようなリサイクルを促進する経済社会システムへの転換が必要である。
(4) 再生資源利用促進法
マテリアル・リサイクルの推進に関しては、再生資源の有効利用を確保するとともに廃棄物の発生抑制と環境保全に資することを目的とした「再生資源の利用の促進に関する法律」(再生資源利用促進法)が平成3年に制定され、同法に基づき事業者による再生資源の利用の促進が図られている。
この法律では、再生資源の利用の促進に関する基本方針を定めるとともに、?再生資源の原材料としての利用を促進すべき業種(特定業種=紙製造業、ガラス容器製造業、建設業)、?容易にリサイクルできるように材質、構造等を工夫すべき製品(第1種指定製品=自動車、エアコンディショナ、テレビ受像機、電気洗濯機、電気冷蔵庫、ニカド電池を使用する16種類の機器)、?容易に分別回収できるように識別のための表示を行うべき製品(第2種指定製品=スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、ニカド電池)、?再生資源として利用できるように品質等を工夫すべき副産物(指定副産物=鉄鋼スラグ、石炭灰、建設廃材)について主務大臣が事業者の再生資源の利用に関する判断基準を定め、これに基づき指導・助言を行い、必要な場合には勧告等の措置が採られることとなっている。
(5) 容器包装リサイクル法
ア 容器包装リサイクル法の概要
排出される一般廃棄物のうち容積比で約60%、重量比で約25%を占め、再生資源としての利用が可能な缶、びん、プラスチック容器等の容器包装廃棄物についてリサイクルを促進することを目的として、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が平成7年6月に制定された。市町村が収集したごみのリサイクルはこれまで市町村の負担により行われてきたが、同法は、容器包装廃棄物について、消費者、市町村、事業者が責任を分担することにより、それぞれがごみの減量化、リサイクルの推進に積極的に取り組む社会システムの構築を目指すものである。
容器包装リサイクル法の円滑な施行を図るためには、市町村、消費者、事業者の三者が協力して、それぞれの役割を果たすことが重要である。
まず、市町村の役割は容器包装廃棄物の分別収集を行うことである。消費者については、市町村が行う分別収集に協力(分別排出)することが求められている。また、特定容器(再商品化義務の対象となる容器)を利用する事業者、特定容器を製造又は輸入する事業者及び特定包装(再商品化義務の対象となる容器包装で特定容器以外のもの)を利用する事業者(これらを特定事業者という)は、市町村が分別収集した容器包装廃棄物について、その使用量や製造量等に応じて再商品化を行う義務を負う。
このように市町村、消費者、事業者の三者がそれぞれの役割を果たすことによって、消費者から排出された容器包装廃棄物の再商品化が進められることとなる(第2-2-9図)。
イ 容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品化の実施
平成9年4月から、容器包装リサイクル法に基づいて、アルミ製容器包装、スチール製容器包装、ガラス製容器、飲料用紙製容器及びポリエチレンテレフタレート(PET)製容器包装の分別収集及び再商品化が始められた。容器包装の区分ごとの全国の分別収集見込量は、第2-2-10図のとおりである。
なお、飲料用紙製容器以外の紙製容器包装及び飲料又はしょうゆ用のペットボトル以外のプラスチック製容器包装については、法の適用が3年間猶予されており、平成12年4月から全面施行されることになる。また、アルミ製容器包装、スチール製容器包装及び飲料用紙製容器については、現状では市町村が分別収集した時点で有償で売却され、利用されているため、特定事業者の再商品化義務対象とはしていない。
(6) オフィスの古紙回収システム
オフィスのOA化等により、オフィスでの紙の使用量が増加しており、特に印刷・情報用紙の使用量の増加が著しい。オフィスからは特にOA用紙系古紙、雑誌古紙、新聞古紙が多く発生しており、このような古紙の回収を促進するための枠組みづくりが各地で進められている。
第2-2-11図に示すとおり、平成7年の古紙全体の回収率は51.6%、古紙の利用率は53.4%であるが、日本製紙連合会の平成7年の調査によると、新聞古紙の回収率が106.7%(チラシを含む)、段ボール古紙の回収率が74.7%であるのに対し、上質・中質紙系古紙及び雑誌古紙の回収率は33.7%と再生利用が進んでいない。これは、?オフィスで発生する古紙が多様であるため古紙の品種別の分別や禁忌品の分別が十分でないこと、?品種別に分別されてもロットが小さいため回収コストがかかること等が要因と考えられる。このため、オフィスからの紙ごみの排出量は増大している状況にあり、東京都の平成7年の調査によれば、区部のオフィスビルのごみの排出量の63.6%(平成6年度)を紙ごみが占めている。
このような中、北海道中小企業家同友会函館支部では、平成7年11月から、会員事業所を中心として、オフィスにおいて生じる古紙の集団回収を実施している。平成9年4月末現在で、70事業所が参加している。
このシステム(第2-2-12図)では、対象古紙を「上質古紙」、「新聞古紙」、「雑誌古紙」、「その他」の4種類とし、効率よく回収するために三つのルートを設定し、各ルートにつき月1回回収を行っている。回収された古紙は、?回収コストが低い、?古紙が安定供給される、?禁忌品の混入率が低い等の理由により、市況より高い価格で回収業者により買い取られ、道内の製紙メーカーに納入されている。平成7年11月から1年間の回収実績は44.2tである。
事業系ごみ、特に古紙の再生利用を進めるためには、こうした複数の事業者間で資源を効率的に回収するシステムを構築することが有効であり、東京都千代田区・中央区の「オフィス町内会」の取組をはじめとして、千葉市、埼玉県浦和市など各地で古紙分別回収のシステム化が進められている。
Box21 生ごみ、畜産廃棄物等の再生利用のための取組
山形県長井市では、農業協同組合、商工会議所、市民らの協力を得て、平成9年2月から、地域で生じた生ごみ、畜産廃棄物等を堆肥化し、その堆肥を用いた地域での有機農産物の生産と消費を目標とする地域循環型の有機性廃棄物の再生利用を始めている。
これは、長井市のごみ収集量の約7割を占める地区において市が生ごみの収集を週2回行い、別に事業者により搬入される畜ふん、畜尿、もみ殻と共に堆肥センターで堆肥化し、生産された堆肥を農家や個人に販売し、その堆肥で栽培された農産物を市内の小売店で販売するというものである。
このリサイクルシステムは、ごみの減量化のみならず、有機農産物の生産・販売という目的も併せ持っているため、より市民の協力が得られており、市の推計によれば、生ごみの分別収集対象世帯のほぼ全世帯が適切に生ごみの分別排出を行っている。
(7) 使用済製品のリサイクル対策
ア 使用済製品の回収による有害な物質のリサイクル
びん、缶等の容器包装廃棄物については、容器包装リサイクル法により平成9年4月から分別収集及び再商品化が進められるが、その他の使用済製品についても、その廃棄等に係る環境への負荷を全体として低減させていくためには、使用済製品を効率よく回収し、適正な処理を行うとともに、再利用率を可能な限り高める仕組みの整備を進めることが必要である。
特に、廃棄後の環境汚染が懸念され、廃棄量が増大している使用済製品(例:電気・電子機器、電池、自動車等)に含まれる有害な物質の環境への侵入量を低減するため、平成8年6月に中央環境審議会がまとめた環境基本計画の進捗状況についての第1回の点検報告にあるように、これらの使用済製品のリサイクルシステムの構築・整備を進めるとともに、事態の推移を見ながら制度化について検討を具体的に行うことが必要である。このような方向を目指して先進的な取組を進めているのが欧州諸国、特にドイツである。
イ 欧州における取組
欧州連合(EU)では、1991年(平成3年)の有害物質を含む乾電池及び蓄電池に関する理事会指令において、各国は、水銀、カドミウム、鉛を一定量以上含む電池については、製造者に対し無料引取り及び表示を行うことを義務付けること、さらに、適切な場合にはデポジット・リファンド制度を導入することを求めている。また、各国は有害物質の削減等についての計画を策定し、理事会に報告することとされている。
ドイツにおいては、例えば、1996年(平成8年)2月のドイツ自動車工業会自主規制書によると、ドイツ自動車工業会は自主的に自動車の引取りとリサイクルを行い、廃車から油類を抜き取った上で、廃車を分解し、その部品と材料の利用を環境と適合した形で行うことを約束している。また、1992年(平成4年)の廃電機・電子機器政令案については、ドイツ国内の意見調整にまだ時間がかかることから、情報技術機器に限定して政令を先行して施行する方向で検討が進められている。情報技術機器の廃棄物処理に関する政令案では、パーソナルコンピュータやモニタ等の電機・電子機器を対象に、製造業者及び販売業者に対し使用済製品の引取り義務等を課す内容となっている。さらに、1992年(平成4年)の廃電池政令案においては、水銀、カドミウム、鉛を一定量以上含む電池を有害な物質を含む電池とした上で、製造者に対し無料引取り及びリサイクルの義務付けが提案されている。
ウ 我が国の家電製品・自動車のリサイクルの現状
我が国の家電製品のリサイクルの現状について見てみると、第2-2-13図に示すとおり、処理の形態は小型製品と大型製品とで異なる。小型製品は、主として一般廃棄物として市町村により回収・処分されており、一方、大型製品は、自治体ルートの回収と家電販売店で引き取られる販売店ルート(逆流通ルート)があり、市町村又は資源回収業者等を経由して資源化・減量化された後処分されている。破砕施設がある場合は、破砕後、選別処理によって鉄くず、銅くず、アルミくず等の金属分が再生資源として回収・再利用され、プラスチック、ガラス、木くず等のシュレッダーダストは焼却・埋立処分される。破砕処理施設がない場合は、原型のまま埋立処分されている。
また、自動車のリサイクルの現状については、我が国の使用済自動車は第2-1-22図で見たように年間400万台程度発生すると推定されているが、現在使用済自動車のほぼ100%が最終所有者から回収されており、解体事業者によって再生可能な部品・金属系材料が取り外され、残余の廃車体はシュレッダー業者によって破砕され各種金属スクラップを回収した後、シュレッダーダストが焼却・埋立処分されている。重量ベースで見てみると、約75%がリサイクルされている。
エ 今後の取組の方向
我が国においても、特に有害な物質を製品に含む自動車や家電製品等のリサイクルについては、社会的関心も高く、関係業界でも取組を進めようとしている。このため、国内での状況のみならず、欧米の動向まで把握し、環境汚染の防止の観点からリサイクルの在り方を中心とした新たな仕組みの検討が行われている。
環境庁では、「有害物質を含む使用済み製品のリサイクルのあり方検討会」において、国内外の実態の把握及び環境汚染対策の仕組み等について検討を行い、平成8年11月に中間報告を取りまとめた。同報告では、?有害な物質を含む部品の回収目標の設定等を通じてリサイクルを促進すべき、?新たに製造される製品に含まれる有害な物質を段階的に削減していくための目標設定等を推進すべきとの提言を行っている。今後は、同報告を踏まえ、?有害な物質を含む部品の回収によるリサイクルの促進については、引き続き、制度化を含めた検討を行い、?新たに製造される製品に含まれる有害な物質の段階的な削減対策については、長期的目標の設定等について調査研究を行うこととしている。
(8) リサイクルを推進していくための課題
経済社会システムにおける物質循環を確保するために、今後、一層リサイクルを推進していくことが必要とされるが、そのためには、次のような課題を挙げることができる。
? リサイクル技術の開発・普及
リサイクル製品の全体の経済性を高めることが必要であり、リサイクルの実施に要するコストを低減化させるようなリサイクル技術の開発・普及を促進することが求められる。
? 製品等のリサイクル性の向上と経済主体間の連携
原材料や製品のリサイクル性を向上させるとともに、生産及び流通のサイクルの中のすべての経済主体の間の連携を、一層緊密にすることも必要である。特に、リサイクルされる場合に、使用される原材料が分別容易であり、製品が分解されやすい設計になっていることが必要である。
? リサイクルに係るコスト負担についての理解
従来は、主として市場取引されるものについてリサイクルが進められてきたため、事業者、消費者等においては、リサイクルは低コストで実現されるものと認識されがちである。しかしながら、リサイクルを進める必要があるものの中には、現状の市場では事業としての採算がとれないものもあり、今後、リサイクルを一層進めていくためには、こうしたコスト負担についての各主体の理解を深めることが必要である。
? リサイクル製品の販路の確保
リサイクルされた原材料や製品の販路を確保することも重要な課題である。このためには、リサイクル製品の流通・利用を円滑化するための環境整備が必要であり、リサイクルを促進する観点からの基準や規格の明確化・見直し等が必要である。また、国、地方公共団体の物資調達においてリサイクル製品を積極的に利用することは、リサイクル製品の市場の育成に重要な役割を果たすことができるものである(本章第4節参照)。
? リサイクルに係る情報の提供
リサイクルは、すべての国民にかかわるものである。消費者は、特に、リサイクル製品の購入、廃棄物の分別排出、リサイクルのための費用の適切な負担等によってリサイクルの効果を上げることに大きく貢献し得る。このためには、事業者や行政からのリサイクルの実施状況や効果等に関する適切な情報の提供が必要である。
(9) リサイクルにおける環境配慮
廃棄物の排出量の増大等に伴い、リサイクル促進の必要性が高まっている中で、リサイクルされる廃棄物に含まれる重金属等の有害な物質に起因する土壌汚染・地下水汚染等の可能性が懸念されている。このような有害廃棄物等のリサイクルに伴う環境汚染防止対策について、早急に検討していく必要がある。このため、環境保全上適切なリサイクルの推進及びリサイクルに伴う二次的な環境汚染防止を図るため、廃棄物等のリサイクルに係る環境保全の在り方について、技術的、制度的な検討を更に行う必要がある。
(10) 廃棄物のエネルギーとしての利用
廃棄物の種類によっては、それを再び原材料として利用しようとした場合、かえってエネルギー消費等の環境への負荷の増大を招きかねない。このため、こうしたものについては、材料として使用した後に燃焼させてエネルギーを回収する方法を採ることが必要である。第1章第2節で見たとおり、多くの地方公共団体において、ごみの焼却に伴い発生する熱の有効利用を図るため、ごみ発電や熱供給を実施している。
廃棄物のエネルギーとしての利用は、地球温暖化対策という観点から、近年ますます重要になってきており、今後とも、このような廃棄物のエネルギーとしての利用は、一層推進していくことが必要である。しかし、廃棄物をエネルギーとして利用する施設のうち、燃料の代替品として廃棄物を利用するように当初から設計されていない施設については、有害な物質、特に重金属等の排出を抑えるため、十分な対策を採る必要があろう。