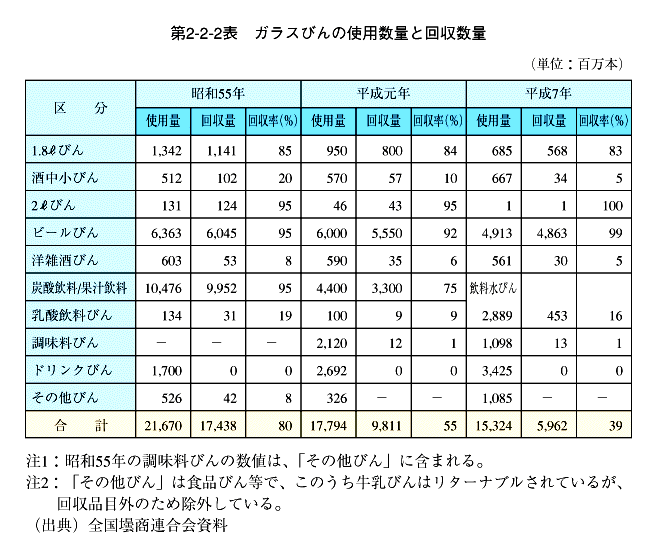
3 使用済製品の再使用(リユース)の推進
経済社会システムにおける物質循環を確保するための廃棄物・リサイクル対策においては、第二に、使用済みの製品について、その形状のまま再使用(リユース)することが必要である。
(1) 使用済製品の再使用の意義
使用済製品の再使用は、一般的に廃棄物の排出量の抑制に寄与するとともに、製品の原材料の採取、製造等に伴う環境への負荷を生じさせない。こうした使用済製品の再使用は中古品、中古車等として行われているほか、容器包装のうちリターナブル容器、リフィラブル容器等で実施されている。
使用済みの製品について、マテリアル・リサイクルが完全に行われれば、廃棄物の排出抑制効果はリユースを行う場合と同等であると考えられるが、実際には、回収したものを原材料としてすべて利用することは難しい。ペットボトル(ポリエチレンテレフタレート(PET)ボトル)について見てみると、生産量は年々増加傾向にある一方で、リサイクルが行われている割合は他の容器包装と比べて低いレベルとなっており今後リサイクル率の向上が望まれるものであるが、リサイクルが行われなかったものについては、埋め立てられるか、あるいは焼却されることになる。
また、使用済製品の再使用に係る総合的な環境への負荷の研究については、いまだ研究事例は少ないものの、ドイツ環境省のライフサイクル・アセスメント(LCA)の手法を用いた研究によれば、ガラス製容器では、輸送距離が100km以内、再使用回数が25回以上であれば、原材料消費、汚染物質の排出及び廃棄物減量化の面では、リターナブルびんの方が、ワンウェイ容器より環境への負荷が少ないことが指摘されている。
Box19 リターナブル容器・リフィラブル容器とは
〈リターナブル容器〉
ボトラー等において再充填(てん)される容器。ビールびん、一升びん、清涼飲料用びん等で実施されている。
〈リフィラブル容器〉
消費者や販売店において再充填される容器。洗剤、シャンプー・リンス等で実施されている。
〈ワンウェイ容器〉
その形状のまま再使用されない容器。リサイクルが行われるものと、使い捨てされるものとに分けられる。
このような使用済製品の再使用は、環境基本計画においては、廃棄物・リサイクル対策の四つのステップにおいて「廃棄物の発生抑制」に次いで採るべき対策として位置付けられている。また、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)においても、事業者及び消費者の責務として、容器包装廃棄物の排出を抑制するため、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用等についての努力義務が規定され、同法の国会審議においても容器包装の再使用の重要性が指摘されている。
(2) 使用済製品の再使用の状況
容器包装について我が国での再使用の現状を見てみると、以前は、主として、ビールびん、一升びん、清涼飲料用びん等のガラスびんのリターナブルシステムが構築されていたが、スーパー、コンビニエンスストア等の登場による流通システムの変化に伴ってリターナブルびんの回収機能が低下してきたことや、消費者の志向がリターナブルびんからワンウェイ容器へシフトしてきたこと等により、リターナブルびんの使用量は減少してきている(第2-2-2表)。このように飲料容器等に占めるリターナブルびんのシェアが一貫して低下しているのに対し、第2-2-2図に示すとおり、ペットボトルやワンウェイびん等のワンウェイ容器の占める割合が上昇しているなど、一方向型の流通システムはますます強まっている傾向にある。
一方、従来専ら経済性の観点から一升びん等のガラス製のリターナブル容器を使用してきた事業者の中には、近年の廃棄物の排出量の増大等を考慮して、ワンウェイびんがコスト的に優位となっても、リターナブル容器の使用を継続している例も少なくない。
(3) 諸外国の取組
諸外国においては、欧米諸国を中心として多くの国において、主に廃棄物の排出量削減の目的でリターナブル容器の使用を促進することとしており、そのための法制度が整備されている。
例えば、デンマークにおいては、ビールと清涼飲料の容器についてはリターナブル容器の使用を義務付けるとともに、金属容器の使用を禁止している。フィンランド、ベルギー及びノールウェーでは、ワンウェイ容器に対し課税することによりリターナブル容器の使用を促進している。また、これらの諸国を含めて、ドイツをはじめオーストリア、スウェーデン、スイスでは、強制的あるいは一定の条件の下にデポジット・リファンド制度(預託金払戻制度)を導入し、リターナブル容器の回収のインセンティブを与えている。
なお、ドイツでは、1991年(平成3年)に制定された「包装・容器廃棄物の発生抑制に関する政令」において、再利用率が政令で定められた比率の72%(ミルクの飲料容器については17%)を下回る飲料容器については、デポジット・リファンド制度の導入を義務付けており、リターナブル容器の使用にインセンティブを与えている。その場合、デポジット・リファンド制度の代わりに、包装材メーカー、容器包装メーカー、素材メーカー及び流通業者の出資により回収システム(デュアルシステム)を構築し、これにより回収等を行うことが認められている。
Box20 デポジット・リファンド制度(預託金払戻制度)
潜在的に環境への負荷を有する製品などにデポジット(預り金)を課し、当該製品又はその廃棄物が適切に返却されることにより環境への負荷が回避された時に払戻金を支払う制度である。OECD諸国の例では、飲料容器において多く見受けられ、その平均的な回収率は、おおむね80%程度であるとされる。また、このほかにも使い捨て電池やプラスチック、自動車など様々な導入例がある。
(4) 使用済製品の再使用の推進に向けた取組
使用済製品の再使用を進めていく際には、業態に配慮しつつ、容器包装のワンウェイやリサイクルによるコストを上回らない使用済製品の再使用の方法が検討されなければならないであろう。
環境庁では、「容器包装の再使用の促進に関する検討会」が平成8年8月に取りまとめた報告書を受けて、平成8年度から、プラスチック製のリターナブル容器の普及を図るためのモデル事業を実施している。製造メーカー、流通事業者など広く参加事業者を募りつつ、モデル事業の設計に着手しており、設計に当たっては、リターナブル容器の素材(ポリカーボネート)及び中身商品(ミネラルウォーター、ウーロン茶等)を決定した。その後、この樹脂の素材及び再使用段階での安全性について研究を行っており、平成9年度は、商品化に向けて、製造・流通・回収等において、具体的なシステムの設計を進めることとしている。
(5) 国民の意識
容器包装の再使用に関して、環境庁では、消費者及び事業者に対する意向調査を行っている。
環境庁が平成8年度に実施した「環境モニター・アンケート」(調査時期:平成8年6月、調査対象:全国の環境モニター1,500人、有効回答数:1,404人)において、容器包装の再使用の促進策について聞いたところ、消費者の多くは、リターナブル容器の規格化・統一化を進めることやリターナブル容器に対するデポジット制度を導入することに賛成であり、学校給食におけるリターナブル容器の使用の義務付けや、公的機関によるリターナブル容器を使用した製品の積極的な購入を行っていくべきであると考えていることが分かった。プラスチック製のリターナブル容器の導入を進めるべきとしている人も多かった(第2-2-3図)。また、事業者アンケート(調査対象:製造業及び小売業126社、有効回答数:43社)によると、リターナブル容器の導入に賛成する事業者もあるものの、小売店や消費者の受入れ可能性等の課題を指摘する事業者も少なくなかった。
また、総理府が平成8年2月に実施した「省エネルギー・新エネルギーに関する世論調査」によれば、ビールびんや一升びん等の再使用容器(リターナブル容器)について、「ごみの排出抑制等に役立つので、積極的に利用すべき」と答えた者の割合が69.5%、「経済性、利便性があれば利用すべき」と答えた者の割合が21.8%、「特に再使用容器(リターナブル容器)の利用にはこだわらない」と答えた者の割合が5.8%であった。