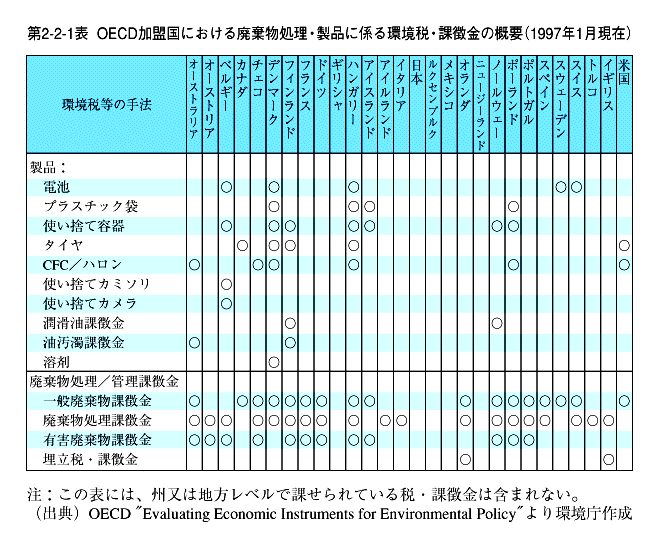
2 廃棄物の発生抑制
(1) 廃棄物の発生を抑制するための事業者・消費者の取組
廃棄物の発生を抑制するためには、製品等の開発、製造、輸入、流通、消費、回収、再生利用のそれぞれの段階で廃棄物が発生することから、製品等のライフサイクルの全段階において対策が講じられる必要があろう。
このため、まず、事業者においては、使い捨て製品の製造販売や過剰包装の自粛、製品の長寿命化等を図るなど製品の開発・製造段階、流通段階での配慮を一層行っていくことが必要である。また、消費者においては、浪費型のライフスタイルの見直し、使い捨て製品の使用の自粛等を進めていくことが求められよう。
また、有害廃棄物の発生を抑制するためにも、製品の設計又は製造の段階から、廃棄物の発生抑制のための配慮が十分に行われること等を推進する必要がある。
(2) 経済的手法の活用
廃棄物の発生抑制対策の一つとして、廃棄物の最終処分を行う際にその量や質に応じた金額を徴収する最終処分課徴金や、不用物の発生が少ない製品を優遇するため、製品の生産、輸入等に際しその量や質に応じた金額を徴収する製品課徴金等の経済的手法の活用が考えられる。このような廃棄物処理・製品に係る経済的手法は、事業者・消費者に対して、環境への負荷の少ない製品の製造や廃棄物の発生抑制を促すため、欧米諸国を中心として多くの国において活用されている(第2-2-1表)。
我が国では、一部の市町村においてごみの排出者から従量制により徴収するごみの処理手数料が導入され、ごみの排出抑制に効果を得ている。社団法人全国都市清掃会議が平成5年度の一般廃棄物処理事業の実態について実施した調査によると、従量制によるごみの有料化を実施している市町村は、家庭ごみについては438市町村(報告のあった市町村のうち13.6%)、事業系ごみについては1,527市町村(同50.2%)となっている。
Box17 製品の過剰包装の見直しに向けた取組
廃棄物の発生を抑制するため、事業者や消費者により製品の過剰包装を自粛しようという取組が進められている。
仙台市においては、資源の有効利用とごみの減量化を図るため、平成6年6月に消費者団体、小売業界、市によって「せんだい簡易包装推進ネットワーク」が設立され、消費者、事業者、行政の三者の協力による簡易包装推進運動が展開されている。
このネットワークでは、消費者と事業者の意見交換を行うほか、平成6年末から、ネットワーク加盟団体の協力の下に御中元、御歳暮商戦に向けた簡易包装推進キャンペーンを実施するとともに、平成7年9月からは、簡易包装運動を地域の一般小売店にまで広げるため、簡易包装に積極的に取り組んでいる店舗を登録する簡易包装推進店制度(平成9年3月現在127店舗)を始めている。また、平成8年9〜10月には、繰り返し使用できる買物袋を消費者に広めるためのキャンペーンを環境保護団体と共に実施するなど、様々な主体のパートナーシップにより簡易包装を推進するための取組を行っている。
ア ごみ処理の有料化の実施例(北海道伊達市)
北海道伊達市では、平成元年7月から、家庭系・事業系を問わずすべてのごみ処理に関して、従量制によるごみ処理手数料を徴収している。
その背景としては、それまで家庭ごみは無料で、事業系ごみは業種や規模に応じ有料(定額制)で処理していたが、昭和44年から供用を開始した最終処分場の残余容量が少なくなったため、ごみの減量化を図ることを目的として、ごみ処理施設(焼却炉・破砕機)を設置したということがある。これにより新たに施設の維持管理費の財源を確保する必要が生じたため、受益者負担の考え方からその一部について、ごみの排出量に応じて市民及び事業者から徴収することとした。
ごみ処理手数料は、可燃物・不燃物ともに、市が収集・運搬する家庭ごみは20l当たりで30円、40l当たりで60円、排出者がごみ処理施設へ直接搬入するごみ(自己搬入ごみ)は100kgまで370円、100kgを超える場合は10kgまでごとに37円となっている。平成7年度における1世帯当たりの年間の平均手数料負担額は約4,084円(1日当たり約11円)であった。
イ ごみ処理の有料化に伴うごみの排出抑制効果
伊達市におけるごみ処理の有料化は、ごみ処理施設の維持管理費の財源確保を直接の目的とするものであったが、ごみ処理の有料化に伴い、ごみの発生抑制とリサイクルが促進された結果、ごみ処理手数料制度の導入(平成元年7月)前後の伊達市のごみ排出量には大きな変化が見られる(第2-2-1図)。有料化が実施される前の昭和63年度のごみの排出量と比較すると平成元年度には23.7%減少し、平成2年度では昭和63年度比37.0%減となった。以降はごみ排出量は漸増しているが、平成7年度においても昭和63年度比22.0%減となっている。
ごみの排出量が激減した要因としては、?ごみの処理に対する関心が高まりコンポストの利用等によりごみの排出が抑制されたこと、?以前から自治会、子供会、婦人会、老人クラブ等によるリサイクルシステムが存在していたこと等が考えられる。また、有料化に伴う不法投棄や条例違反ごみ(手数料を納付していないもの)の問題に対しては、清掃指導員による監視等により対処しており、これらの発生件数は年々減少傾向にある。
他にごみ処理の有料化を実施している滋賀県守山市(昭和57年7月導入)、岐阜県高山市(平成4年4月導入)、島根県出雲市(平成4年4月導入)等においても、有料化を開始した年からごみの排出量は減少化している。排出量の減少率は最も減少した時点で20〜60%程度となっており、有料化に伴うごみの減量効果が長期間にわたって継続している例もある。
ウ ごみ処理の有料化についての課題
ごみ処理の有料化は、このようにごみの排出抑制に高い効果をもたらすと考えられるが、一方で、現在の有料化の実施事例においては、この効果が有料化直後の一時的なものであり、長期的には徐々に元のライフスタイルに戻ってしまう傾向も見られる。
この要因としては、?多くの自治体において手数料にごみの適正処理に必要なコストが十分に反映されていないこと、?ごみの発生抑制・リサイクルが長期的に実施されるような方策が併せて講じられていないこと等が考えられる。ごみ処理の有料化にごみの排出抑制効果を期待する場合には、これらを十分に考慮して導入する必要があろう。
(3) 廃棄物の発生抑制に資するその他の取組
廃棄物の発生抑制に資するその他の取組としては、事業者等が環境保全のために自主的・積極的にとる行動を計画・実行・評価する「環境管理」が挙げられる。自らの活動によるすべての環境への負荷を点検することにより、廃棄物の発生量についての関心・意識を高めることにつながる。このような環境管理については、第3章第3節で詳述する。
環境への負荷の少ない製品を推奨するエコマーク事業やグリーン購入は、発生する廃棄物の量が少ない製品を奨励するものであり、廃棄物の発生抑制に関しても効果があると期待される。これについては、本章第4節で取り上げる。
また、事業者・消費者に対する廃棄物に関する情報の整備・提供を推進することも必要である。
Box18 東京都における事業系ごみ全面有料化
東京都では、平成8年12月から、都が収集する事業系ごみの全面有料化を実施している。これは、東京23区内のごみ量の約6割を占める事業系ごみについて、?事業者自己処理責任の徹底、?ごみの排出抑制・再利用・資源化の促進、?ごみ量に応じた排出者間の負担の公平性の確保を図ることを目的として、従来無料で収集していた1日平均排出量10kg以下のごみについても排出量に応じた手数料を徴収することにしたものである。
事業者は、ごみを事業系ごみと家庭ごみに区別し、事業系ごみにはごみの容量に応じた有料シール(10kg54円、20kg 108円、45kg 243円、70kg 378円)を貼って出すことが義務付けられた。都の推計によると、事業系ごみの有料化による事業者の経済的負担は、全事業所平均で1事業所当たり約4,600円/月となる。
都では、有料化に伴うごみ減量効果は、平年度ベースで都が収集している事業系ごみ量の約10%となるとしており、これは23区のごみ量全体の約3.2%に相当する。
都の調査によれば、有料化導入以降の3か月間(平成8年12月〜平成9年2月)での23区のごみの減量化率は6.8%であったが、都では、事業系ごみのリサイクルシステムが成熟していくことにより減量化は更に進むものと見ている。