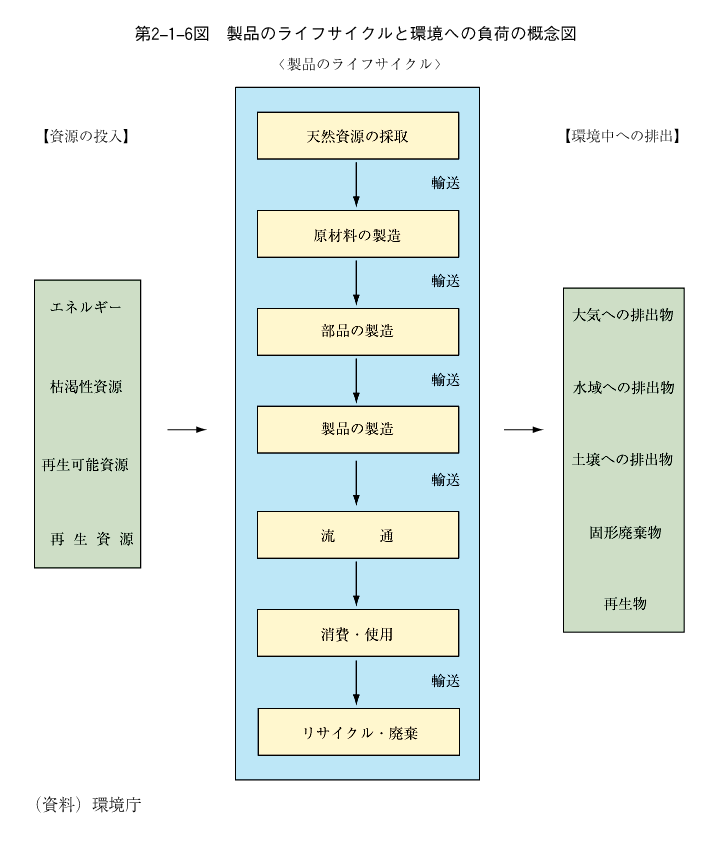
2 生産・消費の増大に伴い高まっている環境への負荷
(1) 我々の経済社会システムと環境とのかかわり
ア 今日の社会経済活動と環境
このような現代の大量生産・大量消費型の経済社会システムは、果たして何をもたらすのであろうか。
我が国の社会経済活動はこの半世紀で急激に拡大し、我々は世界の中でも極めて高水準の「物質的に豊かな」生活を享受できるようになった。我々が健康で文化的な生活を営むためには、食料や家電製品など様々なモノを必要とするが、今日の我々の社会経済活動やライフスタイルは、経済効率や快適性・利便性を追求するあまりに大量生産・大量消費型となり、多大な資源を必要とするとともに、多量で質的にも自然界では分解することが困難な物質を廃棄物、排出ガス、排水等の不用物として環境中に排出することによって成り立つものとなってしまっている。すなわち、資源やエネルギーといった「モノ」の流れから見てみると、「使い捨て」、「一方向」の社会となっていると言える。
こうした環境への負荷について、製品の原料採取から廃棄に至るまでのライフサイクルで見てみると、第2-1-6図に示すとおり、資源を自然界から採取するとき、資源を加工し生産活動を行うとき、製品を輸送するとき、製品を使用し廃棄するとき等のそれぞれの段階で生じている。
イ 我が国のマテリアル・バランス
このような環境への負荷を生じさせている我々の社会経済活動における物質の利用の状況をマテリアル・バランス(物質収支)で見てみよう。我が国では、経済活動への資源の投入、不用物の排出等の物質のフローを試算し、平成4年版環境白書から毎年掲載している。第2-1-7図は平成7年の我が国のマテリアル・バランスである。
我々の経済活動に伴う環境への負荷は、経済活動に商品として実際に投入される物質だけではなく、資源の採取段階での廃棄物の発生や、建設工事に伴う掘削、耕作による土壌侵食など、経済活動で商品として扱われる以前の物質のフローについても考慮する必要がある。このような観点から、本年の環境白書では、国立環境研究所が米国、ドイツ、オランダの調査研究機関と共同して行った研究をもとに、推計方法を見直すとともに、従来の物質の範囲に加えて、国内における建設工事に伴い掘削された土、鉱物採掘時の捨石・不用鉱物、耕作により侵食された土壌の量と、輸入資源の生産の際に発生した捨石・不用鉱物、侵食された土壌、間接代採された南洋材等の量(これらを「隠れたフロー」という)を含めた試算を行った。
これによると、平成7年における自然界からの資源採取量は19.3億t(平成6年比1.1%増)(うち海外からの輸入分は6.8億t(同7.4%増))、製品等の輸入量は0.7億t(同13.1%増)であり、実際に経済活動に投入された資源の量は19.9億t(同1.5%増)である。また、国内における「隠れたフロー」の量は12.2億t(同0.1%減)、海外における「隠れたフロー」の量は25.2億t(同5.3%増)であり、実際に投入された資源量と「隠れたフロー」とを合わせた平成7年の我が国の総物質需要量は57.3億t(同2.8%増)(国民1人当たり45.7t(同2.4%増))である。同様の試算方法により、昭和50年からの我が国のマテリアル・バランスを試算してみると、総物質需要量は、増減はあるもののおおむね一貫して伸び続けており、平成7年には昭和50年の1.38倍(1人当たりでは1.23倍)に増加している(第2-1-8図)。また、平成7年において、新たに蓄積された量は12.6億t(平成6年比2.7%増)、不用物として排出された量は8.4億t(同0.4%減)であり、再生利用されて再び資源として投入された量は2.1億t(同1.5%増)である。
このような我々の経済活動に伴い生じている環境への負荷を、資源の採取に伴う環境への負荷と、不用物の排出に伴う環境への負荷として、廃棄物の排出量の増大と質の多様化による環境への負荷、様々な物質による環境への負荷について見てみたい。
(2) 資源の採取に伴う環境への負荷
資源の採取に伴って生じる環境への負荷としては、鉱物資源等の非再生資源の採取に伴うものと、森林資源等の再生可能な資源の採取に伴うものの二つに大きく分けられる。
ア 非再生資源の採取に伴う環境への負荷
我が国は、第2-1-3表に示すとおり、原油、鉄鉱石等の多くを海外に依存しており、これらの非再生資源の採取に伴う環境影響もその多くが海外で生じている。
鉱物資源の採掘に伴う環境影響の主なものとしては、?地表の直接的な破壊、?資源採取や精錬作業に伴う水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、?大量の捨石・不用鉱物の発生が挙げられる。このような鉱物資源の採掘に伴う環境影響を正確に量的に把握することは困難であるが、前出のマテリアル・バランスでは、このうち鉱物資源の採掘に伴う捨石・不用鉱物の発生量(平成7年)の試算を行っており、これによれば、我が国における鉱物資源の採掘に伴う捨石・不用鉱物の発生量を0.3億t、我が国が輸入した鉱物資源の採掘に伴う捨石・不用鉱物の発生量を22.9億tとしている。
イ 再生可能な資源の採取に伴う環境への負荷
(ア) 森林の伐採による環境への負荷
再生可能な資源の採取に伴う環境への負荷の例としては、森林の伐採によるものが挙げられる。我が国の木材供給の状況を見てみると、平成7年における我が国の木材供給量は丸太材積換算値で1億1193万m
3
(前年比2.2%増)であり、このうち約8割を外材に依存している(第2-1-9図)。我が国は世界有数の木材輸入国であり、1994年(平成6年)のFAO(国際食糧農業機関)の調査によれば、世界全体の輸入量のうち、産業用材で37.2%、製材で10.2%、合板等で14.9%、木材パルプで11.8%を我が国が占めている。
森林の伐採に伴う環境影響としては、地域レベルから地球的規模までの影響が考えられる。まず、一地域の木材資源への過重な依存は、適切な配慮がなされない場合には、地域的な環境悪化を招く可能性がある。木材・薪炭材の資源の不足、洪水・渇水の発生等は、地域社会の安定的発展を阻害することも考えられる。また、地球規模での影響としては、生態系への影響が考えられる。さらに、森林の減少による土壌に対する劣化や地球温暖化への影響も懸念されている。
前出のマテリアル・バランスでは、南洋材の伐採に伴い間接的に伐採された木材の量について試算している。これによると、我が国が輸入した丸太、製材、合板及びウッドチップの伐採・製造に伴って間接的に伐採された南洋材の量(平成7年)を0.8億tとしている。
(イ) 食料生産に伴う環境への負荷
我が国の食料の自給率(供給熱量自給率)を見てみると昭和40年度の73%から平成7年度には42%と大幅に低下しており、我が国は食料の多くを海外に依存している。平成7年における我が国の食料品の輸入額は4兆7791億円に上り、肉類212.7万t、魚介類280.3万t等を米国やアジア諸国を中心とする広範囲の国々から輸入している(第2-1-4表)。
我が国が輸入している食料の生産に伴う環境影響としては、環境白書においてこれまで取り上げた、輸出用のエビの養殖池開発のためのマングローブ林の開墾による海岸生態系の破壊や、サンゴ礁におけるシアン化合物を用いた漁法による生態系への影響、プランテーションにおける農薬の影響等の事例が挙げられる。
また、食料の大量生産のため土地が持つ能力を超えた過度の耕作を行うことにより肥沃(よく)な表土が流出する土壌侵食の問題もある。平成6年度に我が国が輸入した主な農産物を生産するために必要な海外での作付面積は約1200万ha(国内の作付延べ面積の2.4倍に相当)に上っている。前出のマテリアル・バランスでは、我が国が輸入した食用、飼料用の穀物等(輸入畜産物の飼料換算分は除く。)の生産に伴う土壌侵食量について、我が国の穀物の輸入量の中で大きな割合を占める米国の耕地面積当たりの土壌侵食量を用いて試算しており、平成7年においては1.4億tになるとしている。
(3) 廃棄物の排出量の増大と質の多様化による環境への負荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」においては、廃棄物を「一般廃棄物」(産業廃棄物以外の廃棄物)と「産業廃棄物」(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の19種類の廃棄物)とに分類し、それぞれについて処理の方法、最終処分場の構造等の規制を行っている。また、一般廃棄物は、ごみとし尿とに分けられる。
ここでは、廃棄物の排出量の増大と質の多様化による環境への負荷として、ごみ・産業廃棄物が排出されている状況等について概観してみたい。
ア ごみの排出状況
ごみの排出量は国民の生活や社会の活動を反映して変化し、昭和45年ごろまでは増加の一途をたどってきたが、昭和48年の石油危機以後、一時減少し、横ばい又は微増の状態が続いていた。その後、使い捨て文化の広がりや耐久消費財の普及・大型化、製品の短寿命化による家庭ごみ(一般家庭の日常生活に伴って生じたごみ)の増大や、流通・サービス業の拡張、情報化・OA化の進展等に伴う事業系ごみ(事業活動に伴って生じたごみ)の増大等により、昭和61年より再び急激な増加傾向を示していたが、平成2年以降は、ごみ減量対策の進展のほか、景気の後退もあり、ごみの排出量は横ばい傾向にある(第2-1-10図)。また、埋立廃棄物の組成を見てみると、可燃物が減り、焼却灰(燃え殻)が増加している(第2-1-11図)。
平成5年度においては、ごみの総排出量は年間5030万t(東京ドーム135杯分、平成4年度は5020万t)であり、1人1日当たりの排出量は1,103g(平成4年度1,104g/人・日)で、前年度とほぼ同じであった。このうち、市町村において分別収集や中間処理により資源化された量は220万t(平成4年度193万t)、また、住民団体によって資源回収された集団回収量は192万t(平成4年度180万t)であり、市町村における資源化と集団回収を合わせたリサイクル率(再生利用のための回収率)は8.0%(平成4年度7.3%)と増加傾向にある(第2-1-12図)。一方、直接埋め立てられるごみの量と、ごみ処理施設からの処理残さ(焼却灰等)を合わせたごみの最終処分量は1496万t(平成4年度1530万t)となっている。このような平成5年度におけるごみ処理のフローを示すと、第2-1-13図のようになる。
また、都道府県別の1人1日当たりのごみの排出量、年間1人当たりのごみの最終処分量、1人当たりの一般廃棄物最終処分場の残余容量を図示すると、第2-1-14図のようになる。
なお、市町村におけるごみ処理事業経費は、第2-1-15図に示すとおり、昭和55年度以降、年々増加の一途をたどっている。平成5年度においては、ごみ処理事業経費の総額は2兆2833億円であり、このうち施設の建設・改良費が9820億円で、処理費及び維持管理費が1兆3014億円であった。このごみ処理事業経費を総人口で割り国民1人当たりに換算すると、18,272円かかっていることになる。
イ 産業廃棄物の排出状況
産業廃棄物の排出量は、平成5年度においては全国で約3億9700万tとなっており、平成4年度の排出量(約4億300万t)と比較して1.5%減となっている。平成2年度から平成5年度までの年増加率では0.5%となっており、近年、排出量に大きな変化は見られない(第2-1-16図)。種類別の排出量で見てみると、汚泥の排出量が最も多く総排出量の45.5%を占め、次いで、動物のふん尿、建設廃材の排出量が多く、これら3種類で全体の排出量の8割を占めている。業種別の排出量を見ると、建設業、農業の2業種が多く、全体の約4割を占め、次いで、電気・ガス・熱供給・水道業、鉄鋼業、パルプ・紙・紙加工製造業、鉱業の順となっている(第2-1-17図)。
産業廃棄物の処理方法は、種類や排出時の性状で異なるが、平成5年度において、脱水、乾燥、焼却等の中間処理が行われた産業廃棄物は約2億5100万t(全排出量の64%)で、中間処理後の処理残さ量は約9400万tとなっている。処理残さ量のうち約6700万tは、金属等の有価物として再生利用される。全体としては、産業廃棄物の年間排出量3億9700万tに対し、40%が中間処理により減量され、39%が何らかの形で再生利用されている。このような平成5年度における産業廃棄物の処理フローを図示すると、第2-1-18図のようになる。また再生利用の状況について見てみると、金属くず等の再生利用率は90%以上と高い値を示している一方、汚泥や建設廃材のように再生利用率が低く最終処分量が極めて多い品目がある(第2-1-19図)。そして、産業廃棄物の総排出量の21%に相当する約8400万tが、埋立て等により最終処分されている。
産業廃棄物処理施設の設置状況については、第2-1-5表のとおりである。
ウ 廃棄物の処理をめぐる問題
我が国における廃棄物の最終処分の状況について見てみると、ごみ、産業廃棄物の最終処分量は近年横ばいの傾向が見られるものの、平成5年度における廃棄物の最終処分量(約9900万t(一般廃棄物約1500万t、産業廃棄物約8400万t))の容積を推計すると約1億m
3
となり、これは東京都のJR山手線の内側(約65km
2
)に約1.5m積み上げた量に相当するものであり、毎年、ばく大な量の廃棄物が排出され、最終処分されている状況にある。
また、量的な面だけではなく、近年の廃棄物の質の多様化に伴い、有害な物質を含んだ廃棄物が最終処分場(埋立地)に搬入されているため、不適正な管理に伴う地下水や土壌等の汚染への住民の不安が高まっている。環境庁が行った調査でも、安定型最終処分場(Box14参照)から本来検出されるはずがないと考えられていた有害物質が検出されたほか、有機性汚濁の状況を見てみても基準値を超過していたものがあった(第2-1-6表)。
こうしたことから、第2-1-7表及び第2-1-20図に示すように、最終処分場の設置等をめぐって各地で紛争が生じており、最終処分場をはじめとする廃棄物処理施設に対する国民の信頼回復が緊急の課題となっている。
一方、廃棄物の最終処分量の増大に伴い、土地利用の高度化が目覚ましい我が国においては、特に首都圏・近畿圏の大都市圏とその周辺地域において、これらの廃棄物の最終処分に必要な最終処分場の確保が困難な状況となっている。
第2-1-21図に示すとおり、一般廃棄物最終処分場の残余容量は減少傾向にある。平成5年度における一般廃棄物最終処分場は2,321か所(平成4年度2,363か所)であり、その残余容量は1億4931万m3(平成4年度1億5367万m3)と減少している。残余年数(最終処分場として供用できる年数)は全国平均で8.1年分(平成4年度8.2年分)となっており、ここ数年はほぼ横ばい傾向にあるが、平成5年度の我が国のごみの最終処分量の25.8%(386万t)を占めている首都圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)においては、5.0年分(平成4年度4.6年分)と引き続き厳しい状況にある。
また、産業廃棄物の最終処分場の状況について見てみると、平成6年4月現在で、安定型最終処分場は1,639か所、残余容量7889万m
3
と前年比695万m
3
増であるものの、管理型最終処分場は1,011か所、残余容量1億1596万m
3
と前年比1273万m
3
減となっている。平成5年度における産業廃棄物の最終処分量、平成6年4月現在の最終処分場の残余容量から、産業廃棄物の最終処分場の残余年数を推計すると、全国平均で2.3年、首都圏では0.8年と依然として厳しい状況にある(第2-1-8表)。今後は、特に山間、平地等の内陸における処分場の確保が種々の制約条件により非常に困難となることが予想される。
こうした最終処分場の確保が困難になっている状況は、産業廃棄物の不法投棄の一因ともなっており、土壌汚染等の増大のおそれも生じている。厚生省の調査によれば、不法投棄量は平成7年度には建設廃材を中心として44.4万t(平成6年度38.2万t)に上るなど、産業廃棄物の不法投棄は依然として跡を絶たず、住民の産業廃棄物に対する不信感を生じさせる大きな要因となっている。
Box14 廃棄物最終処分場の種類
〈遮断型最終処分場〉
周囲をコンクリート等で固め、雨水等が入り込まないよう覆いを設けるなど、有害物の外界への浸出を遮断した処分場。産業廃棄物のうち、有害物質(アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐(りん)、六価クロム、砒(ひ)素、シアン、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、セレン)を含む燃え殻、汚泥、ばいじん及び鉱さいが対象。
〈管理型最終処分場〉
地下水等の汚染を防止するため、底にシートを張る等の遮水工を行い、浸み出した水を集め、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たすよう処理して公共用水域に放流する設備を備えた処分場。遮断型処分場又は安定型処分場の対象である産業廃棄物以外の産業廃棄物及び一般廃棄物が対象。
〈安定型最終処分場〉
廃棄物の飛散及び流出を防止する構造を有する処分場。性質が安定しており生活環境上の支障を及ぼすおそれが少ないと考えられる安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、建設廃材)のみが対象。
また、プラスチック等を焼却処理する場合において、焼却時に高温になるものは老朽化等している炉を傷める原因となっているほか、焼却温度等の焼却の条件によっては、焼却時に有害な物質を発生する可能性があることが指摘されている。
(4) 様々な物質による環境への負荷
我々は、金属や化学物質等の様々な物質を利用して経済活動を営んでおり、このような物質は現代社会においてなくてはならないものとなっている。しかし、その一方で、生産、輸送、保管、使用、廃棄等の各段階において、多種多様な不用物が環境中に排出され、その性質が環境汚染の原因となっているものがある。
例えば、地球規模で生じている問題としては、オゾン層の破壊がある(第4章第1節参照)。これは、不用物の排出が地球規模での大気の組成に変化をもたらすことによって生じる問題である。また、地域的にも微量の有害な物質が環境中に排出され、環境に有害な影響を及ぼす問題が生じている。
これらの有害な物質には、?水銀、鉛、カドミウム等の重金属、?PCB等の各種各様の意図的に製造された化学物質、?ダイオキシン等の非意図的に生成する化学物質がある。
戦後の高度経済成長の過程で、我が国においては、硫黄酸化物(SOx)による大気汚染や有機水銀による水質汚濁等の深刻な環境汚染によって多くの健康被害者が生じた。これらの原因物質は、工場、事業場の排出ガスや排水に含まれていたものであり、こうした有害な物質に対しては、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」等により、大気・水への排出の直接規制、製造・使用の制限が行われることによって、激甚な公害の防止が図られてきた。
このような問題に加えて、今日では、低濃度ではあるがこれらの物質に暴露されることにより人の健康だけではなく生態系にも影響が及ぶことが懸念されていること、また、生産された製品の使用段階や廃棄段階における環境への負荷により環境汚染がもたらされるおそれが生じていること等、新たな問題が生じてきている。ここでは、このような化学物質による様々な環境影響と、製品に含まれる有害な物質による環境汚染の問題について、見てみることにしたい。
ア 化学物質による環境影響
(ア) 各種各様の化学物質
現代では、多数の化学物質が人為的に製造され、様々な用途に使われている。その種類・量は増え続け、既に世界で商業目的で生産されているものは約10万種類、我が国で流通しているものは約5万種類あり、それらは製品材料として消費されるもの等を除き、何らかの形で環境中に排出される。これらの化学物質は我々の生活を便利で豊かなものにする一方で、その性状、環境中に排出される量によって様々な環境汚染の原因となる。
今日においては、法律により規制されていない物質の中にも、低濃度で暴露されることにより人の健康ばかりでなく生態系に影響を及ぼすものがあることが懸念されている。これらの影響は、発現までに長い時間がかかるが、いったん発現すると取り返しのつかない重大な影響を及ぼすおそれがある。また、環境中に長期間残留する物質については、一たび環境中に放出されると、その浄化は容易ではない。
環境庁では、化学物質の環境中の残留状況を調査し環境における安全性を評価するため、「化学物質環境安全性総点検調査」を実施している。この調査では、調査の優先物質のリスト(プライオリティ・リスト)に基づいて計画的な調査を実施し、環境中の残留が確認された物質のうち生物への蓄積が問題となる物質については、生物モニタリング(魚類、貝類、鳥類中の化学物質濃度の継続監視)を行っている。
平成7年度までの調査結果によれば、752種類の化学物質について調査を行い、このうち、3分の1を超える287種類が環境中(水質、底質、魚類、大気)から検出されている。
(イ) 低濃度汚染による環境影響
従来の環境汚染物質の安全性に関する基準は、ある一定程度以上の環境濃度になると悪影響が生じるという値(「閾(いき)値」という)を基に決められてきた。
しかし、物質の中には、急性毒性や通常の慢性毒性のほか、発がん性(幾つかの段階を経て正常な細胞をがん細胞に変化させる性質)、催奇形性(胎児に奇形を引き起こす性質)、生殖毒性(生殖機能に作用して不妊や流産など出生力に影響を及ぼす性質)等を有するものがあり、この中には、遺伝子毒性のあるベンゼン等のように、ごく微量に存在しても人への健康影響(発がん)の可能性が否定できず、閾値がないと考えることが適切な物質がある。また、現在のそれぞれの暴露レベルが閾値以下であっても、同様の作用によって影響を与える複数の物質又は一定の物質群に暴露することによって、無視し得ない影響が生じることも考えられる。
Box15 発がん性のある物質の数
これまでの動物実験の結果、動物に対して発がん性のある物質は約3,000種、催奇形性のある物質は約1,200種と言われている。
また、1995年(平成7年)に国際がん研究機関(IARC)が公表した化学物質の発がん性に関する有害性評価結果によれば、評価が行われた717物質のうち、これまで発がん性が確認されているものが36種、発がんのおそれがあるとされているものが240種であり、発がんのおそれがないと確認されているものは1種しかない。
(ウ) 様々な経路からの環境汚染
有害な物質の多くは、大気、水、土壌等の複数の環境媒体を汚染するとともに、媒体間でも移動する。例えば、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機塩素系溶剤は、様々な工場や事業場で油分や繊維製品の汚れを落とす目的等で用いられているが、これによる環境汚染は、大気、水、土壌等に及んでいることが明らかになっている。
また、環境中に存在する化学物質は、食物連鎖と生物濃縮を経て、魚介類等の環境中の生物を汚染する。PCBは、環境中で分解しにくく、生物の脂肪組織に蓄積しやすい性質(生物濃縮性)を有する化学物質であり、世界保健機関(WHO)の調査によれば、環境中におけるPCBの生物濃縮の程度は、最大で藻類が120万7千倍、マガキが16万5千倍、ミジンコが4万7千倍、魚類が27万倍となっている。人などへの暴露は、これらの複数の媒体からの吸収、飲料水や食品の採取等を通じて生じることが多い。
イ 製品に含まれる有害な物質による環境汚染
(ア) 製品に含まれる物質の多様化
高度な技術力に支えられた我が国の産業活動は多種多様な製品を生み出し、国民の様々なニーズにこたえてきた。今や我々の日常の生活は、電気・電子機器や自動車など高機能・高性能を持った製品なしでは営むことができないと言っても過言ではない。我々の中で使用されているこれらの製品は、生活水準の向上に寄与してきたが、一方で、製品に用いられている技術の高度化に伴い、製品に含まれる有害な物質の種類が多様化している。第2-1-22図に示すとおり、これらの製品は廃棄される量も多量であり、これらに含まれる有害な物質が環境中に排出されることによる環境汚染のおそれが懸念されている。
製品に含まれる有害な物質のうち広範な用途に用いられているものとして、鉛、カドミウム、水銀等が挙げられる。鉛はその材料としての有用性から、蓄電池、塗料、めっき等に広く利用されており、二輪車を含む自動車や、カラーテレビ、コンピュータモニタ等の家電製品等の最終消費財の一部も構成している。カドミウムは、蓄電池の材料のほか、塗料、印刷インキ等に用いられている。また、水銀は、蛍光灯等の電気機器や温度計等の計量器に用いられている。我が国におけるこれらの物質の需要量について見てみると、第2-1-9表のとおりである。
これらの物質に加え、最近利用が拡大している有害な物質に、アンチモン、ガリウム、ニッケル、セレン、砒(ひ)素等の物質が挙げられる。特に、レアメタルと呼ばれる重金属は、各種の新素材の主役として、電子機器産業、原子力産業、航空・宇宙産業等の先端産業で需要が拡大してきている。我が国は世界のレアメタル類の消費量の約20%を消費するレアメタル消費大国であるという報告もあり、これらによる環境への負荷も増大しているものと推定される。
Box16 重金属による健康影響
〈水銀〉
水銀蒸気暴露のある作業者では、興奮傾向・不眠といった症状が見られ、暴露期間の長期化に伴い、振せん、さらには筋けいれんと増悪する。メチル水銀の場合、神経系、特に中枢神経系への影響が最も重大である。水俣病は、メチル水銀が魚介類に蓄積し、それを経口摂取することによって起こった中枢神経系疾患である。
〈カドミウム〉
カドミウムの慢性中毒により、肺気腫(しゅ)、腎障害、蛋(たん)白尿が発生する。また、貧血、結石、骨代謝異常を伴う例が報告されている。富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、カドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカルシウム等の不足等が誘因となって生じたものである。
〈鉛〉
体内に取り込まれた鉛は骨に沈着する。産業の場で発生する中毒は大部分が慢性中毒であり、貧血、中枢神経等への影響が強く現れる。
(イ) 有害な物質のマテリアル・フローと環境への負荷
これらの有害な物質の環境への負荷を総合的に把握するための方法の一つとして、有害な物質のマテリアル・フロー(物質の採取から廃棄までの流れ)の試算が考えられる。マテリアル・フローが明らかになれば、そこから有害な物質の環境への負荷の状況をとらえることができる。
第2-1-23図と第2-1-24図は、鉛とカドミウムのマテリアル・フローの試算結果である。これらを見てみると、これらの有害な物質はいずれも、その供給の大部分を海外に依存している。重金属は、合成化合物等とは異なり、分解して消滅してしまうことがないため、国内へ流入しストックとなっている有害な物質は、究極的にはそのすべてが我が国の環境に対する負荷となっている。さらに、環境中の蓄積量を累計で見てみれば、既にこれまでに膨大な量が環境中に排出されてきているものと推測される。
製品に含まれている有害な物質のうち、環境中での汚染状況のデータが蓄積されているものは、鉛、カドミウムなどごく限られた物質だけである。これらによる河川、湖沼及び海域の汚染は、工場・事業場における取組が進んだ結果、大幅に改善されてきている。しかしながら、これらの物質についてのマテリアル・フローを見てみると、正確な値は不明であるものの、工場・事業場の排水口から排出される量よりも、使用済製品として廃棄された結果、環境中に侵入してくる量の方が多いと推定されることから、工場・事業場の排水口から排出される排出水に加え、廃棄物の焼却や埋立てに伴う大気、地下水、土壌の汚染に十分な注意が払われる必要があろう。