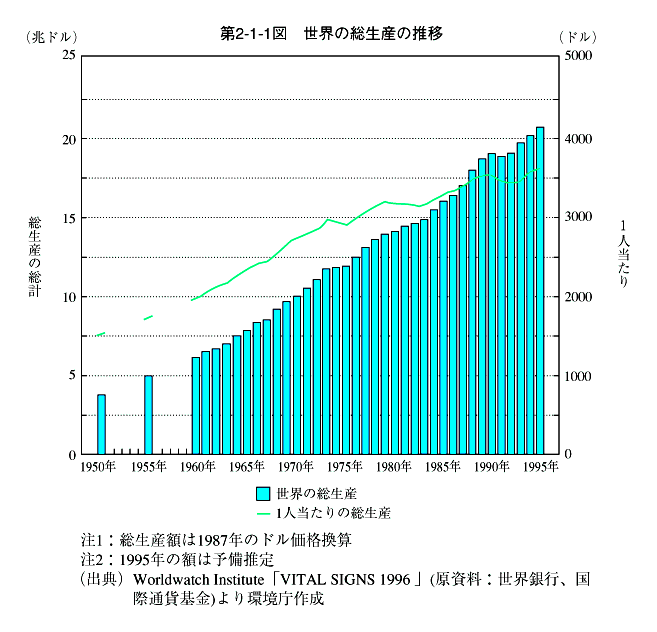
1 巨大化・多様化している今日の我々の社会経済活動
(1) 拡大する経済活動
産業革命以来、200年以上にわたり、先進国を中心として世界の経済活動は拡大の一途をたどってきた。特に、第2次世界大戦後は、人口と社会経済活動の規模は幾何級数的に増大し続けている。
世界の人口は、1900年(明治33年)には16.5億人であったものが、1995年(平成7年)には57.2億人と3倍以上に増えた。また、世界全体の経済規模について見てみると、世界の実質総生産は1950年(昭和25年)では3.8兆ドル(1人当たりでは1,487ドル)であったが、1995年(平成7年)には20.8兆ドル(1人当たりでは3,629ドル)にもなっている(第2-1-1図)。半世紀で世界の総生産は1人当たりでは約2.5倍、総額では5倍以上に拡大してきている。
特に、我が国は、国土面積は世界のわずか0.3%、人口も1億2586万人(平成8年)と世界の約2.2%を占めるにすぎないにもかかわらず、実質の国内総生産(GDP)を見てみると、平成8年までの40年間で総額で9.4倍(1人当たりでは6.7倍)にも拡大し、世界の総生産の約20%を占めるまでになり、世界第2の経済大国となっている。1人当たりのGDPを経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で見てみると、我が国がOECDに加盟した1964年(昭和39年)には21加盟国中17番目であったが、年々順位を上げ、1993年(平成5年)にはついに1位となっている。
(2) 物質的に豊かになっている我々の生活
このようにして我が国は世界の中でも高水準の経済発展を遂げ、我々の生活は「物質的な豊かさ」に恵まれるようになった。日本放送協会放送文化研究所が日本人の意識について5年ごとに実施している調査によれば、「着るものや食べもの、住まいなど、物質的に豊かな生活を送っていると思う」とする人は増加傾向にあり、平成5年の調査では72.6%の人がこのように答えている(第2-1-2図)。
実際、自動車、家電製品等の保有台数・普及率は年々伸びてきている。国別の自動車の保有台数を見てみると、我が国は、世界全体の約1割の自動車(平成7年で6685万台)を保有しており、米国に次いで世界第2位の自動車保有国となっている(第2-1-3図)。また、主な耐久消費財の100世帯当たりの保有台数の推移を見てみると、カラーテレビ、ルームエアコンが一家に2台以上ある家は今や少なくなく、電気冷蔵庫、電気洗濯機等もほとんどの世帯で普及してきている(第2-1-4図)。
また、我々の日常生活に身近なプラスチックと紙の生産量・消費量についても、共に飛躍的に増大してきている。プラスチックの生産量は平成7年までの40年間で約140倍にも増加し、1人当たりの年間消費量は平成7年では90kgとなっている(第2-1-5図、第2-1-1表)。我が国の紙・板紙の生産量も第2-1-5図に示すとおり平成7年までの40年間で13.5倍になっており、1人当たりの年間消費量は平成7年で239.1kgにも上り、国内消費量全体では世界の10.9%を占めるに至っている(第2-1-2表)。