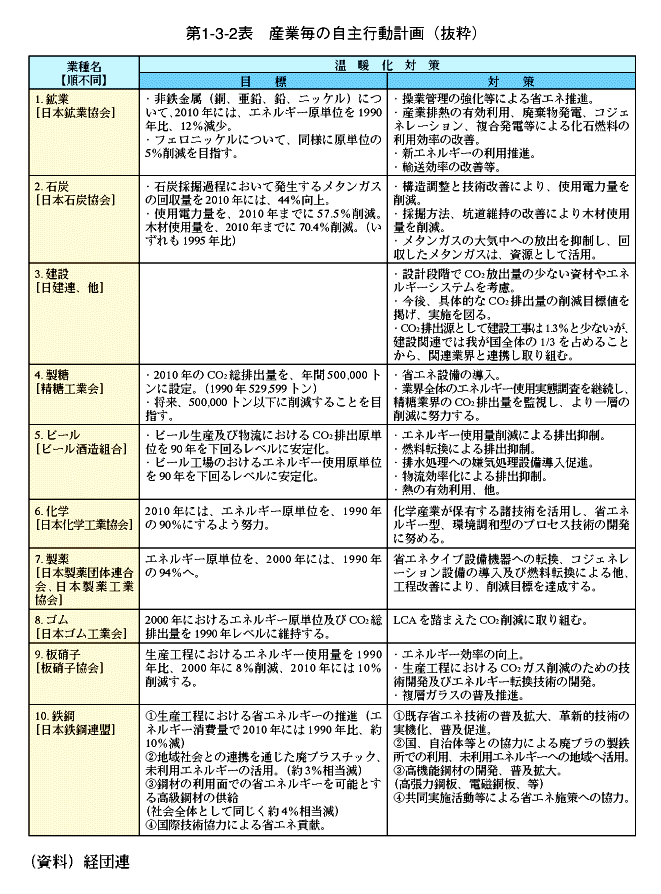
3 自主的な取組の促進
温暖化対策を進める上で、産業界や国民の自主的取組は大きな役割を果たす。
(1) 産業界の取組
我が国の産業界のCO2排出量は、産業部門で約4割、民生の業務部門を合わせると5割以上を占め、今なお最大のCO2排出部門である。産業部門は、今後さらに、自主的なCO2排出削減が求められている。
このような状況を受けて、近年、企業や業界団体において多くの取組が行われており、自主的な行動計画や意欲的な目標を掲げているところが出てきている。経団連は平成8年12月に「産業毎の環境自主行動計画」の中間発表を行った(第3章第3節参照)。この環境自主行動計画には、全体で29業種、131団体が参画しており、各産業が個別に?温暖化対策、?廃棄物対策、?環境マネジメント、?海外事業活動における環境保全の4つ行動を掲げて、それぞれの目標と対策を示している(第1-3-2表)。
この行動計画の中の温暖化対策では、生産過程での省エネ、コジェネレーションの活用、物流効率化、オフィスの省エネなど、様々な対策が打ち出されている。しかし、すべての目標が数値化されているわけではないので、具体的にどれくらいのCO2排出量が削減されるのかは明らかではなく、今後、行動計画の実効性の分析や進捗状況の点検等を行っていく必要がある。
また、このような自主行動計画の策定により、産業界の地球温暖化防止の意識がさらに高まり、また新しい技術の開発なども促進されることも考えられ、今後の産業部門における自主的、積極的なCO2排出の削減が期待されている。
個別の事例を見ると、鉄鋼メーカーのA社では、高炉内で鉄鉱石を還元する際に、コークスの代わりに廃プラスチックを利用している。鉄鋼業では石炭・コークスを原料として多量に使用するため、産業部門のCO2排出量の約32%を鉄鋼業が占めている。このため、廃プラスチックを高炉用還元剤として利用する製鉄工程は、CO2の排出量削減に非常に効果的であり、このようなCO2排出量の少ない生産工程の普及が期待されている。
一方、企業又は業界での取組に関しては、取り組んでいる業界と取り組んでいない業界がある状況から、製造メーカーの上流即ち原料製造、中間財生産でのCO2削減協力、川下メーカーへの協力、下請けや物流委託先への協力、最終製品の使用時、廃棄時のCO2抑制など産業連関の形態を考慮した業界間の連携も必要である。
(2) 地方公共団体の取組
地域における温室効果ガスの排出量は地域で講じられている政策や事業によって大きく左右される。このため、地球温暖化対策においても、地域住民に密着した行政を担う地方公共団体の果たし得る役割は大きい。地方公共団体の中には地球温暖化対策を条例の中に位置付ける動きがあり、また、2005年から2010年の間までにCO2排出量を1990年レベルから20%削減するといった自主的目標を掲げる地方公共団体もある(第3章第3節第2項参照)。また、国際環境自治体協議会(ICLEI)の活動や1995年(平成7年)で3回を数える世界自治体サミットの開催など地球温暖化防止に向けた世界の自治体の連携・協力も進んでいる。
地方公共団体の実施する地球温暖化対策としては、特に公共事業に関連した率先実行的な対策、公共交通機関の利用促進などの交通政策上の対策、廃棄物の減量化、リサイクル、廃棄物発電など廃棄物に関連する対策などが期待され、政府としても積極的に支援を行っていく必要がある。
(3) 国民一人ひとりの取組とNGOの役割
既に見たとおり、近年、国民のライフスタイルに密接に関連する民生部門及び運輸部門のCO2排出量が一貫して増加している。地球温暖化対策を実効ある形で進めるためには、国民一人ひとりが大量消費・大量廃棄型のライフスタイルを改めていくことが重要であるが、この面での動きは未だ芳しいものではない。ライフスタイルの変更を行うためには、日常生活の中で実行可能な取組が自発的な形で進められるとともに、それが国民運動的に広がっていくことが必要であり、その前提としては、国民が、地球及び将来世代のために、手間の増加、ある程度の利便性の低下、経済的負担の増加等となっても、環境保全に取り組むという気持ちを持って行動することが必要である。国民は経済社会の主人公であり、産業部門や公的部門も結局は国民に帰属するものである。したがって、経済社会の変革には、国民自身が変わることが最も重要であるといえよう。
また、前述の新エネルギー法では、エネルギー使用者について新エネルギー利用の促進のために努力する責務を規定しており、国民各層の自主的な取組が期待される。
しかしながら、現在の国民の地球環境問題、地球温暖化問題に対する意識は、世論調査等によれば、関心は持ちつつも具体的に何をすればいいのか分からないというものが多く、国民の積極的な運動は全体として低調である。地球温暖化問題を国民的な運動として盛り上げていくためには、適切な情報提供、例えば、パンフレット、シンポジウムや、さらにそれを根付かせるためには、家庭、学校、地域、企業等の様々な場面での環境教育、環境学習の機会の提供が重要である。その際、地球温暖化の影響や危険性を具体的にイメージできるような資料には大きな啓発効果が期待できる。また、日常生活から簡単にアプローチできるもの、例えば前節で紹介した「環境家計簿」等は効果的であり、一層の普及に努めていく必要がある。環境庁では1996年に環境月間を契機に「環境家計簿」や「アイドリングストップ」等を含む「4つのチャレンジ」を始めており、これは国民が日常生活の中で地球温暖化対策に取り組む手法として分かりやすく、今後もこれらの事業を積極的に展開すべきである。また、これらのものを含めた国民全体のアクションプラン的なものも効果的であろう。
また、環境NGOとして活動している団体や、地域でリサイクル活動や身近な自然保護活動をしているボランティア団体等は、地球温暖化防止に向けた国民の取組の中で、地域におけるリーダー的な、あるいはアドバイザー的な役割が期待されており、その果たすべき役割は大きい。
平成9年12月に地球温暖化防止京都会議(COP3)が我が国で開催されるが、このような地球温暖化問題に対する世界的な会議が我が国において行われることは、地球温暖化問題について国民の理解を深め、また地球温暖化対策を国民レベルで展開する絶好の機会であり、政府全体で国民的な運動を盛り上げていくことが必要である。