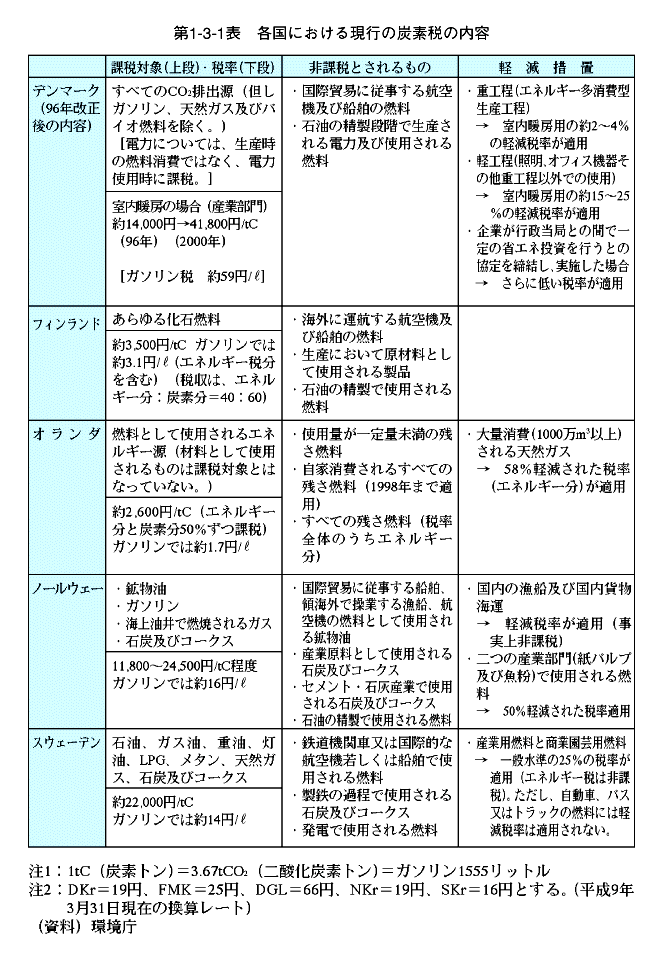
2 経済的な手法
温暖化対策として経済的手法についても期待が寄せられている。経済的手法には助成措置と経済的な負担を課す措置がある。
(1) 助成措置
これまで、エネルギーの効率的な利用を促進することを目的として、種々の金融上の助成措置が講じられてきているが、これらの措置はCO2の排出抑制にも効果を挙げている。
課税の特例措置としては、一定の省エネ効果等を有する設備の取得に対して、エネルギー需給構造改革投資促進税制によって7%の税額控除又は30%の初年度特別償却が認められている。
また、太陽光発電、風力発電、廃棄物発電などクリーンなエネルギーに対しても、第1章第2節で述べたように?補助金、?低利融資、?税制措置等の助成策が講じられている。
今後エネルギーの需要側、供給側双方で省エネルギーや新エネルギーの一層の推進が必要となっている。特に新エネルギーについてはクリーンで新しい利用形態としての展開が期待されている。
今後の省エネルギー対策やCO2の発生の少ない新エネルギーについては、導入の初期段階にあって量産効果等が発揮されておらず、既存エネルギーと比較してなお高コストであることは否めない。このため、金融上、税制上の措置は利用可能な省エネ技術や新エネルギーの導入を促し、CO2の削減に貢献している。新エネルギーの導入については新エネルギー法が制定されたところであり、こうした制度を活用するなど、今後とも、助成のために許される財源の範囲内で、また、助成すべき技術の選択に関し、いわゆる「政府の失敗」の発生を防ぎつつ、技術の進歩に対応しながら、適切な助成措置を講じていくことが必要である。
(2) 経済的な負担を課す措置
CO2の排出に対して経済的な負担を課す措置についても、CO2発生抑制のための手段として有効性が期待され、既に北欧諸国等で炭素税等が導入されている。炭素税は炭素の含有量に応じて課される税であり、CO2を多く排出すればするほど税の負担が大きくなるため、CO2の排出量を削減するインセンティブとなるものである。
製品・サービスの取引価格に環境コストを適切に反映させるための、環境に係る税、課徴金、預託払戻制度(デポジット・リファンド・システム)などの経済的負担を課す措置については、多数の日常的な行為から生ずる環境への負荷を低減させる点で、有効性が期待されるとともに、資源の効率的配分に資するものと考えられている。また、国際的にも推奨されており、欧米諸国等においても様々な活用事例が見られる状況である。
ここでは、炭素税を既に導入しているデンマーク、フィンランド、オランダ、ノールウェー、スウェーデンの5ヶ国の状況を見るとともに、国際機関での検討状況を見た上で、我が国における検討状況を見てみる。
ア 北欧諸国等の炭素税導入状況
(ア) デンマーク
デンマークでは、1993年から既にCO2税が導入されていたが、1996年に税制改正がなされ、CO2税に加えてCO2・エネルギー税、SO2税、天然ガス税、乾電池課徴金、塩素系溶剤税、農薬税等の創設、ガソリン税の引き上げ等からなる、より包括的な新環境・エネルギー税制が導入された。
この改正により、ガソリン、天然ガス及びバイオ燃料を除くすべてのCO2排出源に対してCO2税が課されることとなり、さらに室内暖房についてはCO2・エネルギー税が課され、税率は1996年時点での200DKr/tCO2(約14,000円/tC)から、毎年段階的に上昇し、2000年には600DKr/tCO2(約41,800円/tC)となることが決められている。
課税目的は、CO2排出抑制のための燃料節約や省エネ投資の促進、低炭素集約型の製品への代替促進などの、いわゆるインセンティブ効果である。CO2税は歳入増が目的でないので、税収はすべて還流されるという基本原則の下、?省エネ投資のインセンティブとしての活用、?企業の社会保障負担軽減、?中小企業者に対する補助金に使用されている。
なお、産業部門における生産工程でのエネルギー消費については、重工程と軽工程とに区別し、重工程には一定の軽減税率が適用されている。また、企業が行政当局との間で協定を結ぶことにより、低い税率が適用できる制度もある(第1-3-1表)。
(イ) フィンランド
フィンランドでは、1990年に世界ではじめて炭素税が導入され、あらゆる化石燃料が課税対象とされている。
税率は一律141Mk/tC(約3,500円/tC)であるが、併せて3.5Mk/1,000kWhのエネルギー税も課されている。したがって、フィンランドの炭素税は実質的には炭素・エネルギー税と言える。これらの税による収入の内訳は、エネルギー分が4割、炭素分が6割となっている。
課税目的は、CO2排出抑制のためのインセンティブ効果であり、税収はすべて一般財源として扱われている。
なお、石油精製で使用される燃料、海外で運行する航空機及び船舶の燃料、原材料として使用される石油は非課税となっている。
(ウ) オランダ
オランダでは、1992年に従来の一般環境課徴金に代えて、課税ベースをエネルギー50%・炭素50%とする燃料環境税が導入された。課税対象は燃料として使用されるエネルギー源であり、材料として使用されるものは課税対象とならない。また、電気を生産するときに使用する燃料に対しては課税されるが、電力の消費自体は非課税となっている。
税率は各燃料毎に定められており、さらに炭素分とエネルギー分が50%ずつの割合で構成されている。例えば、ガソリンにかかっている税額を炭素1t当たりに換算すると、約39DGL/tC(約2,600円/tC)となる。
課税目的は、CO2排出抑制のためのインセンティブ効果であり、税収は環境目的の特定財源として使用されていたが、1992年からすべて一般財源として扱われている。
なお、残さ燃料は非課税扱い又はエネルギー分のみが非課税扱いとなり、また大量消費される天然ガスについても58%軽減された税率が適用される。
また、1996年には小口エネルギー消費者を主な課税対象としたエネルギー規制税も導入されている。この税はCO2の発生を抑制するという目的に加え、課税対象を資本や労働に基づく所得から環境の使用へ移行させるという意図もあった。また、課税対象を小口エネルギー消費者に限定したのは、国際競争産業を含む大口エネルギー消費者の過重な経済的負担を軽減するという目的もあった。
(エ) ノールウェー
ノールウェーでは、1991年にガソリン、鉱物油、北海油田で燃焼されるガスを課税対象としてCO2税が導入された。CO2税は従来のエネルギー税に付加する形でかけられ、導入に際して大規模な税制改革が行われたわけではないが、全体として税負担が大きくならないように所得税の減税が併せて行われた。さらに、1992年には、燃料として使用される石炭とコークスも課税対象となった。
税率は、各燃料毎に異なり、622NKr/tC(約11,800円/tC)から1,290NKr/tC(約24,500円/tC)となっており、1995年まで毎年上昇している。また、他のエネルギー税については、1992年に主に産業保護のために鉱物油に対するエネルギー税が引き下げられたが、これを相殺するためにガソリン税の増税が行われた。
課税目的は、CO2排出抑制のためのインセンティブ効果であり、税収はすべて一般財源として使用されている。
産業用原料としての石炭及びコークス、セメント・石灰産業で使用される石炭及びコークスは非課税であるほか、国際貿易に従事する船舶、航空機等の燃料として使用される鉱物油や石油精製で使用される燃料も非課税となっている。
この炭素税の導入によって、1991年〜93年のCO2の排出量は、1年間に3〜4%減少し、約30万tのCO2の排出が抑制された(出典:ノールウェー中央統計局)。
(オ) スウェーデン
スウェーデンでは、1991年に包括的な税制改正の一環として、炭素税とエネルギー付加価値税が導入され、同時に既存のエネルギー税が引き下げられた。課税対象は石油、石炭、天然ガス等の化石燃料であるが、発電用の燃料消費は免除されている。
1993年には炭素税の増税が行われたが、併せて産業部門は他の部門の25%に軽減されたほか、産業部門と園芸部門への既存のエネルギー税もゼロとなった。その後、炭素税の税率はさらに上昇し、1996年時点では370SKr/tCO2(約22,000円/tC)となり、また産業部門への課税も2倍(185SKr/tCO2)となった。
課税目的は、CO2排出抑制のためのインセンティブ効果であり、税収は一般財源として扱われている。
なお、製鉄過程で使用される石炭及びコークスや鉄道機関車又は国際貿易に従事する船舶、航空機の燃料及び発電用の燃料消費は非課税となっている。
スウェーデンの自然保護庁の報告書によれば、1987年と1994年のCO2の排出量を比較すると民生・産業部門全体で約19%の減少が見られ、特に地域暖房において化石燃料からバイオ燃料等への転換が大きく進んだ。CO2の減少のうち、炭素税の効果によるものは約60%と評価されている。
上で述べたように、既に炭素税を導入した5カ国の炭素税は一様ではなく、課税対象、課税目的、税率、軽減措置など様々な特徴を有している。また、課税対象は概ね化石燃料であるため、ほとんどの国で既存のエネルギー税との調整を行っている。さらに、各国の炭素税率には大きな格差があるが、この格差は、既存のエネルギー税体系の違い等各国の個別事情や炭素税を炭素・エネルギー税として導入している場合があるためであり、炭素税の税率だけで単純に比較することはできない。
イ 欧州連合(EU)での検討状況
欧州連合では、その前進である欧州共同体(EC)の時代より炭素・エネルギー税について検討がなされている。
欧州共同体では、EC委員会が1992年(平成4年)に加盟国共通の炭素・エネルギー税導入に関する理事会指令案を採択したが、理事会では各国の意見が一致しなかった。
同指令案の課税対象は、特定の再生可能なエネルギー(太陽光、バイオマス、風力等)以外のすべてのエネルギー源であるが、特例措置として、エネルギー多消費型産業に対する免税あるいは軽減措置が設けられている。
また、税率については、炭素税部分が2.81ECU/tCO2(1,500円/tC)、エネルギー税部分が0.21ECU/G・J(30円/G・J)となっているが、EU加盟国は自国の炭素・エネルギー税の税率をこの税率より高く設定してもいいことになっている。
その後、欧州委員会は1995年(平成7年)に、EC指令案の修正案を提出した。修正案では、加盟国共通の炭素・エネルギー税の強制的な導入という最終目標は維持しつつ、2000年までを移行期間とし、その間は同税の導入については加盟国の大幅な裁量に委ねることになった。本件に関しては、各国共通とされる項目(課税対象、最低税率、税収中立等)について、現在もEU経済蔵相理事会を中心に検討がなされているほか、欧州委員会では既存のエネルギー税を活用することも検討されている。なお、欧州委員会は本年3月に、石油、石炭、電力、ガス等すべてのエネルギー産品にEUレベルでの最低税率を設定し、段階的に引き上げるという内容のエネルギー税指令の提案について委員会レベルで合意した。
また、スイス、ニュージーランドで炭素税の導入が検討されている。
ウ 国際機関等での経済的負担措置の検討状況
OECDでは、1995年の第1回気候変動枠組条約締約国会議を受けて、国際エネルギー機関(IEA)と共同で、先進国で将来的に共通に実施することが可能な温室効果ガス排出抑制や吸収源強化のための政策措置について作業を進めており、その中で炭素税(炭素・エネルギー税)や環境保全に対しディスインセンティブとなる補助金の廃止等について検討が行われている。
1997年3月にOECDとIEAが共同で取りまとめた報告書では、国際線の航空機から排出されるCO2に対し課税する「航空機燃料税」や、いわゆるバンカー油の消費に対する「国際船舶燃料税」等の炭素・エネルギー税が提案されている。
また、1996年のAPECの経済展望レポートの中でも、炭素税が市場メカニズムを通じてCO2の排出量を削減するインセンティブ効果を持つだけでなく、化石燃料に対する依存度の低い技術への代替をも促すとし、炭素税が効果的にCO2の排出量を削減しうるであろうと指摘している。また、地球温暖化問題には不確定事項が存在し、最適な税率を正確に決定することは困難であるが、最適な税率が推定値であっても依然として妥当性を持つ可能性があることや、炭素税の賦課により低所得者層に負担をかけることにつながる可能性があること等についても指摘している。
エ 我が国における経済的負担措置の検討状況
我が国では、環境基本法第22条において経済的な負担を課す措置が位置づけられ、経済的措置を講じた場合の環境保全上の効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査研究するとともに、経済的措置を講じる場合には国民の理解と協力を得るよう努力することが求められた。また、環境基本計画においては、その具体的な措置について判断するため、地球温暖化防止のためのCO2排出抑制、廃棄物の抑制等、適用分野に応じて、環境保全上の効果、我が国の経済に与える影響等について調査研究を進めるとともに、その導入の際には国民の理解と協力を得るよう努めることを求めている。
平成8年7月に閣議報告された中央環境審議会の環境基本計画の進捗状況の第1回点検報告では、国民のライフスタイルに密接に関連する民生、運輸部門のCO2排出量が増加していることから、地球温暖化対策として実効性が期待される経済的措置について、具体的な議論の材料を国民に示し、国民的議論を喚起することが今後の課題として位置づけられた。
環境庁では、炭素税をはじめとした経済的手法について検討を行っている。
平成8年6月に「環境に係る税・課徴金等の経済的手法研究会」第1次報告が発表された。その中では、通常の社会経済活動や日常生活に伴って生じる今日の環境問題を解決していくためには規制手法だけでなく市場メカニズムの機能を活かした経済的手法の活用が不可欠であるとした上で、内外の調査研究と具体的事例をもとに各種の経済的手法の効果と影響を検討し、経済的手法の基本的な考え方を明らかにしている。また、課税対象や税収使途等の環境税・課徴金に関する基本的な論点について考え方が明らかにされている。
平成8年7月には「地球温暖化経済システム検討会」第3回報告書が発表され、炭素1t当たり3000円程度の低率の炭素税を課し、税収(約1兆円)をCO2排出抑制技術導入のための自主的取組への補助金に用いることにより、2000年の排出量を1990年比でわずかながら削減し、2010年で3%削減することが可能、との検討結果を示した。その他自主的取組や地球温暖化対策実施に伴いマクロ経済に生じる正負の影響や、地球規模で行う共同実施活動の費用効果性等についても分析している。同検討会はこの低率の炭素税の各種の政策・措置を組み合わせる案をたたき台として国民的な議論を行うことを提案している。
このほかにも、運輸政策審議会においても運輸部門における地球温暖化に対する対策の検討がなされており、平成8年12月に中間報告がとりまとめられた。この中間報告によると、現行の自動車税の税額区分を排気量別から燃費効率を考慮した区分に再編成し、燃費の良い自動車のほど税額を低くすることによって低燃費車へ誘導を行うことが提言された。
また産業構造審議会においても、気候変動問題に対する今後の取組の在り方の基本的な方向性を明らかにするための検討を行い、平成9年3月に報告書をまとめた。その中で経済的手法について、炭素税については、削減コストを低く抑えることができる場合がある等のメリットが指摘されている一方、?実質的に抑制する効果を得るためには、相当高率のものとする必要があり、国民や企業等に大きな経済的負担になることが見込まれること、?低率の炭素税と当該炭素税収入をCO2抑制対策の補助金等に活用することとの組合せについては、我が国においては既に石油税等を財源とする省エネルギー・新エネルギー対策等が相当程度実施されていることから、新規財源による省エネルギー・新エネルギー対策の必要性、費用対効果等を慎重に検討すべきこと等の問題点が指摘されており、炭素税の導入には今後とも引き続き慎重な対応が必要であるとされている。なお、補助金等の助成的手法については、費用対効果の点から適切か等、種々の観点からケース・バイ・ケースで導入の適否を判断しながら、引き続きその維持・拡充を行っていくことが必要であるとしている。
今後、経済的措置については、その具体的な案を国民の前に明らかにし、その導入について検討するとともに、国民的な議論の展開を図ることが必要である。