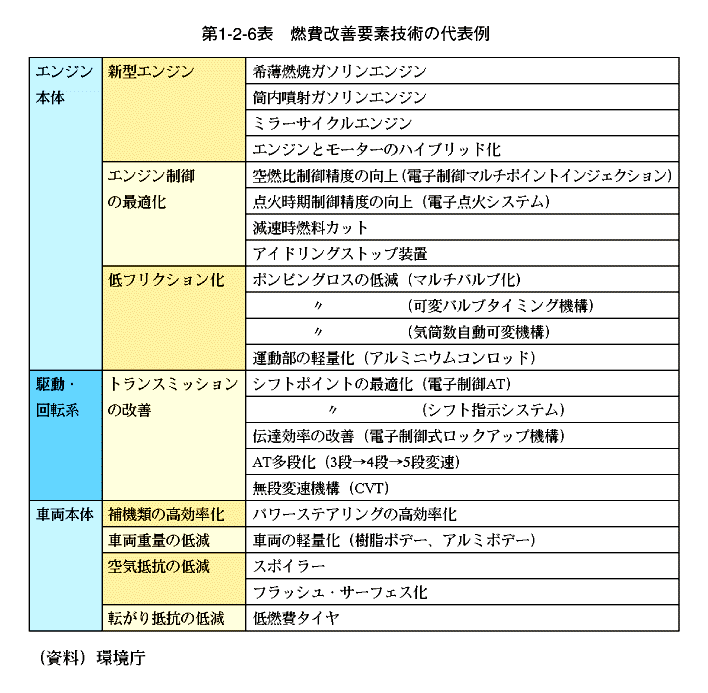
4 運輸部門からの排出の抑制
(1) 自動車単体からのCO2排出量の削減
平成6年度における運輸部門からのCO2排出量のうち自動車からの排出量が87%を占めており(第1-2-19図)、運輸部門からのCO2の排出を抑制するためには、まず交通機関、特に自動車単体からのCO2排出量を減少させることが必要である。
しかしながら、既に述べたとおり、最近の新車の平均的な自動車燃費の状況はむしろ悪化しつつある。(第1-2-20図)。
このような状況から、運輸省と通産省は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法)に基づき、昭和54年12月に「自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」(燃費基準)を告示し、その後見直しを行い、平成5年1月にガソリン乗用車が平成12年度に達成すべき燃費の目標値を車両重量区分ごとに定めた。また、平成8年3月には、2.5t以下のガソリン貨物車についても、平成15年度を目標とする燃費目標値を定めた。現在、自動車メーカーによりこの目標達成に向けた措置が講じられているところである。
CO2排出抑制のための技術としては、大別すればエンジンの改良、トランスミッションの改良、車体の改良等がある。具体的な技術の例を第1-2-6表に示す。
最近、各自動車メーカーでは従来と比べて飛躍的に燃費を向上させる技術が開発されつつあるが、すべての車種においてNOx等の大気汚染物質の排出低減を図りつつ、一層の燃費改善努力が行われることが求められている。
(2) 低公害車の導入
自動車からのCO2排出を削減する方策の一つとして、低公害車の導入がある。現在、実用段階にある低公害車としては電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車がある。
Box8 直接噴射ガソリンエンジン
最近、注目されているガソリンエンジン単体の燃費改善技術として、直接噴射ガソリンエンジンがある。
従来のガソリンエンジンは、ガソリンと空気の混合気をシリンダー内に吸入しているため、超希薄な混合気を安定燃焼させることには限界があった。これに対し、直接噴射ガソリンエンジンは、ディーゼルエンジンのようにシリンダー内にガソリンを直接噴射することで、高精度の燃料コントロールを可能とし、より希薄で高効率の燃焼を実現するものである。従来のエンジンと比べて、30%以上の燃費低減が可能とされる。既に商品化に成功したメーカーもあり、ガソリン車の低燃費化、CO2排出抑制に資する技術として、NOx等その他汚染物質の排出低減を含めた今後の更なる技術開発と普及が期待される。
ア 低公害車の概要
(ア) 電気自動車
電気自動車は、バッテリー(蓄電池)に蓄えられた電気でモーターを回転させて走るものであり、内燃機関を主たる動力源とするガソリン車、ディーゼル車といった従来車とは大きく異なる。電気自動車の最大の特徴は走行時に排出ガスを全く出さず、騒音も従来車に比べて低いことである。また、減速時にモーターを発電機の代わりに用いてその制動力で発電し、再充電することによりエネルギーの有効利用を図る回生ブレーキの技術も一般化している。発電と送電の効率を含めた全体としてのエネルギー効率を見ても、ガソリン車よりも1.5〜1.8倍優れており(第1-2-34図)、環境庁が行った試算によれば、1.5tクラスのバンタイプを想定した走行時とエネルギー製造時を合わせた排出量は、ガソリン車と比べてNOxで約64%、CO2で約58%削減される(第1-2-35図)。さらに、電力需要が少なく、原子力発電の比率が高い夜間に充電を行えばCO2の削減量はより大きくなる。
また、近年、様々な技術開発が行われている。平成8年に国立環境研究所等により、高性能電気自動車「ルシオール」が開発されたほか、国内自動車メーカーにおいても、高性能電池を使用し、最高速度120km/h、一充電走行距離(10・15モード走行)200kmを超えるものが次々と開発されており、ガソリン車との性能差は徐々に小さくなっている。確かに、現時点では、電気自動車は従来車と同じ市場で競合するには、走行距離や最高速度、加速性能、価格等の面でまだまだ十分であるとはいえず、現在の普及状況を見ると地方公共団体や電力会社での試用程度にとどまってはいるものの、今後、量産化に向けた専用設計や高性能電池等の技術開発の進展により、かなりの部分で従来車の性能をカバーすることができるものと期待されている。平成7年度末現在の我が国における普及台数は、約2,500台と推定されている。
(イ) 天然ガス自動車
天然ガス自動車は、天然ガスを燃料とし、従来車と同じく内燃機関を動力源とする自動車である。天然ガス自動車には、圧縮天然ガスを使用するもの(CNG自動車)と液化天然ガスを使用するもの(LNG自動車)があり、現在はCNG自動車が開発の主流となっている。天然ガス自動車は、ガソリン車やディーゼル車と比べてNOxやCO2等の排出を低減させることができ、環境庁が行った試算によれば、1.5tクラスのバンタイプを想定した走行時とエネルギー製造時を合わせた排出量はガソリン車と比べてNOxで約85%、CO2では約35%削減される(第1-2-35図)。天然ガスはガソリンよりオクタン価が高いため大容量エンジンへの適用が可能であり、中・大型のディーゼル車の代替として開発が進められている。平成7年度末現在、小型バン、ごみ収集車、路線バス等として759台が普及している。
Box9 高性能電気自動車「ルシオール」
平成8年に国立環境研究所などにより、高性能電気自動車「ルシオール」(フランス語で「蛍」の意)が開発された。これは、従来のようにガソリン車等の車体をベースにして電気自動車用に改造するのではなく、最初から電気自動車用に設計を行ったグランドアップ車であり、次のような特徴を持っている。すなわち、
? 駆動用モーター、減速ギア、ベアリング、機械ブレーキを一体型にまとめ、これを後輪に組み込むことによって、損失の低下、重量の軽減、車室内の有効利用可能空間の拡大につながる新形式の駆動システムであるインホイールモーターシステム
? 床下のフレーム構造に中空状の空間を設け、そこに薄型の電池を挿入することにより、重心を低くし、構造を極めて簡単にするフレーム構造であるバッテリービルトイン式フレーム
? 電池のそれぞれにBCS(電池状態監視センサー)とローカルチャージャー(充電器)を取り付け、電池の状態をモニターし、個々の電池に均等に充電を行い、さらに、BCSからの情報を基に組電池全体の状況を把握するBMS(電池管理システム)を取り付け、各電池の異常を検出するとともに残存容量を正確にモニターすることができる電池管理システム
といった独自技術を盛り込み、従来型の鉛蓄電池を使用して最高速度130km/h、一充電走行距離130km(10・15モード走行)という高い性能を実現した。
(ウ) ハイブリッド自動車
ハイブリッド自動車は、ガソリンエンジン又はディーゼルエンジンと電気動力を組み合わせ、双方の利点を生かして高効率で走行するものであり、シリーズハイブリッド車とパラレルハイブリッド車の2種類に大別される。シリーズハイブリッド車は、電気自動車の一充電走行距離を伸ばす目的で電池以外の補助エネルギー源が付加されたものであり、補助エネルギー源としては、内燃機関エンジン、ガスタービンエンジン、燃料電池等が考えられている。パラレルハイブリッド車は、内燃機関エンジン車で大きな力を必要とする発進・加速時に、モーターによる駆動力でその一部を補助するもので、このモーターの駆動に必要なエネルギーは、減速時にモーターを発電機に変えて制動力により発電し、電池等に再充電した電力を用いる。電池の代わりにコマのような回転体で、電気エネルギーを運動エネルギーとして蓄えるフライホイール(はずみ車)を用いる技術も研究されている。また、いずれも回生ブレーキの利用等と相まってエネルギー効率の改善によりNOxやCO2等の排出を抑制するものである。現在、大型のバスや貨物自動車等の商品化が進められている。環境庁が行った試算によれば、1.5tクラスのバンタイプを想定した走行時とエネルギー製造時を合わせた排出量はガソリン車と比べてNOxで約20%、CO2では約13%削減される(第1-2-35図)。平成7年度末現在で、176台が普及している。
このほか、大学、自動車メーカー等で実用化に向けた研究が行われているものとして、水素を燃料とするエンジンを用いた水素自動車、動力源としてモーターを使用し、動力エネルギーの全部または一部を太陽電池によりまかなうソーラーカーがある。
イ 低公害車の大量普及のための課題
低公害車を我が国で大量に普及させるためには、いくつかの課題がある。すなわち低公害車の走行距離、加速性能等基本的性能の相対的な低さ、価格の高さ、燃料供給施設の少なさ等である。本質的にはこれらの問題の解消に向けた努力がなされなければならないが、あわせて、低公害車の種類ごとの走行距離、適した車のサイズ等それぞれの低公害車の特性に応じた適切な利用形態について理解を広めることが必要である。環境庁の調査によれば、第1-2-36図に示すとおり、それぞれの低公害車の種類ごとに適切と考えられる範囲が明らかにされている。
ウ 低公害車の大量普及に向けた取組
(ア) 国における取組の状況
低公害車の導入は、NOxやCO2等の排出抑制対策の重要な施策の一つであり、国としてもその導入の支援を行うとともに、国自らが事業者・消費者としての立場から率先して導入していく必要がある。また、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量削減等に関する特別措置法」(自動車NOx法)による自動車排出窒素酸化物総量削減計画の中では、特定地域全体(首都圏及び大阪・兵庫圏)における低公害車普及目標台数は、平成12年度までに30万台程度とされており、また、新エネルギー導入大綱では同年度におけるクリーンエネルギー自動車(天然ガス自動車、電気自動車、メタノール自動車、ディーゼル代替LPG自動車及びハイブリッド自動車を指す)の導入目標を49万台としている。
これを受け、国においては低公害車の普及施策として、?地方公共団体、民間事業者等がバス、ごみ収集車、公害パトロール車等として購入する低公害車の購入費用や、低公害車用燃料供給施設の設置費用の一部を補助する各種の補助制度、?法人税・所得税に係る特別償却又は税額控除、自動車取得税の軽減、といった税制上の特例措置、?実用化支援・技術開発支援、?低公害車フェアの開催、国内で購入可能なすべての低公害車のデータ等を搭載した「低公害車ガイドブック」の発行等の普及啓発活動等を実施している(第2部、第1-1-11表)。
また、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行計画」(平成7年6月閣議決定、率先実行計画)において、国自らの取組として、「政府保有の公有車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合を平成12年度において概ね10%に高めることを念頭に置きつつ、公用車への低公害車の導入の可能性を積極的に検討し、その結果を踏まえ、率先的、計画的な導入に努める」こととされている。平成7年度における導入実績は16,394台中12台とわずか0.1%にとどまっており、目標達成に向けて今後の取組の推進が必要となっている。
(イ) 地方公共団体における取組の状況
また、地方においても、大都市部の地方公共団体を中心に低公害車の公用車への導入、民間事業者等の低公害車導入や最新規制適合車への買い換えに対する補助・融資制度、低公害車フェア等の普及啓発事業といった施策を積極的に展開している。
首都圏の7都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市)では、平成8年3月、電気自動車及び天然ガス、メタノール、ガソリン、軽油、液化石油ガスを主たる燃料とする自動車について、NOx等の「排出ガス指定基準」(原則として法定基準の1/2)を定め、その基準を満たす自動車を公募し、審査の結果基準以下と認められた自動車を「指定低公害車」として指定する「七都県市低公害車指定制度」を発足させ、低公害車の普及促進を図っている。また、これとほぼ同様の制度が平成8年4月に山梨県で、同年11月に京阪神地区の6府県市(京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市)で発足している。
(ウ) 諸外国における取組の例
海外においても低公害車の導入を促進するため様々な施策が実施されている。
a 米国カリフォルニア州における取組
米国のカリフォルニア州では、1900年改正大気浄化法(CAAA)及び州が策定した低公害車導入プログラムにより、自動車メーカーに対して低公害車の販売義務が課せられた。これは、乗用車と小型貨物車について排出ガス中の有害物質の量に応じて暫定低公害車(TLEV)、低公害車(LEV)、超低公害車(ULEV)、無公害車(ZEV、現在これに適合するのは電気自動車のみである)の4つに分類した上で、各自動車メーカーに対し、この4種の低公害車を組み合わせることにより、車両全種を平均した排出ガス基準値を守ることを義務づけるとともに、2003年(平成15年)から販売車両の10%以上をZEVとすることを義務づけたものであり、電気自動車の技術開発と導入の促進に大きな効果を発揮している。
b フランスにおける取組
フランスでは、電気自動車を普及させるため、1992年(平成4年)7月に、政府と産業界が2000年(平成12年)までに電気自動車を10万台普及させることを目標とした「電気自動車に関する基本協定」を締結した。政府は、この協定に基づき、産業、環境、運輸等を担当する関係省庁からなる電気自動車関係省庁会議(GIVE)を組織し、電気自動車の取得に係る補助金の交付や電気自動車の整備のサービスを行っている。
また、協定では、都市地域の駐車場のうち5%に充電設備を設置することが規定されている。これを受けて、パリ市では、フランス電力公社が公共駐車場における充電設備の設置を行った。また、市条例により、パーキングメーターが設置された道路上の駐車スペースや公営駐車場における電気自動車の駐車料金を免除している。
(3) 交通機関の間の連携
さきに見たように、運輸部門からのCO2排出量のうち自動車からの排出量が87%を占めている(第1-2-19図)。また、財団法人運輸経済研究センターの推計によれば、平成5年度の単位輸送量当たりのCO2排出量(炭素換算)は、旅客・貨物ともに鉄道が最も少なく、鉄道と比べると貨物では、内航海運が1.7倍、自動車が10.0倍、航空が59.3倍、旅客では、バスが2.0倍、乗用車が7.6倍、旅客船が4.3倍、航空が7.6倍となっている(第1-2-37図、第1-2-38図)。したがって、輸送機関の間の連携を図りつつ、自動車交通需要を軽減する方策を検討し、CO2排出の少ない交通体系の形成を図ることが必要である。
ア 貨物輸送におけるCO2排出抑制対策
平成6年度における我が国の年間貨物輸送量は5,445億トンキロであり、交通機関別のシェアは第1-2-17図のとおりである。自動車が着実に伸びているのに対し、鉄道は大きく後退している。
輸送機関別の1t当たりの平均輸送キロ数(平成6年度)を見ると、鉄道(JR)が456.4km、自動車が48.3km、内航海運が429.2kmであり、鉄道や内航海運が中・長距離用の大量輸送機関としての特徴を持っているのに対し、自動車には、機動性を生かしたドア・ツー・ドアの輸送が可能であるというメリットがあることがうかがわれる。
CO2排出の少ない交通体系の形成を図るために、貨物輸送については、中・長距離の物流拠点間の幹線輸送において、積極的にモーダルシフト(鉄道輸送、内航海運への誘導)を図るとともに、トラック輸送においても、営業用トラックの利用の促進、共同輸配送の推進、情報システム、集約的物流拠点の整備等を推進することにより、輸送効率の向上を図る必要がある。
(ア) 鉄道輸送への誘導
鉄道輸送への誘導は、トラックやトレーラーを鉄道貨車にそのまま積み込み、鉄道輸送のネックとなっている積み替えの手間や経費の面で改善を図り、トラックと組み合わせて一貫した輸送体制を作ることにより、鉄道貨物輸送の改善を図るピギーバック輸送や、トラックの荷台部分(バンボディ)だけをそのままコンテナ貨車にスライドさせて積み替えることにより、ピギーバック輸送の重量面での輸送効率の不利を解消するとともに、フォークリフト等の荷役機械を必要とせず、省力化に資するスライド・バンボディ・システム等の工夫が行われている(第1-2-39図)。
また、近年、廃棄物輸送の分野で鉄道を利用する動きが出始めている。平成7年10月に川崎市で、市内北・中部から発生する一般ごみ、粗大ごみ、焼却灰を南部の処理センターや埋立地へ輸送する手段として鉄道の利用を開始したのを始め、平成8年から、埼玉県越谷市から福井県敦賀市の処分場までのシュレッダーダスト(廃車を破砕処理した後に生じる産業廃棄物)の輸送を鉄道に転換した例や、埼玉県大宮市の「さいたま新都心」の建設現場から出る土砂を輸送している例などがある。
(イ) 内航海運への誘導
内航海運はトンキロベースで貨物輸送全体の43.8%のシェアを持ち、長距離輸送に強みを持つが、輸送の小口化、高頻度化が進む現在の状況に対応するため、貨物自動車をそのまま積み込むことのできるロールオン・ロールオフ船(RORO船)やコンテナ船、長距離フェリーへの転換を図る必要がある。
イ 旅客輸送におけるCO2排出抑制対策
平成6年度における我が国の年間旅客輸送量は1兆3,603億人キロであり、交通機関別のシェアは第1-2-17図のとおりである。旅客においても自動車が伸びているのに対し、鉄道は後退しており、自動車が旅客輸送の中心となっている。旅客輸送については、鉄道、バス、新交通システム等の公共交通機関の整備を推進するとともに、それらの輸送機関におけるサービスの向上を推進することにより大都市圏をはじめとして公共交通機関の利用を促進する必要がある。
このような施策としては、次のものがある。
(ア) 国内における施策
国内における施策の例としては、都市部を中心とした各地の鉄道、モノレール、新交通システムの整備が行われているほか、公共交通機関の乗り継ぎの利便向上施策として、各地の郊外の住宅団地等でのパークアンドライド(自宅から自分で運転してきた自動車をターミナル周辺に設けられた駐車場に置き、そこから公共交通機関を利用して都心部へ向かうシステム)や、乗り継ぎターミナル等を設置し、追加的な運賃を支払わずに幹線バスと支線バスの乗り継ぎができる大阪市のゾーンバスシステムのような例がある。
Box10 共同輸配送
共同輸配送には、幹線輸送における共同運行と、地域内輸送における共同輸配送がある。
? 幹線輸送における共同運行は、土曜日等の閑散期においてターミナルが近接している等共同化しやすい特別積合わせ事業者間で幹線における共同運行を推進し、積載率の向上、運行便数の削減等輸送の効率化を図るものである。平成6年11月、東京〜大阪間、東京〜愛知間において開始され、平成9年3月末現在で14区間、延37社が実施している。
? 地域内輸送における共同輸配送とは、商店の集中する地区等で多数の貨物車が配送のために集中し、効率の悪化を来しているような場合に、これを改善するため複数の会社の荷物を共同で集配するシステムである(図)。このようなものとしては、福岡市天神地区で発着する荷物を一元化するため、36のトラック事業者が共同出資した株式会社を設立し、地区内を対象とする共同集配を行っている例や、新宿新都心地区の高層ビル内で発生する荷物を共同で引き受ける協同組合を設立し、専従の集配員を置くことにより迅速かつ正確な集配を図っている例があるほか、百貨店業界においても都市部を中心とした各地で共同配送の取組が行われている例がある。
また、平成5〜6年度に環境庁の指導の下で公害健康被害補償予防協会が川崎駅前地区で50店舗を対象に実施した共同輸配送モデル実験によれば、従来型輸配送と比較して直接的なCO2排出量が約46%削減されたと推計されている。
さらに、公共交通機関自体の利便性を高める施策として、幹線道路の中央にバス専用レーンを設け、運行の定時性を確保しようとする名古屋市の基幹バス、バスの空白地域・不便地域の足として、また、公共施設等への足として高齢者にも配慮して整備された武蔵野市のコミュニティバスのような例がある。
(イ) 海外における施策
海外でも様々な先進的な施策が実施されている。
a 米国における取組
米国では、環境保護庁(EPA)が、1990年改正大気浄化法(CAAA)の中で大気環境基準及びその達成スケジュールを設定し、各州は、この基準を達成、維持するための州実施計画(SIP)を作成し、EPAの承認を得なければならないこととされている。多くの地域で自動車から排出される汚染物質の削減が大きな課題となっており、地域の汚染の程度に応じてSIPの中に自動車排出ガスの規制強化や低公害車の導入義務等と並んで交通対策が盛り込まれる。
この交通対策の例としては、公共交通機関の改善、高速道路での多人数乗車車両(HOV)専用レーン・専用ランプの設置や、交通管理組合(TMAs,民間企業が中心となって、開発事業者、交通事業者、公共団体等が参加し、1人乗りマイカー通勤交通削減を目的とする組織)の設置等による相乗りの推進、パークアンドライドやフリンジパーキング(自動車から徒歩・公共交通機関への乗り継ぎのために、都心外周部(フリンジ)、歩行者専用空間の直近、環状道路周辺部に設けられる駐車場)のための施設整備等が挙げられている。これらの施策は、大気汚染物質の排出削減と同時に、CO2の排出削減にも効果があるものであり、我が国にとっても参考となろう。
b シンガポールにおける取組
シンガポールでは、国土の狭さと経済発展による自動車交通需要の伸びに対応するため、徹底した交通対策が行われている。
まず、自動車の取得や保有に対して、購入時の登録料、輸入関税や毎年の道路税といった高額な税等の負担が課せられている。また、より直接的な車両台数の規制を行うため、1990年(平成2年)から、政府が毎月一定数の「自動車の登録に必要な資格」を入札にかけ、車両取得希望者に競わせて落札者(資格取得者)を一定数に限定する車両台数割当制度(QuotaSystem)が実施されている。さらに、都心部の自動車混雑対策として、1975年(昭和50年)から、都心部への自動車の乗入れ規制(ALS,Area LicensingSchime)を導入している。これは、事業所や商業施設が集積している市の中心部を含む、交通が最も混雑する地域に制限区域を設け、時間を限って区域内に流入する自動車に対して料金を課す制度である。
また、こうした交通対策を実施する一方で、一般の自動車交通の代替手段として地下鉄やバスの路線を整備、充実させており、これは自動車交通抑制対策の効果を高めていると考えられる。
c ライトレールトランジット(LRT)
最近、ヨーロッパを中心にライトレールトランジット(LightRail Transit,LRT)という名称で、路面電車の復活、あるいは新設が盛んになされ、都市内交通の新たな動きとして注目されている。
これは、自動車増大による排気ガスやエネルギー問題といった環境問題の解決、高齢者・障害者等の移動制約者も利用しやすい公共交通の確保、都心部の商業活動の活性化等を目的とされたものが多い。このようなLRTでは、低床式車輌の導入、低騒音化のための対策の実施、加減速制能の向上や優先式信号化、専用軌道化による高速化等、各路線に応じた様々な工夫を行い、路面電車の利便性を大きく向上させている。
(4) CO2排出の少ない都市構造の形成
第1-2-7表と第1-2-40図は、都市の人口密度と通勤手段、自動車輸送からのCO2排出量の関係を示したものであるが、都市の密度と移動手段の選択、自動車からのCO2排出量の間には関係があり、例えば、スプロール化した都市では、低密度で大量かつ長距離の交通需要が発生する。過剰な交通が発生するのは、コンパクトな開発を行わず、人間と活動を広い地域に拡散させることに原因があると考えられる。
本来、交通需要を減らすための最も直接的な方法は、移動が必要な距離をできるだけ短かくすることである。都市の土地利用のあり方を変えることによって、公共交通機関や自転車や徒歩が自動車の代替手段となり、自動車使用の抑制が可能になると考えられる。つまり、公共交通機関そのものの整備に加えて、その利用を促す計画的な都市の形成、例えば、職場、店舗及び地域サービスと居住地域をなるべく近接させ、また、駅を中心とした地域に必要な機能を集積させるようなゾーニングによって公共交通機関の役割を高めるといった、高密度でコンパクトな都市を作るための取組が必要である。このような取組として次のような例がある。
ア オランダのABC立地政策
オランダでは、過剰な自動車交通を抑制し、公共交通機関や自転車利用を促進するように事業所の立地を誘導するため、新規の事業所の立地について、業種、業態によってそれぞれにふさわしい位置を指定し、それ以外の地域への立地を規制する「ABC立地政策」と呼ばれる計画を策定している。この中では、A、B、Cの3種類の地区が設定され、それぞれの地区に立地すべき事業所が、交通の発生量と業務活動の自動車への依存度によって分けられている(第1-2-8表)。これによって、大量の交通を発生させる事業所は、駅や高速道路のインターチェンジ付近に立地することとなる。また、各地区ごとに事業所の従業員数に応じて駐車場の設置台数を制限したり、自転車道の整備等の自転車利用促進施策等他の施策と相まって、効果を上げている。
イ クリチバ市(ブラジル)の都市交通政策
ブラジルのクリチバ市では、バス主体の公共交通ネットワークを中心とした都市計画を行っている。バス専用レーンを備えた5本の幹線道路を都市軸と位置付け、これに沿って都市の拡大を進めるという考え方に立っている。すなわち、これらの幹線道路に沿った地域は高密度な商業業務地域とされ、都市軸から離れるに従って住宅地の密度が下がるように用途地域が指定されるなど、自動車交通を抑制することに配慮した計画がなされている。また、同時に、都市内の移動の確保を目的としたRITと呼ばれる統合的バス輸送システムを作り、都市軸の幹線道路のバス専用レーンを走行する幹線バス、幹線バスの乗り継ぎターミナルから伸びる支線バス、幹線バス路線の間を環状に運行する環状軸間バス、原則としてバスターミナルのみに停車する直行バス等それぞれの役割に応じて市内に充実したバス路線網を形成している。
また、都心部にバス専用道路やバス逆行レーン(バス専用の逆行レーンがある一方通行道路)を設ける等バスの優先策とも相まって、毎日130万人を超える人々がバスを利用し、都心部の騒音と交通渋滞が大幅に改善されたと報告されている。
このように、交通計画と土地利用計画の統合によって、自動車利用の低減に大きな成果を上げている例がある。
また、自動車交通の渋滞を緩和し、効率的で円滑な走行を確保することにより、走行中のCO2の排出量を低減するため、道路整備、交通管制システムの整備及び高度化、ITS(高度道路情報システム)の推進、道路工事の平準化や路上駐車対策等の交通対策を推進する必要がある。
(5) 国民一人ひとりの取組
ア アイドリング・ストップ運動
大気汚染防止法は、自動車排出ガスの抑制のため、自動車を運転・使用するにあたって適正な運転等に努めることを国民の責務として規定している。
環境庁では、平成8年度から、具体的な参加行動としての「アイドリング・ストップ運動」を推進している。これは、必要以上の暖機運転、運転者が車から離れている間、荷物の積み降ろしの間等不要と考えられる場合について積極的にアイドリングをやめ、さらに、休息中、人待ち、客待ちのための停車中のアイドリングについても、気候等の状況を考えなるべくやめるよう呼びかけるものである。
また、地方公共団体においても、兵庫県が「環境の保全と創造に関する条例」で一部罰則付きのアイドリング禁止規定を定めており、また、平成7年度末現在、大都市部の公営バスにアイドリング・ストップバスが197台導入されている等多く取組が行われている。事業者レベルでも、(社)全日本トラック協会が環境庁との協力の下、「アイドリング・ストップ宣言」ステッカーを作成し、全国のトラック事業者に参加を促している例があるほか、バス業界、タクシー業界においてもこの運動に参加する取組が行われている。
アイドリングによるCO2排出量は第1-2-9表のとおりであり、一見したところ個々の自動車から排出される量は小さなものと考えてしまうかもしれない。しかし、仮に東京都内のすべての自動車がアイドリングを毎日10分間ずつ短縮したとすると、1年間に約1億9千万l(ドラム缶95万本分)の燃料を節約でき、CO2排出量を炭素換算にして、日本人1人当たりの平均排出量の約4万6000人分の量である約12万t削減できると推計されている。
イ 公共輸送機関の利用等
また、休暇中のレジャー等を始めとして、できる限り鉄道、バス等の公共輸送機関を利用することや、マイカーの経済運転による走行等に心がけ、その購入に当たっては、使用状況に応じた燃費のよい乗用車の選択に心がけることも必要である。
なお、「夏季(冬季)の省エネルギー対策について」(省エネルギー・省資源対策推進会議決定)に基づく普及広報資料による、不経済運転によってむだに消費される燃料を第1-2-10表に示す。
国民は、人間と環境とのかかわりについての理解を深め、日常生活に起因する環境への負荷の低減や身近な環境をよりよいものにしていくための行動を、自主的積極的に進めることが期待されているが、運輸部門においても不要不急の自家用車使用の自粛や経済運転の励行といった日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めることが期待されている。