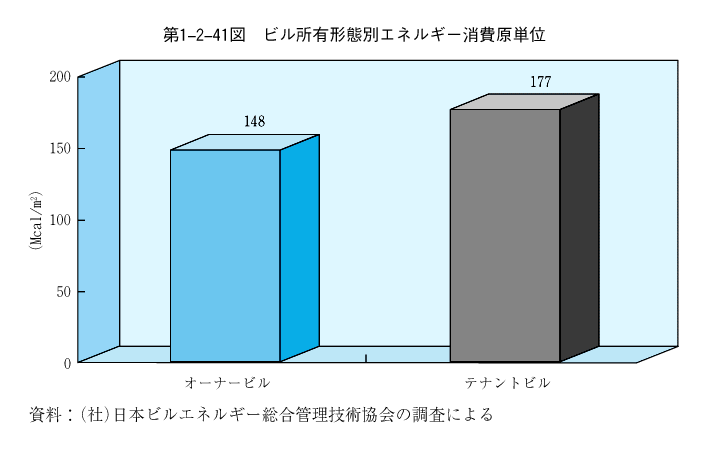
5 民生部門からの排出の抑制
民生部門は、家庭部門と業務部門から成り立っており、それぞれ我が国のCO2排出量の12.7%と12.5%を占めている。双方とも近年CO2排出量の伸びが著しく、これをどのように抑制していくかが、我が国の温暖化対策の大きなカギとなっている。
(1) 業務部門での排出抑制対策
ア 業務用建築物からの排出の抑制
業務部門においては冷暖房用のエネルギー消費は31.8%(平成7年度)を占めている。
業務用建築物において、断熱構造を強化することによってCO2の排出抑制が可能であるが、これに加えて、省エネルギー技術を導入した冷暖房設備、照明設備その他の各種の業務用設備を導入することにより、大きな効果が期待される。
また、(社)日本ビルエネルギー総合管理技術協会が行った調査によると、ビルの所有形態別のエネルギー消費状況は、第1-2-41図のとおり、100%オーナーが入居している「オーナービル」が、100%テナントが入居している「テナントビル」に比べ、約20%も単位面積当たりのエネルギー消費が少ないという調査結果が出されている。この理由としては、オーナービルの場合、エネルギー代もオーナーが支払うことになるので、積極的に省エネルギー設備を導入し、エネルギー管理を行っていること、一方、テナントビルについては、オーナーが空調設備等を設置することが多く、賃貸料を低く抑えるため省エネルギー設備の導入を控えること、また、テナントには設備選択の余地が少なく、エネルギー代は賃貸料に比べ安価なため積極的なエネルギー管理を行わないことなどが考えられる。
通産省と建設省は、省エネルギー法に基づき「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」を告示している。これは、ホテル・旅館、病院・診療所、物品販売業を営む店舗、事務所及び学校のそれぞれについて、建築主が満たすべき断熱構造や空気調和設備及びそれ以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機に関するエネルギーの利用効率を定めたものである。
また、国の率先実行計画(第3章第3節参照)では、国の各行政機関において、事務所の単位面積当たりの電気使用量を平成12年度までに平成7年度の90%以下にすることに向けて努めることとし、第1-2-11表に掲げる省エネルギー設備等の導入、環境負荷の少ない燃料の使用(灯油、LPG、LNG等)、省エネルギー型OA機器への更新とその適切な使用、エネルギーを多く消費する自動販売機の設置の見直し等を推進することを定めている。
イ 業務部門における無駄なエネルギー使用の削減
国の各行政機関では、率先実行計画及び省エネルギー・省資源対策推進会議決定(平成8年7月、11月)に基づき、冷房は28℃程度、暖房は19℃程度に設定するよう取り組んでいるところであるが、民間における冷暖房の設定温度については、冷房はより低く温度設定される傾向にある(第1-2-42図)。過剰冷房や過剰暖房は健康にも悪く、適切な温度設定をすることが必要である。
業務部門において、暖房温度を全国で1℃下げれば、1年間で原油換算約85万kl分のエネルギーを節約でき、また、冷房温度を全国で1℃上げれば、1年間で原油換算約84万kl分のエネルギーを節約できるという試算(前出の「夏季(冬季)の省エネルギー対策について」に基づく普及広報資料による)があり、このような取組によるCO2の排出削減への大きな効果が期待される(この85万klと84万klを合わせた169万klの原油からは、炭素換算約122万tのCO2が排出される。)。
国の率先実行計画では、このほか、?エネルギー供給設備の適正な運転管理、?照明スイッチの適正管理、?階段利用の奨励、エレベーターの間引き運転、?点灯時間の縮減のための定時退庁の徹底等を推進することを定めている。
また、日本全体の事務所等で、昼休みなどの不要時に1日1時間、照明やOA機器(コピー機等)を消すと、1年間でそれぞれ、原油換算約90万kl分、16万kl分のエネルギーの節約となるという試算(前出の「夏季(冬季)の省エネルギー対策について」に基づく普及広報資料による)があり、CO2の排出削減に大きな効果が期待がされる(この90万klと16万klを合わせた106万klの原油からは、炭素換算約77万tのCO2が排出される。)。
(2) 家庭部門での排出抑制対策
ア 家庭における建物の断熱構造の強化
家庭部門では冷暖房用のエネルギー消費が約30%(平成7年度)を占め、(第1-2-25図参照)炭素換算で約1,176万tのCO2を排出している。
家庭部門においても、建物の断熱構造を強化することによってエネルギー消費量の削減が可能となり、CO2の排出を抑制することができる。
断熱効果を高めるための方法としては、?複層ガラスや断熱サッシを導入して、住宅の窓の断熱性や気密性を高めること、また、?住宅を新築する際に、天井、壁、床、開口部といった外部との境界面に断熱建材を使用するなど住宅を保温構造化することが有効である。
通産省と建設省は省エネルギー法に基づき、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」を告示した。これは、全国の気温等を勘案して、都道府県を単位として6ブロックに分け、それぞれについて、住宅を建築する場合に満たすべき住宅の熱損失・日射取得・気密性等構造の基準について定めたものである。
第1-2-43図は、主要先進国の断熱基準値の推移を示したものであるが、各国とも石油危機を契機に強制断熱基準を制定、強化している。
イ CO2発生抑制型の機器の選択
近年、照明や動力等への利用が、民生部門のエネルギー消費に占める割合が高まっており、家庭部門では約36%(平成7年)を占めている(第1-2-25図参照)。また、家庭用電力消費量は、この照明動力等に冷房用を加えたものにほぼ相当するが、第1-2-44図の通り、近年非常に高い伸びを示しており、冷蔵庫、照明、クーラー・エアコン等の冷暖房機器等のエネルギー消費が大きいことがわかる。
一方、第1-2-26図で見たとおり、個別の機器のエネルギー効率は最近あまり向上していない。
このため、今後、個別の機器のエネルギー効率の改善にさらに努めるとともに、エネルギーの利用者側も省エネルギー型機器を選択することが重要である。
Box11 省エネバンガード21
(財)省エネルギーセンターが実施している「省エネバンガード21(21世紀型省エネルギー機器・システム表彰)」は、優れた省エネルギー性、省資源性等を有する民生用のエネルギー利用機器・システム等を公募し、優れたものを通商産業大臣賞・資源エネルギー庁長官賞等として表彰することによる、その開発促進と普及を目的としたものであり、毎年10数点が表彰されている。
平成8年度には、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ等の家庭用機器10点、蛍光灯、産業用空調、パソコン等の業務用機器7点が表彰されている。この「省エネバンガード21」の表彰対象製品も、省エネルギー機器を選択する際の参考となる。
また、家電製品へのタイマーやマイコンの内蔵に伴い、待機時の消費電力が増加しているのでこの削減も有効である。
また、太陽熱や太陽光などCO2を発生しないエネルギーを利用することも重要である。太陽光発電については、既存電源と比較した場合の高コストと設置スペース問題が普及を阻害しているため、個人住宅の空き部分である屋根を活用して導入の先鞭をつけていくことが重要である。
Box12 省エネルギー機器・新エネルギー利用機器の購入に対する消費者の意識
平成8年の2月に「地球的規模の環境問題に関する懇談会」の「地球温暖化問題に関する特別委員会」が実施したアンケートの中に、民生部門で利用できるいくつかの省エネルギー対策についてそれぞれCO2削減に効果があるとした上で、余分にかかる初期費用と差額の回収可能性を設定して示し、その導入意思を問うものがあったが、以下のような結果となった。
(質問)
? 屋根に置く太陽光発電装置
(自己負担額約200万円、電気代の節約での差額回収は困難)
? 断熱性能の高い複層ガラス
(新築住宅で約40万円のコスト高、節約での差額回収は困難)
? 燃費が極めて良い乗用車
(約10万円のコスト高、ガソリン代の節約で差額を回収できない恐れあり)
? インバーターエアコン
(約5万円のコスト高、電気代の節約で差額回収可能)
? 省エネ型蛍光灯
(器具代とランプ2本分で約5000円のコスト高、電気代の節約で差額回収可能)
この結果によると、初期投資額が小さくなるにつれて、また費用の回収可能性があるというものについて、「次の機会に我が家に入れたい」という回答が大きくなっている。また、初期投資額の大きいものも含めいずれの製品についても、「そもそも魅力を感じない」という回答は少数で、関心の高さが伺われる。
これら民生用のCO2の排出抑制に対して有効な製品については、初期投資額が極力小さくなるよう、導入補助制度を一層充実させたり、大量普及によるコストダウンのため行政などで率先導入を図っていくことが必要と考えられる。
また、関心を持つ多くの人に対して適切に情報提供していけるよう、エコラベリングなどを利用して、広く省エネルギー機器等についての情報を普及していく必要がある。
※調査対象・・環境モニター223人、自治体県政モニター725人、主婦ネットワーク186人等1580人
このため、個人住宅への太陽光発電システム等の設置に対して、設置費用の1/2相当の補助を行うとともに、設置者をモニターとして消費者のニーズに合致した機器の性能の向上等を図るモニター事業が平成6年から実施されており、平成8年度は、約2,000件程度(4kW/件)を対象に約40億円(1件当たり最大200万円)の助成が行われている(本節3(2)参照)。また、工事費を含めた機器価格も年々低下しており、この助成措置を合わせると、平成8年度における太陽光発電機器の実質コストは、150〜170万円程度となっている(第1-2-45図)。また、平成4年から、電力会社が一般家庭等に設置された太陽光パネルによって得られた電力を買い取る制度が開始された。この結果、一般家庭では、昼間は太陽光発電によって得られた余剰電力を電力会社に売り、夜間は電力会社から電力を買うことができるようになった。
また、太陽熱を利用するシステムには、集熱部と貯水槽が合体している汲置型・自然循環型の太陽熱温水器と、集熱部は屋根に、貯水槽は地上に設置される強制循環型のソーラーシステムがある。ソーラーシステムは、貯水槽を地上に設置するので、太陽熱温水器に比べ多くの湯を蓄えられることや、吸収式冷凍機と組み合わせると給湯に加え、冷暖房も可能となるなどの利点があり、省エネルギー効果も高い。さらに、建物自体に集熱器、蓄熱器、放熱器の機能を持たせると同時に、通風、日射遮蔽などを考慮して建築を行うパッシブソーラー住宅と呼ばれる手法が開発されている。我が国における太陽熱給湯システムの利用は第2次石油危機を契機に大きく進んだが、石油価格の低迷に伴い近年減少してきており、その一層の普及のための施策の充実強化が必要である。
ウ 無駄なエネルギーの使用の削減と適切なエネルギー機器の利用
これまで述べてきたように、機器・設備の導入時に損失の少ないものを選択していくとともに、これらの機器を損失が少なくなるよう適切に使用し、さらに、極力無駄な使用を控えるようにしていくことが重要である。
(ア) 冷暖房を適正温度で利用
過剰冷房や過剰暖房は健康にも悪く、家庭においても、業務部門と同様、適切な温度設定をすることが必要である。
家庭部門において、暖房温度を1℃下げれば、約43万世帯の年間エネルギー消費量を節約でき、また、冷房温度を全国で1℃上げれば、約32万世帯の年間エネルギー消費を節約できるという試算(前出の「夏季(冬季)の省エネルギー対策について」に基づく普及広報資料による)があり、このような取組によるCO2の排出削減への大きな効果が期待される(この43万世帯と32万世帯を合わせた75万世帯の年間エネルギー消費量は原油換算122万klに当たり、この量の原油からは、88万tのCO2が排出される)。
(イ) 適正な機器の使い方の励行
エネルギーを使う機器の使い方や周囲の状況に少し配慮するだけで、便利さを損なうことなく、エネルギー消費量を削減することが可能である。
例えば、冷暖房については、窓のカーテンを厚手にし、またカーテンやブラインドをきちんと閉めるようにすると冷暖房の効果が上がる。
冷蔵庫については、熱いものは冷まして入れる、無駄な開閉はしない、こまめに温度調節を行う、詰め込みすぎないなどの心がけが重要である。
東京電力が行った推計によれば、つめすぎにより35%、冷蔵庫の温度設定により20%も電力消費が多くなると試算されている(第1-2-46図)。
また、使用していない部屋や窓際の照明は消し、部屋の大きさにあった明るさの照明器具を使うことが適切である。
本節5(2)イで述べたように、家電製品の待機時の消費電力が大きくなっているので、外出時などには本体の主電源を切るとともに、旅行など長期間使用しないときは電源プラグを抜くようにすると大きな効果が得られる。
(財)省エネルギーセンターが行った推計によれば、給湯用としては、ガスコンロの熱効率が約45%であるのに対し、ガス瞬間湯沸器の熱効率は80%以上であるので、湯沸かし器の湯を使う方がガスの節約になる。また湯沸器の口火はこまめに消すだけで、つけっ放しに比べ、年間世帯当たり最大11m
3
のガスを節約する効果があると試算されている。
(ウ) 適正な機器の状態の維持
エネルギー機器を清潔に保ち、正しい位置に設置するなど、適正な状態に保っておくだけでも、エネルギーの消費量は削減できる。
冷暖房機器では、エアコンのフィルターや石油ストーブの燃焼部分、反射板をまめに掃除することにより冷暖房効率が上がる(第1-2-12表)。また(財)省エネルギーセンターが行った推計によれば、室外機を風通しの良い方向に設置し、吹き出し口には物を置かないようにするとともに、冷房時には日光が当たらないようにすると約5%の省エネルギーになると試算されている。
電球や蛍光灯、照明器具の傘は時々清掃すると、明るさが増し、補助照明器具の使用が抑制できる。
冷蔵庫では、ドアのパッキン(冷気漏れを防ぐ)や凝縮器の清掃、霜取りを励行するとともに、日光の当たる場所やガステーブルの側に置かないようにし、風通しの良いところにおくことが有効である。(財)省エネルギーセンターが行った推計によれば、冷蔵庫の周囲の温度が30℃の場合、15℃の時と比べて電力消費量が90%増大すると試算されている。
(エ) 身の回りでの行動とその効果
以上述べたもののほかにも、第1-2-13表に例示したとおり、身の回りでちょっとした配慮を行うことによって、省エネルギーの実践が可能である。ここに掲げたものは、CO2を削減するための省エネルギー行動のほんの一例に過ぎないが、このような小さな行動の積み重ねが重要である。
(3) ライフスタイルの転換
以上述べたとおり、日常生活におけるちょっとした心がけがCO2の排出削減につながり、その積み重ねが大きな効果をもたらす。また、以上に述べたもののほかにも第2章で詳述する廃棄物の排出抑制やリユース、リサイクルのための取組の中にもCO2の発生抑制に寄与するものが多い。
また、国民の温暖化対策に対する関心の高まりは、当然、企業の生産する製品をCO2発生抑制型のものへと転換させる大きな原動力となる。地球温暖化を防止するためには、大量消費、大量廃棄型のライフスタイルそのものの見直しが必要となっており、それができるかどうか、国民一人ひとりがどこまで取り組むことができるか、これが地球の将来を左右する地球温暖化問題への対策を左右する大きなカギとなっているといえる。
Box13 環境家計簿
環境家計簿とは、日々の生活において環境に負荷を与える行動や環境によい影響を与える行動を記録し、必要に応じて点数化したり、収支決算のように一定期間の集計を行ったりするもので、消費者が、環境への負荷の少ないライフスタイルを確立していくに当たり、自らの活動を客観的に評価することに役立つ。現在、様々な地方公共団体、消費者団体等において作成されており、環境家計簿を付ける運動が広がっている。
様々な環境負荷について作成することが可能であるが、温暖化問題に着目すると、毎月の電気、ガス、水道、自動車燃料、廃棄物量等を記入し、所定の計算を行うと、各家庭のCO2排出量がわかる、といったものになっている。
環境庁でも、平成8年6月に「環境庁版」の環境家計簿を開発しており、希望者に配付している。「環境庁版」には、「デイリー」「ウィークリー」「マンスリー」の3タイプがあり、「デイリー」は家計を記入する通常の家計簿として使用しながら、CO2排出量も集計できるのが特徴で、「ウィークリー」はこれを簡素化したものである。この2タイプには環境にやさしい行動のヒントとなる情報も多数盛り込まれている。これらの家計簿に対しては、多数の希望者があり、在庫が切れたため、平成9年3月、平成10年まで使用可能な第2版を作成、配付している。下に示した「マンスリー」は、入門的なもので、1枚で3か月間記載できるようになっている。