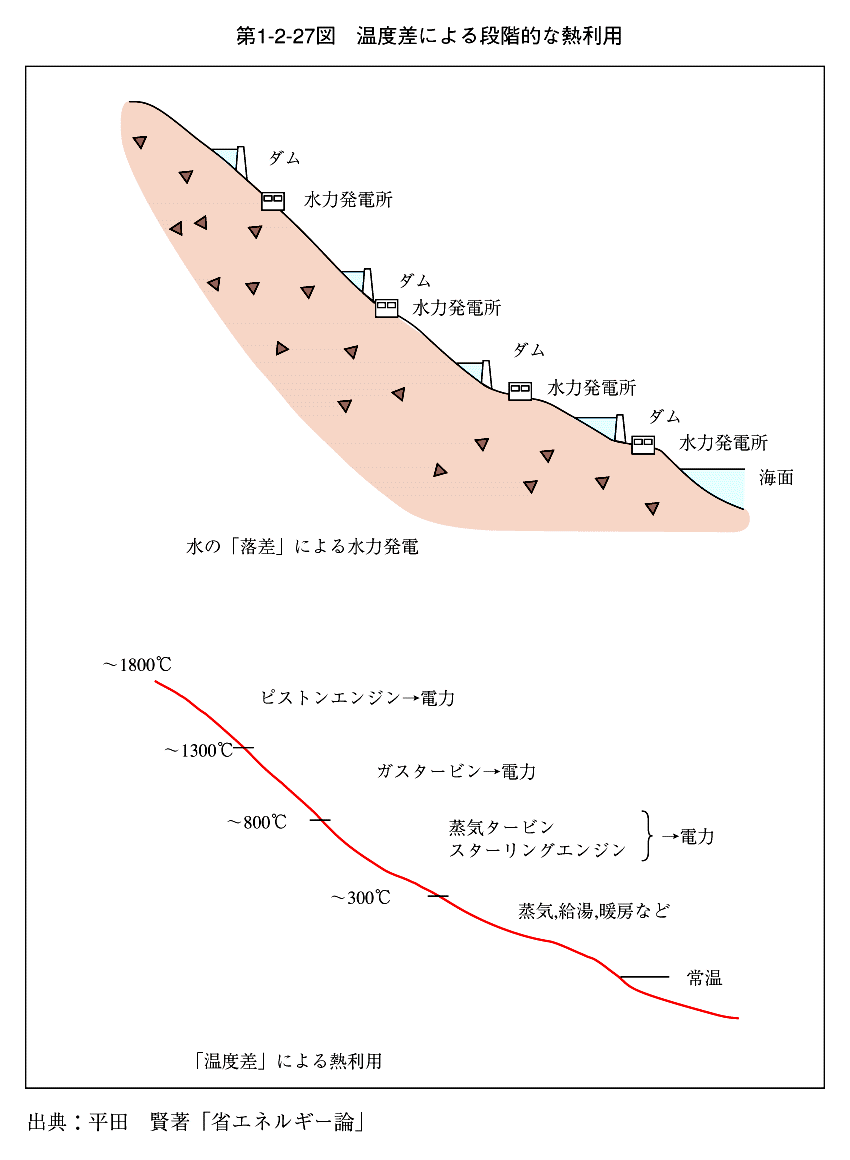
3 産業部門とエネルギー転換部門からの排出の抑制
(1) 一次エネルギー投入量を抑制する方策
産業部門とエネルギー転換部門において、一次エネルギー投入量を抑制していくための方策としては、以下のものが考えられる。その中心はエネルギー損失をできるだけ小さくしていく方策であると言える。
ア エネルギーの段階的利用の推進
化石燃料を燃焼させてエネルギーを得る場合、高温から低温まで第1-2-27図のように様々な利用が可能である。高温の熱からは様々な動力や熱に変換できる上質のエネルギーである電力を取り出し、低温の熱は暖房や給湯用にそのまま熱として利用できる。
このように、エネルギーの段階的な利用を進めることによって、エネルギーの損失を少なくすることが可能となる。
(ア) コージェネレーションシステムの幅広い導入
エネルギーの多段階利用を行なうシステムとして、コージェネレーションがある。
a コージェネレーションの仕組み
コージェネレーションとは、燃焼により発生する熱の高温部から発電に用いる動力を、動力が作られる際に生ずる低温の熱を同時に取り出すものである。電力需要と熱需要が適切に組み合わされた場合は、総合エネルギー効率が80%以上にまで向上する。
この場合、得られる電力と熱の両方を使い尽くせば、エネルギーの損失を少なくするために大きく寄与する(第1-2-28図)。
コージェネレーションには、動力部分のエネルギーを作り出す方式として、1500℃以上の高温領域で燃料が爆発的に燃焼しその高温高圧のガスでピストンを動かす「ピストン内燃方式」、約1100℃程度の高温ガスの中でタービンを連続的に回転させる「ガスタービン方式」及び約500℃の蒸気でタービンを回す「蒸気タービン」方式(一般産業界でよく行われている)等がある。「ピストン内燃」方式やガスタービン方式は、「蒸気タービン」方式と比べて熱をより高温段階から利用することができる。
b 導入の状況
産業分野では、熱需要が相当程度ある工場でコージェネレーションの導入により総合エネルギー効率の向上が期待される。
一方、民生分野では、ホテル、病院、業務用ビル等熱需要と電力需要が適切に組み合わされた場合には総合エネルギー効率の上昇が期待される。さらに発電所の排熱を周辺地域に供給する形及び地域熱供給の熱源としてコージェネレーションを導入することも考えられる。
ガスタービン、ガスエンジン及びディーゼルエンジンを用いたコージェネレーションの設備能力は、平成7年度末現在、産業用が971件、325.6万kW、民生用が971件、約49.1万kWとなっており、これは我が国の総発電設備容量の約1.6%にあたる。
c 諸外国における導入
ヨーロッパ諸国では、コージェネレーションの普及を今後の重要なCO2削減対策として位置付けている。2000年(平成12年)におけるCO2排出量を1990年(平成2年)に対してオランダは3.7%減、デンマークは7.9%減、イギリスは4〜8%減とするとしているが、3国ともその主要な対策の一つとして、コージェネレーションの普及を挙げている。
d 求められる普及の促進
我が国の「長期エネルギー需給見通し」(平成6年6月)では、コージェネレーションについて、2000年度に542万kW、2010年度に1002万kWの出力規模を見込んでいる。
なお、個々の工場・事業場において概ね2000年(平成12年)までに今後導入可能なコージェネレーションは、少なくとも全国で385施設であるという調査結果もある(地球温暖化対策技術評価検討会報告書(平成8年5月)、以下、「技術評価報告書」という。)。
これまでは、コージェネレーションから得られる電力と熱は、ほとんどコージェネレーションを設置した工場・事業場の中だけで利用されてきた。しかし、得られた電力や熱をコージェネレーションを設置した工場・事業場の中だけではなく、社会全体で利用することができるようになれば、コージェネレーションの普及は一層進み、CO2の排出量を削減することが可能になる。
電力会社以外の者がコージェネレーションなどによって得られた電力を他の者に直接供給することについては、規制が行われているが、平成7年4月の電気事業法の改正により、もっぱら一の建物内に限り電気を供給する場合は個別許可が廃止された。このことによって、一層、コージェネレーションの普及が進むことが期待されている。
また、コージェネレーションや太陽光発電などからの余剰電力については、平成4年から電力会社が買い取る制度が実施されており、平成7年度は約1億7千万kWhが電力会社により買い取られている。
平成7年の電気事業法の改正により、電力会社に電力を供給する卸電気事業が原則自由化された。これにより、コージェネレーションによる電力を電力会社に卸供給する際の許可が不要となった。また、同改正により、電力会社の電源調達についての入札制度が導入された。これは、各電力会社が電力の購入規模と購入条件を提示し、電力会社に電力を供給するものが応募し、落札が行なわれるものである。これにより、コージェネレーションによる電力も入札制度を通じて社会全体で利用される可能性が生まれた。また、この改正では、特定の地域に限って電力を供給する「特定電気事業」制度が創設された。これにより、経済性を含めた条件が整えばコージェネレーションによって得られる電力を用いて特定の地域の電力需要に応じることも可能となった。
また、コージェネレーションなどの自家発電設備を電力会社の商用電力系統と連結させるための技術要件についても、技術開発実績等を踏まえて逐次緩和等が行われてきている。
今後、我が国のCO2の排出量を抑制していくためには、コージェネレーションの普及のための一層の社会システムの整備や、制度改善、技術開発が必要である。
(イ) コンバインドサイクルによる発電
現在の火力発電は、ボイラーで燃料を燃やし、まず水を熱して蒸気を作り、次いでこの蒸気がタービンを作動させ、タービンが発電機を回して電気をつくるという「汽力」方式が主流となっている。熱効率を高めるためには、蒸気をより高温にしなければならないが、現在の技術では、566℃程度が実用的な蒸気温度の上限となっており、熱効率は40%程度がほぼ限界である。一方、ガスの膨張力を利用して発電する「ガスタービン方式」では、タービン入口ガス温度をほぼ約1,100℃まで高めることができ、更に、その排ガスの温度を利用して蒸気を作り「汽力」方式の発電を併せて行なうことができる。このような「コンバインドサイクル」発電を行なうと、熱効率は50%以上に上昇する。従来の火力発電方式の熱効率は約39%であるので、このような方式の発電はエネルギー損失の減少に大きく資する。このため、その導入の促進が必要である。
(ウ) 自家発電のリパワリング
リパワリングとは、既設の「汽力」方式のボイラータービンにガスタービンを追加して設置することによって、熱の段階的利用を行なおうとするものである。熱効率が向上する仕組みは、コンバインドサイクル発電と同じであるが、コンバインドサイクル発電が新しく発電機を設置するのに対しリパワリングは既存の発電機にガスタービンを加えるものである。リパワリングを行なうことによって、CO2の発生量は2割程度削減することができる。
イ ボイラーの燃焼管理
燃料を燃焼して熱を得ようとする場合、空気の量(酸素の量)が少ないと燃料の未燃部分が残り、効率が落ちるとともに、不完全燃焼によって人体に有害な一酸化炭素が発生する。一方、空気の量が多すぎると、必要以上の量の空気が熱せられるため燃焼ガスの温度を一定の高さにするためにはより多くの燃料が必要となって、効率が落ちる。したがって、効率的な燃焼を行うためには、完全燃焼を確保しつつ、送入する空気の量をできるだけ少なくすることが必要であり、また排熱を利用して予熱温度を高くしておくことが有効である。
燃焼時において送入する空気の量を適切なものとするための装置として、酸素(O2)制御装置がある。この装置は、燃焼管理を行なうための基礎的な装置であり、導入は進んでいるが、なお相当数の施設では導入されておらず、過剰な空気が送入されている例も多く、この装置の導入を進めることによって、適切な燃焼管理を進める必要がある。
ウ 高温空気燃焼技術の導入
イでは、従来の工業炉において、CO2の排出を抑制する燃焼管理について述べたが、現在、新たな高性能工業炉の開発が進展している。これは、燃焼炉内に吹き込まれる空気を従来よりはるかに高温の1000℃以上(従来は500〜600℃)に予熱し、かつ低酸素濃度に維持し、その高速噴流中に燃料を吹き込むという高温空気燃焼技術を活用するもので、この技術により従来より3割以上のCO2排出削減が可能となるものである。この技術は、工業炉、ボイラーにのみならず、コジェネレーションやごみ発電など幅広い分野で利用することが可能であり、今後、早期に技術が確立され、導入・普及が進むことが期待される。
エ モーターのインバーター制御の導入
負荷変動の多いモーターの場合、運転モードに応じて間欠運転や回転数制御を行なうことによって効率を改善することができる。モーターの可変速制御の方式には各種のものがあるが、モーターに与える電源周波数と電圧を連続的に制御する方式(インバーター制御)が最も効率の高いものである。
オ 工場の排エネルギーの社会的利用
我が国のエネルギーを多く消費する工場では、自工場内で可能な省エネルギー対策は相当進んでいるが、有効に利用されずに捨てられるエネルギーも多く残っている。
a 鉄鋼業におけるエネルギーの利用状況
鉄鋼業は産業部門のエネルギー消費の約24%、我が国の最終エネルギー消費全体の約11%を占め、またCO2排出量では、産業部門の約30%を占めている。
鉄鋼業のエネルギー消費の約80%を占める一貫製鉄所では、使用エネルギーの61%が有効利用され、残りの39%が未使用エネルギー(中・低温排熱が中心)となっている。
有効利用率の向上策として、所内の使用エネルギーの47%が一次的な高温排熱として発生しており、このうちの8%は各種排熱回収装置により既に回収され循環利用されている。利用形態としては、燃料ガスや燃焼用空気の予熱、及び蒸気や電力として回収して利用する方法がある。(第1-2-29図)。
b 工場排エネルギーの社会全体での利用
この大量の未利用の排エネルギーは、経済性の問題や、回収しても温度レベルが低いために製鉄所ではもはや利用先が少ないことから、回収利用が進みにくい。このような事情は他の業種にも同様に存在する。
一方、こうした排エネルギーを社会全体で利用することによって、社会全体のエネルギー効率を上げ、CO2の排出を削減することが可能である。
工場の排エネルギーを工場外で使う方法としては、熱として使うことと電気に変換して使うことが考えられる。このうち熱として送る場合は新たな導管を敷設する必要があり、費用面から近接した場所に対するものに限られる。
しかしながら、鉄鋼業の排エネルギーのうち約27%分(鉄鋼業の投入エネルギーの約10%に当たる)は、地域熱供給のための熱源とすることが可能であるといわれている(第1-2-30図)。これは東京23区の民生部門の熱需要の約7%に相当する。日本の主要製鉄所の大部分は人口40〜50万人以上の都市に隣接しており、地域の熱需要も十分にあると考えられ、排エネルギーの地域への供給が期待される。
一方、電気として得る場合には、既に一部の排エネルギーを利用した発電所を一般電気事業者と共同で作り、その発電の一部を一般電気事業者に売電することが行われている。
カ 2000年以降導入可能な技術
2000年(平成12年)以降においては、以上に述べた技術のより一層の普及に加えて、熱効率が50%以上の高効率ガスタービンを用いた発電や、燃焼において、酸素富化膜の利用により通常の空気よりも酸素濃度を高めることによる燃焼効率の向上などが期待される。
また、生産方法の転換等による革新的な製造プロセスの開発が期待されている。その例としては以下のものがある。
(ア) 溶融還元製鉄法(鉄鋼業)
鉄鉱石と一般炭を直接使用して溶融還元法で製鉄を行う方法。コークスが不用となり、4〜5%のCO2削減効果が期待される。
(イ) 流動床燃焼キルン(セメント業)
セメント製造工程において、従来の回転する窯とバーナーによるロータリーキルンで焼成するのではなく、流動床で焼成する方式である。スケールメリットがあまりないので導入可能なプラントは限られるが、化学反応をより効率化することにより最大10%程度のエネルギー効率の改善が可能となる。
(ウ) ナフサ接触分解法(石油化学工業)
ナフサを分解してエチレン等の石油化学基礎原料を製造する際に、従来の熱分解ではなく接触分解することによって、エネルギー消費量を減少させる方法である。
(2) CO2の排出量の少ないエネルギー源の利用の促進
エネルギーの利用に伴うCO2の排出を抑制していくためには、一次エネルギーの投入量をできるだけ小さくしていくことと並んで、エネルギー源をできるだけCO2の排出量の少ないものへ転換していくことが重要である。
ア 化石燃料の中での燃料転換
化石燃料のなかでは、天然ガスが最もCO2の発生量が少なく、各化石燃料により10^10kcalの発熱量を得る際に発生するCO2の量(炭素換算)は、輸入一般炭は1032t、石油で781t、天然ガスは564tとなっている。したがって、適切な範囲内での天然ガスの導入が望まれており、例えば本節の3(1)アで述べたコージェネレーションシステムについても、燃料として天然ガスを用いれば、CO2排出抑制により大きな効果が発揮される。
イ 安全性の確保を前提とした原子力の利用の推進
原子力については、我が国においては既に総発電量の29.4%(平成7年度)を占める主要なエネルギー源の一つとなっており、また、非化石燃料の中では最も実用化の進んだエネルギーで、発電過程ではCO2を排出しない。
IPCC第2次報告書において、原子力エネルギーは、原子炉の安全性、放射性廃棄物の処分等について一般に許容される対応策が見つかれば、世界の多くの地域のベースロードの化石燃料発電を置き換える可能性がある、とされており、我が国においては、原子力基本法等に基づき、放射性廃棄物の処理処分対策を充実させつつ、安全性の確保を前提として、積極的な情報公開による透明性の確保を図り、国民の理解を得ながら、原子力の開発利用を進めている。
ウ 太陽光等の新エネルギーの利用の推進
太陽光発電等の新エネルギーについては、環境負荷が少ないのみならず資源節約も少ないことから、今後その開発・導入を推進することが重要である。しかし、新エネルギー等の我が国の一次エネルギー総供給に占める割合は平成7年度で1.1%程度に過ぎず、このため、技術開発や導入促進策として支援措置を積極的に講じているほか、平成9年4月、国としての基本的取組体制を明確化し、事業者への金融支援措置を盛り込んだ「新エネルギー利用等を促進するための特別措置法」(以下「新エネルギー法」という。)が第140回通常国会において可決・成立した。
(ア) 太陽光発電
太陽光発電は、地上のどこでも得ることができる太陽光を電気に変換して利用するものであり、発電の過程でCO2やその他の汚染物質を全く排出しない。また、一定の設置面積を必要とするが、電力の消費地に分散して設置することができるため、住宅、行政機関、公共施設、民間企業等様々な建築物の屋根、公衆電話ボックス、自動販売機等無数の場所が対象として考えられる。
太陽光発電は、現状では通常の発電方式に比べコストは高いが、大量に導入することになれば大幅にコストダウンすることが期待されている(第1-2-31図)。
このため、通商産業省では、平成4年度から公共施設等に太陽光発電システムを設置し、フィールドテストを行う事業を実施(平成7年度までの導入実績は71件(1760kw))するとともに、本節5(2)に述べるように、住宅用太陽光発電システムの導入を支援し、量産効果によるコスト低減を図るための補助事業を平成6年度から実施(平成6年度及び平成7年度の実績は1578件(5711kW))しており、これらの取組と、コスト低減に向けた技術開発及び保安措置の規制緩和等制度的環境整備とがあいまって、住宅用太陽光発電システムの価格は、過去3年間で40%に低下している。
Box7 学校における太陽光発電への補助
文部省と通産省では、平成9年度より、環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進に関するモデル事業を実施することとしている。
これは都道府県又は市町村が事業主体となり、公立学校を対象に、太陽光発電や太陽熱利用などの新エネルギーや新しい断熱技術など省エネルギー技術を導入したり、緑化、中水利用などを推進するものであり、資源・エネルギーの有効利用やCO2の排出削減に資するとともに、環境学習の教材とすることを目的としている。
原則として、平成9年度には各自治体で基本計画を策定し、平成10年度以降実際の建物の整備を行っていくこととしており、基本計画の策定に対しては調査研究費を国が負担し、建物等の整備に対しては国が補助を行うこととしている。
また、環境庁では、清涼飲料自動販売機への太陽電池の導入のため、関係業界を交えた検討を進めてきたが、平成8年3月、清涼飲料製造者、太陽電池製造業者、自動販売機製造者等がお互いに協力し、清涼飲料自動販売機の全数の1割に相当する19万3000台(2万8950kW相当)を目標として太陽電池の導入を図る方針について合意した。これを受けて、現在、環境庁では、関係業界の協力を得つつ、太陽電池装着型自動販売機の設置・運営に関する技術的な事項を検討するとともに、関係者間の最適な協力関係と費用負担を実現するようなシステムを構築・合意するため、平成9年度から1年間かけて、100台(15kW相当)の清涼飲料自動販売機に太陽電池を導入する大規模フィールドテストを実施している。
我が国の太陽電池の導入実績は、平成7年度末で約3.5万kWとなっており、その発電電力については自家消費される以外は全て電力会社により販売単価と同じ価格での買い取りが行われている。また、「新エネルギー導入大綱」(平成6年12月)では、2000年度に40万kWの導入を見込んでいる。平成6年度末の世界全体での導入量は約16万kW程度と見積もられており、このうち米国が5.6万kW、EUが7.5万kW程度を占めている。これらの国では、太陽光発電からの電力の買い取りが義務づけられており、その際の価格は、回避可能原価もしくは販売単価の90%といった価格とされている。
(イ) 風力発電等
CO2の排出量を抑制するためには、太陽エネルギーに加え、風力エネルギー、海洋エネルギー、生物の光合成機能を利用する技術によるエネルギー等の開発・導入が期待されている。
風力発電については、第1-2-32図に示すとおり、日本では、1.1万kW(世界第15位)程度導入されているのに対し、世界全体では既に583.9万kWの設備(1996年(平成8年)末時点)が導入され、さらなる開発目標値が設定されている(例えば、2000年(平成12年)時点でオランダ300万kW、ドイツ270万kW、インド、イギリス100万kW等。我が国の目標値は2万kW)。現在、アメリカ、ドイツ、インド、デンマーク等で大規模な導入が進んでいる。例えばドイツでは、1992年(平成4年)末の18万3000kWから1996年(平成8年)末には150万kWへと、4年で8倍強に増大しているが、この背景としては、大量導入のための国の計画に基づいて、発電量や投資額に比例して政府が補助を行ったことや、電力会社に対し、風力発電による電力を消費者価格の90%の価格で買い取ることが義務付けられたことが挙げられる。デンマークでは、1979年(昭和54年)、風力発電の建設投資額の30%を補助する制度が発足し、それ以降は設備のコストダウンが進むにつれ補助率を下げ、普及の基盤が確立した1989年(平成元年)に補助金制度を廃止したが、この制度を契機として風力発電が大きく進展した。発電した電力を電力会社に売電できる制度も確立しており、風力発電の所有者の多くは個人となっている。また、最近では電力会社による設置も進んでいる。
(ウ) 廃棄物発電等
我が国では第2章で見るとおり大量の廃棄物が発生しているが、これを焼却する際に発生する排熱を利用することによって、化石燃料の消費量が削減され、CO2の排出量の削減が期待できる。
廃熱の利用方法としては、電力を作ること(廃棄物発電)と熱として地域に供給する方法があり、ここでは廃棄物発電について見てみる。
a 廃棄物発電の現状
廃棄物発電には、自治体が処理する生活ごみ等の一般廃棄物に係るものと、事業者自ら行う製造工程から発生した産業廃棄物に係るものがある。廃棄物発電は年々着実に増加しており、平成7年度の出力規模は併せて80.5万kWであり、また、発電電力量は一般廃棄物で30.0億kWh、産業廃棄物で8.1億kWhに達するが(第1-2-2表)、我が国の発電供給電力量に占める割合は0.38%である。
b 廃棄物発電の導入可能性
「新エネルギー導入大綱」(平成6年12月)では、廃棄物発電について2000年に200万kW、2010年に400万kWの出力規模を見込んでいる。
一方、技術評価報告書における今後の導入可能性の推定では、2000年までに一般廃棄物発電で113万6,000kW、産業廃棄物発電で5万7,000kWの追加導入が可能であり、2000年での廃棄物発電全体の出力規模は、199万8,000kWに達するとしている。また、第8次廃棄物処理施設整備計画では、2000年に一般廃棄物焼却施設における発電実施率を55%まで高めることを目標としている。
c 廃棄物発電の種類
廃棄物発電には、通常の廃棄物発電に加えて、蒸気タービンにガスタービンを付加して熱効率を上げる「スーパーごみ発電」、また廃棄物の量が少ない場合には、廃棄物をごみ固形化燃料(RDF)化して、RDFを一ヶ所に集めて発電を行う「RDF発電」がある。
「スーパーごみ発電」は、廃棄物焼却ガスをさらに加熱し、高温のガスを得るもので、通常の廃棄物発電と比べ、高効率の発電が可能であり、付加されるガスタービンの容量が適切に設計された場合には、エネルギー効率が高まりCO2削減効果が高い。現在4つのプロジェクトが建設中または計画中であり、平成10年に開業予定の北九州市の新皇后崎工場の「スーパーごみ発電」は、約36,300kWの出力を持ち、国内の廃棄物発電所では最大級で、約20万人分の電力を供給できるとともに、熱効率も25%以上の高効率が期待できるとされている。
また、RDFについては、国内に10ヶ所程度のRDF製造施設があるものの、現在は主に公的施設に対する地域暖房等の熱供給に使われている。RDF発電は、発電に必要となる廃棄物が十分に集まらない地域においても、廃棄物を固形燃料化し、それを発電施設のある場所に集積することで効率的な発電が行えるというメリットがある。RDFによる発電施設については実用化段階への移行が急速に進んでおり、今後通常の廃棄物発電と同様に地域の環境保全対策を講じながら、事業化を拡大していくことが期待されている。
d 廃棄物発電の促進方策
廃棄物が安定的に収集され、一定規模以上の廃棄物焼却施設の整備が可能な都市部では、焼却施設への発電設備の付加が一部では進んでいるが、採算面の問題で発電設備の設置を躊躇している地方公共団体も多い。
廃棄物発電は、これを行うことによる経済的メリットが高まれば、導入は一層促進される。廃棄物発電によって得られた電力のうち自家消費量を除いた部分については、?電力会社に売電する方法と、?当該地方公共団体の他の部署で消費する方法がある。
? 電力会社への売電
廃棄物発電を電力会社に売電する方法としては、本節の3で述べたコージェネレーションの場合と同様、a)電力会社の提示する売電価格で電力会社に売却する方法と、b)入札による方法がある。a)の方法による場合、採算性が問題となる例を見てみよう。
平成7年度に稼働を始めた埼玉県東部清掃組合第一工場は熱効率が20.6%の高効率の廃棄物発電所であり、通常の廃棄物発電の熱効率が10〜15%程度であるのと比較すれば、かなり高い熱効率を達成していると言える。
第1-2-3表は同工場における発電関係の追加的な設備投資額を示しており、また、第1-2-4表は発電部門の経常収入と経常費用を環境庁が試算したものである。現在、電力会社への売電価格は概ね昼間12.8円/kWh、夜間4.6円/kWhであり、平均すると約8.2円/kWhとなる。なお、ドイツでは、「再生エネルギー発電による電力買取法」で電力会社に分散型電源の購入義務を課しており、廃棄物発電の売電価格は、電気料金の65〜75%で設定されている。また、米国では公益事業規制政策法に基づき、回避可能原価に基づいた料金で買い取ることとなっている。
環境庁の試算によれば、現状の出力規模1万kWでは必ずしも経済的なメリットが十分でなく(第1-2-33図)、現状で経済的メリットを確保するためには、処理する廃棄物量を日量500t以上(出力規模、約1万1,713kW以上)に増加させる必要がある。他方、環境保全の観点から廃棄物の発生抑制が求められており、廃棄物の発生量を増大させるべきではなく、出力規模を大きくするためにはより広域的な廃棄物処理が必要である。
また、既存の売電価格設定を前提とすると、「スーパーごみ発電」を行ったとしても、経済的なメリットが生じない場合がある。
また、b)の入札の方法については、入札の競争状況がかなり厳しく、また通常の廃棄物発電は昼間と夜間で出力調整を行うことが困難であることから、廃棄物発電が入札に参入することは困難な状況にある。
? 地方公共団体の他の部門での消費
地方公共団体が自ら発電した電力は、同一地方公共団体内の他の部門に自由に供給することができることになっている。実際、廃棄物発電に要した費用は、電力会社から買電する場合の価格と比べて相当小さいことから、同一地方公共団体の他の電力を使用する施設が廃棄物処理場と隣接している場合には、その施設に電力供給を行っている。
しかしながら、電力を利用する施設が廃棄物処理場と離れている場合には、送電施設を自前で整備するとコスト的に引き合わないのが通例である。この場合、電力会社の送電網を利用すること(自己託送)ができれば、そのコスト如何にもよるが、同一地方公共団体での利用が促進される可能性がある。
また、産業廃棄物の発電の経済性は、既設、新設の違い、規模の経済性、廃棄物の種類等によって変わるが、環境庁の調査では第1-2-5表の結果となっている。
廃棄物発電を促進することは、CO2の排出抑制の観点からも大きな効果が期待されており、そのための一層の社会システムの整備が必要である。