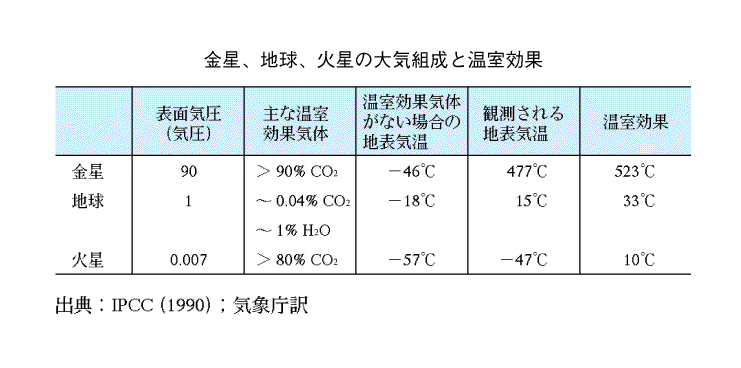
2 地球温暖化のメカニズム
(1) 温暖化が生じるメカニズム
地球をはじめとする惑星は表面が太陽光の放射エネルギー(波長の短い可視光線)によって暖められ、宇宙にエネルギー(波長の長い赤外線)を放出することによって冷える。このエネルギーの出入りがバランスするように表面の温度は決まる。地球の場合、以下に述べる冷却効果と温室効果がなければ、平均気温は理論上5℃となる。
ア 冷却効果
地球に向かって放射される太陽光は、その全てが地球の表面(地表)に到達するわけではない。地球の周りに太陽光を反射する物質(雲や火山から噴出した微粒子)があるときはそれによって反射され、その分は地表に届かない。また、地表に届いた太陽光もその一部は地表面で反射されてしまう。地球の場合は入射光の約30%が反射されて地球を暖めるのに寄与しない。この効果により、地球の表面温度は約23℃低下している。
イ 温室効果
一方、大気中のガスの中には、太陽光の放射エネルギーのような波長の短い可視光線は吸収しないが、地表から宇宙への放射エネルギーのような波長の長い赤外線は吸収する性質を持つもの(温室効果ガス)がある。これらの分子はいったん吸収した地表からの放射エネルギーをあらゆる方向に再放射し、一部は宇宙に出て行くが、残りは地表に放射され、戻ってくる。この結果、地表の温度が上昇する(第1-1-1図)。
地球の平均気温はこの温室効果によって約33℃上がりその結果平均気温は約15℃となっているのである。
Box3 理論上の気温――他の惑星との比較
金星、地球、火星の大気の組成は、表の通り、それぞれ異なっているが、これらの星の現実の地表の気温は、温室・冷却効果の理論によりその大気の組成から推計した通りになっている。
地球の温室効果が33℃であるのに対し、高圧の温室効果ガスがある金星では、温室効果は523℃に達し、温室効果ガスの少ない火星では温室効果は10℃となっている。
(2) 温室効果ガスの種類
自然に存在する温室効果ガスとしては、水蒸気(H2O)、CO2、メタン、亜酸化窒素、対流圏と成層圏のオゾンなどがある。
人為的にもたらされる温室効果ガスには、CO2、メタン、亜酸化窒素、フロン等があり(第1-1-1表)、各人為的温室効果ガスの地球温暖化への寄与の内訳は第1-1-2図(世界全体)、第1-1-3図(我が国からの排出)のとおりである。
(3) CO2の循環
上述のとおり、地球温暖化には、大気中のCO2が大きな寄与をしているが、大気中のCO2はどのようにして発生し、消滅していくのであろうか。
ア 地球大気の生い立ちと地球上の炭素の分布
地球は、約46億年前、太陽の周りのガス状物質が寄り集まってできたものである。ガスが集まってチリ、砂となり、砂の粒子が衝突しあって小石となり、次第に直径10km程度の微惑星が形成されて、これが衝突を繰り返し、1000万年程度の間に、地球などの9つの惑星や隕石などができた。微惑星の衝突エネルギーによって、地球の温度は数千度となり、この高温によって揮発成分が蒸発して、水蒸気やCO2を主成分とした原始大気が形成された。原始大気中には水蒸気が約100気圧、CO2も約100気圧あり、現在の大気よりも非常に濃いものであった(現在の大気は1気圧で、CO2はその約0.03%を占める)。
その後、地球が次第に冷えてくると、大気中の水蒸気は雨となって地表に降り、海ができた。その結果、大気のほとんどは約100気圧のCO2となった。一方、海水は、岩石中のカルシウムが溶けてアルカリ性になっていたため、大気中CO2は、海水に溶け込み、その一部は無機化学反応により石灰石となって沈殿していった。さらに、約38億年前、海水中に生命が誕生すると、生物も海中で石灰石の貝殻、珊瑚礁等を作ったので、大気中のCO2は減少し続け、かわりに、海底に石灰岩が形成された、とされている。
また、約27億年前頃には、海中の生物が光合成を始め、その結果、CO2が有機物として固定されるとともに、酸素が作り出された。このため、CO2を主成分としていた地球の原始大気は、次第に変化していくこととなり、4億年前頃になると、酸素の濃度が現在の10分の1程度まで上昇した。酸素が増加すると、太陽光線によって酸素から生成されるオゾンの濃度も上昇し(オゾン層の形成)、それによって有害な紫外線が吸収されて地表に届きにくくなると、それまで水中にしか住めなかった生物は陸上でも生存が可能となった。陸上の生物のうち、植物は盛んに光合成を行い、大気中のCO2濃度をさらに減少させるとともに、有機物を生産し、その死骸が化石や化石燃料の形で地中に蓄積されていった、と考えられている。
こうして約2億年前に大気中のCO2濃度は現在に近いものになり、かつて全て大気中にあった炭素は、海中の重炭酸イオン、陸上の有機物や石灰岩、地中の化石燃料として蓄積されることになった。現在、炭素は第1-1-4図に示すとおり、大気に7500億t、海洋表層面(海面から水深75m程度まで)に1兆200億t、陸上生態系や土壌や岩屑中に大気中の約3倍の2兆1900億tが蓄積されていると推計されており、さらに海洋中・深層圏には約38兆t、化石燃料として地中深くに何兆tもの炭素が蓄積されていると言われている。
炭素は、このように大気、海洋、陸上生態系等に蓄積され、それぞれの間を循環している。
イ 現在の炭素の循環
IPCCの最新の評価によると、1年間に化石燃料の燃焼とセメントの製造により大気中に放出されるCO2等の量は炭素換算で55億t、また熱帯域の森林が他の土地利用形態に変化することにより約16億tが放出されていると見積もられており、年間71億tの炭素が人為的に大気中に放出されている。
一方、海洋による大気中のCO2の吸収が炭素換算20億tと見積もられており、北半球の中高緯度での森林の再生による吸収が5億t程度、大気中に残留する炭素量が33億tと見積もられている。この合計の58億tと人為的に放出された71億tとの差13億tは、陸上生態系により吸収されていると考えられている(第1-1-2表)。
このように、人為的に排出される炭素量71億tのうち約半分の33億tが大気中に残留し、これにより大気中のCO2濃度は年間約1.5ppmv(ppmvは100万分の1、容積比)の割合で増加を続けている。