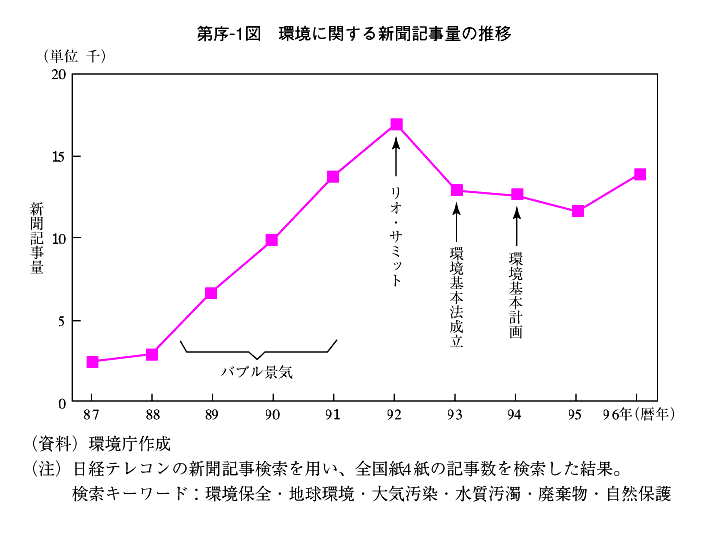
2 危機の現状とその背景
(1) 危機の現状
ア 環境危機の進行
上述したとおり、環境問題の構造が変化したにもかかわらず、それに対する対策や国民意識の変化は遅れている。この構造の変化への対応の遅れが蓄積した結果、地球温暖化問題やオゾン層破壊の問題に見られるように、人為的な活動が環境に与える影響は全地球的な規模となった。このような状況が明らかになるにつれ、このままでは人類だけでなく、地球上の生物全体の生存基盤が失われかねないという認識が国内外で高まってきた。
例えば、環境問題に取り組む研究者、NGO関係者ら有識者約3,200人を対象に(財)旭硝子財団が行っている調査では、平成4年から毎年、地球環境の悪化による危機を時刻で表す環境版「危機時計」の質問をしている。12時を環境悪化による地球滅亡の時刻とし、3時から6時を「少し不安」、6時から9時を「かなり不安」、9時以降を「極めて不安」と分けているが、平成8年には、前年から24分進み、9時13分と危機感が広がっていることを示している。
また、国連環境計画(UNEP)が平成9年1月に発表した地球環境概況報告においても、地球環境は過去10年間悪化の一途をたどっており、すべての地域において、重要な環境問題は各国の社会経済構造に深く影を落としたまま未解決となっている、としている。
イ 環境問題の現状
近年、環境問題が広範化・深刻化しており、人類が地球に与える負荷が増大していることから、現状のまま推移すると、人類のみならずすべての生物の生存基盤である地球環境のバランスが崩れるおそれがある。具体的には次のような問題が指摘される。
(ア) 地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第二次評価報告書によれば、地球温暖化に寄与する主要な温室効果ガスである二酸化炭素(以下「CO2」という。)の濃度は、産業革命前の約280ppmから現在約360ppmにまで増加し、さらに上昇中である。このため、過去百年間で地球上の平均気温は0.3〜0.6度上昇しているが、このような変動は、過去1万年の間に例を見ないものであると言われている。現在のCO2等の温室効果ガスの排出増加傾向が続けば、前述IPCC報告書の中位の予測シナリオによれば、2100年に気温は2度上昇、海面は50センチ上昇することが予想される。50センチの海面上昇で、高潮被害を受けやすい人口は全世界で2倍の約9200万人に増加し、日本の砂浜の7割が消失する。また、地球の全森林面積の三分の一で現在の植生が大きく変化するおそれがある。
南極のオゾンホールは、1996年にも過去最大規模の2600万平方キロに拡大している。また、酸性雨についても、我が国でも欧米と同じ程度のpH4台の酸性を示す雨が降下しており、今後、土壌、湖沼等の被害が顕在化するおそれがある。
(イ) 都市生活型公害や廃棄物処理の問題
二酸化窒素による大気汚染は、近年横ばいの状態にあり、特に、大都市地域における沿道の環境基準の達成状況は芳しくない。これは、自動車交通量の増大、ディーゼル化の進展等が原因と考えられる。
水質に関する環境基準の達成状況を見ると、ここ数年、湖沼については約4割しか達成されていない。また、東京湾の水質汚濁の原因のうち、約7割が生活排水によるものとなっている。
我が国では、毎年、約4億トンの産業廃棄物、約5千万トンの一般廃棄物が発生している。大量消費のライフスタイルを反映して、ここ10年で、産業廃棄物が約35%、一般廃棄物が約18%増加した。これに対し、最終処分場の残余年数は平成5年度末現在で、産業廃棄物で2.3年、一般廃棄物で8.2年しかないのが現状である。廃棄物の不法投棄件数は、平成7年で679件(厚生省調査)に達し、跡を絶たない状況にある。
(ウ) 有害な化学物質による環境汚染
現在、世界全体で約10万種類、日本で約5万種類の化学物質が流通しているが、その中で環境中における安全性が確認されているのはわずかにすぎず、多くの化学物質はその環境中における挙動は解明されていない。また、危険性が指摘されている数多くの化学物質が様々な環境中から検出されている。例えば、船舶塗料に含まれ、生態系への影響がある有機スズ化合物が、依然として環境中から検出されている。また、北極のアザラシからもPCBが検出されており、人の母乳からダイオキシンが検出されている。
(エ) 自然環境の荒廃と生物多様性の喪失
これまでに主要河川の河岸の21%、主な湖沼の湖岸の43%、島嶼部を除く本土の海岸の54%が何らかの人工的な改変を受け、現在も増加傾向にある(85〜92年、環境庁調査)。さらに、二次的自然については、管理がゆきとどかなくなるために荒廃のおそれが増大している。例えば、1ha未満の私有林所有者が林家全体の58%を占めるなど零細な所有者が大半で、林業経営としてではなく、単に資産として山林を所有しているだけの場合も見られる。また、農地のうち耕作放棄地は24万ヘクタールで全体の4.7%にも上り(95年センサス)、全く管理されていない土地が増大している。世界全体では、毎年、日本の国土面積の4割に相当する1540万ヘクタールの森林が失われている。
我が国の野生動物のうち、既に分かっているだけでも、ほ乳類5種、鳥類13種が絶滅した。なお、258種に絶滅の危険が生じているといわれている。現在の種の絶滅の速度は、自然の状態の50倍から100倍のスピードといわれており、地球上で約13分に1つの種の生物種が絶滅しているとの報告もある。我が国においても、ほ乳類の種の約27%、鳥類の18%に絶滅の危険が生じている。その一方でシカによる農作物被害面積は年間2万5千ヘクタールに及び、保護のあり方が問われている例もある。
また、「自然の保護と利用に関する世論調査」(平成8年 総理府広報室)によれば、国民の6割強が自然とふれあう機会をもっと増やしたいと望んでおり、近年のアウトドア志向と相まって人々の自然とのふれあいに対する要望は高まっている。
ウ 何が危機なのか
この「環境危機」の現状を心配する声に対して、「それは知っているが、だからといって何が困るのか。」という反応があるかもしれない。地球が温暖化すれば寒い地方にも快適に住めるようになるだろう、罪のない野生動物が滅びていくのは気の毒だが、しかたがないのではないか、そもそも、今の我々の生活にこれといって大きな差し障りが生じていないではないか、などの反応である。
地球温暖化の影響については本文で詳しく述べるが、イで述べた環境問題の現状が、どういう点で「危機」といえるのかということを考えると、次の2点にまとめられる。
?我々は、再生可能な資源を大量に使用し、また、再生不可能な資源の使用量を、遠からず限界に達することを認識しつつも、依然として増加させ続けており、持続可能な産出量の限界を超えて過剰消費を続けると、資源基盤それ自体を食いつぶし、自然環境のみならず経済・社会をも不安定化することになること。
?我々は、その変化が引き起こす詳細な影響・結果や、変化をくい止め、回復するための方策について、科学的な知見を必ずしも十分持ち合わせていないにもかかわらず、地球全体の気候、豊かな生態系、人体をとりまく環境などのような極めて巨大で複雑かつ精緻な構造を持つものに対し、それぞれ、地球温暖化、自然環境の大規模な改変、環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある多種多様な化学物質の環境への放出などの人為的な作用によって、急激で不可逆的な変化をもたらしていること。
(2) 危機と対策の遅れの国内的背景
環境がこのような危機的な状況にあるにも関わらず、1(2)で述べた構造変化に対する対応の遅れや、前項で述べた環境危機の現状に対する環境保全活動の反応の鈍さはなぜ生ずるのだろうか。その我が国における原因を、?情報・知識の伝達・理解の問題、?不確実性が存在する中での対策の問題、?意識と行動のギャップの問題の3つに分けて、検討していきたい。
ア 情報・知識の伝達・理解の不十分さ
(ア) 情報・知識の伝達における問題
まず、環境に関する情報や科学的知見が十分に国民に伝えられていないことが指摘できる。環境行政における意思決定の基盤となるのは環境の状況や環境汚染のメカニズムなどに関する科学的知見であり、環境行政を適切に進める前提として、科学的知識や情報を国民が正しく理解することが不可欠である。
ドイツ社会調査方法・分析研究所、国立環境研究所、日本放送協会放送文化研究所が実施した調査結果(平成4年)によれば、地球温暖化とオゾン層破壊についての知識の混同がどの程度生じているかを調べるために「地球温暖化は大気にあいた穴が原因である」という文章について正誤を聞いたところ、その正答率は20%台であった(正答は「誤り」)。この結果から、CO2などの温室効果ガスの大気中濃度の増加が地球温暖化の原因となることは知っていても、地球温暖化が起こるメカニズムを正しく説明できる人は少ないのではないかということが推測される。
情報・知識が十分伝えられていない原因としては、まず、公的機関からの情報提供が十分でないことが考えられる。公的機関からの直接的な情報発信の量的拡大の問題については、これまでは、広報・普及啓発予算の制約があったが、インターネットが普及しつつあることで、今後は改善可能であると思われる。環境庁は平成8年3月からパソコン通信(03-3595-3271)により、また平成9年1月からWWWホームページ(http://www.eic.or.jp/)により環境情報の提供を行っている。
一方、「大気中の二酸化硫黄濃度が0.01ppm」などといった個別の調査データの数字については、それ単独では無意味であり、データの信頼性や数値の示す意味などの付加的な情報を伴って初めて情報としての価値が生ずる。公的機関からの情報提供に当たっては、単に観測された数字や調査結果を示すだけでなく、そのデータや調査結果が社会において持つ意味をあわせて提供することが必要である。例えば、経年的な変化とともに示してそれが何に起因しているかを同時に伝え、例えば、自動車交通の増加が原因であれば自動車の使用について再考を促す、などが考えられる。
また、環境に関連する知識を獲得する際にマスメディアの果たす役割は大きい。「環境保全に関する世論調査」(平成5年総理府広報室)によれば、環境情報の入手先(複数回答)として94.6%が「テレビ,ラジオ」を、81.3%が「新聞」をあげており、公的な機関からの直接の情報入手が16.7%であるのに比べて非常に大きな役割を担っている。
例えば、環境に関する新聞記事量の推移を見ると、第序-1図のように、平成4年の地球サミット開催を契機に環境報道量が増大したことが分かる。環境問題が、一時的なイベントとしてではなく、常に考えて行くべき問題であることを国民に広く訴えるためにも、今後も継続的な環境報道がなされることを期待したい。
(イ) 環境科学の専門性・複雑性と理解の問題
次に、仮に問題の所在が伝わったとしても、国民に広く理解されていないことが考えられる。
この理由としては、環境に関する科学知識に高度の技術性・専門性があるため、国民の環境をめぐる科学的な知識や発見に対しての関心や理解が十分ではないことが考えられる。日本を含む先進工業国14ケ国における一般的な科学的知識力・理解力にについて行われた国際比較調査(ミラー、パルド、ニワ、1996)によると、科学的な問題についての議論に参加するだけの一般的な科学的理解力を持っている者の割合は、我が国は17%で、14カ国中13位に留まっている。知識偏重といわれる科学教育の在り方について、現在、体験学習等の実施を通じて改善が図られているが、科学的な事実の理解力を高めるための方策を今後さらに充実させていく必要があろう。
また、現在の環境問題そのものの複雑さも理由として挙げることができる。環境問題は既存の各学問分野の中に留まらず、多数の分野の協力が必要となる学際的分野であり、科学的な事実とともに、その原因や将来的な帰結はもちろん、とるべき対策も多岐にわたる。また、地球温暖化問題の場合に典型的なように、環境に関する科学的知識の高度の技術性・専門性から、最先端の研究成果が短期間に政策決定に反映されることもある。それらのために情報が国民にうまく伝達されにくいという状況が生まれてしまう。今後、情報の伝達に当たっては、様々な段階を想定した伝達方法を工夫する必要がある。
イ 不確実性が存在する中での対策の難しさ
(ア) 環境リスクという新しい考え方の必要性
環境問題の質的変化(影響範囲の拡大、原因・影響の複雑化等)を背景として、因果関係・被害などについて各種の不確実性が存在する中で、取り返しのつかない影響の発生を未然に防止するために予防的措置を講ずる方向に環境政策の主眼を転換する必要性が高まっていることは既に述べた。不確実性が存在する中で未然防止施策を有効に行うためには、多種多様な危険や様々な考慮すべき要因の低減を検討していく必要があるが、この場合、このような危険を完全になくすかすべて許容するかの二分法でとらえると、有害性があっても人の生活に必要とされる物質については、適切な対策をとることができない。従って、現実に施策を行うに当たっては、どの要因・危険をどの程度まで排除・削減し、どの程度まで許容できるのかという観点から考えることが必要となる。
そのためには、環境における多様な要因・危険を相互に比較できるように、できる限り定量的に評価し、総体として低減させていくという環境リスクの考え方の導入が不可欠であり、これにより、異なる課題の間の優先順位を付けることや、異なる分野での同一物質のリスクを総合的に評価して施策を検討することも可能となる。
このように、温暖化問題等の地球環境問題や化学物質による環境への影響などの現代の環境問題への対応においては、不確実性が存在する中で、各種の危険要因の合理的で効率的な削減を図るためには、環境リスクの考え方が重要となる。
(イ) 普及の遅れ
しかし、環境リスクの考え方は、まだ十分な理解を得て普及しているとは言えない。普及が進んでいない理由は、アで述べた情報の不足に加えて、次のような点が影響していることが考えられる。
? リスクの考え方に対する違和感
リスク管理の考え方においては、あらゆる場合にリスクをゼロにし、絶対安全な状態を達成することは現実にはほぼ不可能であるということを認めることや、環境問題を特別のものとしてではなく、環境以外の様々な問題と共通の次元でとらえることが必要となる。しかし、このような考え方に対して、結局はリスクを許容し、環境対策を後退させるのではないかという危惧から違和感を持つことが考えられる。
また、日本人は、文化的・歴史的な背景から外国と比べてリスクに対する感性が乏しいことが考えられる。国際比較調査でも、欧米諸国と比べて環境悪化の健康への影響が少ないと考えているという結果がでている。(第序-2図)。また、日本人は、保険期間中、事故が発生しなければ保険料の支払いを損と考える傾向があり、損害保険でも貯蓄タイプの保険が好まれるという。
? リスクの概念の分かりにくさ
また、リスクそのものが抽象的な概念であるために、分かりにくいことが挙げられる。例えば、化学物質の環境リスクの評価においては、有害性があるか、どの程度の曝露でどのくらいの影響があるか、実際にどの程度曝露されているかを評価し、その結果からリスクを明らかにするという手順をとるが、これらを信頼性を保ちつつどのように算定するのかは難しい問題である。また、環境リスクの多くは未来における影響であるが、これをどのように評価するのか、さらに生体への影響についても、個体に対するリスクを考えるのか、あるいは集団に対するリスクを考えるのか、等複雑な内容を含んでおり、これらが理解を難しくしているといえる。
? リスク認識のずれ
科学者などの専門家がみる科学的リスクと一般市民が認識するリスクの評価が異なっていることが指摘されている。例えば、一般市民は「恐ろしいもの」と「よく分からないもの」のリスクを過大評価する傾向があるとされる(スロヴィック 1987)。このような科学的合理性を超えた心理的な要素があることも考慮してリスクを考える必要があるところに難しさがある。
このような難しさがあるにせよ、環境リスクの考え方は環境施策の推進に有用なものである。どの程度のリスクならば実質的に安全と評価するかは、科学的評価に加えて社会が総合的に判断していく問題であり、その判断に役立つ情報を広く提供し、国民の間で議論を促すことが重要である。
ウ 意識と行動のギャップ
(ア) 意識が行動に結びついていない
第三に、意識と行動のギャップ、つまり、環境保全が必要だということは理解していても、それが頭の中での理解にとどまり、環境保全のための活動を実際に行うところにまでは至っていないのではないかということが考えられる。
環境に関する欧米諸国との国際比較社会調査の結果をもとにした分析(青柳みどり「環境に対する市民の環境保全行動の規定要因についての分析」1996)によれば、現状認識の面については、日本の一般市民は、どちらかといえば環境を優先する考え方をとる傾向があり、外国と比較すると、平均的に見て西欧諸国と同程度である(第序-3図)。
しかし、行動に関しては、現状維持を優先する考え方のグループと環境を優先する考え方のグループという対照的な2グループを比べると、欧米では環境を優先するグループの方が積極的に行動しており、環境を重視する価値観と環境保全行動との関連性が高いのに対し、日本においては、「環境保護団体のデモや集会に参加」以外の行動については2グループ間に統計的に全く差が見られなかった(第序-4-1図,第序-4-2図)。このことは、日本においては、欧米と異なり、価値観や現状認識が直接には環境保全的行動に結びついていないということを示している。
(イ) その原因
この意識と行動のギャップの原因については、平成6年版環境白書(総説p.110〜115)では、?何をしたらいいか分からない、また、行動したとしても、それがどういう効果があるのか分からない?身近に参加の場や購入できる商品やサービスがない?経済的負担になることまではしたくない、という3つの要因を指摘している。
これを別の観点から整理すれば、?及び?は、環境保全活動についての情報不足に起因するものと言えよう。環境保全活動が不活発であることにより、活動に関する情報が地域社会で身近に得られず、活動への参加意欲を阻害するという悪循環に陥る危険性が指摘できる。
?については、日本に限ったことではないが、自分自身で何もしなくても他人の努力によって改善された環境の恩恵を受けることができるという、環境の持つ性質により、行動が阻害されている面もあると考えられる。しかし、それ以外にも、個人の意志とは別に、環境に悪い影響を与えると知っていても社会生活の必要上そのような行動が避けられないような、社会構造的原因が存在することが考えられる。前述の調査においても、各国ともに「自動車の運転の抑制」については有意な差が出にくい傾向が示されている(第序-4-3図)が、これは、自動車の運転を実際に抑制するかどうかの判断においては、環境を優先するという価値観以外にも社会・経済的な要因が働いているためであると推察される。
以上の考察から、環境保全対策が実際に成果をあげるためには、環境に対する意識を高めるだけではなく、環境保全行動を促すための動機付けが必要であり、さらに、動機付けだけではなく、ライフスタイルの変革とあわせて、環境保全のための経済社会システムの改革に向けた施策が必要となることが考えられる。
(3) 本文の構成
以上のことを踏まえて、本文では次のような問題意識を持って記述を行う。
(未来のために、今、何をすべきか)
前項で見たように、日本においては、どちらかといえば環境を優先する価値観を持つ傾向がみられるにも関わらず、環境保全的な行動が盛んになっているというわけではない。
まず行動することが大切であり、今、一人一人が何をすべきなのか、その結果、どんな効果が得られるのかについて、広く理解を得ることが重要である。言い換えれば、市民をはじめとして、各行動主体が自己の行動とその結果引き起こされる社会全体の結果について納得ができるようにしていくことが、人々の行動を環境保全的に変えていくために必要ではないか。また、人々の環境保全行動を促すための効果的な動機付けを含めた対策が必要ではないか。
(環境対策の総合化・科学化)
環境問題が、広域化・構造化・国際化・不確実化したことにより、局所的な環境対策だけでは有効性に限界が生じてきた。今後の環境対策は、例えばリスク管理や環境影響評価制度のように、複雑な相互関係に対応するため、多面的な評価が行えるような、総合的・システム的で科学的なものであるべきではないか。
(価値観の変革の重要性)
これまでに見たように、環境危機とその対策の遅れの背景には、情報や科学的知識・理解力あるいはものの考え方・価値観の問題が大きく影響している。このため、今後の対策としては、環境科学技術の発展や環境教育の充実が重要となるとともに、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした現代社会を支えている我々自身の価値観を問い直すことが必要ではないか。
(環境のための社会制度・システム改革の必要性)
さらに、これまで見たように、個々人の価値観とは別に、環境改善を阻害する社会・経済的な要因が存在していると考えられるため、価値観の変革に加えて、そのような要因を取り除くように社会制度やシステムを改革することが、必要ではないか。
以上のような問題意識を踏まえて、まず、第1章においては、具体的な題材として、危機の中心的課題である地球温暖化問題に焦点を当て、地球温暖化問題に対処するために、これまでの考え方から転換し、あらゆる主体がそれぞれ痛みを分かち合って対策に取り組むこと、具体的には、例えば、排エネルギーの社会全体での有効利用、自動車中心に形成された交通システムの変革が必要であることを訴える。
次いで、第2章においては、モノの循環に着目し、人間の活動により自然界の物質循環が危機に陥っていることを踏まえて、社会経済システムを見直し、物質循環の量・質両面の改善を行うこと、具体的には、例えば、廃棄物・リサイクル対策の基本原則に沿った具体的な廃棄物の発生抑制やリユース・リサイクルの推進が必要であること、環境汚染物質排出・移動登録(PRTR)システムの導入やフロン回収システムの整備などが必要であることを訴える。
さらに、第3章では、環境保全のために具体的行動を起こすための基盤となる分野として科学技術、教育、経済の各分野を取り上げ、まず、環境対策を進める上での知的基盤として、環境に配慮した科学技術の進展や環境面から求められる科学技術の発展の具体的方向性について述べる。次いで、社会的・制度的基盤としての環境教育・自然とのふれあい施策・環境アセスメントの重要性について記述し、最後に、率先実行計画やエコビジネスなどの、国や企業における最近の取組の現状について記述し、今後の施策の方向を検討する。
最後に第4章において、環境の現状を記述する。