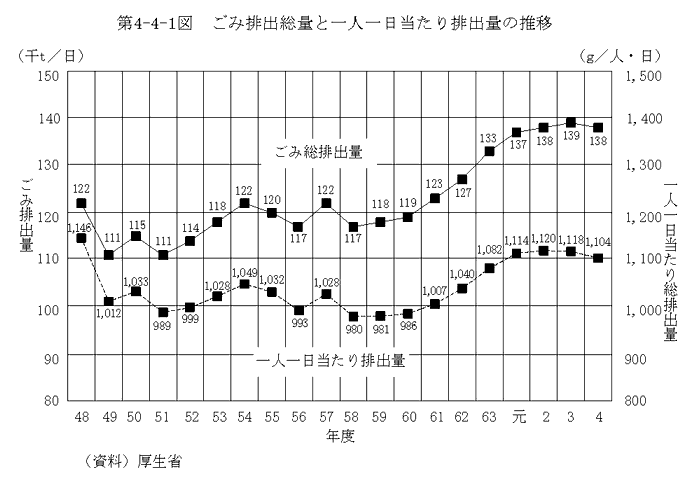
現在の経済社会活動が大量生産、大量消費、大量廃棄型となり、高度化するにつれ、廃棄物量の増大、廃棄物の質の多様化及び最終処分場の残余容量の逼迫等が生じている。これらに伴い、資源採取から廃棄に至る各段階での環境への負荷が高まっており、平成6年12月に閣議決定された環境基本計画では、現在の経済社会システムにおける物質の循環を促進し、環境への負荷を低減させていくため、第一に廃棄物の発生抑制、第二に使用済製品の再使用、第三にマテリアルリサイクル(回収したものを原材料としてリサイクル)を行い、それが技術的困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合、環境保全対策に万全を期しつつ、エネルギーとしての利用を推進することとしている。
(1) 一般廃棄物
一般廃棄物は、人間の日常生活に伴って生じる家庭系ごみ、事業系ごみ及びし尿に分類される。ごみの種類は生活の多様化に伴って増えており、不用になった大型家庭用品など適正処理の困難なごみが問題となっている。
平成4年度のごみ排出量は、年間5,020万トン(東京ドーム約135杯分、3年度は5,077万トン)、前年度比1.1%減(3年度は0.6%増)となっている。また、1人1日当たり排出量は1,104グラム(3年度は1,118グラム)であり、2年連続の減少となった。過去の推移によると、ごみの排出量は戦後の国民生活や社会経済活動の活発化に比例するかたちで増加しており、昭和48年のオイルショックの際に一時減少したものの、その後も依然増加傾向にあったが、平成4年度は9年ぶりに減少になった(第4-4-1図)。減少の要因は、原料対策の進展のほか、景気の後退などが考えられる。
一般廃棄物の処理では、その処分場、特に最終処分場の確保が問題となっており、ごみ排出量の増加に伴って最終処分場の残余容量は急激に減少してきている。平成4年度の最終処分場(ごみ埋立処分地)は2,363か所(3年度は2,250か所)であり、残余容量は1億5,367万立方メートルと3年度の1億5,683万立方メートルと比べほぼ同量であった。残余年数はごみの比重を0.82として計算すると全国平均で約8.2年分となっているが、東京都、神奈川県・千葉県・埼玉県の首都圏地域では4年度のごみ最終処分量は我が国全体の26.5%(約400万トン)を占めるものの、その最終処分残余年数は約4.6年と全国平均を下回っている。
このような一般廃棄物増加によって処分場用地の確保が困難になっていく中で、ごみの排出量の削減やごみの再資源化と再利用が緊急の課題となっており、平成3年には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を改正し、また、「再生資源の利用の促進に関する法律」を制定して、再資源の利用促進に努めている。
さらに、平成7年6月には、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(いわゆる容器包装リサイクル法)が成立した。法律の対象物は、原則として商品に付された全ての容器、包装であり、対象事業者は容器包装を製造もしくは利用する事業者である。また、本法律では、消費者、市町村、事業者の各自に責任を分担させており、消費者は分別排出の責任、市町村は分別収集の責任、事業者は再商品化の責任をそれぞれ負うことになる。本法律の施行により、例えば、分別収集率が90%となった時点においては、一般廃棄物の最終処分量は約55%減少するものと予想されている。さらに、社会全体で過剰包装の抑制やよりリサイクルしやすい素材への転換等が図られれば、さらに廃棄物が減少していくことが期待される。
また、我が国で平成6年の1年間で発生した飲料用缶の空き缶は約371億個と推計され、5年の約318億個に比べて約17%も増加している。環境庁では、全国の空き缶散乱の実態等を把握するため昭和58年度より継続して調査を実施しているが、概ね横ばい状況にある(第4-4-1表)。国や地方公共団体では、空き缶散乱防止対策として様々な取り組みを行っているが、根本的解決には至っておらず、再資源化などの一層の取組が必要となっている。
なお、平成6年度における各種リサイクルの状況は、スチール缶の再資源化率が69.8%、アルミ缶の再資源化率が61.1%とそれぞれ平成5年度(スチール缶61.0%,アルミ缶57.8%)に比べ増加している(第4-4-2図)。また、古紙回収率、古紙利用率についても平成5年度はそれぞれ51.3%、53.1%と高い水準を維持しており、平成4年度(それぞれ、51.2%、52.6%)に比べ増加しているが(第4-4-3図)、平成4年度の一般廃棄物全体の再資源化率は3.9%にとどまっている(第4-4-4図)。
近年、公共用水域の水質汚濁防止の観点から、し尿処理施設からの排水に関心が高まっているが、平成4年度のし尿の処分量(水洗化していない汲み取りし尿総量)は、約3,585万キロリットルで3年度の約3,676万キロリットルと比較してほぼ横ばいであった。また、非水洗化人口は、3,745万人(総人口の30.1%)であり、依然として大きな割合を占める状況にある。
OECD加盟各国の一般廃棄物の排出量については、1975年以降ほとんどの国で増加傾向にある(第4-4-2表)。
(2) 産業廃棄物
平成4年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約4億300万トン(東京ドームの約325杯分)であり、平成3年度の約3億9,800万トンと比べて約1%増となった。昭和60年度からの年平均増加率5%と比較して増加が鈍っているが、これは、平成3年度頃から景気が後退していったことに起因していると考えられる(第4-4-5図)。
排出量を業種別に見ると、建設業、農業がそれぞれ約20%を占め、次いで、電気・ガス・熱供給・水道業、鉄鋼業の順となっている。また、種類別には、汚泥の排出量が最も多く、次いで、動物の糞尿、建設廃材となっており、この3種類で全体の4分の3以上を占めている。
産業廃棄物の処理状況については、全体の40%にあたる約1億6,100万トンが再生利用され、22%にあたる8,900万トンが最終処分されている(第4-4-6図)。最終処分場の残余年数は全国で2.3年と非常に少なく、一般廃棄物以上に最終処分場の確保が大きな問題となっている。特に、首都圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)における産業廃棄物最終処分場の残余年数は、平成5年4月現在で0.6年しかなく、他県で処分しているものも多い。
こうした最終処分場の確保が困難になっている状況は、産業廃棄物の不法投棄の一因ともなっており、土壌汚染等の増大のおそれも生じている。平成7年度の建設廃材を中心として不法投棄された産業廃棄物は全国で約133万トン(6年度は111万トン)にのぼっている(第4-4-7図)。
(3) 有害廃棄物の越境移動
人間の日常生活や社会経済活動によって生じる廃棄物は、生活水準の向上や経済の拡大に伴って、質的な多様化・発生量の増加が進み、発生国内での処理が難しくなるにつれて処理の場所を求めて越境移動する事例が増えてきている。特に、有害廃棄物は処理費用の高い国から安い国へ、あるいは処理に伴う規制の厳しい国から緩い国へと移動しやすく、そのため、受入れ国で適正な処理がなされない場合にはその国の生活環境や生態系に影響を及ぼすおそれもあり、地球規模での有害廃棄物の移動が問題となっている。
有害廃棄物の越境移動の例としては、1976年(昭和51年)にイタリアのセベソで発生したダイオキシン汚染土壌が一時行方不明となり、その後1982年(昭和57年)にフランスで発見されたセベソ汚染土壌搬出事件のほか、ノルウェーの会社が米国からギニアに有害廃棄物15,000トンを持ち込んで投棄した事件、イタリアからナイジェリアへ化学品という名目で3,900トンの有害廃棄物が運ばれて捨てられた事件、米国フィラデルフィアから14,000トンの有害な焼却灰を積載した船舶が各国で受け入れを拒否され、2年余り後にインド洋で投棄された疑いのある事件などが発生している。
有害廃棄物の越境移動は、1980年代前半には例えばヨーロッパ内での移動に留まっていたが、80年代後半になると移動範囲がアフリカや南米の国々に急速に広がり始めた。我が国においては、廃棄物中の有用物を回収するなどのため有害廃棄物が国際取引されている例がある。
こうした地球規模での有害廃棄物の越境移動に対して、国連環境計画(UNEP)を中心に国際的なルール作りが検討され、1989年(平成元年)3月スイスのバーゼルにおいて「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が締結された。我が国も1993年(5年)9月バーゼル条約に加入するとともに、同年12月にはその国内法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」が施行された。さらに、1995年(平成7年)9月には第3回バーゼル条約締約国会議において、リサイクル目的のものを含めて有害廃棄物のOECD及びEU加盟国から非OECD及び非EU加盟国への輸出を1997年(平成9年)をもって、全面的に禁止する(但し、再利用等を目的とするものの国境を越える移動は、当該廃棄物が条約上有害な特性を有しないとされる場合は禁止されない。)との条約改正が採択された。
今後とも有害廃棄物の発生量や輸出入の最小化及び国際協力の推進が課題となっており、国際的な枠組みの下での対策の実施に向けた努力が続けられている。