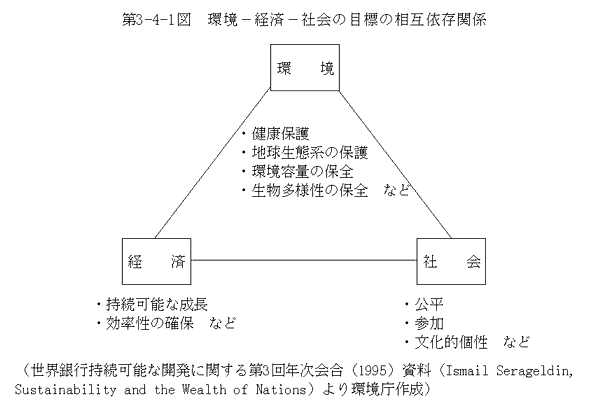
前節まで見てきた様々な課題に示されるように、今日、我々は、生活様式から経済社会のあり方までを持続可能性を基本として変革していくことが求められている。こうした経済社会全体を通ずる変革を可能にするには、人間と環境の関係についての科学的解明、これに基づく長期的な政策の決定、具体的な施策・取組の実行を進めるため、幅広い分野の科学と人類の英知の総合的な力が不可欠である。
従来からの公害問題への対策においては、地域に生じている公害の現状を把握し、その原因となる物質を突き止め、排出の規制を中心とする様々な対策を講じることが課題であった。そのため、科学に期待された主な役割は、環境の測定・分析を通じた原因物質と汚染機構の解明、原因と被害の因果関係の究明、とりわけ健康への悪影響が生ずる汚染濃度(閾値)を判定して政策目標(環境基準など)の根拠を示すこと、さらに、汚染物質の処理・低減技術の開発、実用化である。それには、化学、物理、工学などの応用、公衆衛生学、疫学、病理学などの医学の応用をはじめとする、主に自然科学の関連分野における様々な科学の成果が結集され、問題の解決を支えてきた。また、自然保護の対策においても、優れた自然景観や環境を保護する地域の設定(ゾーニング)を通じた一定の行為の規制、適正な利用の確保が課題であり、自然環境の調査、保護されるべき地域や生物種の判定、人間活動の地域的影響を抑制、防止する技術などに関して、植物学、動物学、森林学、生態学などの応用が政策の基礎とされている。
こうした期待される役割にこたえるうえで、諸科学は、環境問題を個別の事象の束とみなし、それぞれの現象を調査研究し、個別の解決方策を考究すること、いわば、要素還元型のアプローチを主たる方法として取り組んできた。しかし、今日の環境問題は、このような科学の関連分野と手法のみでは解決を図ることはできなくなっている。
その例として、オゾン層破壊問題について考えてみよう。フロンによるオゾン層破壊のおそれが理論として発表されたのは1974年(昭和49年)であり、これが契機となって科学的解明、対応策の策定が次第に進展していった。オゾン層破壊問題に関する科学の課題はきわめて多岐にわたるものである。すなわち、世界のフロンの生産・使用・排出量の把握、成層圏・対流圏でのフロン濃度の測定、フロンの大気中での挙動・寿命の推測、オゾン層の観測、オゾン層破壊の機構の解明とモデル化、将来予測、さらに、オゾン層破壊による有害な紫外線の増加が人に及ぼす影響(皮膚ガン等)、農作物や陸上・海洋生態系への影響の評価(リスク・アセスメント)等が各国や国際機関の科学者により行われた。これにより示された、不確実性を伴うものの長期的に予測される甚大な影響のリスクを踏まえ、有用なフロンが経済活動や生活を支えていることの考慮、フロンの利便性をすでに長年享受してきた先進国とこれから経済発展しようとする開発途上国との異なる利害の調整、代替品・代替技術の開発の見通し、国際的規制の実施方策等を勘案しながら政策の議論がなされた。
前記学説の発表後、米国が早く対応し、スプレーなどへのフロンの使用を段階的に禁止したものの、これに続いたのはカナダほか数か国に過ぎなかった。国際的には、国連環境計画(UNEP)に置かれたオゾン層調整委員会での科学的知見の収集整理に始まり、特別作業部会での条約づくりへと発展し、ようやく1985年(昭和60年)3月「オゾン層保護のためのウィーン条約」が採択された。同年末の英国の研究者による南極上空でのオゾンホール発見の報告は世界を驚かせ、フロンの生産・消費規制を定める議定書の交渉を加速することとなり、1987年(昭和62年)9月に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択された。こうして、前述したような課題について科学的解明を進めながら、国際合意を形成するという重要な先例が確立し、その後も科学的解明の進展に応じて議定書が強化改訂されてきている。
この国境を越えた政策形成のプロセスは、さらに巨大な人間活動に起因し、地球環境の全体に広範かつ重大な影響を及ぼす地球温暖化の問題についても受け継がれている。1988年(昭和63年)にUNEPと世界気象機関(WMO)によって設置された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を中心として科学的解明が行われ、その第1次評価報告書(1990年)を基礎として、国際交渉が進められ、1992年(平成4年)に気候変動枠組条約が採択された。この過程で調査研究され、評価された課題には、温室効果ガスの大気中濃度と過去数万年の推移、世界の温室効果ガスの排出量の推計、過去100年の気温の変化などに加え、全地球での炭素収支の把握、モデルによる気候変動の長期の将来予測、それによって引き起こされる海面水位の上昇、水資源、農業、森林・動植物、沿岸域、エネルギー・都市施設、人間の健康、風水害への影響の評価、これら予測される環境影響のコストの推計等が含まれ、また、政策に関しては、社会経済活動との関係、対策技術の開発評価、対策のコスト、先進国と開発途上国との公平な責任のあり方、技術の移転と資金的措置等について国際舞台で議論が重ねられた。このように、今日の環境問題の解明と政策づくりには、従来の取組をはるかにしのぐきわめて広範囲の諸科学が関わり、かつ国境と世代を超えた合意形成のための経済社会的な課題への考究も不可欠となっている。
前節までに考察してきたテーマについても同様の課題がある。例えば、生物多様性の保全については、国内外の生物多様性の現状把握、将来予測に加えて、生物多様性の価値を現在と将来の世代の観点を含めて評価し、生物多様性を保全しながら持続的に利用していくための政策を基礎付けることが求められている。環境指標は、社会経済活動による環境への負荷、これが環境に及ぼす影響、環境の状況と見通し、政策と取組の有効性を総合的に示すことによって、個人、企業のレベルから地方公共団体、政府の政策決定のレベルまで、共通の理解と合意をつくり、社会の各主体の取組を進めるための重要な手法であり、環境と社会経済活動に関する個々のデータをどのように収集、整理、分析、提供し、相互の関係を明らかにするするかが課題である。環境リスクの考えに基づいたリスク評価、管理は、不確実性を伴う環境問題について科学的な知見を基礎に、人間活動による現在と将来の環境影響のリスクを予測、評価し、環境リスクを総体として管理、低減していく政策決定に資する手法である。いずれも、経済社会システムに起因する環境影響と、環境変化が人間社会にもたらす影響を総合的に評価し、長期的政策づくりを支え、自然環境と人間社会の統合を目指すための課題である。
上に見たように、今日の環境問題は、地域環境の悪化にとどまらず、拡大し続ける人間活動による環境への負荷が地球の有限な環境容量を脅かすまでに増大していることに起因し、様々な自然的・社会的要因が複雑に絡み合って問題が生じている。さらに、不確実な要素をはらむ問題に対して未然防止の考え方に基づく対策が進められなければならない。こうした課題にこたえるには、これまでのように問題を特定の要素に還元して、抜き出した要素に対して技術的な対応を図ることだけでなく、人間と環境の様々なかかわりを包括的にとらえ、長期的な視野に立って、限りある地球環境の中で、どうすれば環境への負荷を減らしながら、現在と将来の世代が真の生活の質の向上を享受できるような経済社会システムを構築していけるかを考究することが必要となっている。
このように持続可能な開発を達成していくには、環境−経済−社会の目標の相互の関連が考えられる必要があろう。環境上の目標としては、健康保護、地球の生態系と生物多様性の保護、環境容量の保全等が基本となろう。また、経済にとっては持続可能な成長、効率性の確保等が、社会にとっては公平、参加、文化的個性等が基本的な目標として挙げられよう。元来、社会と経済の間では、目標を両立させる難しさとともに、これらの目標が相互依存関係にあること、すなわち一方の発展にとってもう一方の安定が不可欠であることが理解されている。持続可能な開発を目指す上では、環境−経済−社会の目標相互の依存関係を踏まえて、これらを統合していくことが求められる。(第3-4-1図)持続可能な開発とは「固定された状態で調和しているのではなく、資源の開発、投資の方向、技術開発の傾向、制度的変革が現在及び将来のニーズと調和のとれたものとなることを保障する変化の過程」(環境と開発に関する世界委員会)なのであり、今日問われているのは、これらの目標をバランスをとって満たしていく道筋を明らかにし、その方向に社会を進めていくことであろう。
こうした長期的観点に立ち、環境−経済−社会の目標を統合しながら達成していくには、それを可能にするような人間と世界の関係の認識、問題構造の理解、目指すべき目標、具体的な取組を明らかにする人類の英知が必要である。諸科学がこの課題にこたえていくには、地球環境問題を個別の分野にとどめるのではなく、学問全体に課せられた大きな課題としてとらえ、結集して取り組むことが求められる。
例えば、経済学においては、将来世代と共有している地球環境の有限性、環境の価値と利用するコストの評価、公平な負担の原理を考察することが課題となる。生態学について、自然生態系のメカニズムの解明に加え、地域と地球レベルでの自然環境の生命維持機能の評価、人間活動と生態系との持続的な関係の究明も必要となろう。物理や化学の各分野における研究や応用についても、経済効率の追求に資する研究開発だけでなく、技術が経済社会を通じて環境に及ぼす影響を予測解明し、自然の働きをいかしながら持続可能な社会の構築を助けるような理論や技術の開発が求められよう。さらに、地球生態系を生存基盤とし、技術や経済社会を作り大きな影響力を持つ生物として、また、過去−現在−将来を認識し、公平、責任といった行動規範に従う人間として、環境倫理をわきまえることが基本となろう。こうした自然科学、社会科学、人文科学の英知を持続可能性を軸に統合し、地球環境学を構築していくことを通じて、持続可能な社会を支える新たな認識枠組み(パラダイム)が根付き、現下の諸課題にこたえるための科学的解明と政策選択肢の提示が可能となるであろう。
国際社会においては、オゾン層破壊に関する科学者によるアセスメント・パネルや地球温暖化に関するIPCCのように、幅広い科学分野にわたる調査研究の推進、その成果の総合評価、政策の基礎づくりが進展してきている。我が国も、オゾン層破壊に関する科学アセスメントに対しては、「オゾン層破壊の科学アセスメント:1994」の作成に当たり執筆者等を派遣しており、また、IPCCの活動に対しては、1990年(平成2年)の報告において第2作業部会(地球温暖化の環境的・社会経済的影響)の副議長、1995年(平成7年)の報告書において第2作業部会(地球温暖化の影響適応及び緩和策)のサブグループA(エネルギー供給・使用分野)の議長、評価ガイドライングループ(影響、対応等)のチームリーダーを務め、各部会に執筆者を派遣するなど、参画、貢献してきている。しかし、報告書で参照される文献の内訳に我が国のものを見ると、IPCC1990年報告での参照論文1,250のうち8件、1995年報告においても参照論文2,200のうち24件にとどまっている。このように、我が国において、自然科学、社会科学、人文科学の幅広い学術研究を地球環境問題の解決を軸に据えて統合、総合化していくことは緊要の課題であり、各方面からの提言がなされている。
内閣総理大臣の主催により開催された「21世紀地球環境懇話会」が平成7年1月にとりまとめた報告「新しい文明の創造に向けて」においては、新たな地球環境科学・技術に向けた再編・創造に関して「現代の科学技術は細分化・専門化がますます進んでいるが、その一方、環境に関連する科学技術は既存の個別学問分野の中に内包されたままに置かれているのが現状である。各個別学問分野の融合も図られようとしているが、現状では地球環境をシステムとしてトータルに理解するためには不十分である。そのためには、新たな視点に立って地球環境科学を構築するとともに、併せて他の科学の分野もそれに応じて再編していくことが必要である。」、「人文・社会科学においてこそ環境の価値付けを積極的に行うことができ、また、このことによって、科学技術との間に環境を軸としたより広範かつ密接な接点が形成され、両者の融合・再編が進み、地球環境問題への総合的な取組が発展する基礎が形成されるからである。」とされている。
また、平成7年4月に学術審議会が行った建議「地球環境科学の推進について」においても、「地球環境問題の特性を踏まえ、その解決に向けて取組を進めるためには、従来の取組に加えて、新たな発想と視点の下に、人文科学、社会科学から自然科学までの幅広い学術研究を地球環境問題の解決を軸に据えて総合化することによって、地球環境科学という新たな問題解決型の総合科学を速やかに構築することが求められている。」、「地球環境科学とは、人類の生存基盤である地球環境の理解を深め、人間活動の影響によって損なわれた地球環境の維持・回復に関連する諸問題の解決に資する総合的・学際的科学であり、そのために大気、海洋、陸域、生態系等に関わる地球環境変動のメカニズムを解明するとともに、人間活動と地球環境の相互関係を踏まえて、影響の予測及び対応策に関する研究を行い、環境調和的な人間活動のあり方を考究するものである。」と新しい地球環境科学の必要性をうたっている。
学会や研究者の中からも、地球環境問題の視野に立って分野横断的な研究と政策提言を行おうとする動きが出てきている。平成7年に発足した「環境経済・政策学会」は、経済、法律、社会学、工学、農学、倫理学ほかの幅広い分野の研究者、さらに行政、産業界、NGOからの参加も得て学際的な研究活動、提言を目指している。さらに、野外調査を基礎に研究を行ってきた動物学、植物学、人類学、生態学、地質学、地理学ほかの伝統ある学会が結集して、自然と人間の共存を図るための自然史研究を進めようとする「自然史学会連合」が発足した。
こうした各方面での意識の高まりと実践が、前述したような総合的な調査研究の推進、そのために必要な体制の強化へと結実していくことが切に望まれる。