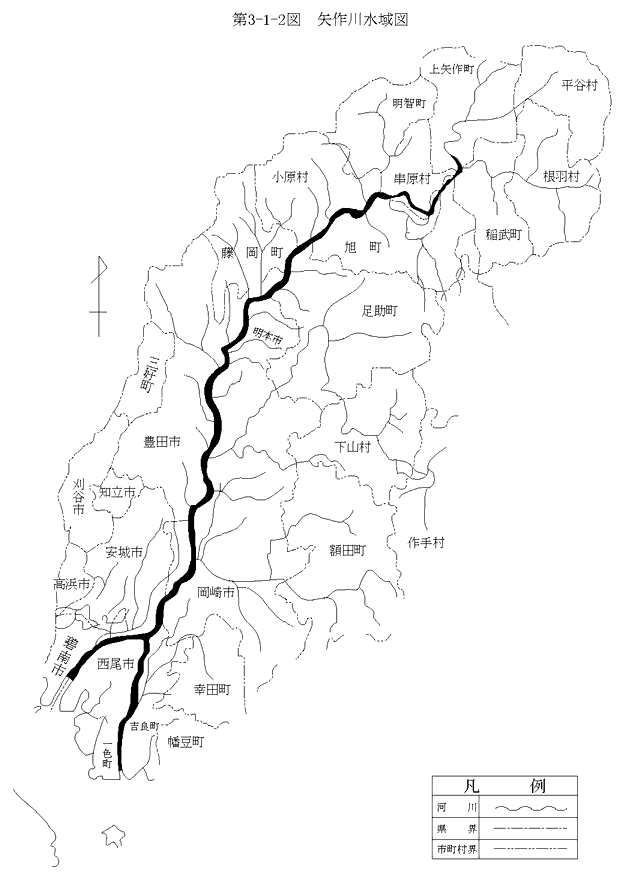
2 地域を越えるパートナーシップ
上に見てきたような地域における取組を基礎に、例えば水系などの一つの環境のつながりを通じた取組、都市と農山村の連携による取組へと拡がりを持った、地域を越えたパートナーシップによる取組が展開されつつある。
(1) 環境のつながりを通じたパートナーシップ
水系等の環境のつながりは、地域社会を連ねて、複数の地方公共団体に及んでいることが通常であり、そこでの環境問題の解決は、一地方公共団体のみで対応できるものではなく、その環境に係わる様々な主体による広域的な対応が求められる。しかしながら、関係者の考え方、利害は、地域や業種、立場により様々で、必ずしも全てが一致しているとは限らない。
一方では、交通、物流、社会資本の整備に伴い、蛇口をひねればきれいな水が出て排水口に流せばどこかに流れていくというように、環境のつながりと切り離された生活となり、自らの生活が環境に支えられていて、その環境を保全していくという意識が希薄になってきている。
一つの環境を共にする様々な主体が、環境のつながりを通じて連携して、その恵みを再認識し、その環境の保全に共同して取り組んでいくことが今日必要となっている。ここでは、水系をめぐっての事例をとりあげる。
ア 民間団体を中心に構築された河川管理システム −矢作川沿岸水質保全対策協議会の取組−
矢作川は、長野県の山岳部に源を発し、愛知県中央部を貫流する延長122?の河川で、三河湾に注いでおり、流域は愛知、岐阜、長野3県の27市町村に及んでいる。(第3-1-2図)
矢作川は、昭和40年代に、上流部の鉱工業排水や乱開発により濁り、水稲や沿岸漁業に大きな被害を与えた。また、流域の土地利用が大きく変化し、水需要の増大や水の汚れをめぐって利害が対立するようになった。
このため、昭和44年に、下流の農業団体と漁業団体とにより「矢作川沿岸水質保全対策協議会」が組織され、「流域は一つ、運命共同体」を合言葉に、事業所の排水の水質浄化、造成工事の施工の指導、行政への働きかけによる乱開発の防止等の活動を展開した。
実績を重ねていく中で、水質保全のための土木施工技術の蓄積、環境管理のための環境アセスメント、環境モニタリング等の科学的な管理手法の習熟により、水域の管理手法を構築し、行政や事業者と一体となった活動により大きな成果を上げている。例えば、造成工事中には、県、市町村、地域住民代表、利水団体代表からなる「公害防止連絡会議」がもたれ、環境の変化や地域の状況が報告され、事業者における濁水を出さない施工技術の採用、市町村間での開発調整、事業者の努力に対する地域の社会的な認知につながっている。(第3-1-3図)
この協議会の活動は、流域市町村により昭和46年に発足した「矢作川流域開発研究会」(研修会等による担当者の意識改革)、開発事業者により昭和61年に発足した「矢作川環境技術研究会」(建設工事における濁水処理技術の研究普及)、下流域住民により昭和48年に発足した「矢作川をきれいにする会」(率先した学習活動、定期的な工場・開発現場の巡回)など地域ぐるみで支えられている。また、地域の環境教育という点でも、豊田市の小学校で昭和51年から毎日矢作川の水をくみ透視度を計測している息の長い取組がある。
また、協議会は、上流の児童を潮干狩りに招待したり、新鮮な魚介類を山村に運ぶなど上下流域の交流による相互理解の促進を進めている。平成3年には、交流事業を進めるため、流域市町村により財団法人矢作川流域交流振興機構が設立されている。さらに、平成3年には、矢作川の水源にある長野県根羽村と下流に位置する愛知県安城市が、協力して水源の森を管理し、伐採時にはその収益を分け合う「水源の森分収育林事業」を始めるなど、水源となる森林の保全にも目を向けた活動を行っている。
このように、協議会という民間団体が、濁水を出さないための各方面への働きかけと対策に関する知見の蓄積と実践、相互理解を得るための取組を進めたことにより、地域の環境をトータルとして評価する「矢作川方式」と呼ばれる独自の流域管理システムが地域に定着している。この活動は、国連環境計画(UNEP)等の河川、湖沼の流域管理に関するケーススタディでも取り上げられている。
イ 県境を越えた地方公共団体と住民のパートナーシップ −桂川・相模川流域の環境保全−
山中湖を水源とし、山梨県から神奈川県を流れ相模湾に至る相模川(山梨県内では桂川と呼ばれる。)水系は流域の住民及び神奈川県民の貴重な水道水源であるとともに、工業用水、農業用水など多様な用途に利用されてきており、過去から現在にわたり様々な恩恵を流域に与えてきた。(第3-1-4図)山梨県と神奈川県では、この相模川流域の環境保全を、県境を越え、市民、事業者、行政が連携して進めるという取組を進めている。
両県の行政における取組は、昭和55年神奈川県知事が山梨県を訪れた際、相模川水系の水質保全問題について意見交換が行われたことに始まるが、相模川の水質保全を上下流域の協力のもとに進めようという動きが具体化されてきたのは、平成4年11月に両県の間で「山梨県・神奈川県水質保全連絡会議」が設置されてからである。約3年後の平成7年8月に行われた連絡会議では、「桂川・相模川流域環境保全行動推進事業」について両県間で合意が形成されるに至った。
この事業は、複数の県にまたがる問題に対して共同で取り組むこと、流域住民の積極的な参加による実践活動が柱になっていることの2点が大きな特徴としてあげられる。(第3-1-5図)この事業の一環として平成7年10月から12月にかけて行われた合同クリーンキャンペーンでは、ごみ拾いを行い、集めたごみを分別して地域ごとのごみの散乱実態を調べる「クリーンエイド方式」による活動が行われた。これに加えて水質調査、水生生物調査が行われ、小中学生、一般市民の他、漁業協同組合の関係者、地元信用組合など延べ5,500人もの参加者があった。
また、山梨、神奈川両県議会も、両県議員による意見交換会を開催し、この事業を積極的に支持することを表明している。
一方、これと並行して、市民団体による流域のネットワークづくりが進められた。
神奈川県では、平成7年7月に、相模川をより良くするために行動し、河川を巡る豊かな環境と流域文化を未来に引き継いでいくことを目的として「市民ネットワーク・相模川」が設立された。また、山梨県では、平成7年8月に、首都圏の釣り人を中心に構成するグループの呼びかけで、桂川流域の市民団体が「桂川をきれいにする会」を発足させ、桂川からごみをなくす運動を開始した。この会は、親子で川に親しむイベントや流域の環境団体、市民に呼び掛けてシンポジウムを開催するなどの活動を行っているが、このシンポジウムに「市民ネットワーク・相模川」のメンバーが参加し、上流・下流の市民団体の連携、交流が形成された。
さらに、この動きと重層的に、相模川の河川環境保全を県域にとらわれず市民の視点から進めようという「桂川・相模川流域ネットワーク」が、平成7年10月に山梨県の上野原町に山梨・神奈川両県の市民約60人が集まって設立された。河川環境を守るには、目の前を流れる川の流域だけでなく、川の上流の環境保全にも目を向けることが大切と、横浜の環境市民グループが中心となり、相模川上流の山梨県の市民グループに、県境を越えてともに活動しようとネットワーク設立を呼びかけた。ネットワークでは水質測定調査から始まり、水源環境保全基金づくり、水質環境問題への理解を深める学習会の開催などに取り組んでおり、将来的には環境分野の活動だけでなく、生活習慣や産業構造が異なる上流と下流の市民どうしの文化交流にも活動を広げていきたいとしている。
このように、行政、住民それぞれが県境を越えた取組を繰り広げようとしており、これらのネットワークの連携への動きもみられる。平成8年3月には、市民団体も参加して、流域のほぼ中央に当たる山梨県大月市で公開シンポジウムが開催された。また、「桂川・相模川流域環境保全行動推進事業」は、平成7年度から9年度までの3年間を予定しているが、この期間内に流域の行動指針となる「流域アジェンダ」(仮称)の策定とこれを実践していく組織となる流域住民、事業者、行政で構成する「流域協議会」(仮称)を設立し、長期的な取組を進めていくことを目指している。
この取組は、県の枠を越え、市民の実践活動の促進を両県が合同で行うものであり、環境基本計画に掲げられている地方公共団体の連携による取組の実践といえるものであるが、地方公共団体ばかりでなく、広範囲にわたる住民相互の連携及び地方公共団体と住民のパートナーシップによる事業が企業を含む様々な主体の参加の下に行われている点で注目されるものである。
(2) 都市と農山村の連携 −阿蘇グリーンストック運動−
昨年の環境白書においては、雑木林と人間関係の共生関係を例に挙げ、人間活動も輪の中に組み込んだ里地の生態系循環のメカニズムについて報告した。このように、かつての社会においては、地域の生産、消費、廃棄はいずれも地域の生態系のメカニズムの中で行われ、人と自然との間に持続的な共生関係が育まれ、人間活動もその輪の中に組み込んだ生態系の循環が成り立っていたということができる。
しかし、地域の経済社会を構成する地理的な広がりが大きくなり、生産構造が多資源投入型になり、消費構造も大量消費型になるとともに、人間活動は、地域の生態系循環の枠を越えるようになり、過疎化、高齢化という人口要因も相まって、地域の生態系保持のメカニズムも機能しなくなってきている。里地の生態系循環のメカニズムも、エネルギー転換や化学肥料の使用により、農業と里山が切り離され、その結果として里山が経済的有用性を失い、次第に減少していく状況となっている。
一方で、今日の市場経済の下で、地域の生態系の保持、環境保全の価値を経済システムに組み込む動きが芽生えてきている。このような取組は、我々の生活が大きな生態系循環の中にあることや環境と日常生活とのつながりを再認識させる。農山村を単なる食料や木材の生産地としてだけ見るのではなく、今日の大量生産、大量消費、大量廃棄の生産・消費構造の見直しへとつなげていく鍵をこのような取組の中に見いだすことはできないだろうか。
阿蘇地域の広大な景観要素であるススキあるいはシバの草原は、野焼き、千年以上にわたる放牧、干草狩りという地域の営みにより今日まで維持されてきたものである。また、阿蘇山は周囲128?の外輪山に囲まれた世界一のカルデラ火山として知られ、5つの一級河川の源流として九州5県に飲み水や農業・工業用水を供給しており、九州各地の人々の生活は阿蘇の自然の恵みを受けて成り立っている。
しかし、日本有数の草原景観を奏で、九州各地に豊かな水の恵みをもたらす阿蘇の自然を支えてきた生活基盤が、牛肉の自由化等を背景とする畜産業の低迷、過疎化や高齢化の進展による人手不足などの情勢の変化の中で徐々に失われつつあり、野焼きなどを通じて積極的に自然に働きかけてその維持を図っていくことが困難な状況になってきている。
野焼き、放牧、採草といった営みがなくなれば、草原は本来の自然植生である森林に遷移していくと考えられているが、そうなれば、これまでの地域の生態系と人々の生活や経済との共生関係は崩れ、この地域で人が生活する基盤が失われることにつながる。人間の手の入らなくなった一部の草原では、低木が育ち始めているが、山火事の危険性を指摘する声があるほか、地域の生態系にどのような影響を与えるかについては十分に解明されているわけではなく、この地域の自然生態系全体をどのように管理していくかという観点からの調査と計画が必要になっている。
このような状況の中で、人々の生活を支えている阿蘇の草原や森林、水田を次世代に引き継ぐべき「緑と水の生命資産」(グリーンストック)ととらえ、地元住民、都市住民、行政、生協、地元企業等のパートナーシップにより、農林畜産業の振興、自然環境の保全及びグリーンツーリズムの推進を図り、この水と緑の資産を次世代に引き継ぐことを目指した「阿蘇グリーンストック構想」が、平成7年4月に設立された財団法人阿蘇グリーンストックを中心に進められている。(第3-1-6図)
阿蘇に住む人々が農業、畜産業、林業という営みを通して守り続けてきた緑や水の資産を都市住民と農業者との連帯を図って守っていくために、設立以来、生協等との産地直送取引関係を構築し赤牛の自然飼育による生産の継続・育成を図るとともに、阿蘇地域の草原、森林、水田とそれを支える農林畜産業についての理解を深めるためのシンポジウムの開催を行ってきた。
しかし、阿蘇の大規模な自然は、人的にも経済的にも、過疎化、高齢化した地域社会がひとり支えられるものではなく、農産物を通じた取組の他に、人の交流を通じて農村を豊かな生活空間・余暇空間として形成していくことが不可欠である。また、都市部からの移住者を含めた新たな農林畜産業の担い手の養成も必要である。このことから、平成8年からは、阿蘇の大自然に対して単に通過型の観光にとどまらず、地域の自然と共生した生活を体験してもらうことを通じて、地元住民、都市からの移住希望者、余暇を求める人々が共に農村の活力ある暮らしをつくる「ニューファームビレッジ計画」が進められている。
これまで阿蘇の大自然と共生し、責任を持って対してきた地域自らの手で、都市住民も含めて地域の自然と持続的な関係を構築しようとする計画が進められている。これに対し、都市住民の側が自らの生活を持続可能なものへと変革していく取組としてどこまで受け止められるか、どのように阿蘇の自然とかかわっていくことができるか、それらの取組を支える経済社会の条件をどのように作っていけるかが、この地域での持続的な自然と人間との関係を構築できるか否かの鍵となろう。