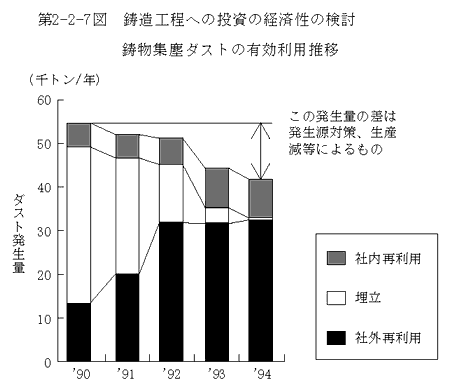
2 環境コストを内部化し経済活動の質を高める考え方へ−「環境効率性」の視点−
本節の冒頭で述べたように、都市・生活型公害や地球環境問題は、環境への負荷に伴い社会に生じるコストを明確に認識して十分な対策を行うことをせず、これらのコストを市場メカニズムの中に適切に織り込まないまま膨大なエネルギーや資源を消費してきたことに原因がある。従って、こうした問題を解決するためには、地域と地球の環境には限りがあることを認識し、環境を利用することによって生じる社会的コストを内部化することによって、環境と経済を統合するような経済社会システムを構築していくことが不可欠である。とりわけ、経済社会の中で大きな部分を占める事業者は、持続可能な経済活動の中に環境保全を織り込むことを通じ、自主的、積極的に環境への負荷を低減していくことが求められている。
我が国がかつて経験した激甚な産業公害は、企業が環境規制の強化に対応するために、技術開発とそれを応用する汚染防止装置への投資を行うというかたちでの環境コストの内部化によって克服されてきた。この際、環境コストの内部化は、生産コストの増大、製品価格の上昇、売り上げの縮小、利益の減少へとつながり、あたかも環境と経済がトレードオフの関係にあるように考えられがちである。しかしながら、こうした考え方は、これまで我が国が歩んできた道を振り返ってみる時、必ずしも当てはまっているとは言えない。我が国が世界の国々の中でも早期に厳しい自動車排出ガス規制等を実施してきたことが、結果的に自動車の技術開発を大きく促進したことはよく知られているところであり、また、こうした環境規制に伴う環境コストの内部化がマクロ経済に与えた影響については、環境庁が行った分析(昭和52年版環境白書)やOECDの日本の環境対策レビューによって、長期的な経済成長の足枷にはならなかったことが実証されている。
都市・生活型公害や地球環境問題を解決するためには、これまでのような特定の環境汚染物質をその排出口において除去するだけでなく、資源・エネルギーの利用、製品の生産・消費、不用物の放出という過程を通じて生ずる環境への負荷を減らすように、環境コストを経済に内部化することが必要となっている。このようにより広い環境コストを内部化し、そのコストを最も効率的に削減することによって環境への負荷を低減していくということは、言い換えれば、いかに少ない環境への負荷で必要な財やサービスを生産・消費するかという「環境効率性(Eco-efficiency)」に基づいた経済活動を行うということである。環境対策が、短期的には痛みを伴うことがあっても、長期的には必ずしも経済成長にマイナスには作用しないということは、先に述べたとおりである。さらに、環境効率性に基づいた企業行動、例えば、生産工程から環境への負荷が発生することを前提としてその除去のために資源・エネルギーを費やすよりも、汚染物質を減らすこと又は発生させないことを前提とした予防的対応を可能とする環境技術を開発・応用する環境投資は、生産工程における資源・エネルギー効率を高めることも可能にする。こうして、従来から投資を行う際に考慮されてきた経済効率性の考え方を改善し、長期的に経済活動の質を一層高めることにつながる。
(1) 低負荷型技術による環境効率性の追求
このように環境効率性に基づいた経済活動は、環境への負荷の低減と健全な経済活動という2つの経営課題を両立させ、環境と経済を統合し、持続的発展が可能な経済社会の構築に寄与すると考えられる。
従来の環境対策においては、既存の原料、生産工程から汚染物質や廃棄物が出ることを前提に、いかにこれらを処理してできる限り環境中に排出しないかに対応したエンド・オブ・パイプ技術と呼ばれる技術が広く利用されてきた。
これに対して、近年、汚染物質や大量の廃棄物の排出を前提にするのではなく、生産工程においていかに環境に負荷を与える汚染物質や廃棄物を発生させないか、いかに環境への負荷の少ない製品やサービスを生産するか、または、いかに廃棄物を資源化するかに対応した技術、言い換えれば、いかに少ない環境への負荷で財やサービスを生み出すかをめざす低負荷型技術が開発・応用されている。そこで、ここでは、環境庁において調査研究を行った生産工程における具体的な低負荷型技術への投資事例によって環境効率性を考察してみよう。
ある自動車メーカーは、エンジンの鋳造工程から出る鋳物廃砂の削減を目的とした環境投資を行った。この自動車メーカーでは、生産工程から出される鋳物廃砂のうち、粒径の大きなもの(年間5,000トン)を鋳物砂として再利用し、粒径の小さなものの一部(年間約15,000トン)をセメント原料として社外で再利用し、残り(年間約35,000トン)を埋立処分していた。しかし、埋立処分場の残存容量が減少してきたこと、埋立処分費の増加が懸念されたこと、社内の環境対策計画の中で廃棄物の削減目標を設定していたことなどから、社内外で廃砂の再利用拡大を図ることとし、廃砂の選別の徹底のための廃砂回収装置の設置、廃砂の空気輸送管の配管、廃砂貯留タンクの設置等の環境投資を行った。結果的に、約10億円の初期投資に対して、99%の廃砂埋立量の削減及び年間約3億円のランニングコストの圧縮が実現できた(第2-2-7図)。このメーカーは、省資源・省エネルギーに関しては投資回収年数3年以内という投資基準を設けていたが、埋立処分場の延命化、社外に公表している環境対策計画の目標達成の観点から投資が実行され、環境効率性を大きく高めることができた。
また、ある醤油醸造業者は環境投資により廃棄物をなくし、特定フロン使用を廃止した。この醸造業者は、生醤油の発酵を止める火入れ工程で発生するタンパク質が凝固した滓を、珪藻土を用いて濾過することにより固液分離を行い、液体を生醤油に戻すとともに、残される珪藻土等(年間930トン)は廃棄物として委託処理していた。しかし、珪藻土の購入費や処理費用に限ってみても、その負担が年間5千万円程度にもなることから、その費用削減が企画された。採用された工程は、滓の固液分離のために珪藻土に代えて膜を用いるもので、廃棄物が発生しなくなるだけでなく、滓の全量が発酵工程又は充填工程へと戻せることになり収率が高まったほか、従来の濾過機の工程転換に伴い、省力化も可能となり、無人運転ができるようになった。この対策の初期投資額と主なランニングコストの比較表は第2-2-2表のとおりであり、約5億円の投資により、ランニングコストは年間1億円程度減少する計算となった。なお、同社は、税金等を含め、また、設備使用年数10年を前提に利益率を求め、それが8%以上のときは投資を決定している。本対策の利益率は12%強であって社内の投資基準を満たしていた。この対策の効果は、年間930万トン発生していた廃棄物がなくなり、あわせて生産される醤油の量が年間570キロリットル(3,600万円弱に相当)増加したことであった。また、同社は、製麹工程で麹冷却(冷風)用として使用していた特定フロン使用のターボ冷凍機を吸収式冷凍機に変更し、特定フロンの使用を廃止した。第2-2-3表からわかるように、冷却にフロンを使用せずに済むほか、費用の比較では、直焚き吸収式冷凍機の方が水冷式チラーユニットより有利であることがわかる。
以上の投資事例から、環境への負荷を低減していくために、製造工程や製造技術の変更も含めて見直しを行い、環境対策を内部化する投資決定が経済的合理性にも通ずるという環境効率性の考え方が理解される。この際、環境への取組の中長期的観点から従来の投資決定のルールについても状況に応じて適切に改めることにより、短期的、経済的に引き合うかどうかを焦点として環境投資を単なるコストの増大要因と見なし環境と経済をトレードオフの関係としてとらえる考え方を脱しうることがわかる。
(2) 環境効率性を実現していくための企業活動のデザイン
環境への負荷を低減することを目的とした環境投資が、企業の経済活動の質を高めることは先に述べたとおりであるが、環境への負荷の低減を効果的、効率的に行っていくためには、従来のようなエンド・オブ・パイプでの対応だけでなく、製品のライフサイクル全体や産業構造全体に視野を広げて対応していくことが必要である。そのため、ここでは、環境効率性を実現していくための企業活動のデザインとして、製品のライフサイクルのあらゆる段階を評価して環境への負荷の低減を図るライフサイクルアセスメントや、新しい産業の編成によって全体としての環境への負荷の低減を図るゼロ・エミッションについて取り上げる。
ア ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment)
ライフサイクルアセスメント(以下、LCA)とは、製品等(財、サービス)の環境への負荷を生産−流通−消費・使用−廃棄という一連のプロセスを通して定量的、科学的、客観的に把握、評価する手法のことである(平成7年版環境白書)。現在のLCA研究の多くは、大気汚染物質、水質汚濁物質、温室効果ガス、エネルギー消費量、廃棄物量等の環境への負荷データを評価の対象としている。LCAは、基本的には、?製品間の環境への負荷の大きさの比較をするといった目的の明確化、?製品等や技術について資源、労働、金額、環境への負荷がどのように投入、かつ算出されているかを明らかにするためのデータ収集、?対象製品等から発生する環境への負荷が社会にどのような影響を与えているかを明らかにするインパクト評価、?インパクト評価で明らかになった問題点を具体的に改善するための施策を検討し、その効果を定量化する改善評価の4つのプロセスから構成される。LCAの効用には様々なものが考えられるが、例えば、事業者にとっては、製品ライフサイクルの各段階での環境への負荷の発生程度の把握や製品のライフサイクル全体を対象とした最適化設計が可能になること、競合製品と比較した場合の優位性を主張する科学的根拠を得られることなどがある。消費者は、LCAの結果に基づき、商品の選択的な購買、使用を通じて環境への負荷の低減に貢献することができ、また、環境行政の観点からは効果的なリサイクルの推進のための施策等の立案のほか、環境ラベルの認定やその基準作成等のためのデータの収集に役立つ。
環境にやさしい企業行動調査によると、上場企業では、「製品又はサービス等に係る主要な環境負荷の把握、評価の際に、LCAもしくはLCA的な手法を用いた事前評価、製品アセスメント等を実施していますか」との問に対して、「既に実施している」と回答した企業が3.7%であったのに対して、「実施には至っていないが、研究段階である」、「LCAについては関心があり、情報収集段階である」と回答した企業が合わせて63.8%となっており、LCAに関してかなり高い関心が持たれていることがわかる(第2-2-8図)。
LCAの考え方を用いた研究としては、1969年(昭和44年)の米国のコカ・コーラ社の飲料容器を対象としたものが最初であり、欧州においてもほぼ同時期に研究が始められた。我が国のLCA研究の歴史はまだ浅いものの、環境配慮への関心の高まりとともに、その研究対象分野についても容器・包装材、家電製品、建築物、電力等のサービス等大きな広がりを見せている。しかしながら、LCA実施に不可欠な環境への負荷排出量等のデータが整備されておらず標準的な手法も確立されていないため、LCAの普及・促進の観点から大きな障害となっており、特に、信頼性の高いデータの有無は、LCAを活用した研究結果の質を大きく左右することから、信頼性の高いデータベースの整備が必要となっている。
先に述べたISOにおける環境マネジメントシステムの国際規格化の中には、LCAの検討も含まれており、LCAについては、TC207の第5分科会(SubCommittee 5)の下に5つのワーキンググループが設置され、現在、LCAの国際標準化のための検討が鋭意行われているところである。環境にやさしい企業行動調査によると、上場企業では、ISOにおけるLCAに関する国際的なガイドラインの検討について、聞いたことがある程度という回答も含めて7割以上が「知っている」と回答しており、LCAの国際的な規格化についてはかなりの企業が認識していることがわかる。
ここで、LCAを具体的に応用した研究事例を見てみることにする。第2-2-9図は、平成5年に日本生活協同組合連合会が行った「容器包材の環境評価に関する中間報告」に示された紙製の飲料容器に関する評価結果である。この図からわかるのは、まず、水消費量、水質汚濁の環境への負荷項目は材料製造段階での発生割合が特に高いことである。これは「パルプ」の製造に起因するものであるが、このことから、環境への負荷を低減するためには、容器のリサイクルを促進する必要があること、パルプ製造時の排水処理を徹底する必要があること、ペーパスラッジを適切に焼却する必要があることがわかる。また、パルプを冷蔵車(チルド車)で輸送していることから、大気汚染の項目では運搬の占める割合が高い。このため、環境への負荷の低減には、チルド車そのものに対する改善のほか、配送効率の向上、設定温度の見直し等が必要であることがわかる。固形廃棄物発生量の項目では廃棄の占める割合が高く、リサイクルの必要性等が読みとれる。
イ ゼロ・エミッション(Zero Emission)
ゼロ・エミッションとは、全産業の生産工程を再編成し、廃棄物(不用物)がすべて原料として活用されるような新しい産業集団をつくることなどによって、廃棄物自体の発生がない循環型産業システムを構築していこうとする考え方のことである。
ゼロ・エミッションは、1994年(平成6年)7月に国連大学(UNU)で開かれた第1回「ゼロ・エミッション研究構想(ZERI)」研究会の場で発表され、翌1995年(平成7年)4月には第1回世界ZERI会議が開催された。現在、国連大学では、ゼロ・エミッションに関する8つのプロジェクトが検討されている。この8つのプロジェクトは、?ある企業の廃棄物を他の企業が原材料として活用する新しい産業集団の創出、?応用可能な自然現象の仕組みを利用した革新的技術の開発、?毒性の強い物質を原料として使用している産業の構造の見直しという3つの目的を持ったそれぞれのカテゴリーに分類されており、具体的には、ビール醸造業と水産養殖業等の組合せ、鳥類が作り出す生分解可能なワックスの応用、水銀の使われている機器のリースシステムの検討等が行われている(第2-2-4表)。
(3) 環境の有する受容能力の活用
人間活動の蓄積や事故による環境への影響を環境の有する受容能力の活用によって緩和、低減する手法にバイオレメディエーションがある。
バイオレメディエーションとは、微生物や植物が持つ化学物質等の分解能力、変換能力、蓄積能力を利用して環境汚染物質を削減あるいは除去することで、環境汚染修復技術のひとつとして注目を集めている。我が国では、この技術に関しての実用例はなく、研究段階であるのに対して、土壌や地下水の汚染が早くから顕在化していた米国では、1980年(昭和55年)に「包括的環境対処補償責任法(スーパーファンド法)」が制定されて後、種々の修復技術が開発されていく中でバイオレメディエーションもスーパーファンドサイトの汚染修復技術として採用されている(第2-2-10図)。
実際の海外での適用事例を見てみる。例えば、1989年(平成元年)に米国アラスカ州の南海岸で起こったエクソンバルディーズ号の座礁は、4千万リットルの原油流出をまねき甚大な海洋汚染を引き起こした。これに対して米国環境保護庁(EPA)は、海水中に親油性の栄養剤等を散布し、土着の石油分解菌を活性化させることにより、流出原油を処理した。また、ドイツ北部のディンスラーケンでは、地盤沈下によりパイプラインが破損し、約275,000リットルの石油が漏れ出し土壌汚染を引き起こした。この土壌汚染の修復は環境保護事業会社が請け負い、掘り起こした汚染土壌に微生物と栄養剤を混合することによって処理を行った。
環境汚染修復に役立つ微生物の持つ性質には石油の分解のほかにも可能性が指摘されている。例えば、悪臭は、毎年集計される公害苦情件数の中でもかなりの比重を占めているが、我が国では1985年(昭和60年)以降、微生物を利用した生物脱臭と呼ばれる技術が下水処理場やし尿処理場を中心に実用化されつつある。従来から悪臭物質を処理する方法としては、活性炭による吸着法、オゾンによる酸化法、高温で燃焼する方法等がよく利用されているが、こうした方法は、処理効率が高く、安定的である一方、化学薬品の大量使用、廃液処理、多量なエネルギー消費等の点で問題がある。これに対し生物脱臭の利点は、特別のエネルギーを必要としないことや有害物質が副生物として出る可能性が低いことなどが挙げられる。この生物脱臭は微生物能力と脱臭能力との関係が今のところ明確に説明されていないものの、省エネルギー型の新しい悪臭処理方法として、また、有害化学物質の排出処理法として期待が持たれている。
そのほか、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素を固定する微生物、健康への影響が懸念されているトリクロロエチレンを分解する微生物、赤潮やアオコの発生原因物質であるリン酸を分解する微生物等の研究が行われている。