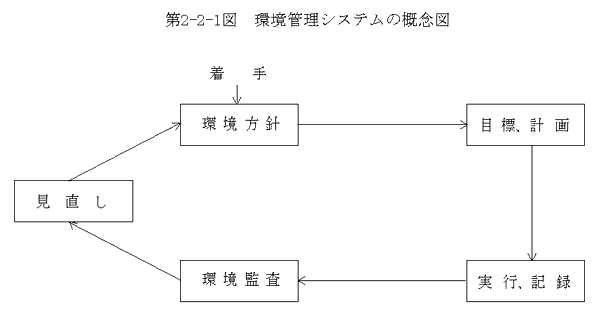
1 環境配慮を内部化する企業活動
(1) 環境管理・環境監査の普及
環境管理とは、企業等の事業組織が、法令等の規制基準を遵守することにとどまらず、自主的、積極的に環境保全のために取る行動を計画・実行・評価することを指し、そのための、?環境保全に関する方針、目標、計画等を定め、?これを実行、記録し、?その実行状況を点検して方針等を見直すという一連の手続きを環境マネジメントシステム(環境管理システム)と呼ぶ。そして、この環境マネジメントシステムの中で自主的な環境管理に関する計画等の実行状況の点検作業を環境監査と呼んでいる(第2-2-1図)。
環境庁では、平成3年以来毎年、「環境にやさしい企業行動調査」を行い、我が国での環境管理、環境監査への取組状況等について調べている。その平成7年度の調査(東京、大阪、名古屋証券取引所1部、2部上場企業2,154社及び従業員数500人以上の非上場企業等4,278社対象。有効回収数及び回収率は、上場企業946社、43.9%、非上場企業等1,826社、42.7%。第2-2-2図)によると、環境管理への取組状況の概要は第2-2-1表のとおりである。また、平成3年以来の上場企業の回答を見ると、回収率の変動があり、直ちに比較するには問題が残るが、経営方針、目標、行動計画、監査については第2-2-3図に見るように、策定、実施している企業が着実に増えてきていることがわかる。
以上のように、環境管理、環境監査については、全体的に見て上場企業の方が取組が進んできており、非上場企業においても取組が広がりつつあることが示されている。
環境監査は、もともと環境に対する意識が高く、積極的に環境保全に取り組んできた企業が率先して行ってきたものであるが、その背景には、環境法令への違反から生じ得る損害賠償の責任や社会的紛争を回避する対症療法的な対応という考え方から、いかに環境への負荷を低減させるかを念頭に置いた考え方へと変化してきていることや、消費者の環境問題への意識の高まりに応じた環境に配慮した製品やサービスの供給へと重点が移ってきていることが考えられる。
例えば、我が国においては、汚染物質を排出している企業は、著しい公害問題を引き起こしてきた企業がその補償に多大なコストを負担せざるを得なくなっている状況を認識し、また、公害防止施策の強化に対応して、1960年代後半から1970年代にかけて公害防止の努力を行ってきた。こうした企業の取組が進んだために、著しい公害問題は相当に改善されてきた。しかしながら、これらの公害防止努力は、法令や条例が定める規制値や基準を満たすというように、外から与えられた条件をクリアーすることが主目標であり、目標を達成してしまえば、さらに改善していこうというインセンティヴは十分働かない。今日の課題である環境への負荷の低減に継続的に取り組んでいくためには、企業の環境保全努力の効果と成果を評価し、その結果に基づいて新しい目標に取り組んでいくという自律的なシステムが必要である。その方法のひとつが環境マネジメントシステムである。
また、企業や消費者の環境保全に対する意識が高まってくると、優れた企業は、自らがどのように環境保全活動に取り組み、どれだけ効果を上げているかを外部に伝えようとし、消費者は、企業がどのような環境保全の努力を行っているかという情報を得ようとする。このように、社会に対して企業が行っている取組を公正に伝えていくためにも、このシステムが大きな役割を果たしている。
欧米の企業では、従来からの社会監査の流れを汲んで、1970年代から環境管理、環境監査についての取組が始められた。イギリスではBS7750と呼ばれる環境マネジメントシステムの規格が1992年(平成4年)に作られ、また欧州連合の制度としてはEMAS(Eco-Managementand Audit Scheme 環境管理・監査スキーム)がある。現在のEMASは1993年(平成5年)7月に発効したもので、企業が環境保全の実績を継続的に改善していくことを目的とし、そのための方策として、環境方針の策定、方針に基づく目標の設定、目標を達成するための計画の策定、目標の達成度の定期的な評価、評価結果の公表を定めている。
また、世界共通の規格等の設定を行う非政府間国際機関であるISO(国際標準化機構)では、1992年(平成4年)9月の理事会における環境管理に関する新しい技術委員会の設立提案を受けて、環境管理に関する技術委員会TC207(TechnicalCommittee 207)を発足させた。現在はこの委員会において、環境管理及び環境監査の国際規格である「ISO14000シリーズ」の1996年(平成8年)の発効に向けた検討が進められている。我が国では、ISOに加盟している日本工業標準調査会(JISC)に、学識経験者、産業界、消費者、労働界、マスコミ、環境関連、規格関連の代表者からなる環境管理規格審議委員会を1993年(平成5年)6月に設立し、このTC207での検討に対応している。また、「ISO14000シリーズ」の発効とほぼ同時期に、国際的に整合性のとれたJISを制定することについて検討している。
我が国の企業のISOによる環境管理及び環境監査の国際規格化への対応については、環境にやさしい企業行動調査によると、「大いに関心があり、ISO規格に基づくシステムの認証を受ける予定でいる」と回答したのは、上場企業で20.8%、非上場企業で12.4%、「ISO規格に基づくシステムを構築する予定ではあるが、認証を受ける予定はない」と回答したのは、上場企業で7.8%、非上場企業で3.0%となっており、回答のあった上場企業のうち30%程度、非上場企業のうち15%程度がISO規格に対応する予定であることがわかる。しかし、一方で「関心はあるが、特別な対応はしていない」と回答したのが上場企業で23.4%、非上場企業で36.9%、「特に関心はない」又は「ISOについてよく知らないのでわからない」と回答したのが上場企業で13.2%、非上場企業で26.1%となっており、現在のところISO規格への対応を予定していない企業も数多く見られる(第2-2-4図)。これを特に環境管理の取組が進んでいると思われる製造業について見ると、認証を受ける予定でいる企業は、上場企業で28.3%、非上場企業で28.7%、システムは構築するが認証は受ける予定はない企業が、上場企業で9.5%、非上場企業で5.8%となっており、やはり製造業においてはISO規格に対する関心が高いことがわかる。
欧州のダウケミカル社は、1991年(平成3年)に、58の特定の化学物質や有害廃棄物等の排出量を1988年(昭和63年)を基準として1995年(平成7年)までに50%削減するという自社目標を掲げた。同社は、この目標を1994年(平成6年)にはほぼ達成し、現在は2000年(平成12年)に向けた新たな削減目標を策定している(第2-2-5図)。また、同社は「環境効率性(Eco-efficiency)」の考え方を基に5つの視点を設け、持続可能な開発の実現に向けた取組を行っている。5つの視点には、?製品のライフサイクル全体における原材料、廃棄物の徹底した削減(MaterialIntensity)、?ライフサイクル全体を通してのエネルギー使用量の徹底した削減及び高エネルギー効率製品の使用促進(EnergyIntensity)、?環境、健康、安全面での品質改善(Environment Quality andHealth)、?再生資源の利用やリサイクルの可能性を考慮する資源保全(Resource Conservation)、?耐久性や有用性を高めることにより複数の環境改善効果を持つような機能の改善(FunctionalityImprovement)を挙げている。そして、それぞれの視点に基づき、製品を船積みする際の積み荷を覆うフィルムの量の削減、断熱材の供給によるエネルギー効率の高い住宅設計への寄与、フロンを使わない工程での発泡スチロールの生産、欧州自動車メーカーとの提携によるクーラー冷媒のリサイクルシステムの構築、電子機器等に利用される放熱効果に優れた窒化アルミニウムの開発等を実現している。また、米国のデュポン社でも同様に自社の環境に関する目標を設定し、その達成に向けた取組を行っている。デュポン社は、例えば、1987年(昭和62年)の排出量を基準として2000年(平成12年)までに有害物質の大気中への排出を60%削減し、発ガン物質の大気中への排出を90%削減するという目標を設定した。この目標は、1993年(平成5年)に有害物質については達成され、発ガン物質についても90%達成されている。両社ともこうした環境に関する目標やその達成状況については毎年環境報告書を作成し、公表している。
(2) 環境投資・環境経費の把握
企業が環境への配慮を事業活動に組み込んでいく上では、環境保全に係る投資や経費を把握していくことが、効果的かつ効率的に環境保全を行うために有益であると考えられる。国際的には、国連の「国際会計・報告基準専門家政府間作業部会」において、1989年(平成元年)から環境に係る財務情報の把握に関して検討が行われている。
我が国においては、環境保全に係る投資や経費の把握について標準的な手法は確立されておらず、一定の基準もまだないものの、一部の企業では、予算や決算処理の段階で環境保全に係る投資や経費を一般の投資や経費と区別して集計している。環境にやさしい企業行動調査によると、上場企業においては、予算又は決算段階で、環境保全に係る投資のみを区別して集計している企業が94社、9.9%(平成6年度は95社、10.5%)、経費のみを区別して集計している企業が49社、5.2%(平成6年度は70社、7.7%)、投資及び経費ともに区別して集計している企業が147社15.5%(平成6年度は146社、16.1%)となっている。また、予算と決算とを比べると、予算において環境に係る投資や経費を把握している企業の方が多くなっている。
集計している内容は、投資については、「生産設備の末端等において、汚染物質などを処理することを目的とした機械設備(公害防止設備)の設置のための投資額(土地代も含む)」(59.8%)、「公害防止設備の改良のための投資額」(59.2%)、「事業所内及び周辺の緑化、美化、景観等の環境改善対策の投資額」(52.5%)の割合が他と比べて高く、経費については、「廃棄物や公害防止設備から出る汚泥等の処理を請負業者に委託する経費」(64.2%)、「公害防止設備の維持、修理等のメンテナンス係る経費」(51.6%)の割合が高かった。こうした投資額や経費を把握することは、自主的な環境管理における目標の達成に向けた取組や規制強化等による環境対策の実施に伴う支出額の管理、自社の環境に関する情報提供に役立つと考えられる。しかし、一方では、集計の際の問題点として、環境保全投資、環境保全経費の定義や範囲が不明確であること、現在の方法では特別な投資額や経費の集計が不可能であることなどが挙げられており、環境に関する財務状況を把握することができる新しいシステムが必要とされていることがわかる。
また、同じく環境にやさしい企業行動調査で、我が国の企業が持っている投資に対する考え方について見ると、上場企業が環境保全に係る投資を決定する際の考え方として第1位に挙げたもののうち最も多かった回答は、「規制等に応じて環境対策の必要性から決定している」(42.6%)であり、次いで多かった回答は、「環境負荷の削減効果だけでなく、原材料削減、廃棄物削減等の収益効果も含めたトータルなコストを考慮して決定している」(15.4%)であった。これによれば、まだ環境対策を受け身で行っている企業が多いものの、環境投資を経営戦略のなかで積極的に位置づけている企業も現れ始めていることがわかる(第2-2-6図)。