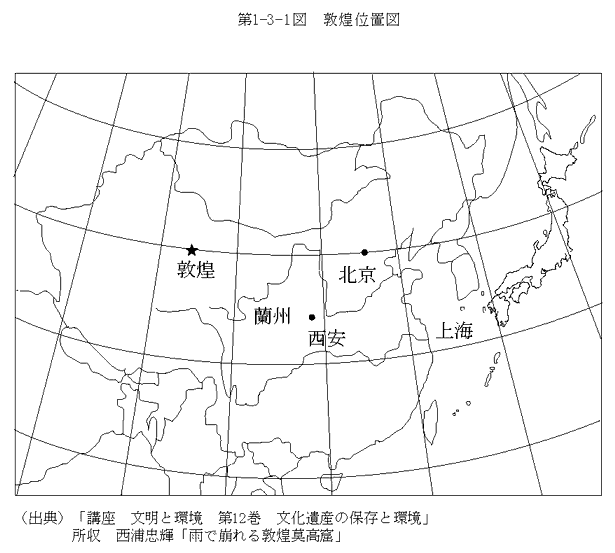
2 環境への負荷がもたらす芸術・文化への影響
今日、人類の様々な活動に起因する自然環境の破壊の程度は、自然の有する自浄能力・再生能力を越えている。人類は、自らを取り巻く自然環境を破壊することによって、一生物としての存在そのものを危機的な状況に陥れ、また、これまで築き上げてきた文化遺産・芸術作品を多数破壊、損傷するに至っている。その具体的な事例を見てみよう。
ア 地球温暖化の進行により深刻な影響が懸念される文化遺産
中国の敦煌莫考Aは世界を代表する仏教芸術の宝庫であり、人類の貴重な文化遺産として世界的に広く知られている(第1-3-1図、第1-3-2図)
。敦煌はタクラマカン砂漠の東端に位置し、莫高窟は敦煌の南東にある。切り立った岸壁に南北1.6?にわたって石窟が掘られ、その数は約500を数える。石窟の内部には5世紀から14世紀にかけて描かれた壁画が余すところなくひしめき、彩塑像も多く存在する。これらの壁画や彩塑像は長い年月の間に自然及び人為的な劣化を受けており、その保存対策が緊急の課題となっている。
東京国立文化財研究所は、1986(昭和61)年に敦煌文化財の保存修復に関して調査研究を始め、翌1987(昭和62)年からは、中国敦煌研究院と莫高窟の壁画、彩塑像の保存、修復についての共同研究を進めてきている。自然状態での劣化としては、彩色層のひび割れや剥落、壁面の浸食や洞窟の埋没、さらには塩類晶出による彩色の剥落や、経年による顔料の変退色などが挙げられる。共同研究の結果、こうした劣化の主原因は水であることが明らかになりつつある。敦煌莫考Aは砂漠地帯の極めて乾燥した環境下にあり、年間の平均降雨量は30?程度に過ぎないが、このわずかな雨水が世界の貴重な文化遺産を傷めているのである。
このことは、長期的に見た気象環境の変動は、莫高窟の保存と極めて密接な関係にあることと示すものと考えられる。このことを以下で見てみよう。
我が国における過去2000年の気候変動を、各古文書資料と湖底堆積物から復元し、中国との対比を行った調査結果を見ると(第1-3-3図)、我が国と中国の変動傾向は類似しており、紀元後400年から600年頃までの寒冷期の後、600年頃から1000年頃までは、中国では温暖期となっており、この時期は莫高窟での壁画制作の最盛期(唐代)に当たる。また、当時は現在に比較すればやや湿潤な環境のために、植生の回復や水資源の増加があったと推定され、砂丘の形成・移動が停滞し、人的往来にも有利となるなど、復元される古環境はいずれも当時の人間の活動にとっては、現在よりも好条件であったことを示唆している。中国科学院・蘭州氷河凍土研究所が敦煌西部の氷河分析を行い、11世紀から20世紀の気温変化を調査したところ、13世紀から始まった寒冷化は19世紀にピークに達した後、温暖化に転じ、現在、19世紀に比べ、年平均気温で、約1度上昇している。こうした古気候の復元は、敦煌付近の環境が他の地域と比べてやや変動が小さい特徴を示しており、それは遺跡の保存の点でも有利に作用したと考えられる。
このように、敦煌では19世紀までの寒冷・乾燥環境は壁画の保全に良好な条件をもたらしていたと考えられるが、今後の地球温暖化のさらなる進展により100年で1ないし3.5度の気温上昇が予測される(気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の1995年の第2次報告書による。)ことから、降雨量の増加及び集中豪雨の可能性が考えられる。その結果、石窟内への雨水の下方浸透による、急激な壁画破壊の進行が危惧されるとの指摘がある。今後は、こうした長期的な気象環境の変化を想定して、保存対策を講ずるよう努力する必要があろう。
イ 地下水の変化によって影響を受ける文化遺産
ナイル河はエジプトの生命の源泉である。しかし、このナイル河は、例えばアスワン付近において、度々の渇水と氾濫を引き起こし、住民を悩ませてきた。このため、水量を可能な限り平準化してより有効に利用しようと、1970(昭和45)年、アスワン・ハイダムが建設され、これにより、エジプトとスーダンの領内では、ナイル河の水をかんがいに利用することが可能となるとともに河の氾濫がなくなるに至った。しかし、長い歴史を有するナイル河のかんがい農業は氾濫水を利用してきたものであり、土地は毎年の氾濫水により洗浄され、塩性化を避けることができたと言われる。現在、ダムによる水の利用は広範な土地の塩性化を引き起こし、今では、かんがいした土地の35%が塩害に苦しんでいると指摘されている。
このナイル河下流のギザからダハシュールまでの間は、世界文化遺産に指定されているピラミッド地帯である。ギザのピラミッドの傍らには有名なスフィンクスがあるが、現在、このスフィンクスはアスワン・ハイダムによって環境が変化し大きな被害を受けていると指摘されている。ダム建設の結果として、地下水中の塩分濃度が高くなり、それが毛細管現象で上昇し、水分の蒸発によって塩の結晶が生じる。これが岩の割れ目に成長しており、スフィンクスの頭部が落下する危険さえ生まれてきていると指摘されているのである。なお、このダムの建設は、地中海東部沿岸の漁業にも大きな影響を与えているとも指摘されている。
ウ 酸性雨による文化遺産・芸術作品への被害
「ライン川を下り、ケルンの街に向かって吹き下ろす北風は、死の風だ。つんと鼻をつく臭いを交えながら、茶色っぽいもやで空を黒ずませる。古い街の狭い通りを吹き抜け、ゴシック様式の大聖堂の巨大な尖塔を取り囲む。600年前の芸術家の手が彫り、磨いた繊細な石の透かし彫りの表面のすみずみまで吹き渡る。腐食性をはらんだ風の幕は、最も神聖な信仰の象徴も容赦しない。天使たちは羽をもがれ、預言者たちは重い病にかかっているようだ。この建築遺産を守ろうという必死の努力にもかかわらず、その美しい顔は死に至る病に永遠に傷つき、同じ病が地球上に伝染病のように拡がっている。パンテオンの大理石やノートルダム寺院の壁などはぼろぼろになった。自由の女神は大がかりな補修工事が必要になり、リンカーン記念館は修復不能なまでに損傷を受けている。」
出典)ルイーズ・B・ヤング「地球の報復 大気に映る環境破壊」時事通信社
上の引用にあるように、酸性雨によって数多くの芸術作品が被害を受けている。有名なケルン大聖堂の被害は酸性雨によるそれの代表的なものであり、正面入口は天使やマリアの石像が取り巻いているが、その顔や体は無残に崩れて原形をとどめおらず、腐食してしまっていると報告されている。
また、こうしたもののうち、破壊が最も顕著に示されているものの一つとして、ルール地方にあるヘールテン城壁の石像が挙げられる。この他、英国におけるウェストミンスター寺院やセント・ポール大聖堂なども被害を受け、また、フランスにおけるランス大聖堂では美術史上名高い「ランスの微笑み」の石像が酸性雨で溶けて顔の形がわからなくなっているとされている。シャルトル大聖堂の「シャルトルの青」として美術史上著名なステンドグラスも酸性雨によって退色が確実に進行し、また、ギリシアにおいてもヨーロッパ芸術文化の源とされるアテネのアクロポリスの丘のパルテノン神殿やエレクティオン神殿のカリアティードは鼻が欠け衣のひだが見えなくなるほどに腐食しているとされる。イタリアでは、ローマのカピトリーノの丘のマルクス・アウレリウスの青銅の騎馬像も、酸性雨によって全身に凸凹ができ、1981(昭和56)年に馬から切り離されて大修理を受けている。
このように、酸性雨の被害は、報告されているだけでも、極めて貴重な芸術作品の多くに及んでしまっている。
また、我が国でも、文化庁において、金銅仏や燈篭などについて、酸性雨による影響に関する調査が進められているところである。
以上のように、我々は、自らが引き起こした地球環境問題等によって、先人の残した貴重な文化遺産や芸術作品を失おうとしているのである。
一方、環境に働きかける芸術活動の中には、自然破壊・環境破壊をもたらす活動があるという指摘もあり、こうした観点からも自然環境と芸術とのかかわりについて考察することは意義があろう。