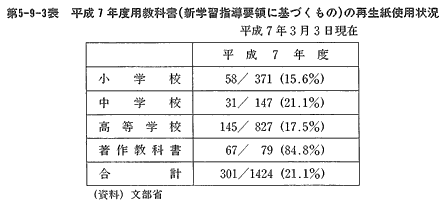
3 環境教育・環境学習等の現状
(1) 学校教育における環境学習
学校教育においては、各教科、道徳、特別活動などを通じた学校教育全体の中で、相互の連携を図りながら、環境に関する学習が行われている。例えば、社会科において身近なゴミの問題について調べ、その調査結果を発表したり、理科において地域の河川等の水質調査を行うなど各学校では身近な地域の環境問題の大切さを学ぶ学習など各種の取組が進められている。文部省においても、これらの取組を支援し、環境教育の一層の振興を図るため環境教育指導資料の作成等の施策を実施している。
また、再生紙を用いた教科書の使用等が進められることは、児童・生徒のリサイクルへの理解を深める契機となることから有意義なことであり、平成7年度度用教科書の口絵、裏表紙等への再生紙の利用状況は21.1%である(第5-9-3表)。
(2) 社会教育その他多様な場における環境教育・環境学習
ア 学習拠点の整備
通常の事業活動や日常生活に起因する今日の環境問題の解決のためには、経済社会を構成する各主体による自主的、積極的な取組が不可欠となっている。これらの取組を推進するためには、行政から住民等に対する一方的な知識や情報の提供にとどまらず、個々の住民等の関心やニーズに応じて、情報提供等を行ったり、あるいは住民等の自主的な学習や実践活動等に対して支援を行うことが重要である。その支援策の重要な柱として、環境学習センター、環境情報コーナーといった環境保全活動促進拠点の整備が各自治体において進められており、これまでに、都道府県レベルで20程度の自治体において整備が実施され、平成6年度には、東京都学習センター等の整備が行われた。
また、自然とのふれあいは、単に自然があるというだけで成り立つものではなく、快適かつ安全な利用の推進のためにはそれらの活動の拠点となるべき施設の整備が不可欠となっている。自然歩道、キャンプ場などの公共的施設の整備に対する国民の期待は高まっている現状にある。すぐれた自然環境を有する国立・国定公園から身近な自然地域にまで及ぶ広い範囲においては、自然観察路、園地、野営場、ビジターセンター、公衆トイレなどの整備が行われており、なかでも、家族が自然とふれあいながら長期滞在でき、環境にやさしい施設を基本としたキャンプ場としてエコロジーキャンプ場の整備を平成5年度より開始している。平成6年度は、新たに磐梯朝日国立公園羽黒地区、富士箱根伊豆国立公園達磨山地区、北長門海岸国定公園須佐湾地区において事業に着手した(第5-9-4表)。
イ 学習機会の提供
最近では自然観察会、星空観察等の体験的学習などが実施されており、環境庁では昭和63年から「全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)」を毎年夏と冬に行い、夜空を観察するという簡単な方法を通じて大気環境保全意識の高揚を図っている。平成6年度夏期の参加は408団体9,948人となっている(第5-9-5表)。また、昭和59年より一般市民の自主的な参加のもと、カゲロウ、サワガニなどの水生生物の調査により水質を判定する全国水生生物調査を実施している。この調査は、小・中・高校生を始め、婦人会等一般市民の自主的な参加により行われており、参加者は年々増加し、平成5年度においては過去最高の3万6,080人であった(第5-9-3図)。
ウ 人材の育成・確保
環境教育・環境学習、環境保全活動、自然とのふれあいを効果的に推進するためには指導的役割を果たす人材の育成・確保が必要である。また、国民等による環境保全のための自主的、積極的取組が進められることが不可欠であるが、これらの取組を支援するため、「環境保全アドバイザー」等の環境保全活動の促進に資する人材の育成・確保が一部の自治体において行われている。国立公園においては、環境庁職員である国立公園管理官(レンジャー)が全国28ヶ所の国立公園に配置されており、現地の管理業務に当たるとともに公園利用者に対する自然解説活動の企画・実施等を行っている。そのほか、国立・国定公園ではボランティアが大勢活躍しており、自然公園指導員は国立・国定公園の保護と適正な使用のための利用者指導や情報提供などを行い、現在約3,000人が、また、パークボランティアは国立公園の自然解説や美化清掃等の業務の補助を行う人々で、現在約1,500人がそれぞれ活躍している。