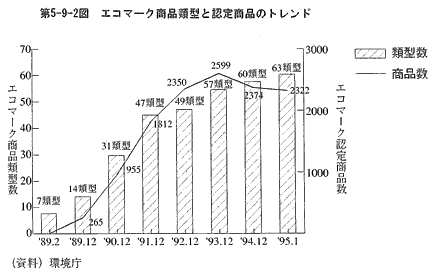
2 環境保全の具体的行動の現状
(1) 自主的な環境管理
事業者は経済活動の中で大きな部分を占めており、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動の見直しのためには事業者の取組が重要である。今日では通常の事業活動に起因する環境への負荷が増大しており、様々な事業活動に際して、公害防止をはじめ環境への負荷の低減を自主的積極的に進めることが必要となっている。このため、事業者において、自主的積極的に環境保全に取り組もうという動きが国内外において高まっている。こうした中で事業者の自主的な環境保全のための重要な取組の一つとして「環境管理」という手法が生まれてきた。
これについて、国内においては、平成3年4月に経済団体連合会が我が国企業が環境問題に取り組む基本理念等を示した「地球環境憲章」を発表、平成4年10月には通産省が「環境に関するボランタリープラン」の作成を所管業界団体に要請し、平成5年2月には環境庁が「環境にやさしい企業行動指針」を公表している(第4章第5節参照)。
また、非政府間機関であるISO(国際標準化機構)においては、環境管理について、1993年(平成5年)から、専門委員会を設け国際標準化の検討を行っている。
(2) 望ましい活動の推奨
エコマーク事業は、エコラベリング事業の一つとして環境への負荷の少ない製品を推奨するためのもので、平成元年2月より開始された。エコマークは、商品類型ごとに定められた環境への配慮項目を満たしているかどうかを、各分野の環境問題の専門家からなる「エコマーク推進委員会」が審査し、認定を受けた商品に付与される。100%古紙使用のトイレットペーパーや太陽熱利用給湯システムなどのエコマーク対象商品は、事業開始以降年々増加基調で推移し、平成7年1月現在で63類型2,322ブランドあるが(第5-9-2図)、商品の中には、ステイオンタブ缶のように一般化したことからエコマークを付ける必要性がなくなり、対象品目から外れたものもある。
平成5年2月に行われた「環境保全に関する世論調査」によると、エコマークを知っていると回答した人が3,754人のうち53.0%、エコマーク商品を購入したことがあると回答した人が17.4%という割合であった。
(3) 民間団体の活動の支援
民間団体の自主的積極的な環境保全活動を支援することを目的として、地球環境基金では数多くの民間団体に対して助成を行っている。平成5年度は、ロシアのバイカル湖における酸性雨調査等の技術指導や各家庭でのエネルギー・CO2排出量の削減運動など254件21億1,900万円の要望に対して104件4億600万円の助成を行った(第5-9-2表)。