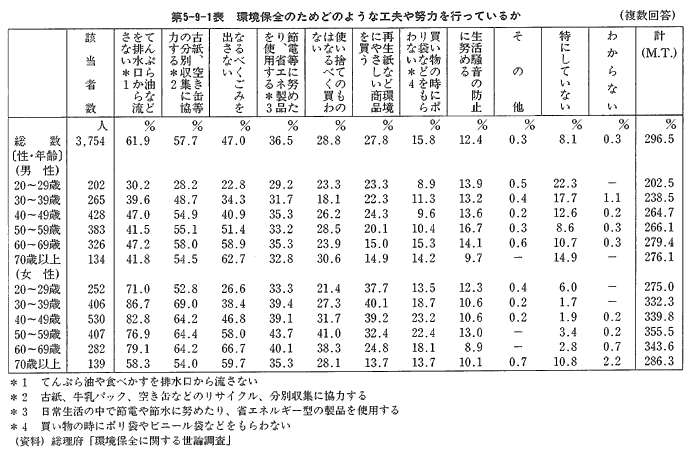
1 環境に関する国民、事業者等の認識と行動の現状
(1) 国民の認識と行動
環境基本計画では、国民には、人間と環境との関わりについての理解を深め、日常生活に起因する環境への負荷の低減や身近な環境をよりよいものにしていくための行動を、自主的積極的に進めることが期待されている。
平成5年2月の総理府による「環境保全に関する世論調査」では、現在関心のある環境問題については、「生活排水、ごみなど生活に起因する問題」を挙げた人が、3,754人のうち64.4%と最も多く、次いで「地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球環境問題」を挙げた人が55.6%となっている。日常生活の地球環境に対する影響についての認識では89.3%の人が「日常生活は地球環境に影響を与えている」と回答しており、今日の環境問題とその原因について正確に把握していることがわかる。また、毎日の暮らしの中で環境保全のためにどのような工夫や努力を行っているかという問いに対しては、「てんぷら油や食べかすを排水口から流さない」と回答した人が最も多く(61.9%)、以下、「古紙、牛乳パック、空き缶などのリサイクル、分別収集に協力する」(57.7%)、「なるべくごみを出さない」(47.0%)の順であった(第5-9-1表)。
また、平成5年4月に大東京火災海上保険が行ったアンケート調査「主婦と『環境問題』」によると、環境問題から連想することは何かという問いに対して1,000人のうち最も多い361人がゴミ問題を挙げており、主婦のゴミ問題に対する関心の高さがうかがえる。
(2) 事業者の認識と行動
事業者は、環境基本計画の中において、様々な事業活動に際して、公害防止をはじめ環境への負荷の低減を自主的積極的に進めること、また、その能力を活かした積極的な環境保全活動、環境保全に関する事業活動(エコビジネス)の発展に向けた積極的な取組が期待されている。
平成6年度に環境庁が行った「環境にやさしい企業行動調査」によると、回答企業906社のうち、環境に関する経営方針を制定している企業は45.7%となっており、今年度中に制定する予定の企業3.2%を含めると約半数を占めている(第4-5-2表)。また、環境に関する経営方針の内容については、環境に関する経営方針を制定していると回答した企業416社のうち「環境問題に関する現状認識と企業の取組方針(理念)」を挙げた企業が91.3%、「事業活動に伴う環境への負荷をできるだけ低減させること」を挙げた企業が80.5%となっている。
実際に企業が事務段階で広く行っている具体的な行動の内容について見ると、「オフィスにおいて省エネ、省資源を実施」が73.7%と一番多く、次いで「廃棄物・古紙等の分別の徹底及びリサイクル」の69.4%、「再生紙や再生品の使用」の67.4%の順になっている。
(3) 民間団体の認識と行動
環境保全に関する活動を行う非営利的な民間団体は、環境基本計画において、公益的視点から組織的に活動を行うことにより、環境保全に大きな役割を果たし、特に、草の根の活動や民間国際協力などにおける活躍が期待されている。
平成4年に環境庁が行った我が国の環境保全団体の状況に関するアンケート調査によると、アンケートに回答した386団体のうち常勤の有給スタッフがいない団体の割合が49.2%、1人から3人の団体の割合が16.6%、4人から9人の団体の割合が14.2%という結果が出ており、国内の環境保全団体は規模の小さいものが多く、しかもその運営の多くはボランティアに任されていることが分かる。また、同調査によると、6割に当たる233団体が、国内の一部の地域で活動している地域型団体となっており、残りのほぼ2割づつを国内全域で活動している全国型団体と国内外で活動している国際型団体が占め、地域型団体の割合が多いことがわかる。活動形態については、団体全体で見ると実践活動や啓発(教育)活動が多く、個別に見ると地域型団体では実践活動の割合が、全国型団体、国際型団体は啓発(教育)活動、調査研究活動の割合が高い。また、主な活動分野については、地域型団体が自然環境・水質汚濁・リサイクル・地域の環境に偏っているのに対し、全国型団体、国際型団体は比較的種々の取組を行っている(第5-9-1図)。