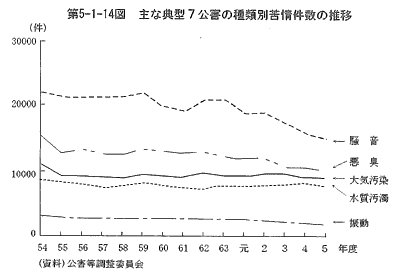
3 騒音・振動・悪臭の現状
騒音・振動・悪臭は、主に人の感覚に関わる問題であるため、生活環境を保全する上での重要な課題となっている。それぞれの苦情件数は全体的に年々減少傾向にあるものの、各種公害苦情件数の中では大きな比重を占めており(第5-1-14図)、発生源も多様化している。
(10) 騒音・振動
騒音は、日常生活に関係の深い問題であり、騒音に係る苦情件数は、地方公共団体に寄せられる各種公害苦情件数の中で最も多く、平成5年度は15,094件で、前年度の15,539件と比べ約2.9%減少した。苦情件数の内訳を見ると、深夜営業・拡声機・家庭生活などのいわゆる近隣騒音に係るものが5,885件と最も多く、次いで工場・事業場の5,347件、建設作業場の2,743件の順となっている。近年の苦情件数の推移を見ると、工場・事業場騒音及び建設作業騒音を含め全体では減少しているが、家庭生活騒音では横ばいとなっている。
騒音については、一般居住環境、自動車交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音のそれぞれに対して、地域の土地利用状況や時間帯に応じて類型分けされた環境基準が定められるとともに、工場・事業場及び建設作業や自動車単体の騒音について規制基準等が定められている。
平成5年度から、道路に面する地域を除いた一般地域における環境騒音の環境基準適合状況について調査を行った。その結果、全測定地点11,205地点のうち7,883地点が適合した。また、定点を決めて、定期的に測定を行っている地点で見ると、8,133地点のうち5,816地点が適合している。
自動車騒音については、朝・昼間・夕・夜間の4時間帯のそれぞれについて住居環境の種類や車線数によって値が定められている環境基準や、都道府県知事が都道府県公安委員会に対し、騒音規制法に基づき所要の措置を要請する際の基準となる要請限度があるが、全国測定地点4,605地点のうち、環境基準を達成できなかった地点(4時間帯のすべて又はいずれかで非達成)は、3,988地点に及んでいる。このうち、要請限度を超過した地点(4時間帯のすべて又はいずれかで超過)は、全国で1,460地点にのぼっている(第5-1-15図)。また、5年継続測定地点1,600地点で見ると環境基準を達成できなかった地点は全国で1,402地点と、引き続き高い水準で推移しており、自動車交通騒音は依然として厳しい状況にある(第5-1-16図)。
今後の自動車騒音対策については、中央環境審議会から、平成7年2月に自動車一台ごとの規制の強化について、また、同年3月に道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の総合的対策について、それぞれ答申が出されたところであり、これらに沿って総合的な対策の推進を図っていくこととしている。
航空機騒音については、低騒音型機材の導入・空港周辺の整備等の対策が行われており、東京・大阪・福岡等の代表的な空港周辺では環境基準制定当時に比べると全般的に改善傾向にある。
新幹線に起因する騒音については、従来からの対策によりかなりの改善が見られるものの、環境基準未達成の地域がかなり多く残されている。こうした地域のうち、東海道・山陽新幹線沿線は住宅密集地が連続する地域等、東北・上越新幹線沿線は住宅が集合する地域等において、75デシベルを超える地域については特に対策が講じられている。また、新幹線以外の在来鉄道においても津軽海峡線や瀬戸大橋線の新線開通に伴って騒音・振動の苦情がよせられ、これらの問題への対策が講じられている。
また最近では、拡声機・カラオケ・ピアノ・ペットの鳴き声・自動車の空ぶかしなどの都市生活等による騒音問題への取組の一環として、地域の好ましい音を含めた音環境を生活環境の一部として捉えるサウンドスケープ的手法を積極的に取り入れた生活騒音防止対策のための新しい取組が国・地方公共団体で始まっている。例えば、東京都の練馬区では環境庁の委託を受け、寺院の鐘の音が区内の中学生にどのように聞かれているかを調査し、「ねりま・鐘の音マップ」を作成した(第5-1-17図)。
振動については、平成5年度における苦情件数は2,083件で前年度比5%の減少であり、ピークであった昭和48年の4,648件の45%程度となっている。発生源別では、依然として建設作業の割合が44%と最も多いが、近年、苦情件数は減少している。また、全体の苦情件数の推移を見ても近年は減少傾向にある。
(11) 悪臭
悪臭は、人に不快感を与えるにおいの原因となる物質が大気中に混じることにより感じられ、騒音・振動と同様、感覚公害であるため、我々の生活に密着した問題である。
悪臭苦情件数は、ピークであった昭和47年から年々減少し、平成5年度は9,978件でピーク時の半分以下となっているが、昭和50年代半ばからは漸減ないし横ばいの傾向にある。(第5-1-18図)。悪臭は、典型7公害に係る苦情件数のうち騒音についで多く、都道府県別に見ると東京都(972件)、愛知県(887件)、大阪府(660件)、埼玉県(535件)、千葉県(523件)の順となっており、この上位5都府県で総苦情件数の3分の1以上を占める。発生源別には、前年度に引き続きサービス業・その他(2,357件)が最も多く、次いで畜産農業(2,143件)、個人住宅・アパート・寮(1,265件)の順となっており、いわゆる都市・生活型に分類される悪臭苦情件数の割合が増加する傾向にある。
こうした状況に対処するため、?複合臭(複数の悪臭物質が相加・相乗されるなどして人の嗅覚に強く感じられる問題)が問題となり現行の悪臭物質ごとの濃度規制基準によっては対応が困難な区域については、これに代えて、人間の嗅覚を活用し悪臭の程度を測定する「臭気指数」を用いた規制基準を導入できることや、?国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関し、国民、地方公共団体及び国が果たすべき役割の規定を設けることを内容とする「悪臭防止法の一部を改正する法律案」を第132回国会に提出したところであり、今後、同法に基づき総合的な悪臭防止対策の推進を図ることとしている。