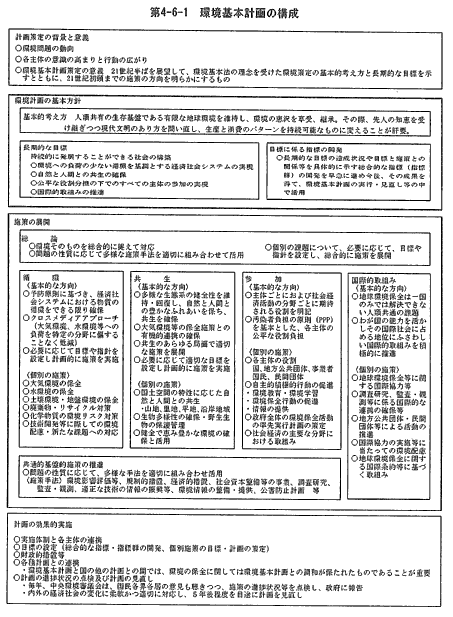
2 環境基本計画の概要と効果の高い対策の推進
(1) 環境基本計画と効果の高い対策の推進
環境基本計画は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定めたものである。この計画は我が国初の閣議決定された国レベルの包括的な環境計画であり、行政のすべての分野にわたって環境保全の考え方を織り込むことによって、トータルな視点で持続的発展が可能な社会を構築するために基本的に重要な要素となりうるものであると考えられる。また、同計画の内容も新たな視点と構成を持ったものとなっており、「効果の高い環境対策の推進」という観点から見て、意義のあるものになっていると思われる。このような観点で環境基本計画を見ていくことにする。
(2) 計画策定の意義
環境基本計画は、平成5年11月に制定された環境基本法の第15条に基づき、内閣総理大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議により決定されるもので、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものであり、昨年12月16日にその初めての計画が閣議決定された。
今回定められた環境基本計画の全体の構成は、計画策定の背景と意義、環境政策の基本方針、施策の展開、計画の効果的実施の4部に分かれている(第4-6-1図)。
第1部は計画策定の意義を扱っている。21世紀半ばまでを展望し、環境政策の長期的な目標を定めた上、21世紀初頭までの国の施策を体系的に定め、地方公共団体、事業者、国民などに期待される取組を明らかにしたものである、との本計画の策定の趣旨を述べている。第2部は、環境政策の基本方針であり、環境政策の基本的な考え方や、これを受けての4つの長期的な目標を定めている。第3部は、施策を定めている箇所であり、同計画の約3分の2の分量を占める部分である。ここでは、4つの長期的な目標に沿って施策を掲げるほか、これらの目標の達成に共通して役立つ施策について一括して定めている。第4部は、計画の実施の仕組みを定めており、具体的には、財政措置や国の各種の計画との関係、計画の進捗状況の点検と計画の見直しなどについて定めている。
計画策定の背景と経緯について定める第1部では、これまでの環境問題の推移を踏まえた上で、今後の経済社会の見通しを踏まえた環境問題の今後の動向についての認識を示し、今後対応すべき環境問題の特質等を整理している。それは第1に、環境問題が、人の健康、生活環境、自然環境といった分野別にとらえるのではなく、環境そのものを総合的にとらえる必要があるということである。第2には、今日の環境問題の多くは、通常の事業活動や日常の生活行動による環境負荷の増大に起因する部分が多く、その解決のためには、経済社会システムのあり方や生活様式を見直していくことが必要であり、そのために、広範な主体による自主的、積極的な環境保全に対する参加が必要だということである。その第3は、今日の環境問題が、地球的規模の空間的広がりと将来世代にもわたる時間的広がりを持ち、人類の共通の課題となっており、このため国際的連携を強化するとともに長期的視野に立った予防的措置が必要であるということである。
このような特質を持った現代の環境問題に対応するためには、従来からの規制を中心とした環境政策の進め方だけでは不十分であり、日常的な事業活動や生活からの環境負荷が社会全体として小さくなるような多様な取り組みを、環境全体としてみて改善がなされるように有機的かつ整合的に進め、社会全体を環境への負荷の少ない持続可能なものにしていく必要がある。このような総合的、体系的取り組みを進めるためには、その全体を見渡した一覧的かつ総合的な指針が定められることが非常に効果的な方法であり、またそれが行政の全分野の責任者の合意として定められることはその実施を効果的に進める上で必要なことである。このような意味で、環境基本計画の策定は新たな時代の環境政策を効果的に進める基礎となる性格を持つものであるといえる。
(3) 環境政策の基本方針
第2部の環境政策の基本方針では、基本的考え方を示した上で、長期的な目標として、人と環境の望ましい関係を明らかにした上で、この計画の4つの長期的な目標を定めている。人と環境の望ましい関係については次のように定めている。「環境は、大気、水、土壤及び生物等の間を物質が循環し、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っている。人類存続の基盤である有限な環境を、健全で恵み豊かなものとして維持して行くには、これらの環境の構成要素が良好な状態に保持され、また、その全体が自然の系として健全に維持されることが必要である。このためには、科学的知見の充実の下に、予見的アプローチを用い、環境への負荷が環境の復元能力を超えて重大な、あるいは取り返しのつかない影響を及ぼすことがないようにするとともに、生産活動等において自然の物質循環を活用しつつ、人間が多様な自然・生物と共に生きることを確保する必要がある。」そして、その上で、以下の4つの長期的な目標を定めている。
その第1は、環境への負荷が自然の物質循環を損なうことから生じる環境の悪化を防止するため、環境への負荷をできる限り少なくし、循環を基調とする経済社会システムを実現することである(以下「循環」という。)。第2は、大気、水、土壤及び多様な生物等と人間の営みとの相互作用により形成される環境の特性に応じて、かけがえのない貴重な自然の保全、二次的自然の維持管理、自然的環境の回復及び野生生物の保護管理など、保護あるいは整備等の形で環境に適切に働きかけ、その賢明な利用を図るとともに、さまざまな自然とのふれあいの場や機会の確保を図るなど自然と人との間に豊かな交流を保つことによって、健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との共生を確保することである(以下「共生」という。)。第3は、以上の「循環」、「共生」の実現のためには、浪費的な使い捨ての生活様式を見直す等日常生活や事業活動における価値観と行動様式を変革し、あらゆる社会経済活動に環境配慮を組み込んでいくことが必要であり、このため、あらゆる主体が、人間と環境の関わりについて理解し、汚染者負担の原則等を踏まえ、環境へ与える負荷、環境から得る恵み及び環境保全に寄与し得る能力等それぞれの立場に応じた公平な役割分担の下に、相互に協力し、連携しながら自主的積極的に取り組み、環境保全に関する行動に参加する社会を実現することである(以下「参加」という。)。第4は、我が国自らが環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を率先して構築するにとどまらず、我が国の経験や技術等、その持てる能力を活かすとともに、我が国の国際社会に占める地位に応じて、地球環境を共有する各国との国際的協調の下に地球環境を良好な状態に保持するため、国のみならず、あらゆる主体が積極的に行動し、国際的取組を推進することである(以下「国際的取組」という。)。
これらによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築することを、同計画は長期的な目標としている。
これらの長期的目標の特色は、従来の環境政策が主として環境の状況について、大気、水などの媒体別に分けるなどした上で、いくつかの項目を選んで目標を設定し、あるいは環境保全のために汚染物質の排出量や、環境悪化防止のための施策の目標を立てていたのに対して、文明のあり方自体にまで遡って社会経済システムや生活様式のあり方を問い直し、より根本的かつ総合的な「循環」、「共生」といった長期的な目標を置いているという点である。これらは、UNCEDの方向に沿ったものである。すなわち、UNCEDは、そこで採択されたアジェンダ21にも現れているように、環境と経済の統合による持続可能な開発の実現を目指したものであり、社会経済全体の問題として環境問題をとらえ、また、社会の各主体の参加や、グローバル・パートナーシップを重要なものとした。また、この認識は、本白書が環境と文明に関して第1章で得た認識とも共通のものである。
このような環境政策の長期的目標を明らかに定めたことは、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に向けて施策を合理的かつ整合的に連携して行い、環境の改善を全体として効果的に進めることに役立つことと考えられる。
しかし、他方、これらの長期的目標はこのままでは定性的なものであることも確かである。環境基本計画について検討を行ってきた中央環境審議会は、昨年7月に検討結果の中間とりまとめを行いこれを広く一般に公開して意見を求めたところ、この点について国民やマスコミ等から疑問が多く寄せられた。目標が具体的、数量的でないため、その達成度合いを評価することが困難ではないか、結局計画の具体的実施が十分に進まないおそれがあるのではないかという趣旨の意見である。このような意見を踏まえて、中央環境審議会において審議の上、答申及び決定された計画では「これらの目標の達成にむけ施策の効果的な実施を図るためには、これらの目標の達成状況や施策との関係等を具体的に示す指標あるいは指標群が定められることが望ましい。」とそれらの意見の趣旨を認めた上で、「こうした指標については内外で調査研究が活発に行われているものの、現時点では、その成果が十分ではなく、本計画に組み入れられる状況にはいたっていない。」という状況であるため、「このため、環境基本計画の長期的な目標に関する総合的な指標の開発を政府において早急に進め、今後、その成果を得て、環境基本計画の実行・見直し等の中で活かしていくものとする。」として、政府が早急に指標の開発を進めるべきこととした。
これらの指標は、広い範囲の経済社会政策を環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとの観点から評価する尺度となるものであり、これが具体化することにより、計画の実効性がより高められ効果的な環境対策の展開に大いに資するものと期待される。なお、国際的にも、総合的な環境指標あるいは持続可能な開発に関する指標の開発が進められており、例えば国連では持続可能な開発についての指標の開発作業が進められており、UNCEDのフォローアップの機関として国連に設置され、1997年に予定されている環境と開発に関する国連特別総会に向けて作業を行っている持続可能な開発委員会(CSD)のハイレベル会合でもその作業の推進を支持することが明言された。また、OECDでも先進国首脳会議での支持を受けつつ、政策決定において用いられる環境指標の開発が進められている。
本計画の策定を受けて、このような指標の開発に向けた予備的な検討が開始されており、平成7年度には政府の関係省庁の参加により本格的に指標の開発が進められる運びとなっている。
(4) 施策の展開−総論
第3部施策の展開では、前述の4つの長期的な目標に沿って、その達成に向けたさまざまな施策を整理し、掲げている。
なお、ここに掲げられる個別の課題に係る目標や指針については、環境基本計画の基本的な方向に沿いつつ、それぞれの枠組みにおいて、それぞれの課題の状況や各種対策の効果等について検討を行い、課題相互の関連や施策相互の関連に配慮しつつ必要に応じてこれを設定し、総合的に施策の展開を図ることが必要であり、かつ効果的であると考えられる。同計画は、個別の課題に係る数量的な目標としては、環境の状況、環境への負荷、個別の施策に係る事業量、主体別の取り組み等に関して、本計画に記述したものなどがあるとした上で、直接には個別の目標を定めず、これらの目標は、個別の法令に基づき、又はそれぞれの決定の枠組みの中で定められるものであるが、今後は、環境基本計画の基本的な方向に沿い、総合的な見地からの所要の検討を行い、必要に応じ見直しを行うとともに、施策の効果的な実施を図る上で必要な分野については、具体的目標を設定し、個別の計画を策定することとする、としている。
(5) 施策の展開ー環境への負荷が少ない循環を基調とする経済社会システムの実現
ここには、環境への負荷が少ない循環を基調とした経済社会を築くための施策について定められている。ここで環境への負荷とは環境基本法にいうとおり「人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの」である。環境負荷という概念は従来から環境政策の主な対象となっていた特定の有害物質の一定量以上の排出行為等を含むことはもちろん、それだけでなく、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるような、ごみを発生させること、有害性のない物質を環境中に排出すること、自然から資源を採取することなどをも含んだ一層広い概念である。
我々の文明は第1章でみたように、持続性に十分配慮することなく環境の利用を急速にかつ加速度的に拡大し、その結果環境に大きな影響を与えてきた。そこにはこの循環の視点が十分でなかったといえるだろう。この循環という目標を社会経済活動や生活のあらゆる場面に織り込んでいくことが、効果の高い環境保全につながるのであり、ここで定められる施策はそのようにとらえられるものである。
同計画では、まず循環を目指す各種施策を進める際の基本となる考え方として、いわゆる予防原則の考え方やクロスメディアアプローチを採るべきことを定めている。これらについては第1節でも触れたが、これらは効果の高い環境対策を進める上の重要な要素である。
同計画では予防原則については、「重大な、あるいは取り返しのつかない破壊のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって環境悪化を予防するための費用対効果の高い手段をとることを延期する理由とすべきではないという考え方に基づいて施策を進める。」と定められている。被害の発生の確実性や、程度、その機序の解明などについて科学的な確実性が十分でない場合であっても、それを理由に対策を遅らせて取り返しのつかない事態を招くべきではなく、むしろ、早期の対策は少ない費用で高い効果が上げられるという観点から積極的に進められるべきであるという考え方に基づいて施策を進めるべきことを定めたものである。UNCEDで採択された環境と開発に関するリオ宣言の第15原則と同趣旨である。
クロスメディアアプローチは、大気、水、土壤といった複数の環境媒体を全体的にとらえて環境負荷を減らす対策を講じるということである。これに関しては「大気環境、水環境、土壤環境等への負荷を、特定の分野に偏することなくできる限り低減させることを目指し、廃棄物・リサイクル対策や化学物質の環境リスク対策、技術開発等に際しての環境配慮、新たな課題への対応等の横断的な施策も含め、各般にわたる施策を実施する。」と定められている。
さらに個別の課題として、同計画では、大気環境、水環境、土壤・地盤環境等の保全、廃棄物・リサイクル対策、化学物質の環境リスク対策、技術開発に際しての環境配慮などについて、今後の方向を明らかにしている。その中で、地球温暖化対策について中期的な取組のあり方を定めるなど、計画策定以前から取り組まれている分野について、これまでの経過を踏まえた上で新たな方針を追加的に定めるなどしているほか、この計画として新たに施策の方針を決定したものがある。
いくつかの主要な例を挙げると、一つは水環境についてである。従来から重視されてきた水質に加え、水量や水生生物、水辺などを含んだ概念である「水環境」を施策の対象とした。その中では自然の機能にも着目し、農林業で利用されている自然についても天然林施業などによる保水力のある森林の造成や管理、地下水涵養能力を有する水田の適切な管理の促進などの施策を位置付けている。廃棄物・リサイクル対策については、「第1に、廃棄物の発生抑制、第2に、使用済み製品の再使用、第3に、回収されたものを原材料として利用するリサイクルを行い、それが技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合、環境保全対策に万全を期しつつ、エネルギーとしての利用を推進する。最後に、発生した廃棄物について適正な処理を行うこととする。」として各種対策の優先順序を明確にしたほか、コストや責任の分担などについても方針を示し、閣議決定レベルで初めての政府の統一的な方針を定めた。また、環境リスクをできる限り定量的に評価し、その総体としての低減を化学物質対策の狙いとして定めた。さらに、「予見的アプローチ」についても「今後、人の活動による環境の負荷により環境が悪化するおそれが生じる場合には、科学的知見の充実の下に、予見的アプローチを用いて、環境への影響を未然に防止するための施策を実施するよう努める。」と定めた。
(6) 施策の展開−自然と人間との共生の確保
共生に係る基本的な方向について同計画は「持続可能な形で環境を賢明に利用することを通じて、地域地域における多様な生態系の健全性を維持・回復するとともに、日常生活、事業活動、余暇活動等の様々な場の中で自然と人間との豊かなふれあいを保ち、自然と人間との共生を確保する。」と定めている。ここでの考え方は、国土の各地域の自然的・社会的特性に応じて、自然的な環境を保全するとともに、賢明な利用、ふれあいを行っていくべきであるということである。つまり、人為的影響の少ない原生的な自然やすぐれた自然を保護するだけではなく、人為の加わった自然も自然の一つのあり方として認めた上で、持続的な形での利用を通じた自然環境の維持など図っていく必要があるということである。
このような趣旨から、例えば農林水産業についても、農地等における生物の生息・生育地の確保、農薬や化学肥料を節減した環境保全型農業の促進、森林・農地等における自然環境維持のための施策などを位置づけている。
農業などの産業活動に環境保全の視点を織り込んでいくことで、産業活動を継続しつつ環境破壊を防止するだけでなく、むしろ環境の保全に積極的にいかしていくことは、環境と開発の統合という理念にかなうとともに、効果の高い環境保全の考え方に沿ったものであるといえる。第1章に見たように、人類の文明はこれまで持続性のない農業によって自らの文明の基盤である環境を損なってきた例をいくつも持っているが、むしろ環境保全的な農業により、環境の保全に寄与することができる面もあるのであり、さらに、林業については、地域の特性に応じた適切な森林の造成及び保育・管理を進めることにより、森林の持つ環境保全能力を発揮させることができるものであり、そのような形で環境と共生していくことが必要なのである。
同計画はまた、健全な生態系の基礎として国際的に重要視され、条約が結ばれるに至った生物の多様性の保全の必要性についても重要なものとしてこれについて定めている。環境の利用を拡大し、地理的にも地球全体に資源を求めている今日の我々の文明は、環境の復元能力を超えた資源採取による資源の減少と生息・生育地の縮少等による野生生物の種の減少等の問題を生じさせ、生物の多様性の確保が大きな課題になるに至っている。「生物の多様性は、人間の生存の基盤となっている自然の生態系を健全に保持し、生物資源の持続的な利用を図っていくための基本的な要素であり、個々の生物種や地域地域における個体群が維持され、全体として生態系が保全されること等により確保される。」(同計画)ものであり、生物の多様性によって豊かで恵みの多い自然の生態系の健全性や持続性が維持されるのである。単に希少種などの保護にとどまることなく、生態系全体を適切に保全するために生物多様性を保持していくことが重要である。
また、同計画では、地域づくり等における健全で恵み豊かな環境の確保とその活用について定めており、親しめる水辺づくり、都市の緑化、自然環境と一体をなしている歴史的環境の保全などについて定めている。都市の緑化等の対策は災害に強い都市づくりの施策と相通じる面も多く、適切な連携によってよりよい街づくりが行える可能性があろう。
(7) 施策の展開−公平な役割分担の下でのすべての主体の参加の実現
ここでは、「循環」、「共生」を実現するために、あらゆる社会経済活動に環境の配慮を組み込んでいくことが必要であるとの観点から、あらゆる主体が公平な役割の下に、相互に協力・連携しながら自主的積極的に参加する社会を実現するための政府の施策のあり方及び各主体に期待される取組について定めている。
参加に係る基本的な考え方として、まず、役割分担の公平性について詳しく論及されている。環境へ与える負荷に応じた分担、環境から得る恵みの程度に応じた分担、環境保全に寄与し得る能力による分担などそれぞれの立場に応じた公平な分担が必要である旨が述べられているが、特に、「今日ではすべての主体が通常の事業活動や日常の生活を通じて直接及び間接に環境への負荷を与えていることを認識し、汚染等による環境利用のコストを価格に織り込むことなどを求めたOECD等の汚染者負担の原則を踏まえ、環境保全のための各種措置の実施費用を汚染者が負担するなど、各主体が責任ある行動をとることが重要である。」としている。汚染者負担の原則は、環境利用のコストを正しく価格に反映させることを通じて、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するためのものである。この原則を踏まえ、環境保全のための各種措置の実施費用を汚染者が負担するなど、各主体が責任ある行動をとることの重要性を強調したことは、経済的効率性を確保しつつ環境保全対策の効果を高めていくとの観点からも意義の深いものである。
さらに、同計画では国の果たすべき役割に加え、地方公共団体、事業者、民間団体が果たすように期待される役割についても記述している。各主体の役割については前節においても論じたところであるが、環境保全対策の効果を高めていくとの観点からも重要であり、同計画でも単に原則的な事項を定めるのみならず、国際標準化機構(ISO)で検討されている環境管理手続きを踏まえつつ、監査等を自主的に進めること、事業者・消費者としての国が環境に優しい行動を率先して採って行くための行動計画を早急に作成すること、公益性の高い活動を行っている環境民間団体が法人格を取得できるような方策を検討すること、融資等の対象企業による環境配慮の実施状況を勘案して融資等を行うことなど社会経済の各分野ごとに各主体に期待される取組を記述している。また、各主体の自主的積極的行動の促進のための環境教育・環境学習などについても閣議決定レベルとして初めて国としての方針を明らかにしている。
これらのうち、事業者・消費者としての政府の率先行動計画については、米国やイギリスなどが先行しているが、我が国でも本年夏までには計画を策定するべく、関係省庁一体となった検討作業が開始された。この計画策定後は、計画に沿って、政府各省庁の物品の調達、営繕工事、庁舎管理などが環境保全型に変わっていくと見込まれる。
(8) 施策の展開−環境保全にかかる共通的基盤的施策の推進
環境政策の政策手段の中には、循環、共生、参加、国際的取組の各目標に共通して重要なものがある。環境基本計画第3部第4章はこのような共通的基盤的施策について定めている。ここでは、「環境影響評価等」、「規制的措置」、「経済的措置」、「社会資本整備等の事業」「調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等」、「環境情報の整備・提供」などについて定められている。
環境影響評価等については、「国等の施策や事業の策定・実施に当たって、あらかじめ環境保全上の配慮を行うことは、総合的な環境保全を図るために極めて重要である。この考え方は国内外において広く認識され、定着してきている。環境影響評価の実施をはじめとして、環境保全上の配慮を一層徹底するため、以下の施策を推進する。」として「国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮」、「公共事業の計画段階等における環境保全上の配慮」、「環境影響評価の実施」、及び「総合的な調査研究等の推進等」について定めており、国民の意見も多数寄せられた環境影響評価制度の今後のあり方については、「関係省庁一体となって調査研究を進め、その結果等を踏まえ、法制化も含め所要の見直しを行う。」と定められた。
規制的手法については、「規制的措置は、環境コストを市場メカニズムの中に適切に織り込む効果もあり、従来からの施策を適正に実施していくとともに、今後とも問題の性格、効果、影響等を勘案しつつ規制的措置を適切に活用する」と定められた。
経済的措置については、通常の事業活動や日常生活を含む広範な社会経済活動に起因する今日の環境問題の発生の大きな要因として、「これらの活動による環境への負荷に伴い社会的に生じる費用についての認識が明確でなく、対策が十分に行われてこなかったことから、これらの費用が市場メカニズムの中に適切に織り込まれていなかったことが挙げられる。」と指摘した上で、「このような問題については、規制的措置、経済的措置などの政策手段を適切に活用し、社会構成員それぞれが環境の保全に適合した行動をとることを促すことが必要である。」との認識を明らかにした。
経済的措置のうち、経済的負担を課す措置については、慎重な議論を要することから、「環境基本計画検討の中間とりまとめ」では、表現が分かりにくく、政府の考えが不明確であるとの批判があった。そこで、最終的に決定された計画では、文章の明確化が図られた。すなわち、「環境への負荷の低減を図るための経済的負担を課す措置は、環境への負荷を生じさせる活動等を行う者に対して現在まで支払われてこなかった新たな負担を求めるものでもある。」との趣旨を明確にし、その上で、「その具体的な措置について判断するため、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活型公害対策、廃棄物の抑制などその適用分野に応じ、これを講じた場合の環境保全上の効果、国民経済に与える影響等につき適切に調査研究を進める。」と定め、さらに廃棄物の発生抑制及びリサイクル促進のための経済的措置に関しても、処理手数料の徴収の推進、預託払い戻し制度(デポジット・リファンド・システム)などの経済的措置の活用の検討などが明記された。
社会資本整備等の事業については、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していくには、・・・環境の保全に関する社会資本整備等の事業を推進することが必要」であり、また、「社会資本整備等の事業に当たっては、その環境に及ぼす影響について計画段階から調査予測等を行い、その結果に基づき十分な環境保全対策等を行うことが必要」であることを明記した。さらに、環境保全上の支障を防止し、またはこれに資する公共的施設の整備等の事業の推進の際には、「これらの事業の環境保全上の効果等について適切な評価を行う。」とし、環境の保全上の効果を高めることを確保するために必要な効果等の評価の必要性も明記した。
調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等については、環境の状況の把握、環境の変化の機構の解明、環境の保全に関する施策の適正な策定等のためにこれらが的確に行われることが不可欠であり、その推進のための諸施策が定められている。
調査研究の推進については、自然科学のみならず、人文、社会の幅広い分野において進めることとし、必要な場合には関係省庁が一体的な取組を行うこととした。また、今後取り組むべき課題をいくつか例示し、環境リスクの解明と評価に関する課題、統合された環境・経済勘定システムの確立等の環境と経済との相互関係に関する課題、環境政策の国際的動向や実施効果の評価等に関する課題、不確実性を伴う環境変化に対応した政策決定の在り方に関する課題、といった、環境政策の効果を総合的に高めていくために必要な新しい観点の課題を明記した。
また、環境情報の整備、提供については、環境保全施策を科学的総合的に推進していくためにその体系的な整備及び利用を図ることが必要であるため、環境情報の体系的な整備、環境情報の国民等への提供、環境解析等システムの整備等、国における基盤の整備について定めている。必要な情報の整備や提供等も、環境保全対策の効果を高めるために必要な要素であり、第4節でも記述したところである。
公害が著しい等の地域における総合的な対策の推進に関しては、「現に公害が著しい地域等の特定地域における公害の防止を図るため、公害防止計画を策定し、一貫性が保たれた施策を総合的かつ計画的に推進する。」と定めれられている。
環境保健対策については、「公害による健康被害については、予防のための措置を講じ、被害者の発生を未然に防止するとともに、被害者に対しては、汚染者負担の原則を踏まえて迅速かつ公正な保護及び健康の確保を推進する」と定められている。
(9) 国際的取組の推進
地球環境問題への我が国としての取組は、以上に紹介した「循環」等を目指す施策の中に組み込まれているので、この章では、それらとの重複を避けて、我が国から外国や国際社会への働きかけなどの対外施策を中心に取組の方針を定めている。
ここでは、まず、地球環境保全が、「一国のみでは解決できない人類共通の課題であり、我が国の能力を活かし、その国際社会に占める地位にふさわしい国際的取組を積極的に推進する。」との基本姿勢を示した上で、地球環境保全等に関する国際協力等の推進、調査研究、監視・観測等に係る国際的な連携の確保等、地方公共団体又は民間団体等による活動の推進、国際協力の実施等に当たっての環境配慮、地球環境保全に関する国際条約等に基づく取組について定めている。
具体的には、自由な貿易と環境保全とが相互に支え合うようにするための方策など国際的な連携が必要な課題についての議論や枠組みづくりに、我が国が積極的に参加、貢献するとの方針、地球環境保全のための資金供給の中心的な仕組みである地球環境ファシリティ(GEF)への積極的な参加、アジア・太平洋地域において率先した役割を果たすこと、我が国の環境ODAの引き続きの拡充・強化、有償資金協力及び無償資金協力の弾力的運用、国際的な役割を果たしていくための国内基盤の整備としての、国、地方公共団体、民間における人材の育成・確保などについて定めている。また、調査研究に当たっての国際的なネットワークづくり、地方公共団体による国際協力の実施や事業者の海外活動に当たっての環境配慮の重要性などについて定めている。
地球環境対策の効果的な実施のためには、国際的な取組が重要であり、また、その対策には国内の環境問題に対する対策と共通する要素がある。したがって、国内的及び国際的取組を連携して、又は一体となって行うことにより国内環境問題及び地球環境問題の両方について対策の効果を高めていくことが必要である。
(10) 計画の効果的実施
環境基本計画の第4部では、大綱的計画である同計画を具体的に効果的に実施するために、実施主体と各主体の連携、目標の設定、財政措置等、各種計画との連携、及び計画の進捗状況の見直し、について定めている。
各主体の取組の必要性及び目標の設定に関しては計画の第3部までに記述されているところであるが、計画の効果的実施という観点から改めてこれについて定めている。また、財政措置等については計画で定められた各種施策の実施を効果的に推進するため必要であるので特にここで「必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める。」と定めている。さらに、各種計画との連携については、環境基本計画が目標とする環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築のためには、他の計画との連携が必要なことから、「環境基本計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画であり環境基本計画と国の他の計画との間では、環境の保全に関しては、環境基本計画との調和が保たれたものであることが重要である。」との原則を定めた上で、「国の他の計画のうち、専ら環境の保全を目的とするものは、環境基本計画の基本的な方向に沿って策定、推進する。また、国のその他の計画であって環境の保全に関する事項を定めるものについては、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるものであり、このため、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図る。」と定めている。
また、最後に、計画の効果的実施のための「計画の進捗状況の点検及び計画の見直し」について、「環境基本計画の着実な実行を確保するため、毎年、中央環境審議会は、国民各界各層の意見も聴きつつ、環境基本計画に基づく施策の進捗状況等を点検し、必要に応じ、その後の政策の方向につき政府に報告する。」と定めるとともに、情勢の変化に応じてより効果的な計画としていくよう、「内外の経済社会の変化に柔軟かつ適切に対応して、環境基本計画の見直しを行うこととし、見直しの時期は、5年後程度を目途とする。」と定めた。
これらに関する具体的な取組として、環境保全に関する行政を総合的に推進することを主たる任務とする環境庁では環境基本計画推進本部を環境基本計画の閣議決定と同日の昨年12月16日に設置し、計画の具体化のための検討を開始した。また、広範な関連政策の整合的な実施には政府部内の連携が重要であり、各省庁に共通する課題などへの対応を検討するため整合的な実施が必要であることから、各省庁に共通する課題などへの対応を検討するため、昨年12月末には、環境庁企画調整局長が主宰し、関係の22省庁の局長クラスの幹部職員が参加する「環境基本計画推進関係省庁連絡会議」が設置された。この会議では政府としての率先実行計画づくりなどが進められている。
また、各省庁連携し、政府一体となった効果的な施策を実施するため、平成7年度の環境庁予算案では、政策調査に要する経費を環境庁に計上し、必要に応じて各省庁に移し替えすることにより、政策の立案段階からの各省庁間の連携を図ることとしている。
また、従来から行われている環境保全経費の見積方針を通じた各省予算の調整についても、経費の整理を環境基本計画に沿ったものに変え、同計画の進行管理に役立てていく手はずが取られた。なお、平成7年度予算案における環境保全経費の額は、約2兆6,000億円であり、国の予算総額の1.6%となっている。
環境保全対策の多くにおいて実施の中心となっている地方公共団体に対しても、本計画は環境保全に関する総合的な計画を策定することへの強い期待を示している。既に昨年11月現在で7つの都道府県・指定都市において環境に関する基本条例が制定され、6団体で総合的な環境計画が策定されている。なお、地方における環境基本計画具体化のための支援措置として、環境庁の平成7年度予算案には、環境基本計画の4つの長期的な目標を実現するべく地方公共団体が新たに行う独自事業のうち先駆的なものなどを対象とする補助金が計上された。