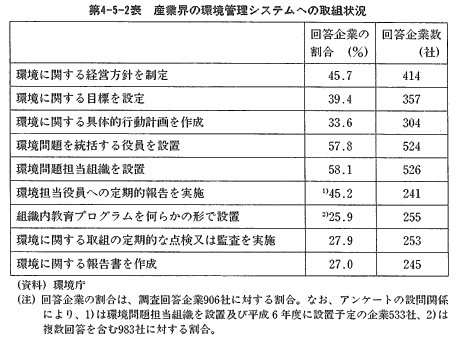
3 産業界、事業者における取組
事業者においては、経済団体や各企業による地球環境保全のための憲章や自主的な環境に関する行動計画の策定、環境保全のための体制の整備、自主的な環境監査の実施、技術移転への取組等自主的積極的行動が進展している。
(1) 環境管理・環境監査における自主的な取組
環境問題に対する世界的な関心の高まりの中で、経済社会の主要な担い手である企業等の事業者においても、法令等の規制基準の遵守にとどまらず、自主的・積極的に環境保全の行動を取ろうとする機運が高まっている。平成6年度に環境庁が実施した「環境にやさしい企業行動調査」(対象は上場企業2,177社、回収数は906社で回収率は41.6%、以下本節では、「環境庁企業行動調査」という)によると、環境管理システムへの取組状況の概要は第4-5-2表のとおりである。
環境管理システム等の国際標準化は、国際標準化機構(ISO)において検討されており、その専門委員会であるTC207では、各国の関心が高い環境管理システム(EMS)及び環境監査(EA)についての検討が行われている。環境管理システムの内容としては、?環境管理に関する方針の作成、?環境に関する目的・計画の作成、?実施・運用(体制整備、従業員の訓練、文書管理等)、?点検・是正(記録、環境管理システムの監査等)、?経営者による環境管理システムの見直しといった組織内の一定の手続きを規定し、システム自体の改善を直接の目的とするものと考えられている。こうした環境管理システム導入の利点としては、環境に対する顧客の期待への対応、公共・社会との良好な関係の維持、責任範囲の限定、投入資材・エネルギーの保全、コスト制御等が挙げられ、積極的な取組を行う企業は、対症療法的な取組を行う企業よりも競争力を高めることができると考えられている。
国際標準化機構(ISO)において検討されている環境管理システムの国際標準化についての企業の今後の対応は、環境庁企業行動調査によると、「関心はあるが特別な対応はしていない」が35.0%と最も多く、次いで「大いに関心があり情報を収集している」の27.2%、「大いに関心があり今後の対応を検討している」の20.2%、「ISOについてよく知らないのでわからない」の15.2%となっている。このうち製造業の26.4%(153社)が今後の対応を検討していると答えている。
我が国では、平成5年6月、ISOに加盟している日本工業標準調査会(JISC)の下に、環境管理規格審議委員会が設置され、ISOにおける規格策定作業への対応、国内規格及び制度のあり方についての検討が積極的に進められている。また、電機・電子関連企業を中心とした日本環境認証機構(JACO)の設立、日本化学工業協会による化学物質の環境・安全を自主管理するレスポンシブル・ケア活動の推進及び日本生活協同組合連合会による取組等の環境管理への自主的取組が始められている。
事業者の環境管理については、環境基本計画で環境保全のための具体的行動として促進される重要な柱として位置付けられており、環境への負荷を低減する手段として、製造業等の一部の業界だけでなく、環境への負荷を生じさせる事業者が幅広く参加でき、一層普及促進される必要がある。環境管理の普及に関しては、平成6年11月に関係省庁連絡会議が設置されたところである。環境庁では、我が国にとって望ましい環境管理の促進・支援方策を検討しているところである。
(2) LCA、環境への負荷の低減に資する製品等の取組
事業者の環境保全に関する取組において、ライフサイクルアセスメント(LCA)と環境ラベルも国際的な標準化についての検討が行われつつある。LCAは、製品等の環境負荷を生産−消費・使用−廃棄という一連のプロセスにおいて定量的、科学的、客観的に把握、評価する手法であり、その活用により環境への負荷の低減を図るものである。LCAの対象となる環境への負荷として、エネルギー消費による二酸化炭素排出、大気汚染物質の排出、水質汚濁物質の排出、資源の消費と廃棄物の排出、さらに、森林の喪失・破壊、騒音、臭気、生態系への影響等が考えられている(第4-5-3図)。
LCA手法の過程は基本的に、?課題の定義、目的、対象の範囲と単位、対象フェイズ等の基本要件の設定(GoalDefinition)、?ライフサイクルの各プロセスでの物質、エネルギーのインプット及びアウトプットの詳細なデータ調査(InventoryAnalysis)、?環境問題との関連からデータを分析し、評価する環境負荷影響評価(Impact Assessment)、?全般的な環境負荷等を改善するための変更点の抽出等を行う環境負荷改善評価(ImprovementAssessment)の4つのステップで構成される。
LCAは、製品開発やシステム開発における環境配慮、さらには企業活動の環境負荷の削減等に際して極めて有効な手法と言うことができるが、LCAの確定的な手法は未だ確立されておらず、LCAの標準化については、国際標準化機構(ISO)において総論的な原則についての検討が進められている。今後の課題として、収集されたデータの質の信頼性を高め、個別に実施されるLCA手法の検証が可能となることが必要である。また、LCAの普及により、我が国のエコマーク事業等の環境ラベルへの導入に期待されるほか、製品の環境品質の向上にも活用されうるとの指摘もなされている。
(3) 企業の環境保全及び環境負荷低減のための具体的取組
平成6年度の環境庁企業行動調査においては、製造業及び電気・ガス供給業(対象593企業)、建設業(同87企業)、流通・サービス、運輸・通信、金融・保険業等(合計226企業)の3つの業種グループの取組と、事務段階及び社会貢献活動等の全業種(906企業)共通の取組についてアンケート調査を実施しており、以下では、この結果を基に企業の環境保全のための具体的取組について見てみることとする。
ア 製造業及び電気・ガス供給業の取組
技術開発・製品(商品)開発段階では、「環境負荷の小さい製品の開発・設計」を行っている企業が51.6%と最も多く、次いで「リサイクル可能な製品の開発・設計」の36.1%、「再生資源を利用した製品の開発・設計」の34.1%などであり、これと比較して、LCA等の製品アセスメントによる製品チェック(14.5%)や製品使用の長期化やモデルチェンジの再検討(16.5%)は、あまり行われていない(第4-5-4図)。
資源採取・原材料購入段階では、「十分な環境対策の下で採取又は製造された原料、中間財の購入」を行っている企業が19.9%であるが、「特に資源採取・原材料購入段階での取組はない」(45.7%)、「不明」(23.6%)など、資源採取・原材料購入段階での取組は進んでいないと考えられる。
製造段階では、「産業廃棄物の減量化」を行っている企業が72.0%と最も多く、次いで「工場緑化及び環境整備」の60.9%、「省エネ・省資源(コージェネレーション、地域冷暖房、サマータイム制等の実施)」の59.7%などと全般的に取組は進んでおり、「汚染物質の出ない(少ない)製造工程への転換」(51.4%)、「廃熱、排水等の回収、再利用」(47.0%)、「原材料の投入量の削減」(34.9%)や「各種製品に使用する部品や材料の少数化」(32.5%)といった環境への負荷の低減に資する取組が始められている。
流通・販売段階では、「包装、梱包の減量化」を行っている企業が48.2%と最も多く、次いで「通い箱の使用」の45.0%、「環境負荷の少ない包装材等の利用」の39.8%などの取組が行われている。
廃棄段階では、「廃棄物管理票(マニュフェスト制)の導入」を行っている企業(53.5%)に次いで「使用済み容器包材の回収、リサイクル」(36.4%)、「使用済み製品の回収、リサイクル」(27.5%)の取組が主に行われている。
イ 建設業の取組
建設業での具体的な取組は、「建設資材及び建設副産物の削減、リサイクル及び適正処理」(72.4%)、「建設廃棄物の減量、リサイクル」(69.0%)等の廃棄物減量化等の取組、「環境に配慮した工法の工夫」(60.9%)、「開発・設計に当たり自然環境や都市環境に極力配慮」(50.6%)等の開発・設計及び工法等での環境配慮のほか、「再生資源の利用促進」(51.7%)や「省エネルギーの推進」(51.7%)、「熱帯材の使用削減、代替」(37.9%)等の取組が行われている(第4-5-5図)。
ウ 流通・サービス、運輸・通信、金融・保険業の取組
まず、流通・サービス業(82企業)では、「再生紙の利用(買い物袋、カタログ、パンフレット、レシート等)」(68.3%)、「包装の減量化(簡易包装、買い物袋持参奨励等)」(57.3%)、「製品及び包装の回収、リサイクル(空き缶、空きびん、トレイ、牛乳パック、乾電池等)」(43.9%)の取組に加え、再生資源を利用した製品(45.1%)、環境への負荷の小さい製品(37.8%)、リサイクル可能な製品(34.1%)の販売等が行われている。運輸・通信業(24企業)では、低公害車の使用や運転方法の工夫(66.7%)、共同化等への多頻度配送、輸送等の見直し(25.0%)等の取組が行われている。金融・保険業(62企業)では、環境保全に資する金融商品の販売(19.4%)、融資又は投資案件に対する環境保全に関する審査の実施(3.2%)の取組が行われている(第4-5-6図)。
エ 事務段階及び社会貢献活動等の本業以外の取組(全業種共通)
「オフィスにおいて省エネ・省資源を実施」が73.7%と最も多く、次いで「廃棄物・古紙等の分別の徹底及びリサイクル」の69.4%、「再生紙や再生品の使用」の67.4%となっており、この上位3項目では全体の約7割の企業が実施している。次いで「地域活動への参加」の42.5%、「エコマーク商品を極力使用」の38.3%などとなっている。また、社会貢献活動については、環境関連基金や団体への支援(22.7%)、環境関連キャンペーンの実施(15.1%)、情報提供としての環境関連講座等の実施(11.1%)等が行われている。
企業内におけるリサイクル・ごみ減量、省エネといった取組が、各事業所にてエコ・オフィスづくりとして進められており、事業所ビルの古紙を共同で回収しリサイクルを促進させることを目的とした企業グループの取組も始められている。また、企業の職場における取組では、従業員や管理職への社内環境教育も行われており、日本労働組合総連合会の環境問題への取組指針に見られるように、環境保全に関する労働組合活動も始められつつある。
これまで見てきたように、製造業、建設業及び流通業等においては、製品等の原料採取、製造、流通、消費及び廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供及び過剰包装の見直し等の取組を進め、再生資源等の環境への負荷の低減に資する原材料等の利用や共同輸配送等合理化された物流サービス等の環境への負荷の低減に資する役務等の利用、さらに、製品が廃棄された後の適正処理等の環境への負荷の低減に協力することなどが必要である。なお、平成6年6月の産業構造審議会地球環境部会の意見具申である「産業環境ビジョン」でも、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的な発展が可能な社会を構築するとの観点から、企業の自主的、積極的な環境問題への取組を促進するため、主要15業種における事業活動の各段階の環境配慮の組込みの方向、再生資源発生産業と受入・利用産業の連携等の業際的な協力による環境負荷低減のための取組の方向等を具体的・体系的に示している。
また、各業種が相互に協力・連携して環境保全の行動を進めるよう努めることも求められるが、環境庁の企業行動調査によると、全企業906企業中12.1%の企業が「取引をする相手方、関連子会社について環境問題がないかの事前チェック」を行い、建設業87企業中40.2%の企業が「施業主への環境配慮に関する働きかけ」を、運輸・通信業24企業中8.3%の企業が「発注元への環境配慮に関する働きかけ」を行っている。
一方、金融は経済活動の中で重要な役割を果たしており、金融機関の主たる業務としての融資業務や投資関連業務は、企業に対する資金供給を通じて企業の投資行動における環境配慮に関し影響を及ぼし得る。融資等の審査対象となる投資には、公害防止投資をはじめ、事業所内や周辺の緑化等の環境改善対策のため投資、原材料・廃棄物の減量化等を目的とし結果的に費用減少が起こるような生産工程の低負荷化のための投資、逆に環境汚染を引き起こすことにつながる生産設備投資など、環境に関連する様々な投資がある。欧米諸国では、金融機関の融資等に関連した環境浄化責任が問われる事例も見られ、金融機関においても環境保全への取組として環境担当組織の設置や環境報告書の作成等の先進的な取組が見られる。我が国の金融機関においても、融資や投資の際に対象企業の行う事業における環境配慮について勘案していくことが期待される。
また、環境に関する情報提供については、環境セミナーや市民講座等による情報の提供を行う企業も少なくなく、金融機関においても、環境についての情報が不足しがちな中小企業等に対して情報を提供し助言者としての役割を果たすことなどの取組が期待されている。平成5年11月に行われた神奈川県の中小企業における環境保全に関する取組の調査によると、環境に配慮した製品・技術の開発、環境保全のための機器・設備の導入及び従来の公害対策を行っている企業は多いが、環境に関する経営方針、目標、担当部署等の環境管理への取組は進んでいない状況にある(第4-5-7図)。
(4) 企業の環境保全支出と情報開示
昨年度の環境白書では、継続的な環境投資が持続可能な経済社会の構築にとって重要な要素となっていることを示した。その環境投資の主要な部分である企業の環境保全投資においても、継続的に実施されることが重要である。
平成6年度の環境庁の企業行動調査によると、環境保全に係る費用負担について、「業績に深刻な影響がなければできるだけ負担したいと思う」と回答した企業が最も多く67.9%、「業績に関わらず負担したいと思う」と回答した企業が8.3%、「現在の諸規制をクリアできるだけの最小限の負担で十分だと思う」と回答した企業が13.1%であった(第4-5-8図)。
次に、環境保全に係る支出の集計状況を見てみると、企業の環境保全に係る投資額や経費について、他の投資額や経費と区別して集計している企業は、「投資額を区別している」企業が全体の10.5%、「経費を区別している」企業が7.7%、「投資額、経費ともに区別している」企業が16.1%で合計34.3%(311社)となっており、昨年度の投資額や費用を集計している企業の29.7%よりやや増加している。環境保全支出の集計に当たっては、支出科目や集計のルールが明確でないとの問題点もあり、アジェンダ21の第30章「産業界の役割の強化」に掲げられている環境コストを会計や価格設定メカニズムに内部化するような考え方や方法論の開発、実施が必要とされるところである。
こうした環境保全支出を積極的に開示し、環境への取組を国民にアピールする動きについては、「各企業に共通の基準を作成した上で、開示を行った方がよい」とする回答が全体の42.3%と最も多く、次いで、「大いに結構であり、日本の企業も開示した方がよい」が26.7%、「同業他社との競争上、開示しない方がよい」は6.5%で、「開示をした方がよい」と前向きにとらえる回答が約7割にのぼっている。さらに、企業が環境に関する取組を公表している状況は第4-5-3表のとおりである。
企業の環境に関する取組については、経営方針、具体的目標、行動計画は公表されつつあるが、その取組に対する点検・監査やその内容を記載した環境報告書及び年次報告書等によって公表することは、一部の先進的な企業の取組に限られていると言える。企業の自主的積極的な取組の開示については、開示の結果、企業を取り巻く各主体によって企業の取組が適正に判断され、自主的な努力が報われるような社会的環境づくりが必要とされ、それによって企業の環境保全に関する取組が一層促進されていくことが期待される。