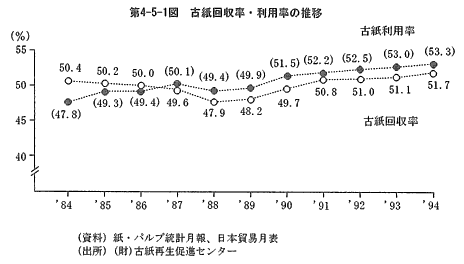
2 消費者、民間団体における取組
消費者、民間団体は、国民に対し、自らの生活に起因する環境への負荷に対する問題意識や、大量消費・大量廃棄型の生活様式の改善の必要性に対する認識が深まっている。そのような認識により、再生紙等環境への負荷の少ない製品やサービスの選択、節電等による省エネルギー、洗剤の適正な使用等の生活排水対策、ごみの減量化、リサイクルのための分別収集への協力等により、日常生活に伴う環境への負荷の低減に対する努力が進められている(第4-5-1図)。
また、地域のリサイクル運動、ナショナルトラスト運動、緑化運動や環境美化活動、身近な水域の保全活動等への参加による地域の環境保全が広まる一方、民間団体の活動への支援を通じた国際的な活動による地球環境保全の取組への参加も進展している。さらに、人間と環境との関わりについての理解を深めるために積極的に自然を体験するなど、自ら学習に努める動きも見られる。自然の仕組み、人間の活動が環境に及ぼす影響、人間と環境の関わり方、その歴史・文化等について幅広く理解が深められるようにするとともに、知識の伝達だけでなく、自然とのふれあいの体験等を通じて自然に対する感性や環境を大切に思う心を育てることが必要とされている。
(1) 環境保全活動への参加の状況
環境について何か行動を起こしてみたい、あるいは既に活動を行っているが更に活動の幅を広げていきたいという意識は、積極的な市民活動の取組を支え、一層活発な取組を促すものと考えられる。平成6年12月の総理府世論調査「消費者問題に関する世論調査」では、消費生活に関して入手したい情報として、「商品の安全性や危険性についての情報(添加物、品質、材質、取扱方法など)」(53.0%)、「商品テストや商品・サービスの比較調査などの情報」(31.7%)などのほか、「リサイクル等の環境保全や環境問題に関する情報」(20.2%)が挙げられている。こうした国民、消費者としての環境保全活動への参加の意識によって広がりつつある取組を以下において見てみることとする。
環境とのふれあいを行う活動は、自分やまわりの人々の生活、人と自然との新しい関係を発見するための街、人、自然を観る活動にはじまり、農村の人々や自然とのふれあいを目的として農村を歩くカントリーウォークやゲームを通して自然や環境について楽しみながら体験し、理解を深めるネイチャーゲーム等が挙げられる。
米国でアメリカ森林財団と西部地域環境教育会議の後援によって進められているPLT(ProjectLearning Tree)は、子供たちに資源保護と環境の状況を理解させ、子供たちが環境について何を考えるかを学ぶのではなく、どうやって考えるかを学ぶための総合的な環境教育教材である。その活動のネットワークは教員、企業、環境行政担当者等にわたり、米国、ブラジル、フィンランド、スウェーデン、カナダ等の国々では、2,000万人以上の小・中学校の生徒がPLTを使用している。我が国においても、PLTが始められつつある。
また、自然に入り山菜や野草を採取するに当たっては乱獲や新芽の保護、その他採取のマナー等自然保護について注意を要することは言うまでもないが、食べるという行動を通じて自然との共生を意識したり、日常の食生活やライフスタイルの見直しを考える活動や、衣食住の必要なものをすべて背負い、自然の中を単独で行動するバックパッキングというアウトドア活動、ドイツで見られるクラインガルテンといった農産物生産を通じて農村の自然とのふれあいを図る市民農園づくりの活動も行われている。
自然観察では、野鳥の生息環境を保護するためのサンクチュアリ活動、山の中の野生動物を観察するアニマルウォッチング、海の中の自然や生物を観察するスノーケリング等が挙げられるが、身近な川や池の汚れを調べる水質調査、全国規模での酸性雨調査、大気汚染等の環境問題を理解することにつながる星空観察等の調査も市民により行われている。
また、自然と人々の営みの結果として現れてくる音を風景の一つとして捉え、音環境について考えるサウンドスケープ(音の風景)の視点に立った活動が行われており、例えば、鳥の声や樹々のざわめき等の自然界の音、人間の話し声やその他の様々な活動の音、そしてその地域における人間の記憶につながるような音に耳を澄ましながら歩き探索すること(サウンドウォーク)も行われている。
地域における活動への参加状況では、使用済みのびんや古着・古布等のリサイクル活動のほか、海・川・街などの散乱ごみを拾うクリーンアップ活動、市民レベルでのビオトープ(生物の生息空間)の保全・復元活動、農山村エコミュージアムづくり、里山の雑木林の保全・管理、清流や美しい川を守るための川の活性化・再生活動、湧水や緑の減少に対する水辺環境保全活動、ホタルの住む環境の保全活動等が挙げられる。また、身近な自然等の買取りや環境保全活動に協力するナショナルトラスト活動も重要な活動の一つである。
平成5年度の環境庁モニターアンケートにおいては、「開発途上国の環境問題に参加してみたい」とした人は49.9%にのぼっており、そのうち協力したいとする内容は、「地球環境基金等の公的基金、制度への協力」が61.3%、「開発途上国の環境改善のための国内のNGOやボランティア活動に協力」が58.2%などとなっている。こうした開発途上国の環境改善のためのNGOやボランティア活動への参加については、世界中の絶滅の危機に瀕する野生生物の保護や開発途上国での自然保護区づくり等の自然保護活動、国内で環境と開発について考える開発教育や自分たちの生活と熱帯林破壊との関わりについて学習する熱帯林保護活動への参加などの活動が行われている。
また、小・中学生からの提案や意見などを集めて、世界各国の首脳や各界のリーダーをはじめとした多くの人々に伝える活動及び、開発途上国でのマングローブ等の植林活動や熱帯林の保護等の活動を行う市民団体についての情報提供や開発途上国NGOとの間の国内外のネットワークづくり等の海外協力活動も行われている。その他の環境関連のネットワークに関しては、情報NGOとしての環境問題専門のパソコン通信ネットワークづくりや環境教育活動のネットワークづくりも行われている。さらに、市民を対象としたシンポジウムの開催、全国各地の市民活動支援、NGOの意見による政策提言等の活動を行う市民団体の取組のほか、サークル活動や学園祭等を通じた大学生によるキャンパスエコロジー活動も各大学で行われ始めている。
(2) 消費者における環境保全活動の取組
我が国では、グリーンコンシューマー活動に関して、商品と企業評価を中心とした買い物ガイドが民間団体により作成されており、各地域で積極的に展開されつつある(第4-5-2図)。これらの活動においては、消費者の買うという受動的な行為は、製造・販売を行う企業に対して積極的に働きかけ、環境に配慮した商品の開発や販売を促進させる能動的な行為へと変わりつつある。こうした消費者の買い物の選択により環境配慮を行っていく活動は、国民自らのライフスタイルを変革させる可能性をもつほか、小売業をはじめとする流通業や製品を生産する製造業に大きな影響を及ぼすものである。例えば、海外では、消費者サイドからの評価の結果、環境対策に積極的な店とそうでない店の売上高に変化が起こった事例があると言われている。
このような消費者の視点からの取組は、消費の面に加え、企業への投資の面からも試みられている。これは、企業の社会的側面を判断基準にして株式・債券投資を行う社会的責任投資の一つで、「グリーン・ポートフォリオ」と市民グループにより呼ばれるもので、企業の環境問題への取組状況により投資先の決定を行うというものである。欧米では、既に投資信託等を通じて社会的責任投資が始められているが、国内での取組は未だ完成されたものではなく、環境問題における情報開示度、取組体制、戦略的計画性、パフォーマンス等の環境面からの企業評価についての新たな試みとして考えられつつある。
さらに、こうした環境保全活動に関連して、ドイツのエコバンクに見られるように、任意組合設立により環境保全に資する融資を行う試みが始められようとしている。また、国際的NGOが民間金融機関の開発途上国向け債権を買い取ることにより、その債務返済の代わりに自然保護のための支出を要請するという債務環境スワップも行われており、開発途上国の環境保全支出額が債権購入のための資金提供額の1.1〜8.4倍(ワールド・デット・テーブルによる1993年12月迄の実績値)となるようなレバレッジ(てこ)効果や開発途上国の債務の削減等の効果を同時に生み出すものとして注目されている。