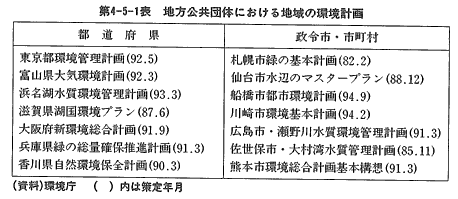
1 地方公共団体における取組
従来より地方公共団体は、公害問題に対処し自然環境の保全に取り組むなど重要な役割を果たしてきたが、近年、環境問題の広がりに対応し、持続可能な社会づくりを目的とした地域環境保全の役割が期待されている。このため、地域の自然的社会的条件に応じて、取組の目標・方向等の設定・提示、各種制度の設定や社会資本整備等の基盤づくり、各主体の行動の促進など、国に準じた施策やその他の独自の施策を自主的積極的に策定し、国、事業者、住民等と協力・連携しつつ、多様な施策を地域において総合的に展開することが期待されている。
(1) 環境基本条例等の制定と地域の環境計画の推進
地方公共団体においては、地球環境や自然環境等の環境を広くとらえその総合的な保全を図る立場から、環境基本条例の制定や検討の動きが見られる。例えば、平成6年7月には東京都が「環境基本条例」を、また、7年3月には三重県が「環境基本条例」を制定している。これらの条例は公害防止や従来の条例で規定していた環境保全に加え、積極的に快適環境を創造することを目指し、かつ地球環境保全に関しては行政の方針や役割を明示し、講ずべき施策や行動指針を明らかにしようとしたものである。また、その推進に当たり、「環境総合計画」や「環境保全基本計画」の策定も掲げている。
我が国の環境行政の一つの特色は、地域レベルにおける地域特性や対象分野に応じた各種の地域の環境計画の策定とその推進であるが、地域の環境問題から地球的規模にまで広がった今日の環境問題の中で、横断的な関連施策を総合的・計画的に推進、強化していくための新たな環境計画が策定されつつある。これまで地域の環境計画は、地域の環境の状況、社会経済の状況、行政と住民との関係等の地域の実状に応じ策定され、計画を必要とする背景や目的によって様々な形態の計画が策定されてきた(第4-5-1表)。
地域の環境計画が対象とする環境の範囲は、当初、典型7公害と自然環境が主であったが、徐々に風害、電波障害、日照阻害等の生活環境や景観、ランドマーク、歴史文化資源等にも及び、さらに、近年は、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染、熱帯林等の森林の減少、野生生物の種の減少等の地球環境問題や、廃棄物、ヒートアイランド現象、都市における水及びエネルギー等の循環、多種多様な化学物質などの問題へと広がりが見られる。
(2) ローカルアジェンダ21の策定
地方公共団体の中には、近年、ローカルアジェンダ21を策定するところも現れている。ローカルアジェンダ21は、平成4年(1992年)に開催された環境と開発に関する国連会議(UNCED)で採択されたアジェンダ21で提唱されたものであり、我が国では、5年2月に神奈川県で「アジェンダ21かながわ」が策定されたのを始め、都道府県を中心に策定が進められている。また、市区町村においても、6年3月に東京都板橋区が「アジェンダ21いたばし」を策定するなどの取組が進みつつある。
ローカルアジェンダ21は、アジェンダ21が目指す持続可能な開発(Sustainable Development)の実現に向けた地方公共団体の行動計画として策定されるものである。地球的な規模で発生する環境問題であっても、その原因や解決策は一人ひとりの生活に直結するものであり、持続的発展が可能な社会の実現に当たっては、地方公共団体での地域に根ざした取組が重要との認識が国際的に認められている。このため、我が国の地方公共団体、とりわけ市民により密接な関係を有する市区町村において、今後自主的な策定が推進されることが期待される。
(3) 環境保全に関する行動の率先実行
地方公共団体においては、事業者・消費者としての環境保全に関する行動を率先して実行する取組が行われているが、平成6年11月環境庁で行われた348の地方公共団体への調査によると、その取組状況は「エネルギー使用量の抑制、ごみの分別等のその他の行政事務に当たっての環境保全への配慮」が88.5%、「財やサービスの購入・使用に当たっての環境保全への配慮」が85.3%、「建築物の建築、管理等に当たっての環境保全への配慮」が81.6%、「職員に対する環境全般に関する研修等の実施」が60.3%となっている。
こうした地方公共団体の取組として、例えば、全庁的なエコオフィス運動を推進している神奈川県、環境保全の手引書を作成し全職員に徹底を図っている熊本市、公用車のNOx削減・省エネ等の自動車公害対策等を実施している川崎市などの取組が見られる。
(4) 国際環境協力等
環境庁が実施した「地方公共団体による平成5年度の地球環境保全施策等調査」(都道府県、政令指定都市を対象)によれば、国際環境協力分野での施策を実施した地方公共団体は延べ83団体、122件に達しており、前年度の72団体、93件に比べ大幅に増加し、地方公共団体の国際環境協力は年々活発になっている。
地方公共団体が培ってきた環境保全に関する知見を活かした協力や民間団体による草の根レベルの活動や企業による社会貢献活動等の各般の協力を推進し、地球環境保全等に関する国際協力の実効性を向上させることが必要とされている。その中でも、姉妹都市・友好都市、国際的な自治体の協力団体等の枠組みを通じた協力をはじめとする地方公共団体の自主的な取組は国際協力を推進する上で重要となっている。前述の調査によると、アジア地域における環境協力が多く、開発途上国への人材派遣、途上国からの研修受入れ等が行われている。アジア地域以外では、京都市のナイジェリア等への職員派遣や千葉県のブラジルから研修生の受入れが挙げられる。
このように地方公共団体においては、海外諸国の地方公共団体との直接的な連携を模索するようになっており、環境保全分野の国際協力を積極的に展開している。地球環境問題に取り組む地方公共団体のための国際組織である国際環境自治体協議会(ICLEI)には、我が国からも15団体(1994年9月現在)が参加している。
1994年(平成6年)5月、デンマークで採択された「持続可能な社会に向けてのヨーロッパ自治体憲章」では、自治体は社会や国家の基本であり、持続可能な方法による問題解決のための最小単位であることがうたわれており、欧米諸国では、都市や地方公共団体の役割が重視されるようになっている。なお、地方レベルでの税・課徴金等の経済的手法の活用につき、国際的な場において議論が行われるようになってきている。また、開発途上国においても、地方レベルにおける環境対策の重要性を認識する国が増えており、途上国自治体から我が国の地方公共団体に対する環境協力の要請が今後増加していくものと考えられている。