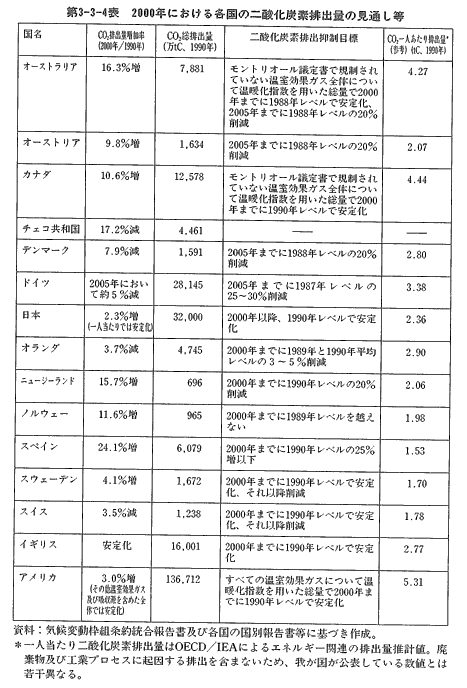
3 地球温暖化対策の効果の将来見通し
(1) 我が国における見通し
以上、地球温暖化が我が国にもたらす環境影響について見てきたが、多方面にわたり深刻な影響が生じることが予想された。我が国においては、地球温暖化防止のため、平成2年に「地球温暖化防止行動計画」を決定し、二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出抑制対策、二酸化炭素吸収源対策、科学的調査研究や普及・啓発、国際協力等、広範な対策を実施している。そして、その対策効果の見通しを気候変動枠組条約の規定に従い、条約暫定事務局へ送付した情報の一環としてまとめている。
まず、二酸化炭素の排出量については、エネルギー需要の動向と密接に関わっていることから、平成6年6月に改訂された「長期エネルギー需給見通し」等を基に予測がなされている。「長期エネルギー需給見通し」では、6年度以降新たに実施される追加的な省エネルギー施策を織り込んだ場合の2000年度(平成12年度)におけるエネルギー需給の政策目標を立てており、各主体による真摯な取組によりこれら追加的施策が十全に実施された場合には、工業プロセス、廃棄物分野における削減分とも合わせ2000年度時点で約3千4百万tC(炭素換算トン)の排出削減が見込まれ、総排出量は約3億3千万tCになると見通される。この結果、一人当たり排出量は約2.6tCとなり、1990年度(平成2年度)実績値(2.59tC)と比べほぼ横這いであることから、「地球温暖化防止行動計画」の二酸化炭素排出に係る目標の第1項(一人当たり二酸化炭素排出量について2000年以降概ね1990年レベルでの安定化を図ること)については達成できる見通しである。他方、総排出量については、1990年度実績(約3億2千万tC)に比べ、炭素換算で若干増加することとなり、行動計画の目標の第2項(革新的技術開発等が早期に大幅に進展することにより、二酸化炭素排出総量が2000年以降概ね1990年レベルで安定化するよう努めること)の達成に向け一層の努力が必要となっている。また、先に見たように、近年の我が国の二酸化炭素排出総量の伸びは鈍化しているものの、平成4年度の我が国の総排出量は、既に2000年度時点での排出見通し値に達している。今後は、平成5年の省エネルギー法の改正等の既存施策、さらには新たに追加される省エネルギー施策等の効果も徐々に現れてくるものと考えられるが、相対的に高い伸びを続ける民生・運輸部門の動向も踏まえ、一層の取組が必要な状況にある。
二酸化炭素吸収源については1990年度に比べ若干増加すると見通される。また、メタン排出量については1990年度値を下回ると見込まれる一方、亜酸化窒素については若干増加すると見通される。
(2) 各国における見通し
1990年に比較した各国の2000年における二酸化炭素排出量の見通し及び各国の温室効果ガス排出抑制目標等について第3-3-4表に示す。
気候変動枠組条約では、先進締約国は二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出量を1990年代終わりまでに従前のレベルに戻すことが重要との認識の下に政策・措置をとり、その内容及びその効果の予測等に関する情報を送付することとされている。各国の予測手法等については前提条件が異なっており、単純に比較できない面もあるが、同条約暫定事務局が作成した統合報告書によると予定している政策・措置をとった場合、2000年時点の二酸化炭素排出量が1990年レベルを下回るとしている国はドイツ(ただし2005年を対象)、オランダ、デンマーク等5か国、1990年レベルと同水準である国がイギリスとなっている。また、アメリカ、日本、スウェーデンについては、約2〜4%程度、その他カナダ、オーストラリア等の国については、約10〜24%超過するとされている。
メタンについては、カナダ、スペインを除く13か国が排出量の予測を行っており、このうち、オーストラリアを除く12か国が1990年レベルを下回るとしている。さらに、亜酸化窒素については、カナダ等を除く11か国が予測を行っており、このうち、ドイツ、イギリス、アメリカ等6か国が1990年レベル以下となる見通しである。
また、これら各国の排出状況と、各国がそれぞれ掲げる温室効果ガス排出抑制目標を照らし合わせると、二酸化炭素等の排出見通しが自国の目標以下としている国は数か国である。ただし、各国の排出抑制目標は多岐にわたっている。
なお、統合報告書によれば、2000年の排出量を1990年レベルに戻すことが困難であるとした締約国の多くが、追加的な温室効果ガス排出抑制のための政策及び措置の立案・実行を検討中であるとしている。
(3) 地球温暖化の心配のいらない未来に向けて
これまで見てきたように、このまま十分な対策を講じなければ、我々の将来世代が地球温暖化による深刻な影響を受ける可能性がある。地球温暖化対策の究極的な目的は、気候変動枠組条約にもあるとおり、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガス濃度を安定化させる」ことであり、IPCCの予測にかんがみれば、この目的の達成のためには、いずれ、世界全体で温室効果ガスの排出量を削減していかなけらばならない。このため、今や、先進国、途上国を問わずすべての国が共通だが差異のある責任の下、可能な限り広範な協力の下で対策を進めていくことが不可欠である。
このような観点からは、まず、先進各国が、現在の条約上の約束の実施に向け最大限の努力を図る必要があるとともに、条約の究極の目的達成に向けた更なる努力を行う中で主導的役割を果たしていかなければならない。
我が国は、このような背景の下で、昨年12月に閣議決定した「環境基本計画」において地球温暖化対策に積極的に取り組んでいく決意を新たにした。同計画では、長期的には気候変動枠組条約の究極の目的を目指し、中期的にはそのための国際的枠組づくりに努力するとともに、国際的な連携の下で一層積極的な対策の実施に努め、当面は地球温暖化防止行動計画に掲げる目標を達成するため、積極的に施策を推進していくことを明確に定めたところである。
また、国際的には、1995年(平成7年)3〜4月、ベルリンで開催された同条約の第1回締約国会議において、条約上の明確な規定のなかった2000年以降の期間の取組を検討するプロセスの開始が決定された。この決定は、2000年以降の取組につき、政策及び措置を定めること並びに2005年、2010年、2020年といった特定の期間内の数量化された抑制及び削減目的を設定すること等をめざし、第3回締約国会議(1997年)で結論を採択すべく、できる限り早期に検討プロセスを開始するもので、この取組には議定書等の採択を通じて約束を強化することも含まれる。
これらを踏まえ、我が国としては、先進国の一員として、今後の国際的枠組みづくりの中で主体的役割を果たすとともに、我々一人ひとりを含む社会の各主体が地球温暖化防止に向けた責務を自覚し、役割を分担することによって、国内での温室効果ガスの排出抑制及び吸収源対策にこれからも最大限の努力を傾注していく必要がある。また、国際的協調を図りつつ、環境協力を積極的に進めることにより、開発途上国を巻き込んだ全地球的な対応を進めていかなければならない。
そして、これらの取組を着実に進めることによって始めて、人類共有の生存基盤である有限な地球環境とともに、我が国の恵み豊かな環境についても将来にわたり引き継いでいくことができるのである。