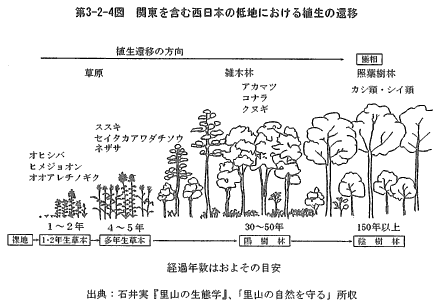
2 人の営みの中で維持されてきた平地、里地の自然
先に見たように、平地自然地域、里地自然地域には人口の99%が居住し、人々の日常的な生活空間となっている地域であり、その自然環境については、むしろ、人間活動の営みの中で、維持されてきたという側面も強い。以下では、そのような例として、いわゆる里山の雑木林と阿蘇等の地域の草原をとり上げるとともに、人間活動との関わりが途絶えてしまった結果、それらの減少や改変が進んでいる状況について見てみよう。
? 雑木林
雑木林を形成するクヌギ・コナラ林などは二次林と呼ばれるもので、ブナ林や照葉樹林といった極相林が伐採等により消滅した後にいくつかの段階の植生遷移を経て生成するものである。第3-2-4図は、関東以西における遷移のパターンの例を示したものである。それによると極相林を伐採した後の伐跡地に、まず侵入するのは種子を広範囲に散布する草本植物である。その後、1、2年生の草本は、多年生の草本にとって代わられ、多年生の草本もコナラやアカマツ等の陽樹林の成長が進むと太陽光を受けることができなくなり、植生遷移が進む。さらに、陽樹林の成長が十分に進み、林床にササや下草が繁茂し、立木の密度が高まり樹冠が閉ざされると、今度は林床に落ちた陽樹林の種子が発芽、成長できなくなり、そのような状況でも成長が可能なシイやカシなどの陰樹(照葉樹)にやがて遷移していく。こうして、自然の状態で放っておけば、最終的に裸地はこれ以上遷移が進まない極相林となる。
里山の雑木林はこの陽樹林の段階で人間が手を加え続けることにより植生遷移を中断することによって歴史的に維持されてきたものである。雑木林は「薪炭林」とも呼ばれるように、薪や炭の供給源として、また、肥料の供給源として、農山村で重要な役割を果たしてきた。里山では、3〜5年おきに柴刈りが行われ、刈り取った柴は燃料として用いられた。また、薪や炭にするためのクヌギ等の立木の伐採は15〜30年を周期として行われたが、毎年少しづつ順番に伐採することにより、自然に再生産が繰り返されるようなサイクルができあがっていた。こうして、毎年一定量の薪炭材を収穫しながら、それが里山の手入れの役割を果たすことにより、極相林への植生遷移が中断され、里山が長い間維持されてきたのである。
また、里山の雑木林は我々に身近な生き物を多く育んできた。例えば、国蝶であるオオムラサキやギフチョウ等の蝶類、カブトムシやクワガタムシなどの甲虫類は雑木林をその生息地としている。また、下草刈りや間伐によってチョウ類の幼虫の餌となる食草や成虫の密源植物の生育が促進され、雑木林の落葉によって作られるたい肥がカブトムシの幼虫の格好の住みかとなるなど、里山の人間活動がこれらの生き物の繁殖を促進させていた側面もある。さらに、手入れの行き届いた里山の明るい林床には春先に野生のツツジやカタクリなどの花も多く見られ、里山は生産の場のみならず、「遊山」の場としての役割も兼ね備えていた。
ギフチョウやカタクリ等これらの雑木林の昆虫や草花の中には、かつての氷期からの遺存種として生物学的に貴重なものも多い。そしてこれらの種の遺存は人間活動による自然への働きかけがあって始めて可能であったとされる。すなわち、一説には、雑木林と人との共生関係は繩文時代中期の焼畑耕作にまで遡れると言われており、焼畑耕作とその後の里山の形成という人間の営為の中で、氷期における自然植生であった落葉広葉樹林が雑木林という形で現在の自然植生である照葉樹林への植生遷移を免れ今日まで存続してきたとされ、その生物要素たるギフチョウ等についても遺存し得たと考えられている。
以上のように、かつての里山では、人間の自然への積極的な働きかけを通じて、そこに生息する生き物も含めて人と自然との間に持続的な共生関係が育まれ、里山全体として、人間活動もその輪の中に組み込んだ生態系循環が成り立っていたのである。
ところが、昭和30年頃から燃料が薪炭から石炭、さらには石油やガスへとエネルギーの転換が進み、さらに農業肥料もそれまで里山から供給されてきたたい肥から化学肥料へと変化すると、薪炭材や落ち葉の供給源としての里山はその経済的価値を急速に失い、農業と里山はほぼ完全に切り離されることとなった。人間活動とのつながりが途絶えた里山では、中断していた植生遷移が再開され、鬱蒼と生い茂る照葉樹林等の極相林へと変化していくこととなる。このことは、本来の植生への変化と見ることもできるが、人の手が入らなくなった里山では例えばギフチョウやカタクリなど人間活動と関わりの深い多くの種は存続していくことができない。より問題なのは、経済的有用性を失った里山は「未利用地」として、開発可能地としてしか認識されなくなり、自然の植生に戻る間もなく急速に開発の対象となっていったことである。すなわち都市近郊では里山を切り開いて宅地や工場用地の造成が進められているとともに、樹種的に低質材としかみなされない雑木林は針葉樹への樹種転換が進められ、雑木林の大幅な減少が生じた。このような構図の下に、上でみたような平地、里地の自然の減少と改変が進んでいるのである。
? 阿蘇地域における草原
阿蘇の広大な景観要素であるススキあるいはシバの草原も人と自然との一種の共生関係の下に育まれてきたものであり、我が国の二次草原を代表するものである(第3-2-5図)。阿蘇や九重、霧島山系の火山地帯は、古くから牛馬の山地であり、牛馬の飼育のため、放牧用の草地とともに、冬季の飼料である干し草を得るための採草地が、数百〜千年以上にわたって維持されてきたといわれる。ススキやシバの二次草原は、野焼き、放牧、干草刈りによって発達し維持されており、これらの人為的干渉がなくなれば、草地は本来の自然植生である森林に遷移していく。野焼きは3月中下旬、草原が森林へ遷移するのを防ぐとともに、その年の生産性を高めるために行われる。ススキやネザサ等の牛馬が好んで食べる火に強い地下茎の発達したイネ科の野草を残し、火に弱い灌木類や害虫を除去する働きを持つ。野焼きには防火線づくりなど多くの人手と経験が必要である。4月上旬になると放牧が行われ、冬の間、狭い畜舎にいた牛馬が一斉に草原に放たれる。干し草刈りは9月中旬から10月中旬にかけて行われ、刈り取られた干し草は冬場の牛馬の飼料となる。このようなサイクルを有する人の営みの中で、阿蘇地域の広大な草原が維持されているのであり、それによってオオルリシジミ等の草原性のチョウやヒゴタイ等の草原性の大陸系遺存植物などの貴重な生物の生存が可能となっている。
ところが、火入れを必要としない常緑性の外国産草種の導入による草原の牧野への改変、過疎化や高齢化の進展による人手不足、牛肉の自由化等を背景とする畜産業の低迷など国内外の様々な情勢の変化により、野焼き等を通じて積極的に自然に働きかけてその維持を図っていくことが経済的に見合わなくなってきており、その結果、伝統的な草原景観の維持が困難な状況となっている。
これら雑木林及び草原の例に見られるように、もともと経済的な必要性から維持されてきた自然形態が、同時に地域の身近な自然としての恩恵をも地域住民にもたらしていたようなケースについては、このような自然を現代に引き続き残していくためには、それが「開発可能地」としてではなく、その存在の必要性が何らかの形で経済社会の中に組み込まれていることが必要となろう。