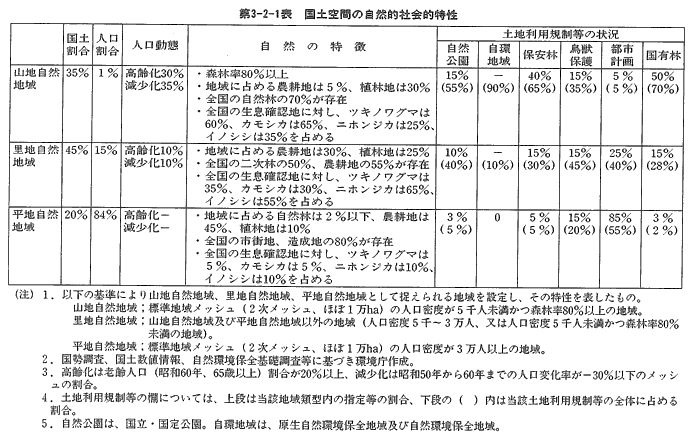
1 平地、里地の自然の特徴と状況
(1) 平地、里地の自然の特徴
環境基本計画においては、我が国の国土空間を自然的社会的特性に応じて山地自然地域、里地自然地域、平地自然地域、沿岸海域の4つに類型化している(第3-2-1表)。同計画では、このうち、里地自然地域を「人口密度が比較的低く、森林率がそれほど高くない地域」、平地自然地域を「人口密度が高く、農耕地等も多く存在し、市街地等の大部分が存在する地域」としてとらえている。
里地自然地域には、全国の農耕地の55%、二次林の50%が存在するなど二次的自然が地域に占める割合が高くなっている。同地域はこれまで、農林水産業等様々な人間の働きかけを通じて環境が形成され、また、野生生物と人間が様々な関わりを持っていた地域で、我々のふるさとの原型として想起されることも多い。山地自然地域ほどではないが、高齢化、人口の減少が進んでおり、地域の活性化が求められている地域でもある。
平地自然地域の特性は高密度な人間活動が行われていることである。社会経済活動の進展に伴い、生活排水等による都市内中小河川をはじめとした水質汚濁や自動車排出ガス等による大気汚染といった都市・生活型の公害の発現を見るなど、日常生活による環境への負荷が集中して起きている地域でもあり、そこに残された緑は、都市気候の緩和、粉塵吸着などの大気浄化、騒音緩和等の諸機能を果たしているほか、身近な生き物とともに我々の生活に潤いを与えてくれる貴重な存在でもある。
平地及び里地自然地域には我が国の人口の99%が生活しており、これらの地域の自然は人間活動との日常的な関わりがより深いものである。
(2) 平地、里地の自然の状況
平地、里地の自然は急速に我々のまわりから姿を消していっている。その様子をまず、山林と対比される平地林の減少に見てみよう。関東地方における山林と平地林を合算した森林面積全体では、統計上、1960年(昭和35年)〜90年(平成2年)の間に5.6%の減少にとどまっている。しかしながら、山林と平地林に分けてみると、山林については、同期間に1.2%減とほぼ横這いの状態が続いているのに対し、平地林については19.7%という大幅な減少となっている(第3-2-2表)。特に、栃木県では33.2%、神奈川県では31.6%、東京都で29.8%と顕著に減少している。同期間の関東地方の一都六県の平地林の減少面積の合計は696km2となり、東京23区を上回る面積の平地林が失われたことになる。この減少を時期的、地域的に見てみると、神奈川県、東京都、埼玉県では1960年(昭和35年)〜70年(45年)の間に大幅な減少が見られるのに対し、千葉県、群馬県、栃木県については、1970年(45年)〜80年(55年)にかけての減少面積の割合が高く、茨城県では、1980年(55年)〜90年(平成2年)の減少割合が最も高くなっており、順次、都心から郊外に開発地域が拡大していった状況がうかがえる。
また、森林面積の減少とともに、森林の断片化が生じている。第3-2-3表は関東地方で今でも比較的雑木林の残っている埼玉県所沢市等の5か所について断片化の状況を見たものである。1960年代初めと1980年代半ばを比べると、単位面積当たりの森林面積の割合及び1個の森林面積の平均が減少しているのに対し、森林の個数及び隣接する森林との平均距離が増大している地域が多く、森林の断片化が進んだことが分かる。第3-2-1図からは所沢における二次林の断片化が進んだ様子を視覚的にとらえることが可能である。雑木林に限らず、生息地の断片化は、生息地面積の減少、他の同種の生息地との連絡の遮断、外部の空間との接触の増大等を通じてその生態系に影響を及ぼす。生息地面積の減少は、オオタカのような多くのえさを必要とする上位の捕食者の生息を不可能にし、生息地の連絡の遮断は他の生息地からの種の補充を困難にすることにより種の消滅の可能性を増す。また、外部空間との接触の増大は本来、雑木林の周辺部にのみ生息する生物や植生の雑木林内部への侵入を招くことにより、生態系の改変をもたらす。
さらに、雑木林等の身近な緑の喪失に伴い、普段なにげなく見られた身近な生き物も姿が見られなくなってきている。例えば、東京都板橋区の調査によれば、カブトムシは昭和30年代までは区内の雑木林を中心に32メッシュで見られたのが、昭和50年代には12メッシュで確認できたのを最後に現在では全く見られなくなっている(第3-2-2図)。
開発から免れている雑木林についても、その荒廃が進んでいる。人の手が入らなくなり、下草などが生い茂るようになった見通しの悪い雑木林は廃棄物の格好の捨て場となっており、不法投棄が進んでいる。不法投棄には、一般の大型ごみのようなものと事業者が産業廃棄物を大規模に投棄する場合の両方が見られる。警察庁の調べによると、検挙で立証された産業廃棄物の総量は平成6年度において約111万トンとなっており、そのうち約6割が山林、原野に投棄されている(各論「環境の状況及び環境の保全に関して講じた施策」第6章第2節3参照)。特に産業廃棄物の場合、有害廃棄物等により周辺一帯に土壤汚染等様々な被害がでることが懸念される。
さらに、地方の農村等における自然や農地についても、高齢化や過疎化の進行により、その管理主体が失われ、持続的な保全・管理が困難な状況となっている。大都市圏への人口、資本、情報の集中や農林業の展望の不透明さ等により、地方の農村地域においては人口の流出、高齢化、農林業等の産業の衰退等の間に悪循環が生じ、その中で耕作放棄地の割合も高まっている(第3-2-3図)。耕作放棄の生態系への影響という点では、例えば水田の場合、耕作放棄に伴い一般に植生が変化し、次第に開水面積が小さくなることにより、カエル、ドジョウ、トンボ(ヤゴ)といった水生生物が生存できなくなり、食物連鎖を通じてそれらを補食する生物の生存も困難となる。
また、高齢化や人口減少の下で、農地や林野を管理する人的、経済的な余裕がなくなっていることから、ゴルフ場等の開発の提案に対し、農地や林野を手放す誘因も高いものとなっている。これらの地域では、いわゆるバブル経済時には、地域振興の観点から大規模リゾート施設の整備が次々に進められ、適切な環境配慮がなされない場合には、自然環境への悪影響が懸念された。現在は、バブルの沈静化で一頃のような具体的な開発圧力自体は弱まっていると考えられるものの、農村地域における過疎化、高齢化、産業の衰退という社会状況に基本的な変化はなく、同地域の自然等に対する潜在的開発圧力は依然として高いものとなっている。