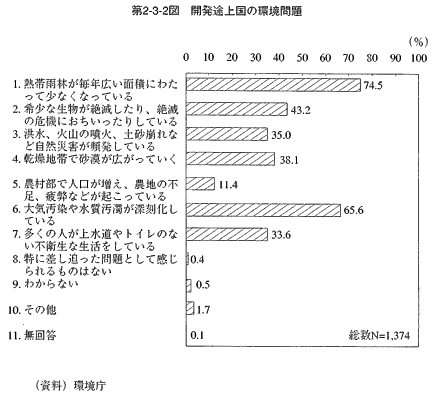
2 我が国のアジア・太平洋地域における環境協力等
開発途上地域、特にアジア・太平洋地域の環境の保全は、我が国と同地域が共同で取り組むべき全人類的な課題であり、人口、資源、開発、環境といった幅広い問題の中で地球的な視野に基づき、世界各国、国際機関等と幅広く国際協力を進めることが必要である。
平成5年度に環境庁で行われた環境モニターアンケート「環境分野の途上国支援について」によると、開発途上国の環境問題の中で対策を早急に取る必要があり差し迫った問題と思うものは、熱帯雨林の減少(74.5%)が最も多く、次いで深刻な大気汚染や水質汚濁(65.6%)、野生生物の絶滅及び絶滅の危機(43.2%)などとなっている(第2-3-2図)。また、日本政府が開発途上国の環境改善に取り組むべきこととして、環境保全技術の移転(64.9%)、環境保全に取り組むNGOやボランティア活動に対しての補助(51.3%)、環境保全に役立つような事業への資金援助(39.8%)、開発途上国の技術者や行政官の日本での研修(38.1%)、国際機関への派遣(37.8%)、国際的な条約や取り決めの締結等に向けての指導的役割(33.0%)などとなっている。
このように国民が我が国の今後の国際的取組について期待することは多く、我が国の能力を活かした積極的な役割を果たすことが求められている。このため、地球環境保全に関する政策の国際的な連携を確保し、開発途上地域の環境への協力を進めるとともに、こうした国際協力の円滑な実施のための国内基盤の整備、調査研究及び監視・観測等における国際的な連携の確保、地方公共団体又は民間団体等の活動の推進、国際協力の実施等に当たっての環境配慮に努めていくことが必要とされている。
(1) ODAによる我が国の環境分野における支援
1987年(昭和62年)、「環境と開発に関する世界委員会」の報告書「われら共有の未来」により打ち出された「持続可能な開発」という概念は、環境と開発は不可分の関係にあり、開発は環境や資源という土台のもとに成り立つものであって、持続的な発展のためには、環境の保全が必要不可欠であるとする考え方である。国民の生活を改善するために開発を必要とする開発途上国においても、開発のみでは将来の世代の発展の基礎となる環境が損なわれること、言い換えれば、環境の保全が今日の世代の生存を支えるだけでなく、将来の世代に対しても永続的にその生存を支えるものとして必要であるとの認識がなされるようになった。
持続可能な開発は、環境保全を直接の目的とした事業を行うことと開発一般において環境を損なわないように配慮することにより実現される。開発援助について見てみると、環境保全のための法令整備、行政機構作り、行政官・技術者の養成、環境監視体制作り、土地利用計画策定、自然保護区・国立公園整備、上下水道整備、公害防止設備整備、廃棄物処理体制作り、土壤侵食防止、植樹等、環境保全を直接の目的とする援助を行うとともに、各種開発のための援助を行う際に、その援助が環境を損なうことにならないかを事前にチェックし、必要に応じ対策を講じることである。以下では、持続可能な開発に向けての我が国の開発援助について見てみることとする。
我が国が環境保全を直接の目的とする政府開発援助、いわゆる環境ODAの考え方を初めて明確に表明したのは、1989年(平成元年)のアルシュ・サミットにおいてである。ここでは、環境ODAの重点分野等を示すとともに、二国間、多国間の環境ODAの金額について、1989年からの3年間で3,000億円を目途として拡充・強化に努力することを表明した。この目標は、3年間で4,075億円を実現して達成された。さらに、1992年(4年)6月、環境と開発に関する国連会議(UNCED)において、我が国は1992年度(平成4年度)より5年間にわたり、環境分野への二国間及び多国間政府開発援助を9,000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化するとした環境ODAに関する目標を表明した。そのフォローアップ状況としては、1992年度(4年度)及び93年度(5年度)の合計で5,083億円の実績を上げ、既に目標額の半分以上を達成している。一方、1993年(平成5年)の我が国のODA(支出純額ベース、東欧向けを含む)は、1兆2,756億円であり、このうち二国間ODAは9,077億円であった。二国間ODAの59.5%に相当する約5,400億円は、アジア地域に向けられたものであり、この中で同地域に対する環境分野の援助も実施されている。
平成4年6月30日に閣議決定された「政府開発援助大綱」では、その基本理念において、環境の保全を先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全人類的な課題と位置づけ、途上国の自助努力に対する支援を通じて地球規模での持続可能な開発が進められるよう努めることとした。また、環境基本法においては、第2章第6節で地球環境保全等に関する国際協力等を推進するため国は必要な措置を講ずるように努めることが規定され、さらに、環境基本計画においては、我が国は環境と開発の両立に向けた開発途上地域の自助努力を支援するとともに、各種の環境保全に関する国際協力を積極的に行うこととしている。
このような環境協力の強化の方針に基づき、我が国は、居住環境、森林保全、公害対策、自然災害防止、自然環境保全等を内容とするODAにより環境分野の途上国支援を積極的に進めている(第2-3-3表)。具体的には、専門家の派遣、研修員の受け入れ、地域の公害対策計画づくり等のための開発調査などの技術協力、無償・有償の資金協力、国際機関への拠出を行っている。
また、我が国は環境問題に対する途上国の対処能力の向上を重視しており、タイ、インドネシア、中国においては、研究、研修、モニタリングを集中的に行う環境センターを無償資金協力により設立し、併せて研修員の受入れや専門家の派遣を組み合わせたプロジェクト方式技術協力を行っている。さらに、環境分野のODAを推進するに当たっては、環境ミッションを始めとする各種調査団の派遣を通じて、開発途上国との政策対話の強化や優良案件の発掘に努めている。
政府開発援助の実施に際しての環境配慮については、政府開発援助大綱の基本理念・原則、更に1989年(平成元年)6月の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」の申し合わせにより、強化を図ることとしている。援助実施機関のうち円借款を担当する海外経済協力基金(OECF)は、1989年(平成元年)10月に「環境配慮のためのOECFガイドライン」を作成し、融資先が適切な環境配慮を行っていることをチェックする等の環境配慮に努めている。また、技術協力を担当する国際協力事業団(JICA)も、1990年(2年)2月の「ダム建設計画に係る環境インパクト調査に関するガイドライン」を始めとして、分野別に順次環境配慮ガイドラインを策定しており、事前調査に際して環境への影響をチェックすることとしている。同時に、いずれの機関も環境担当組織の拡充、調査団への環境専門家の参加等の措置に努めている。
環境基本法においては、引き続きこのような環境配慮の強化が図られることが重要との見地から、第35条第1項で国は国際協力の実施に当たり、その国際協力の実施に関する地域に係る地球環境保全等について配慮するように努めることを規定し、また、環境基本計画においても、国の国際協力の実施等に当たり、引き続き、環境配慮に関するガイドラインを的確に運用するとともに、人材の養成をはじめ環境配慮の実施のための基盤を強化し、国際機関等とも連携しながら、適切かつ効果的な環境配慮を実施することとしている。
(2) アジア・太平洋地域の環境保全に関する取組
アジア・太平洋地域の環境保全の推進に当たっては、地域内の各国、国際機関等と幅広く協力を推進するとともに、様々な議論の場において我が国が率先した役割を果たし、同地域における環境政策の連携を図る必要がある。以下、アジア・太平洋地域において取り組まれている関連施策について、その概要を見てみることとする。
アジア・太平洋環境会議(エコ・アジア)は、持続可能な開発を実現していくためのアジア・太平洋地域の役割と課題、今後の新たな協力のあり方等について共通の理解を深めるため、1991年(平成3年)、1993年(5年)に引き続き1994年(6年)6月に環境庁の主催により開催された。本会議は、アジア・太平洋地域内諸国の環境大臣を含む政府関係者、国際機関関係者、民間団体関係者、学識経験者等が参加し、域内各国政府や関係機関等の長期的な環境保全に係る取組の推進に資することが期待されている。
北東アジア地域の環境協力については、環日本海環境協力会議が平成4年より毎年開催されている。第1回の新潟会議、第2回のソウル会議に引き続き、環境庁は兵庫県との共催により、平成6年9月兵庫県城崎町で第3回環日本海環境協力会議を、中国、ロシア、モンゴル、韓国の参加を得て開催した。第3回会議では、CSDのフォローアップ、持続可能な都市、生物多様性等のテーマについて活発な意見交換がなされ、各分野における協力の強化等について合意がなされた。
ESCAP地域における環境協力については、南アジア、ASEAN、南太平洋地域で1980年(昭和55年)前後に相次いで地域的環境プログラムが作成されたが、北東アジア地域では近年まで地域的取組が行われておらず、同種のプログラムの作成が期待されている。ESCAP/北東アジア地域環境協力会議は、1993年(平成5年)2月に続き、1994年(6年)11月に第2回会議を開催しているが、地域協力が不可欠な越境汚染や地球規模の環境問題について、重要な協力の枠組みを与えるものとなると予想され、また、きめ細かな意見交換等を通じて環境問題に対する国際的理解の共通化を図ることにも資するものと考えられる。また、ESCAPでは、5年毎にアジア太平洋環境大臣会議が開催されており、本年(1995年)11月に開催が予定されている。
また、アジア・太平洋地域における気候変動枠組条約の円滑な実施を支援するため、1995年(平成7年)3月にバンコックにおいて第4回地球温暖化アジア・太平洋地域セミナーが環境庁及び国連アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)の主催で、国連環境計画(UNEP)等の協力を得て開催された。これまで1991年(3年)1月に名古屋市、1993年(5年)3月にバンコック市、1994年(6年)3月に大阪市において開催されており、第4回セミナーでは、?気候変動問題に関する国際的な取組の進捗状況、?各国における取組状況、?アジア・太平洋地域における地球温暖化対策のための地域協力等について議論が行われた。
国連環境計画の主導によりウイーン条約及びモントリオール議定書が採択され、これに基づいたオゾン層破壊物質の排出削減努力が各国でなされている。日本等の先進諸国においては、技術・資金の供与、科学的知見の集積、普及・啓発等における国際貢献が求められており、オゾン層保護に関する様々な分野の学識経験者・関係者等による知見の発表、意見・情報の交換等を行い、オゾン層保護対策の円滑な推進に資することを目的として、平成3年度に中国とタイ、5年度に韓国とインドネシアにてオゾン層保護セミナーが開催された。
アジア・太平洋地域においては、平成4年1月の「日米グローバル・パートナーシップ行動計画」に基づき、日本が分担して地域内の研究協力の枠組−アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)−の構築を推進している。APNは、途上国を含む各国において地球環境研究を推進し、各国の地球環境問題への対処能力を高めるため、政府レベルの協力体制を構築するものであり、現在我が国が暫定事務局を担当している。7年3月に開催されたAPNに関する第3回ワークショップにおいては、APNの対象となる科学的テーマ及び組織・手続き面等についての議論をとりまとめた共同声明が採択され、APNが実施段階に入ったことが宣言された。
海洋環境保全について、国連環境計画(UNEP)は、国際的な閉鎖性水域及びその沿岸海域等の環境保全を図るため、海域を共有する国々に対して共同の行動を取るよう働きかけてきたが、1975年(昭和50年)から現在まで12の地域海計画が策定されている。日本海等を中心とする北西太平洋地域海計画は、1991年(平成3年)よりその策定の検討が行われていたが、1994年(6年)9月に行動計画が中国、日本、韓国及びロシアで採択された。
東アジア地域において着実に酸性雨問題に取り組んでいくための地域共同の取組の第一歩として、酸性雨のモニタリング及びネットワーク化が重要であり、その実現のための地域内協力が必要であるため、環境庁は現在「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱している。各国間での測定データ、情報等の共有、更に酸性雨問題について共通の認識に基づいて対策を着実に実施し、必要な国際協力を推進していくべきであると考えられるため、関係機関等の協力を得て、平成5〜7年度の3年間にわたり専門家会合を開催し、東アジア各国及び関連国際機関の専門家による意見交換、検討を経て、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想を行うことを目指している。
水鳥とその生息地である湿地の保全について、今後の各国間の協力のあり方やそれぞれの国内で取り組むべき活動等を検討し、湿地及び渡り鳥の保全戦略や行動計画を策定することを目的として、東アジアからオーストラリア地域にかけての水鳥の渡りルート沿いの地域の関係国から専門家等の参加を得て、東アジア〜オーストラリア地域湿地・水鳥ワークショップが平成6年11月に釧路市にて開催された。本会議の結果、渡りルート沿いの保護区のネットワークの構築、水鳥保護の行動計画の作成等を内容とする声明が発表された。
アジア・太平洋地域の開発途上国において今後一層深刻化していくことが懸念される産業公害に対し、我が国は、産業公害克服の経験を踏まえ、民間企業等が有する知見を活用しつつ、その経験・技術を広く移転・普及等を行うことが重要である。例えば、グリーンエイドプランでは、環境技術協力、開発途上国との密接な政策対話、人づくり及び研究・調査の協力等を推進し、産業界の専門家を活用し、様々な協力ニーズに的確に対応できる体制の整備を行っている。
(3) 地方公共団体の環境協力
アジア・太平洋地域の急激な都市化、工業化及び人口増加等による環境の状況の悪化に対処するため、これまで国を中心として様々な環境協力が実施されてきているが、途上国からの要請の増大や多様なニーズの中で、我が国の地方公共団体も協力が求められている。
北九州市は友好都市大連市との間で環境協力を積極的に推進し、同市の特色を活かした実務的な友好都市交流として注目されている。1993年(平成5年)12月、北九州市より大連市を環境保護特別区と指定することが中国側に提案され、1994年(6年)初め、中国政府はそれを決定し、同年の国家環境保護重点事業に組み込んでいる。大連環境特別区建設計画は、北九州市の環境水準を目標として掲げており、上下水道及び処理施設の整備、工場移転、規制の強化、監視体制整備、研究開発体制整備などの事業を10年から15年で達成し、その成果を中国全土ひいては周辺開発途上国に広めていくものである。今後、北九州市は、関係機関に協力を要請するとともに、北九州国際技術協力協会(KITA)を始めとする関係者との協力体制を作り、産官学の連携のもとで協力を推進していくこととしている。
また、横浜市では、民間企業と同市の共同の海外技術交流事業を契機とした国際協力活動により、アジア・太平洋地域の地域レベルでのネットワーク構築やITTO(国際熱帯木材機関)への支援等の取組を行っている。1982年(昭和57年)には「アジア太平洋地域における自治体の都市づくりに関する横浜国際会議(第1回アジア太平洋都市会議)」を開催し、アジア・太平洋地域の都市間で技術的なアドバイス、研修・視察等を行う組織「CITYNET」に対する積極的な支援を行うなど、都市間交流ネットワークづくりの活動を推進していくこととしている。また、環境分野における技術職員の海外派遣、環境監視センターの視察や研修員の受入れ、国際的な環境保全活動に取り組む団体への助成、国際環境保全ボランティア登録制度等の国際協力を行っている。
このほか、広島市と四川省重慶市との友好連携による公害防止や森林保護の環境協力事業や、広島県、四川省、広島市、重慶市の4者共同による酸性雨に関する取組が進められている。森林保護事業では、外材輸入量が全国一である広島県が国際的貢献を目的として、緑化技術の専門家派遣、研修生受入れ、植林活動への県民ボランティア参加等が行われ、また、酸性雨の研究では、重慶市環境科学研究所内に「酸性雨研究交流センター」が開設され、酸性雨に関する調査研究等が進められている。
これまで見てきたように、地方公共団体は、地域レベルでの一つ一つの行動の積み重ねとグローバル・パートナーシップに基づく持続可能な社会の担い手として、率先して環境協力に取り組んでいく必要がある。そこで、我が国と地理的・文化的に最も近いアジア地域の地方自治体と我が国自治体との間の環境協力に向けた国際的な取組を推進するため、環境庁ではアジア地域地方自治体環境イニシアティブ推進事業を行っている。中国、インド、インドネシア、フィリピン及びタイの5カ国を海外参加国とし、各国3自治体(蘇州、ボンベイなど合計15自治体)について、環境問題の現状と課題の概要調査及び我が国自治体と各国自治体とのモデル環境改善事業の発掘を行い、具体的な自治体レベルの環境協力の手法の開発などにつなげていくこととしている。
(4) 企業、民間団体における取組
我が国企業は活発に事業の海外展開を図っており、アジア・太平洋地域においても同様に活動を行っている。従来、エビをはじめ木材や鉱石等の輸入や有害廃棄物の輸出を背景として、我が国企業とアジア・太平洋地域の環境問題が指摘されてきた。また、海外進出企業の環境対策では、アジア・太平洋地域においても事業活動に際しての適正な環境配慮が重要であるが、(社)経済団体連合会の地球環境憲章の策定に見られるような産業界の自主的な取組が進められているほか、適切な環境配慮による取組の進展が図られることが求められている。環境庁では、平成6年度において、タイ、インドネシア、マレイシア、フィリピンの在外日系企業について環境配慮活動の動向調査を行っている。
企業のアジア・太平洋地域における環境協力活動については、マレイシアにおける熱帯林保護活動、アジア地域でのオゾン層保護に関する会議開催などの社会貢献活動が行われている。また、アジア・太平洋地域諸国の環境対策において今後環境投資が増加することが予測されることから、我が国企業による公害防止装置をはじめとする環境保全技術移転が行われている。
例えば、米国商務省等の推計によると、台湾の環境市場は1991年(平成3年)で907百万ドルであり、そのうち輸入の占める割合は約68%となっている(第2-3-4表)。インドの公害防止装置市場は、1990年(2年)では400百万ドルでそのうち輸入の占める割合は20%、また、中国の水質汚濁防止に係る支出は1991年(3年)では約433百万ドルで、輸入額50百万ドルのうち日本からの輸入が40%、オーストラリアが25%、米国が8%の割合を占めている。また、韓国では、1991年(3年)の企業の公害防止支出は732百万ドルであるが、韓国エネルギー資源省によると、今後1995年(7年)に大気汚染、1996年(8年)に水質汚濁に対する規制強化により、国内の環境投資は1992年(4年)の12.5億ドルから2000年(12年)の45億ドルに増加すると予測している。こうした環境市場を通じた我が国企業の経済活動は今後一層活発化するものと予想され、アジア・太平洋地域の環境対策に資することが期待される。
民間団体のアジア・太平洋地域での取組について見てみると、アジア・太平洋のNGO代表、研究者等により、1994年(平成6年)11月、アジア・太平洋NGO環境会議が京都で開催され、アジア・太平洋地域各国の環境問題の調査研究活動を協力して行うこととしている。
アジア・太平洋地域諸国との協力の推進や国際協力の重要性の普及啓発において、民間団体の果たしている役割も大きく、多数の団体が環境協力の推進に取り組んでいる。アジア・太平洋地域における環境保全活動において、平成6年度の地球環境基金による助成案件のうちアジア・太平洋地域に関するものは58団体約2億9,500万円となっており、開発途上地域における環境保全活動の国内外の団体数のうち67.4%(助成金額では約68%)を占めている。主に、植林、緑化、自然環境保全、大気汚染及び水質汚濁防止、マングローブ林等の環境保全、環境会議・セミナー等の開催、その他普及啓発などの活動が積極的に行われている。また、地方公共団体の協力を得て、中古の大気汚染測定機を中国、ゴミ収集車をベトナムへ提供し、地域の環境保全に貢献している活動も始められている。
(5) アジア・太平洋地域の持続可能な発展と我が国の役割
アジア・太平洋地域は、21世紀に向けて世界で最も活発な経済活動が展開される見通しにあり、こうした経済活動により、域内各国の相互依存度は高まり、域内の人や物の流れは一層活発化すると予想される。他方、工業化や生活水準の向上によりエネルギー消費量が急激に増大し、硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質や二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量増加とともに、水質汚濁、有害廃棄物による汚染等の環境問題が深刻化することが懸念される。同時に、森林、土壤、淡水資源、生物多様性等の自然環境の悪化も懸念され、環境悪化の影響が、国や地域のみならず、地球環境全体に及ぶことが懸念されている。
こうしたアジア・太平洋地域における環境問題に対し、持続可能な発展は最も重要な視点である。アジア・太平洋地域は、持続可能な発展を達成する上で極めて重要な時期にあり、同地域での環境問題への取組は持続可能な開発の概念が実現可能であるかどうかの試金石となるものと考えられる。国連アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)では、1991年(平成3年)に採択された「アジア太平洋地域における環境上適正で持続可能な開発に向けての地域戦略」や「環境と持続可能な開発委員会」の開催を通じた域内協力の枠組みづくり等を行っており、また、アジア・太平洋経済協力(APEC)では、1994年(6年)3月に環境担当大臣会合が開催され、域内における持続可能な開発実現に向けた環境保護と経済成長の密接な関連性が再認識されている。以下において、アジア・太平洋地域の特性を活かした持続可能な発展を進めるための重要な視点と我が国の役割について見てみることとしたい。
アジア・太平洋地域諸国では、大都市において生活排水等による水質汚濁や自動車排出ガス等による大気汚染が深刻化しており、産業公害が同時並行的に発生している状況にある。また、農村地域では森林減少や土壤流出等の環境問題も起こっている。さらに、近年では、地球温暖化、オゾン層破壊等の地球環境問題への対応も課題となっている。このようなアジア・太平洋地域諸国における環境問題の多様性を十分認識した上で、個別の問題に対してきめ細かな協力を進めるとともに、地球環境問題等も射程に入れた総合的、抜本的な対策のための協力も進めていくことが必要である。
また、アジア・太平洋地域の環境問題を考える場合、その背景にある人口の増加、貧困、都市化、工業化等と統合して問題をとらえる必要があり、また、自然環境の保全を考える際にも、地域住民の生活安定と自然環境基盤の適切な管理といった観点からのアプローチが必要とされる。環境協力に当たっては、各国における真の環境ニーズを的確にとらえ、また、それぞれの国の発展段階に応じた適切な技術のあり方について検討し、これらに対応した協力を推進していくことが重要である。
アジア・太平洋地域諸国は多様な経済発展段階及び産業構造にあり、あらゆる面で相互依存が深まりつつあるが、経済活動に伴う様々な環境への負荷に対しては、経済発展段階や産業構造及び自然環境に応じた適正な責任を分担し合うことが合理的である。特に、酸性雨や海洋汚染など国境を越えた環境問題への取組や開発途上国の環境破壊の防止など、地域としての持続可能性を確立するために環境と開発における域内の協調が重要となるものと考えられる。
一方、アジア・太平洋地域諸国が環境政策を着実に進めていくためには、例えば、経済政策との統合、運輸政策への環境配慮、人材育成における環境教育など各種政策との統合が必要とされる。経済開発においては、持続可能な開発を反映させ、環境影響評価及び汚染者負担の原則の適用等により、経済成長に関する政府の基本的な考えに環境配慮が組み込まれなければならない。アジア・太平洋地域諸国における開発担当部局と環境担当部局の協力により、持続可能性を保持できる様々な方向に政策立案、プロジェクトの企画及び実施を導いていくことが必要である。我が国としては、各国において対応できる組織や人材等の実態を把握し、また、これらの人材の適応能力を向上させていくための各種手段を強化していくことが必要である。
昨年度までの環境白書で見てきたように、経済の高度成長期においては、企業は設備投資や新しい技術の導入を積極的に行うことが可能であることから、アジア・太平洋地域諸国においても、企業は積極的な環境投資を行い、環境技術の導入を促進し、この地域全体の経済成長と環境保全を両立させていくことが必要とされる。これは、持続可能な発展の基礎となるものである。我が国の環境技術の移転においては、単なる環境技術の輸出のみではなく、各国の産業育成、エコビジネスの展開に資することが必要であり、同時に我が国企業による環境分野の地域協力や研究協力も積極的に行われることが期待される。
我が国の地方公共団体においては、環境分野での現場における経験が多く蓄積され、経験を有する人材も多い。これらの人材が国際的に積極的に参画しやすい環境をつくることも必要である。また、地方公共団体の人材を登用するだけでなく、姉妹都市や友好都市等のネットワークを通じた地方レベルでの環境協力を地方公共団体自らが進めていくこと、更にはそうした知見を国レベルの協力にインプットすることも重要である。
民間団体においては、よりきめ細かな援助や環境協力を推進していくために、援助国及び受入国における民間団体の果たす役割は大きい。民間団体のネットワーク等を活用し、現地の住民やNGO等と十分なコミュニケーションを持って地域に貢献する事業を行っていくことが必要である。
今日の広範な環境問題に対処し、持続可能な開発を世界規模で達成していくためには、開発途上国に対する協力も視野に入れつつ、自然科学のみならず人文・社会科学的視点をも加えて地球環境問題に立ち向かうための戦略を総合的に研究し、内外に向けて提言を行うような世界に開かれた機関が必要であるという提言もなされている。
また、本年11月に大阪にてアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会合等の開催が予定されているところ、発足当時の経緯から経済問題に限定されたフォーラムとしての性格付けを与えられているAPECが、それぞれの作業部会(WG)等において環境配慮を組み込むとの昨年の環境専門家会合での結論を踏まえ、本格的に環境問題への検討が進められていくこととなっている。APECは将来の貿易投資の自由化を最大の課題として取り組んでいるが、このような経済政策においても、我が国の積極的な関与の下、アジア・太平洋地域において環境配慮が進んでいくことが期待される。
アジア・太平洋地域の持続可能な発展を実現していくためには、将来の世代にわたって長期的な視野に立った取組が必要であり、環境と開発に関する将来展望に関する的確な情報が政策立案に当たっての基礎となる。現在、環境庁のアジア・太平洋環境会議(エコ・アジア)では、関係諸国・機関の専門家によるアジア・太平洋地域の2025年を見通した長期展望プロジェクトが開始されており、このような将来展望を描くことは、地域内の政策担当者の間の共通認識の形成に貢献し、ひいては、地域協力の円滑な推進につながるものと考えられる。
以上のように、アジア・太平洋地域の持続可能な発展に向けて一致して取り組むべき課題は多い。アジア・太平洋地域では、今後ますます相互依存関係の深まりが予想されることから、環境分野の地域協力の一層の推進及びそのためのメカニズムが必要とされている。環境庁のアジア・太平洋環境会議(エコ・アジア)においては、各国及び地域の政策立案並びに共通の環境問題に取り組むに当たっての共通認識の醸成及びパートナーシップの形成に貢献するような継続的な取組が期待されている。このような努力は、世界の他の地域、とりわけ開発途上地域に対するモデルとなりうるものであり、アジア・太平洋地域での環境協力を推進していく上で、我が国のイニシアティブの発揮が必要である。