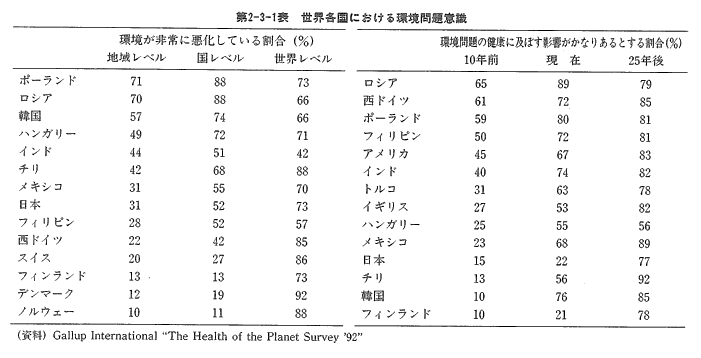
1 アジア・太平洋地域諸国の取組の状況
これまで見てきたように、アジア・太平洋地域諸国においては、人口増加、貧困、都市化及び工業化等により環境問題が深刻化している。こうした環境問題に対する市民の環境問題への意識を見てみると、1992年(平成4年)のギャラップインターナショナルの調査では、韓国、インド、日本、フィリピン等の国の人々が、地域、国、世界のそれぞれのレベルで環境問題を考えた場合、環境が悪化していると考えるレベルは、日本、フィリピン等の国では世界レベルでの環境が非常に悪化しているとするのに対し、韓国、インドでは、国レベルの環境が非常に悪化しているとしている。また、10年前、現在、25年後の3時点において、環境問題の健康に及ぼす影響がかなりあるとする割合を見ると、日本、フィンランド等の国々では現在の影響より将来の影響を比較的重視している傾向にあるのに対し、フィリピン、インド、韓国では、現在と将来の両方に影響が大きいと答えている(第2-3-1表)。
また、アジア・太平洋地域の環境問題の原因の一つには、技術、資金及び人材の不足などから、人口や工場が集中する都市部における上・下水施設等の衛生設備やインフラが整備されていないことや、企業の工場等において環境保全対策技術・設備が不十分であることも指摘されている。平成4年度にアジア経済研究所がタイ国国家経済社会開発庁と共同で行ったタイの企業(603社)に対する意識と対策に関する調査によると、公害防止施設が必要と考えている企業は大企業36.4%、中企業19.7%、小企業11.3%で、逆に必要ないと考えている企業は大企業53.3%、中企業73.8%、小企業75.6%となっており、企業規模により公害防止設備設置への意識の違いが現れている。また、3年度に中国国家科学技術委員会科学技術促進発展研究中心と共同で行った調査(対象211企業、1,734人)によると、中国の公害防止設備の稼働状況について、固定資産額が1万元から5,000万元までの小規模の企業では、公害防止設備に関し資金不足を挙げる企業が多いが、固定資産額が1億元以上の企業では、資金不足よりも専門技術者の不足を挙げる企業が多い傾向にある(第2-3-2表)。
中国では、多くの公害問題が発生しているが、その一つに石炭への高い依存度から生じる二酸化硫黄やばいじんによる大気汚染がある。中国のエネルギー供給に占める石炭の比重は非常に大きく、一部の地域では硫黄分を多く含む石炭が使用され、また、工場、発電所などでの公害防止設備が進んでいない状況にある。これは、公害防止装置を設置するよりも課徴金を払った方がコスト安になることがあり、企業の環境装置導入へのインセンティブが低いことも一つの要因となっていると指摘されている。また、公害防止設備をはじめ、一般に機械設備のエネルギー利用効率が低いことも指摘されている。
一方、環境保全のための行政の取組、規制等に関しては、環境監視及び管理に関する法・規制・制度や組織は整備されつつあるものの、管理や指導を行うための技術、資金、人材の不足、汚染物質発生者に対する指導の不徹底、一般の意識の低さ等の理由から、有効に機能していない場合も多いと言われている。以下では、中国、韓国、インドネシア、タイ等の国々を例にとり、アジア・太平洋地域各国の環境行政に見られる環境問題への取組の状況を概観してみることとする。
(1) 中国
中国の行政レベルについては、中央と地方とに分けられ、国レベルの環境政策を決定するのは国務院環境保護委員会であり、その事務機関としての国家環境保護局が環境部局間の協力や調整等のマネージメントの役割を担っている。このほか、国務院の19部(省)には司(部)及び局レベルの環境保護機構が設立され、また、電子工業部及び軍隊等にも環境委員会が設立され、それらは所管の範囲内の汚染防止や生態保護を行っている(第2-3-1図)。
中国の環境政策を見てみると、?環境汚染の未然防止、?汚染者負担、?環境管理の3つの政策が基本となっている。環境汚染の未然防止に関しては、新たな生産設備と環境保全設備の設計、着工、稼働を同時に行い環境汚染を未然に防止する「三同時制度」や環境影響評価制度、汚染者負担に関しては、公害防止設備投資額の一定割合以上の投資、環境汚染の著しい企業の期限付き汚染防止対策及び汚染排出費徴収制度(課徴金制度)、環境管理に関しては、環境保護の責任の範囲や目標を協定書によって明確にする「環境保護目標責任制」、事業所に対する「汚染物質排出許可証制度」、「都市環境総合整理定量システム」、「汚染物質集中処理制度」及び、事業所に対して発生源の防止対策や防止方法の決定等を行う「汚染源期限内処理」である。また、中国では環境保護法が環境政策に関わる基本法規であり、三同時の原則や汚染排出費徴収制度等の基本政策が規定されている。
また、中国では、1994年(平成6年)3月、計20章、78項目からなる「中国アジェンダ21(中国21世紀の人口、環境及び発展に関する白書)」が制定されている。この「中国アジェンダ21」には、中国の持続的発展戦略と対策が明記され、「第2章 持続的発展のための戦略と重要行動」において、「中国は経済が急速に発展する歴史段階に入っているが、経済基盤が弱く、技術水準が低いため、資源消費量が多く、汚染が深刻である。また、生態系の基礎が弱いために、各種の矛盾が交錯し、激化している」との認識の下で、「中国社会経済の基本的特徴と資源環境の拘束状況から、合理的な資源の活用、生態環境の保護を経済発展の枠組みに組み込まなければ、経済成長の持続は困難であり、後世に持続的発展の条件を残すことも難しい」としている。そして、「中国の現有の発展戦略、政策、計画及び管理メカニズムでは、持続的発展要求に応えることは難しく、総体的な発展戦略、目標の制定並びに重要行動を採択し、持続的発展に関する構想を十分に反映させるとともに、人口、経済、社会、生態系及び環境の協調的発展を実現しなければならない」とした今後の環境問題への取組の方向性が位置付けられており、環境行政の進展が期待されている。
(2) 韓国
韓国では、中央政権の強化により地方自治が育ちにくい政治状況にあったとされ、タイ、インドネシアと同様に、環境行政は中央政府が公害防止の対策に当たり、地方公共団体は公害防止に熱心ではなかったことが指摘されているが、最近では、韓国政府内で環境行政組織の大幅な改編が行われている。
韓国では、1973年(昭和48年)に保健社会部の衛生局内に公害対策課が設置され、それが1977年(52年)に環境管理局となり、1980年(55年)に保健社会部の外局として環境行政を主管する環境庁を経て、1990年(平成2年)には環境庁が環境処に昇格し、国務大臣である環境処長官を長とする独立した組織となった。そして、1994年(平成6年)12月の組織改編により、環境処は環境部に昇格し、その重点施策として、干ばつ対策と水道管理、廃棄物の適正な処理のほか、大気分野でのディーゼル自動車の排出ガス規制、LNGや低硫黄油等の供給及びオゾン警報制、生態系保全のための自然環境保全事業の推進を進めている。同年12月の飲用水管理法の制定と水質環境保全の改正や水道環境施設の整備による水道管理、廃棄物の重量基準回収料金制度に見られるように、これまでの事前予防と事後管理の両建てから、事前予防と汚染者負担の原則の拡大適用に大きな比重を置くようになっている。
(3) インドネシア
インドネシアでは、人口環境担当国務大臣が環境関連施策の企画立案及び関係する各省庁で実施される施策について所要の調整を行ってきた。環境問題に関連する個別の施策の実現はその事業の実施権限をもつ機関との調整を経て初めて可能となり、具体的な施策の実施は原則的に関係する個々の省庁によって行うこととされていた。しかし、このような従来からの体制では、今後深刻化していくことが予想される環境問題に総合的かつ機動的に対応することが困難であるとの認識から、1990年(平成2年)6月、大統領直属の政府機関として環境管理庁が設置された。人口環境担当国務大臣は1993年(5年)4月、人口部門を切り離して環境担当国務大臣を配置し、環境問題に関する政策の立案を行い、一方、環境管理庁は環境保全対策の実施、環境監視等を行うこととされている。
インドネシアの開発計画と環境保全の調整については、開発計画の調整と開発予算の配分権限を有している国家開発企画庁の中の天然資源環境局が行っている。また、内務省地域開発総局の中に環境・開発構造局があり、地域開発における地方政府との調整を行っているほか、関連省庁ではそれぞれ独自に環境施策を実施している状況にある。地方の環境行政は、主として中央政府の地方機関としての機能を有する州知事あるいは関係省庁の地方機関が実施するものであり、地方公共団体が主体的に行う体制には必ずしもなっていないとされている。
インドネシアでは、1994年(平成6年)から25か年にわたる第二次長期開発計画が始まり、その第一段階として第6次5か年開発計画(1994〜98年度)が開始されているが、その中では特に環境保全に関する方針と施策が掲げられている。インドネシアにおける環境保全対策上の障害としては、自然資源及び環境管理に係る政府の機構制度の限界、自然資源及び環境管理のための法令の未整備、環境に係る科学技術に関する知識をもった環境専門家等の人材不足等が指摘されている。
(4) タイ
タイ政府は、1991年(平成3年)10月にスタートした第7次国家経済社会開発計画の中で、経済の持続的成長、所得の公平な分配とともに、環境保全を開発目標の一つとして位置付けている。国家開発計画の目的自体に環境保全が位置付けられたのは、今回の計画が初めてであり、この計画の一環として、1992年(4年)4月新環境保全法が公布されている。また、科学技術エネルギー省は科学技術環境省と改称され、従来環境行政を担当していた環境庁に代わり、科学技術環境省の下に環境計画局、公害対策局、環境保全推進局の3局が設置されている。この環境計画局の中には、東部、東北、南部、北部の各地域環境室が設けられており、地域の環境保全対策に取り組むこととされている。タイの県や郡レベルでは、一般に環境行政を専門に取り扱う部局はなく、テーサバーン(自治市町)、スカーピバーン(衛生区)等においても、バンコックやチェンマイ等の都市を除き、環境行政組織は存在していないとされている。
タイの新環境保全法では、組織強化及び規制強化と並び、環境管理計画の策定と環境基金の創設が盛り込まれている。タイの環境管理においては、環境行政を担当する多くの省庁間の政策に関する調整不足のため、社会経済、天然資源、環境保護に関する施策の重複や矛盾が起きていると指摘されている。また、環境保護と公害防止についての認識不足に基づく民間企業、政府等の対策の遅れ、中央政府による環境行政の一元的な意思決定、官民における環境対策を担当する人材不足も大きな問題となっている。
タイ、インドネシアの例に見られるように、アジアの開発途上国における環境行政は、一般に、公害対策を中心とした環境行政組織が中央政府に置かれており、地域レベルでは、広域行政圏や州単位で置かれている中央政府の地方機関により、環境関係法令の施行や環境モニタリング等が行われるとともに、関係省庁の直接的な監督による環境管理や環境規制が行われている。
1994年(平成6年)に米国ハワイ州にある国際共同研究機関「東西センター」で行われたアジア・太平洋地域の国、地域、州政府等60以上の環境行政機関に対する調査では、各国の環境庁の人数は太平洋諸島諸国では平均約10人程度、フィリピン、タイ等のアジア5カ国では平均約170人、香港、シンガポール、台湾のNIES諸国・地域では平均約800人、日本を含む先進工業国では平均約3,000人とその規模は大きく分かれている。その中で、小規模の環境機関では、最高責任者は首相や閣議メンバーの大臣となっていても、実際は省庁の局課の幹部クラスにより運営されている例が見られ、他の行政分野に比べ、国政上のプライオリティが低い傾向が見られる。また、いずれの国においても、環境行政は環境行政専門機関も含め多数の省庁の共同の活動として行われている。このため、関係行政機関の間の調整、連携が重要になってくるが、各国それぞれの事情の違いもあり、環境行政機関に必ずしも十分な権限が与えられていないとの指摘が調査対象となった環境行政機関からなされている国もある。
環境基本計画では、環境と開発の両立に向けた開発途上地域の自助努力を支援するとともに、各種の環境保全に関する国際協力を積極的に推進することとしている。アジア・太平洋地域諸国の環境分野における対処能力の向上は大きな課題の一つであると言えよう。