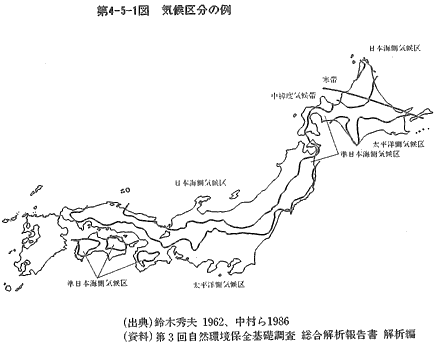
(1) 我が国の自然生態系の現状
ア 気候と地形
日本列島はアジア大陸の東側に位置し、北緯24度近くから46度近くへと広がって南北に細長く、緯度的な変化に富んでいる。札幌と鹿児島の緯度差はマニラとジャカルタの緯度差より小さく、バンコクとシンガポールの緯度差にほぼ等しいが、気候の差に関しては札幌と鹿児島の差の方がこれらの都市の間の差に比べて圧倒的に大きい。これは、南北の気温差の大きな中緯度帯に日本列島が存在するからである。また、同じ緯度で北アメリカ大陸沿岸と比較すると、日本より少し高温であるが南北の気温差はほぼ同じ程度である。日本各地の年平均気温は、低地ではオホーツク海沿岸が一番低温で約5℃、沖繩と小笠原では約22℃、南鳥島では約25℃である。
一方、日本はアジア大陸から日本海や東シナ海等によって隔てられているため、冬のシベリア大陸の厳しい気候は緩和され温和な気候となる。日本付近には黒潮とこれから分岐した対馬海流という暖流と親潮及びリマン海流という寒流が流れており、これらの海流も我が国の気候に影響を与えている。また、北西季節風に伴う豪雪や梅雨、台風によってもたらされる降水は、日本を水資源の豊かな国にしている。日本は世界の平均年降水量(約1,000mm)を上回るところが大部分で、南北の違いは比較的小さい。
日本の気候の大きな地域性は、起伏に富んだ山脈が日本列島を縦横に走っているために脊梁山脈をはさんでその両側に現れることであり、日本海側と太平洋側の気候の違い、特に冬の天候の違いは際立っている。また、日本アルプスをはじめとする3,000m級の山々を有し、国土の約60%が山地となっており、一般的には気温は高さとともに低下するため気温低下の割合である気温減率は日本では100mに付き約0.7℃になると推定され、日本の急峻な地形では気候はさらに変化に富んだものとなっている(第4-5-1図)。
こうした気候の変化による自然環境への影響に加え、これまでにみてきた地球の温暖化やこれに伴う降雨の変化、オゾン層の破壊による紫外線照射量の増加、硫黄酸化物や窒素酸化物等の大気汚染物質による酸性雨などといった人間活動による環境条件の変化は自然環境にも影響を及ぼすものとなる。
イ 植生と人工表土地
昭和63年に取りまとめられた第3回自然環境保全基礎調査植生調査の結果では、自然植生や代償植生のほか植林地や耕作地植生も含めたなんらかの植生(緑)で覆われている地域は全国土の92.7%で、そのうち森林は国土の67.5%を占め、森林の割合は世界的にみても高いといわれている。
自然林や自然草原などの自然植生は急峻な山岳地・半島部・離島といった人為の入りにくい地域に分布しており、平地・丘陵・小起伏の山地などは二次林や二次草原などの代償植生や植林地・耕作地の占める割合が高くなっている。また、大都市の周辺では、市街地などで面的にまとまった緑を欠いた地域が広がり、国土全体では自然性の高い緑は限られた地域に残されているのが現状である。
自然状態を保った自然植生、すなわち植生区分の?ハイマツや高山植物に代表される寒帯・高山帯植生、?エゾマツ・トドマツ・ダケカンバ・オオシラビソなどの亜寒帯・亜高山帯植生、?ブナ林やエゾイタヤーシナノキ群落などのブナクラス域自然植生、?シイ林・カシ林・タブ林などのヤブツバキクラス域自然植生と、?河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生は、全体で全国の19.3%となっている。自然植生の分布を見ると、2分の1以上にあたる58.7%が北海道に分布しており、他に東北及び中部の山岳部や日本海側と沖繩に多い。一方、近畿・中国・九州では分布が非常に少なくなり、小面積のものが山地の上部や半島部や離島などに点在しているにすぎない(第4-5-2図)。
こうした植生は一般に時間を経るに従って変化し、最終的に安定的な生態系である極相となる。日本の気候では、?南西諸島から東北南部に広がる、タブ・カシ・シイといった常緑広葉樹(照葉樹)の森林、?九州南部から北海道南部までの、常緑広葉樹林よりは寒冷な地域に広がるブナ林などの落葉広葉樹の森林、?北海道に広がる、エゾマツ、トドマツといった針葉樹とミズナラ等の落葉広葉樹の混成する針広混交林、?エゾマツ、トドマツ林に代表される亜寒帯針葉樹林などが代表的な気候的極相の植生である。日本を代表する自然性の高い地域ではこうした極相の植生が見られているが、その地域は必ずしも多くはない。
日本の代表的な自然植生と気温(温量指数:暖かさの指数と寒さの指数)との関係を見てみると、第4-5-3図にようになる。温量指数とは、月の平均気温が5℃を越える月を植物が生育できる期間とし、逆に5℃未満の月を非生育期間と仮定して算出される一種の積算温度である。暖かさの指数は月平均気温が5℃を越す月の平均気温から5℃を引いた値を加算してもとめられ、また、寒さの指数は月平均気温が5℃未満の月の平均気温から5℃を引いた値を合計した数値のことである。この結果、エゾマツ・トドマツ林・ブナ林及び照葉樹林を代表するスダジイ林は基本的に暖かさの違う地域に分布していることが分かる。
本章第1節でみた地球温暖化等による気温の変化は植生に大きな影響を与えることが懸念されている。IPCC報告書によると、予想されている平均気温の上昇は2025年までに約1℃、21世紀末前に約3℃となっているが、今と同じ状態で毎月の平均気温が1℃あるいは3℃上昇すると仮定すると、例えば現在温量指数が69.4℃・月でエゾマツ・トドマツ林出現分布の南限あたりの気候条件に等しい札幌の温量指数は、2025年で76.7℃・月、21世紀末で92.7℃・月となる。このことは、札幌は2025年の段階でエゾマツ・トドマツ林が出現できる温量指数の範囲からはずれ、また21世紀末にかけてブナ林の出現する温量指数の範囲となることにより、植生に大きな影響を与えることが予想される。気温の変化は地域や季節によって大きく異なることが予想されるため、単純な結論を出すことはできないが、地球温暖化が日本の植生にも大きな影響を与える可能性は否定できない。
我が国の植生を自然度区分によって見てみると、自然林・二次林・植林地を合わせた森林は国土のおよそ3分の2となっており、人為的に成立した植生である植林地は国土の24.7%を占め、全国の広範な地域に分布している。植林地や各種の耕作地にその他の市街地等を含めると、国土の半分以上の53.3%が人工的な植生の地域、あるいはまとまった緑のない地域といえる。また、農耕地と市街地・造成地等を合わせると26.7%を占め、国土の4分の1に達している(第4-5-1表)。
国土に占める構成比の増減をみると、森林全体では+0.2%とほとんど変化はないが、自然林・二次林をあわせて-3.9%と減少、植林地は+4.1%と増加しており、自然林・二次林のかなりの部分が植林地に変化したと考えられる。また、農耕地が-1.8%と減少している一方、市街地などが+1.5%と増加している(第4-5-2表)。全国の植生は森林では自然度の低い森林が増加し、森林以外ではまとまった緑のみられない市街地などが増加するなど、自然度の低下や緑の減少が進んでいるといえる。
平地・丘陵地などの我々の活動領域に近い地域では、二次林や植林地・耕作地が多い。二次林は、ブナクラス域でのミズナラ林、ヤブツバキクラス域でのコナラ・クヌギ等の雑木林及びマツ林、シイやカシの萌芽林などによって構成され、その多くは薪炭材の採取や肥料用等としての落葉下草の採取などの人の生活を介して維持されてきた林である。これらは我々の生活の場にも近く身近な自然として広く親しまれてきた貴重な緑となっているが、二次林の利用度の減少や山村の過疎化等により人の手の介入が急減しているため、二次林はその姿を変えつつある。
一方、前述の植生自然度区分によると、家屋・ビル・工場等の建築物や道路などの自然の乏しい人工表土地(市街地など)は、同じ期間の間に4.3%から5.8%へと1.5パーセントポイント増加している。人工表土地は自然の物質循環の中でみると特異なものであり、例えば林地では歩道の約20倍程度の浸透能力があるなど、人工表土地は林地に比べて雨水が浸透しにくい。また、樹木は蒸発散作用により気化熱の消費から高温になることを防ぎ、また同時に空気中に水分を供給して乾燥化を防ぎ、その他にも防音・汚染物質の吸着等種々の機能を発揮しているが、樹木の少ない表土地ではこうした機能が少なくなる。人工熱は様々な人間活動により排出されるため人工表土地では自然の気候よりも高温乾燥の傾向にあり、国土の自然環境にも影響を及ぼしているのではないかと懸念されている。
ウ 動物相
我が国の生態系の一部を構成する動物の分布は、島国という地理的特徴や気候・植生といった諸条件により特徴付けられている。北海道と本州を分けるブラキストン線や屋久島と奄美諸島を分ける渡瀬線などいくつかの動物の分布境界線が知られており、例えば、日本に生息する代表的な中・大型獣9種をブラキストン線を境として3つの分布型に分けると、北海道にのみ分布するのはヒグマ、本州以南にのみ分布するのはツキノワグマ・カモシカ・ニホンザル・イノシシ・アナグマ、両地域に分布するのはキツネ・タヌキ・ニホンジカなどとなる(第4-5-4図)。
植生は、動物の餌場や隠れ場所等として動物の生息条件に大きな影響を与え、動物種と植生は深い関係をもっている。第4-5-5図は、ほ乳類の生息情報の得られた植生の内訳を表しているが、例えば、ツキノワグマやカモシカは落葉広葉樹林でその中でもブナ林等で多く、キツネは農耕地やクヌギ・コナラ林といった雑木林で多く生息が確認されている。
また、気候も動物相に大きな影響を与える。前述の温量指数とチョウ類の分布を対照させてみると、クモマベニヒカゲ・ギフチョウ・ミカドアゲハのそれぞれの生息域は植生に規定される要素もあるが温度にも深く関わっていることが分かる(第4-5-6図)。植生の場合と同じく温暖化による気候変動が動物種の生息に深刻な影響を与える可能性があることも予想される。
エ 自然景観
自然の造作による滝・溪谷・山岳地等の景観として優れている地形や地質及び自然現象は、それぞれ特徴的な生態系を形作っているとともに、我が国では地域のシンボルであるほか、学習やレクリエーション及び観光・自然探勝などの場として、また自然景観への感動から人間性を回復する場として貴重な存在となっている。
平成元年に取りまとめられた第3回自然環境保全基礎調査の自然景観資源調査によると、我が国の自然景観資源数は15,468資源であり、最も多いのは滝(2,488カ所)であり、以下峡谷・渓谷(996カ所)、非火山性孤峯(993カ所)、湖沼(872カ所)、海食崖(734カ所)、砂浜・れき浜(632カ所)の順でこれら7資源で全体のほぼ半数を占めている。自然景観資源の分布状況は日本アルプスを抱える中部地方が全体の22.2%、次いで東北地方の21.4%、九州地方14.2%、関東地方10.5%の順であり、類型別の分布状況では火山景観・山地景観とも中部地方に最も多く、石灰岩地形は中国地方に多く分布している。一方、水系では河川景観が中部地方、湖沼景観は東北地方に多く、海岸景観は九州地方が豊富である。
自然景観資源の保護の現状をみると、国立公園等なんらかの保護制度下にある資源は約半数であり、国立公園内には全体の23.2%、国定公園内には14.6%が分布している(第4-5-7図)。種類別にみると、保護制度下にない(不明を含む)資源数が保護下にある資源数を上回っているものは、非火山性孤峯、鍾乳洞、河成段丘などである。また、利用状況では利用の特定できる資源は全体の13.3%であり、これらの年間利用者は1〜5万人の範囲の資源が最も多く、総資源数のうち3分の2近くはなんらかの開発行為あるいは当該開発行為の二次的影響を受けている。その種類として最も多いものは人の立ち入り(15.8%)で、次いで農林業開発(10.0%)、観光開発(9.5%)の順である。
世界自然遺産とは「世界遺産条約」に基づく「自然遺産」として観賞上・学術上又は保存上等の見地から顕著な普遍的価値を有する自然の地域のことであり、良好な自然状態が残され十分な保護措置がとられている人類共通の財産として、繩文杉に代表されるヤクスギ巨木群をはじめ海面から標高1,900mに至る特殊な植物相を誇る屋久島地域(鹿児島県)と原生的なブナ天然林を有し希少な鳥類が生息する白神山地地域(青森県、秋田県)が、我が国で初めて世界遺産一覧表へ登録されることが平成5年12月に決定した。
平成6年1月現在、同一覧表に登録された自然遺産は106地域(うち複合遺産16地域)であり、世界遺産一覧表に記載の危険にさらされている自然遺産は7地域ある。世界の自然遺産として登録されている地域の例としては、グランドキャニオン国立公園・イエローストーン国立公園(米)、グレート・バリア・リーフ(豪)、ガラパゴス諸島国立公園(エクアドル)などがあり、危険にさらされている自然遺産はニンバ山脈(ギニア・コートジボアール)、エバーグレーズ国立公園(アメリカ)などである。
(2) 地域毎の生態系の現状
ア 山岳地
山岳地の大部分は森林に覆われ、野生生物の生息・生育地であるとともに様々な資源を我々に与えてくれる場である。森林被覆度と傾斜度との関係を第4-5-8図に示すと、平均斜度が大きくなるにつれて森林面積の占める割合が大きくなることや傾斜度が30゜を超えるところではほとんどが森林で覆われていることが分かる。こうした山岳地の森林は、土壤流失等の環境被害を防ぐ重要な役割を果たしている。山岳地を覆う森林には人工林も少なくなく、傾斜が大きくなるとその割合も減少する傾向にあるが、傾斜度30゜以上の急傾斜地においても人工林の割合が13%を超えており、近年ではかなりの奥山まで人の手が入っていることが分かる。
山岳地には、日本に残された自然のままの生態系が多く存在しており、第3回自然環境保全基礎調査によると、ブナ林のうち自然度の高いものの分布(メッシュ数)の多い地域は山岳地がほとんどを占め、照葉樹林の分布の多い地域は島しょ部とともに紀伊山地・九州山地等の山岳地に偏っている。また、山岳地は多様な生態系を有していることも多く、例えばチョウ類の種数の多い地域をみると秩父山地を始めとする山岳地で数多くの種が生息していることが分かる(第4-5-3表)。高山についても、寒冷な厳しい環境の中で高山植物や高山蝶などによって構成される特異な生態系が残されている。
山岳地は、古くから信仰の対象・地域のシンボル等我々の精神生活に重要な役割を果たしており、これに加えてレクリエーション・観光の場としての役割も重要になっている。自然景観資源調査では、自然景観としてよくみられるもののうち上位の3種(滝、火山、峡谷・溪谷)はいずれも山岳地においてみられる自然景観である。
近年は山間地域の人口が減少し、多くの人手を要する人工林の管理をはじめとして山岳地環境の利用や管理が衰退してきており、山岳地の自然環境とその利用との関係が急速に変化しようとしている。
イ 湖沼
我が国には、山岳地帯にある湖沼をはじめ、海が後退してできた海跡湖のように平野部や海岸近くに存在するものなど様々な湖沼が数多く存在している。環境庁では、天然湖沼のうち原則的に1ha以上の480湖沼を調査対象湖沼として第4回自然環境保全基礎調査湖沼調査を平成3年度に実施した(480湖沼のうち2湖沼は消滅)が、調査対象湖沼の面積は2,374.37km
2
で国土面積の0.63%にあたっている。集計・解析対象となった476湖沼の湖岸線総延長は3,184.2kmに達し、これらの湖岸線改変状況は自然湖岸56.6%(崖地でないもの45.0%と崖地のもの11.6%)、半自然湖岸12.4%、人工湖岸30.3%、水面0.7%となっている。第2回調査から比較して自然湖岸は減少しており、大部分の湖岸線が人工湖岸化している。
一方、湖岸線土地利用状況は、自然地56.7%(樹林地36.9%とその他の自然地19.7%)、農業地23.0%、市街地・工業地・その他19.6%、水面0.8%となっている。全国的にみると、水面状況にある部分も含めて自然地が保全されている土地は57%、農地や市街地や工業地化している土地等なんらかの人為改変を受けている土地は43%となっている。自然地は樹林地を主体に減少し、市街地ほかに転換している。
湖岸線に隣接した地域が市街地化あるいは工業地化されることになると、市街地や工業地の進展とともに周辺地域もまた整備される状況であり、このような土地利用が行われる場合には湖岸線の人為改変を伴うことが多い。人工湖岸率50%以上且つ市街地率30%以上の改変の進んでいる湖沼は27湖沼であり、そのうち第4回調査で新たに追加された湖沼は、坂田池と久々子湖の2湖沼である。
1945年(昭和20年)以降第4回調査時点(1991年)までの46年間に、干拓・埋立が行われた湖沼は66湖沼でその面積はおよそ347km
2
であり、干拓・埋立面積の累計値は集計・解析対象湖沼の総面積の14.6%に相当している。これら干拓・埋立の総量の98.5%(55湖沼)が1945年(20年)から第2回調査(1979年)の戦後の34年間で行われており、このうち4湖沼は干拓により完全に消滅した。
特定湖沼60湖沼を対象とした調査において、生息する魚種数の1湖沼当りの平均はおおよそ25魚種であるが、最も魚類相が豊富に報告されている湖沼は浜名湖の257魚種で第2位の中海の96種と比較しても飛び抜けて多い(第4-5-4表)。主要外国産移入魚種では、ニジマス(サケ科)が21湖沼、ソウギョ(コイ科)が22湖沼、ブラックバス(サンフィッシュ科)が20湖沼、と特定湖沼のおよそ1/3の湖沼で生息の確認がされたことが報告されている。外国産移入種の生息する湖沼の数は、さほど大きな経年変化は認められておらず、ブラックバス等外国産の移入魚も各地の湖沼で定着しつつあり、湖沼の魚類相を変化させる要素の一つとして今後もその推移を注目する必要がある。
ウ 河川
河川の自然環境については、全国の一級河川の幹川等を対象として昭和54年と60年に環境庁で第2,3回自然環境保全基礎調査河川調査を実施しており、調査した河川の水際線11,412.0kmのうち、平水時の水際線が護岸等人工構造物と接している水際線は全国で2,441.5km、全河川延長の21.4%である。第2回調査と比較すると人工化された水際線の延長は全国で249.3km、構成比で2.2%増加している(第4-5-9図)。人工化された水際線延長の増加が大きいのは本州−太平洋(中・南)水系群(116.3km)、及び本州−日本海水系群(109.1km)である。この増加を構成比でみると九州−日本海水系群が20.5%増と突出している。
この調査では水際線の人工化と河川の生物相との係わりを把握することを大きな目的の一つとして水際線の改変状況を調査している。河原の土地利用状況を見ると、幅100m以上の河原の存在区間は全国で5,055区間であり、構成比では全河川区間の44.3%にあたっている。内訳を見ると全河川区間に対して33.3%が自然地、7.6%が農業地、0.8%が未利用造成地、2.6%が施設的利用地である。土地利用別の河原の変化は全国では自然地の減少、農業地及び施設的利用地の増加という傾向にある。
ダムや堰などの河川横断工作物は、魚類の遡上を助ける適切な処置を講じない場合には、魚類の生息域を分断することがあるため、環境庁では、魚類の生息条件を把握するため昭和60年の河川調査にて河川横断工作物を調査している。河川横断工作物における魚道の設置割合は30.6%であり、魚類の遡上が可能な工作物は全体の約60%となっている一方、魚道のある河川横断工作物のうち約12%にあたる83箇所はよく機能していない。河川横断工作物がない、あるいはあっても魚道がよく機能してサケ・サクラマス・アユ等の遡河性魚類が調査区間の上流端まで遡上可能な河川は、網走川や高瀬川など13河川となっている(第4-5-5表)。第2回調査から第3回調査の間で河川上流端までの魚類の遡上が不可能となったのは、尻別川・四万十川・白川の3河川であり、これらの河川では上・中流域の河川横断工作物の設置が魚類遡上が不可能となった要因となっている。
魚類の遡上可能区間の構成比が高い河川(河川延長の90%以上遡上可能)は9河川であり、魚類の遡上可能区間の構成比が低い河川(遡上可能区間が河川延長の10%未満)は6河川であった。
我が国の河川は、急勾配という地形的条件と多雨のため、洪水が頻発するとともに、河床や流況が不安定である。また、近年では水需要が生活水準の向上等に伴って増加しており、治水・利水等を目的とした多目的ダム等の河川横断工作物を河川上流部に建設しているほか、河川の中下流部では堰等の建設を実施している。例えば、長良川河口堰では魚類の遡上等自然環境に及ぼす影響について様々な議論がなされているが、環境等の調査を実施し、環境保全等に万全を期すこととしている。今後とも河川横断工作物等の設置に当たっては魚類等の生態系に関する影響について十分な調査を実施することが必要である。
河川別の魚数の生息状況は第4-5-6表にまとめたとおりであり、生息魚数の多い河川は信濃川・筑後川の63種を最多としてほとんどが本州の主要河川である。動物相に関するブラキストン線によって本州と隔てられている北海道地方の河川及び急流路で流化する水系や流程の短い河川には生息魚種の少ない河川が目立っている。
エ 湿地・干潟
湿地と干潟は自然環境の中で特異な生態系を構成しており、水生生物や水鳥等の生息地として重要である。「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」では、湿地は湖沼・河川・湿原・干潟等を含む広い概念でとらえられている。湿地では水量が一般の表土に比べ多く、こうした環境を好む動物種・植物種しか生息できないため特異な生態系を形成しており、水生生物や水鳥などの絶好の生息地となっている。
日本ではラムサール条約の登録湿地として、これまで釧路湿原(北海道)、伊豆沼・内沼(宮城県)、クッチャロ湖(北海道)、ウトナイ湖(北海道)の4ヶ所が登録されていたが、釧路でのラムサール条約第5回締約国会議の開催中の平成5年6月10日に、霧多布湿原(北海道)、厚岸湖・別寒辺牛湿原(北海道)、谷津干潟(千葉県)、片野鴨池(石川県)、琵琶湖(滋賀県)の5ヶ所が追加登録され、現在同条約の登録湿地は計9ヶ所となっている。
干潟は、海域環境の中でも特異な海洋生物や水鳥等の生物の生息環境として重要な生態系である。また、干潟の多くは一般に汚染が進行しやすく浄化の進みにくい内海にあるため、干潟の持つ水質浄化能力にも注目が集まっている。例えば自然干潟は、人工のものに比べてより多くの浄化能力を有しているとの研究もある。平成元年度から3年度にかけて環境庁が実施した調査によると、現存する干潟の総面積は51,462haであり、面積が1,000haを越える大規模な干潟は熊本県有明海から4件報告され、これらを含め有明海には全国の干潟の約40%が分布していた(第4-5-7表)。また、4,076haの干潟が昭和53年以降に消滅したことも明らかとなり、その原因の約46%が干潟の多く存在する内海に面する地域の開発により埋め立てられたものとなっている(第4-5-8表)。
干潟の保全については、自然公園法や鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律等による保全に加え、瀬戸内海環境保全基本計画に基づき干潟の保全等を進めることとされているほか、瀬戸内海環境保全特別措置法によって、富栄養化による被害発生の防止・自然海浜の保全・埋立に当たっての環境保全上の配慮等の総合的な施策が進められている。
オ 海岸
自然状態を保持した海岸は生物の生産及び生息の場として重要であるばかりでなく、しばしば優れた風景を構成しレクリエーションの場としても古くから利用され親しまれてきた。都市化や産業の発達に伴い高度成長期には海岸線の人工的改変が急速に進められた。
日本の海岸線の総延長は32,472kmであり、このうち本土部分は58.3%にあたる18,919kmを占めている。島しょ部分については、面積が全国土面積の5%に満たないにもかかわらず、海岸線は41.7%の13,553kmと長く、本土よりも複雑な海岸線を形成していることが分かる。全国の海岸の区分比をみると、自然海岸は56.7%と約半数を占め、次いで人工海岸が28.6%である。島しょ部を除く本土部分では自然海岸は46.0%と半数以下となり、かわって人工海岸が36.5%と3分の1以上を占める(第4-5-10図)。
昭和53年から59年までの変化をみると、減少した自然海岸の総延長は565kmとなり、約3%の自然海岸が失われたことになる(第4-5-11図)。減少した自然海岸では砂質海岸が多く占め、岩石海岸や浜の発達していない海岸に対し、海岸保全事業や開発が砂質海岸で多く行われたことが分かる。こうした海岸の自然環境保全については、自然公園法や瀬戸内海環境保全特別措置法などによって取り組まれている。
カ 都市周辺
我々の生活の周りにある緑や馴染みの深い動植物の存在は見過ごされがちであるが、国土の自然環境の一部を構成しているとともに、自然と親しみつつ日常生活を営む上で不可欠な要素となっている。また、こうした都市周辺の自然環境は、ヒートアイランド現象の緩和など都市地域の気候条件や環境の改善に役立つほか、それ自体が都市の大気や水質及び土壤の環境の状況を映し出す役割を持っている。
自然環境保全基礎調査では植生をその人為の影響の度合に応じて分類し調査を行っているが、これを自然植生・二次植生・植林地・農地等・市街地の5区分にまとめて首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)と愛知県と大阪府の自然状況を分析すると、こうした地域のいずれもが全国平均に比べ自然植生が極めて少ない一方で、緑の少ない市街地の割合が多いことが分かる(第4-5-12図)。また、都市近郊では、二次植生がいわゆる里山として身近な自然や野生生物の生息地を形づくっているが、こうした植生も全体的に少ない。都市地域やその周辺の自然環境の保全については、自然公園や保安林並びに緑地保全地区等の指定を行い、そこでの環境改変を規制することや公園・緑地等を整備する公共事業等が行われている。
都市化に伴い表土がコンクリート等の人工物で覆われ、また冷房・暖房等が普及して排熱が増加することによりヒートアイランド化や乾燥化が生じ、その結果局知的な気候の変化によって生態系に影響が出ている(ヒートアイランドについては、本章第8節参照)。例えば、東京では本来暖かい地域の植物であるシュロが自生する例がみられ、逃亡ペットである熱帯地域産のワカケホンセイインコが繁殖している。乾燥化の影響としては、関東平野では社寺林・農家の屋敷林等のスギが衰退していく現象がみられるが、これは乾燥化により水分の吸収力に劣るスギが弱ってきたのではないかとの指摘もある。
一方で、山地に生息していたイワツバメや冬鳥のハクセキレイなど近年都市周辺環境に適応し生息地が拡大している例もあり、周辺地域から都市部への進出による生態系の変化も進みつつある状況にある。
キ 農山村
農業は、自然の生態系に人為を加えることによって作物を栽培し、我々にとって有用なものを採取しようとする活動であり、自然環境へ様々な影響を及ぼしている。農薬や化学肥料などの資材等は農業生産上必要なものではあるが、これに過剰に依存することにより環境への負荷を増大させることが懸念される。
一方、長期間営まれてきた農業は独自の生態系を農地及びその周辺地域に形造っている。日本の代表的な農業である水田耕作は、過去の長い伝統によって用水路や用水池や畔からなる独自の生態系を形造り、カエル・ドジョウ・ホタル・トンボといった身近な生物の生息地となってきた。
農山村近郊の山は、薪炭材の採取や燃料材としての柴刈と肥料用の落葉採取が繰り返され、クヌギ・コナラ・アカマツ等で構成されるいわゆる里山林に覆われている。こうした農山村の環境ではヨシゴイやアオバズク等の鳥類やギフチョウやウスバシロチョウ等のチョウ類の生息が多く確認され、我々の身近な生き物によって独自の生態系が構成されている場合も多いことが分かる(第4-5-13図)。
昨今、農山村人口の減少や省力化の為の機械化等の進行は農山村の自然環境を大きく変えようとしている。燃料としての薪炭材や柴が使われなくなったことにより里山の二次林は人の手が入らなくなり、下草が繁茂してきている。これはより自然性の高い植生への遷移の一環と見ることもできるが、里山の二次林を以前のままの姿で保全するためには、適切な下草刈等を行う必要がある。
水田の中で周辺の森林等とあいまって豊かな生態系を有する谷津田は、山間に多く存在するだけに採算の面から放棄されやすく、その姿を変えることが予想される。また、今後の農業の変化は農山村の自然環境にも大きな影響を及ぼすことも予想される。農山村の自然環境保全については、自然公園や保安林等の地域指定などのほか、環境への負荷軽減に配慮した環境保全型農業の推進等が行われている。
(3) 途上国等における自然生態系の現状
ア 森林
近年、熱帯地域に位置する開発途上国における急激な森林の減少に対し、今までにないほどの関心が高まっている。熱帯林減少の原因は?非伝統的な焼畑耕作、?過度の薪炭材採取、?不適切な商業伐採、?過放牧などと指摘されているが、こうした直接の原因の背景には開発途上国における貧困、人口増加、土地制度等の社会的経済的な要因があげられる。
熱帯林は、炭素の吸収源や地球の放射及び水バランスの調整に重要な役割を果たし、生物多様性の保全のためにも重要な機能を有している。近年における熱帯林の急速な減少は森林資源の枯渇のみではなく、そこに生息する生物種の減少をまねき、回復不可能の段階にあると危惧されている。熱帯林に生息する生物は地球上に生存している生物の50〜80%になるといわれ、熱帯林の減少によってこのような動植物種が滅びたり、種の維持が困難なほどに生息地が狭められることが懸念されている。
森林は世界の陸地の約3分の1を占めており、1991年(平成3年)現在で世界には森林が38億6,108.1万ha存在していると見積られている。このうち開発途上地域に存在する森林は近東・極東5億5,030.5万ha、中南米8億8,757.0万ha、アフリカ6億3,185.8万ha、その他4,392.7万haとなっており、これらを合計した面積は21億1,366.0万haであり、世界の森林の54.74%を占めている(第4-5-9表)。
1993年(5年)に国連食糧農業機関(FAO)によって公表された「1990森林資源評価プロジェクト」の最終報告では、全熱帯林面積は1990年(2年)末で17億5,600万haであり、これに対し1980年(昭和55年)末では19億1,000万haであり、この10年間の年平均森林減少は1,540万haであった(年平均減少率0.8%)。熱帯林面積を地域別に見ると中南米が最大であり(全熱帯林の52%)、続いてアフリカ(30%)、アジア太平洋地域(18%)の順である。年平均の森林減少は中南米740万ha(年率0.8%)、アジア太平洋地域390万ha(同1.2%)、アフリカ410万ha(同0.7%)となっている(第4-5-10表)。
生態区域別の森林減少と森林劣化の過程について、低地降雨林及び湿潤林地域・低地乾燥林地域・山岳湿潤林地域をアフリカ・アジア・ブラジルの3地域別にみると、第4-5-14図では森林面積の変化を、?劣化(林冠密度の低下又は攪乱の増加)、?断片化(森林の3分の2が失われた部分的森林減少)、?森林から他の樹林地への森林減少(森林の喪失及び休耕期間の短い農業への転用)、?森林から非林地へ森林減少(樹木の完全な喪失及び恒常的な農業への転用)の4グループ分けでとらえている。これらの3地域では、低地湿潤林地域における森林喪失・断片化・劣化の率が高くなっており、アフリカとアジアでは森林減少が初期段階としての断片化や劣化を伴っているのに対し、ブラジルでは変化を生じた土地はほとんど森林を喪失し非林地に急速に移行しているのが分かる。
こうした熱帯林の減少による影響は、大面積の消失により多くの野生生物種が絶滅の危機に瀕するおそれがあることに加えて、森林消失による大量の二酸化炭素の放出が地球温暖化を加速させるおそれが懸念されている。森林は、木材・燃料・飼料等の多様な産物の供給源となっている森林バイオマス(地上有機物の現存量)が存在する陸上生物群系であり、木部繊維や林冠の葉の中に炭素を固定する最大の能力を有している。また、森林バイオマスの約50%は炭素であるといわれ、多様な環境条件下における森林生態系の構造的・機能的な特性を比較・検証するに当たっても有用な情報でもある。
カリブ海・中央アフリカ・島部東南アジアの各地域では森林バイオマスが1ha当り200トンを越えているのに対し、最も低い値は熱帯南部アフリカ及びアフリカ・サヘルに見られる。また、非常に高い人口圧力のために、南アジアでは人口一人当りのバイオマスが著しく低いことがわかる(第4-5-11表)。森林バイオマスの年平均の減少量は25億トン強と推定され、そのうちの50%以上が南米地域で、約30%が熱帯アジア、約20%が熱帯アフリカで減少している。
森林の減少、特に熱帯林の減少に対しては、国際熱帯木材機関(ITTO)やFAOといった国際機関による協力や二国間の協力が進められている。また、平成6年(1994年)1月、新しい国際熱帯木材協定(ITTA)が「西暦2000年までに、輸出に係る熱帯木材及びその製品を持続可能な経営が行われている森林からのものとすべく、生産国の政策実施能力を強化する」旨のいわゆる2000年目標を盛り込んだ内容にて採択されている。
イ 土壤
土壤は、農業や牧畜といった経済活動の基盤であり、土壤の劣化や喪失によりこれらの経済活動が不可能になるだけではなく、人間の生活自体にも大きな影響を与える。サヘル地方を始めとするアフリカ各地などでは他の燃料確保策や収量増加策が貧困等により無いため、樹木や草の再生力を超えて薪の採取や牧畜が行われたり、移動式耕作の周期を短くすることがしばしば見られる。このため、土壤の劣化や喪失を招きやすくなる。こうした地域の人々は干ばつに備えるだけの資力もないため、ひとたび干ばつが起こると環境難民として他の土地あるいは都市へとさまようなことになる。いわゆる砂漠化の問題は貧困問題と密接に関係している問題といえる。つまり、土壤の劣化や喪失といった砂漠化問題の原因としては、地球的規模での大気循環の変動による乾燥地の移動という気候的要因と乾燥地及び半乾燥地の脆弱な生態系の中でその許容限度を超えた人間活動が行われたことによる人為的要因の2つが考えられている。
1991年(平成3年)UNEPが発表したレポート「砂漠化の現状及び砂漠化防止行動計画の実施状況について」によると、世界には61億ha以上の乾燥地が存在し、地球の陸地の40%近くを占める。そのうち9億haがきわめて乾燥している地域でいわゆる砂漠であり、残りの52億haの一部が人間活動の結果で砂漠化が進行している。こうした乾燥地域では、世界人口の約5分の1の人々が居住し生活を営んでいる。1991年(3年)に行われた評価では、乾燥地域における農地の約70%である約35億6,000万haが砂漠化により影響を受けており、地域別に見ると、劣化している割合が大きいのは北アメリカ・アフリカ・南アメリカの順であるが、面積でみるとアジアが最も多く、アフリカがそれに次いでいる。
また、土壤の劣化にさらされている地域は11億3,830万haで、極めて乾燥している地域を含めた乾燥地全体の18.3%を占める。土壤劣化の態様は降雨による土壤の流失などによる浸食が最も多く、次に表土が吹き飛ばされるといった風による侵食、塩害やアルカリ化といった化学的な劣化・湛水化などの物理的な劣化と続いている(第4-5-15図)。大陸別でみると、被害を受けている面積が最も広いのは、アジアであり、アフリカ、ヨーロッパと続くが、乾燥地面積に占める土壤劣化の割合を見ると、アフリカが81.1%とずば抜けて多く、アフリカの乾燥地の8割の土壤が劣化しつつある。
旧ソ連国内では、1988年(昭和63年)に発表された旧ソ連環境白書によると、600万haの農地が湛水化の影響を受け、年間15億トンの豊かな土壤が降雨によって失われているため、土壤流失が大きな社会問題となっている。例えば、アラル海地域は牛の牧畜と原始的な灌がい農業が行われていたが、近年綿花農場への集約的な灌がい事業のための非再生的な水利用によって、アラル海に流れ込むアムダリヤ川とシルダリヤ川の流量が激減した。UNEPの報告によると、1957年(昭和32年)から1989年(平成元年)の間に水面は約14m低下し、湖水の量は面積で約30km
2
、水量で約3分の1が失われた(第4-5-12表)。
こうした河川デルタでは激しい乾燥と塩害が引き起こされ、アラル海地域の生態系及び野生生物や植生がひどく劣化し、数10万haの灌がい地が塩害にさらされた。綿花生産が行われていた多くの土地は肥沃さが失われ、主要な農業生産量は低下し、医療施設の深刻な不足や中央水道施設の欠如とあいまって、この地域の人々の健康の悪化も生じた。また、アラル海の後退でできた新しい土地は風によって表土や塩分が吹き飛ばされ、この塵が距離にして最大200kmも運ばれるおそれもあり、土地劣化のもう一つの原因ともなっている。
こうした砂漠化問題に対しては、1993年(平成5年)5月より砂漠化防止条約に関し政府間交渉を開始し、1994年(6年)6月の条約策定を目指して条約作りの作業が進められているところである。我が国では、これまで主として植林や乾燥地農業支援の観点から取り組みが行われてきたが、上記のような国際的動向に適切に対応するため砂漠化問題への取り組みを強化することともに、砂漠化の防止における多国間及び二国間の協力が進められている。
ウ 南極
1991年(平成3年)10月、スペイン・マドリッドにおいて採択された「環境保護に関する南極条約議定書」は、その前文で「南極の環境及びその生態系の包括的保護は人類全体の利益」となることを示しており、南極は、科学的な観測や研究の場として、そして人間の開発の手の及んでいない唯一の大陸として、その貴重な自然環境や生態系とともに今後とも保護されていくべきものである。
南極の環境について概観してみると、南極条約の規定が適用される地域は南緯60°以南の地域であり、総面積5,250万km
2
うち陸地は1,400万km
2
を占め、そのうち南極大陸は1,205万km
2
である。南極の平均気温は-50℃であり、南極大陸自体の98%は陸氷に覆われ、その平均的な厚さは2,450mにもなる。南極における人間活動は、こうした厳しい環境や南極条約による制限によって調査や研究活動に限られている。
こうした厳しい南極環境においても生態系が形成されている。夏の間に氷の間からわずかに現れる陸地に、藻類を中心とする生物が生息し、生態系を形成する。南極の陸上には種子植物が2種知られているほか、菌類・藻類・苔類等が存在する。南極の陸地を繁殖地とする鳥類も存在し、ペンギン類を始め15種ほど知られている。哺乳動物は陸上には生息していないが、南氷洋には哺乳類としてアザラシ・オットセイ・アシカ類が6種、クジラ類ではシロナガスクジラ等のひげ鯨6種とマッコウクジラ・シャチ等の歯鯨が10数種生息している。海鳥は南大洋上で65種ほど生息し、魚類(120種以上)やオキアミなども数多く生息している。こうした生物は南極の環境の中で固有かつ貴重な生態系を構成している。
一方、南極は「科学の大陸」とされているように、気象観測や地球物理学といった研究の場として貴重な存在である。既に述べたようにオゾン層の破壊や氷床コアの古大気分析についての研究が、南極における観測データを基に進められている。南極氷床の氷は数十万年から現在にいたる連続した氷でできており、氷床の内陸部では積雪は蓄積される過程で気候や環境に関するさまざまな情報をもつエアロゾルやガスをよく保存する。この氷床の気泡を抽出し分析することにより、過去の大気組成を知ることができ、例えば第4-5-16図では過去200年の二酸化炭素の濃度推移が、ハワイでの最近の連続観測の結果と定量的によくつながることが示されている。
こうした南極の環境は、南極条約が南極における人間活動をほぼ科学調査のみに限ってきたことや「南極の動物相及び植物相の保存のための合意措置」等の追加措置によって保全されてきた。しかし、近年南極を訪れる観光客が年々増加しており(第4-5-17図)、今後も観測活動の活発化とともに増加するものと見込まれ、各国の観測基地からの廃棄物の発生量増加も問題となってきている。