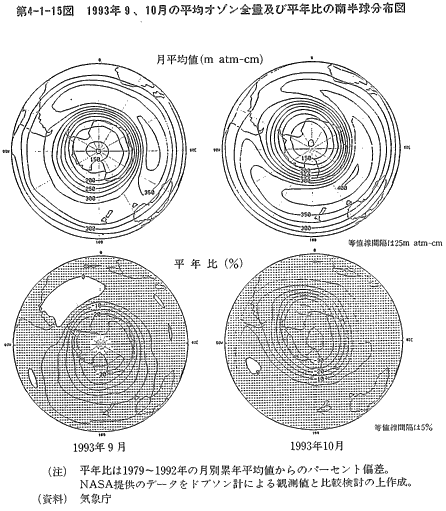
2 地球規模の大気環境の現状
地域的な問題にとどまらず、国境を越えて影響を及ぼす大気環境問題も懸念されている。オゾン層破壊の問題、地球温暖化の問題、酸性雨の問題である。
オゾン層破壊の問題については、モントリオール議定書の改正等を受けて、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の運用及び改正により、既存規制物質の削減スケジュール前倒し及び新規規制物質の追加等の規制強化を行うとともに、環境負荷が小さく安全性の高い代替物質の開発、中小企業等の代替品の転換を促進するための情報提供、並びにCFC等の回収、再利用、破壊を進めるための社会システムのあり方に関する検討及び破壊技術に関する調査研究等を進めている。
地球温暖化問題については、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を目的とする気候変動枠組条約の締結及び平成6年3月21日の同条約の発効を踏まえ、1990年代の終わりまでに温室効果ガス排出量を従前のレベルに戻すことが条約の目的に寄与するものであるとの認識の下での国家政策及び措置の採用並びにその効果の見積り等に関する情報の締約国会議への送付のための準備、条約の円滑な実施に向けて検討を行っている条約交渉会議への参画などを積極的に進めている。
酸性雨については、実態解明と対応措置の検討を進めるため、監視測定網の充実強化、酸性雨と原因物質の定量的因果関係の解明、陸水・土壤・植生等のモニタリング、各種影響予測モデルの開発等の調査を総合的に進めている。また、国際会議を開催し、東アジア地域における酸性雨モニタリングネットワークの構築に向けた取組を進めている。
(7) 成層圏オゾンとクロロフルオロカーボン(CFC)等
オゾン層の破壊は、成層圏下層(高度約15〜30km)にあるオゾン層が人工的に作られたクロロフルオロカーボン(CFC、いわゆるフロンの一種)等によって破壊され、オゾン層に吸収されていた有害な紫外線の地上への到達量が増加することによって、人及び生態系に悪影響を与える問題のことである。
CFCは噴射剤・冷媒・洗浄剤・発泡剤などの用途として使用され、無臭・不燃の非常に安定な化合物であるため対流圏(地上約15kmまでの大気)では分解せず成層圏に達し、紫外線によって分解されて放出する塩素原子が連鎖反応的に成層圏オゾン(O3)を破壊する。CFCのほか、消火剤のハロンや四塩化炭素及び1,1,1-トリクロロエタン・ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)・臭化メチルなどもオゾン層を破壊することで知られている。なお、CFCは温室効果ガスとして二酸化炭素より大きな地球温暖化能力を有することが知られている。
南極においては、1970年代末から毎年春にオゾンが著しく少なくなる「オゾンホール」と呼ばれる現象が現れており、1989年(平成元年)から1993年(5年)にかけて5年連続して最大規模のオゾンホールが観測されている。第4-1-16図から分かるように、オゾンホールの規模を表すオゾンホールの面積・最低オゾン全量・オゾン破壊量の3要素のうち最低オゾン全量とオゾン破壊量は1993年(5年)が最悪となっており、10年前の1983年(昭和58年)に比べてオゾンホールの面積とオゾン破壊量はともに2.3倍に拡大し、最低オゾン全量は57%に減少している。
1993年(平成5年)のオゾン全量の特徴としては、全球的に平年よりも少ない状況が全ての月を通じて見られたことと冬季北半球高緯度でオゾンが少なかったことが挙げられる。1993年(5年)における日本上空のオゾン層の状況については、国内4地点(札幌、つくば、鹿児島、那覇)における月平均オゾン全量の推移を第4-1-17図に示している。1993年(5年)の1月は国内4地点が揃ってその月の過去最小値を記録し、札幌では6月までその月の最低値を記録した。
こうしたオゾン層の破壊により有害紫外線(UV-Bといわれ、波長が280〜315nmのもの)の地上への到達量が増大することが分かっており、有害紫外線の増加は人体に対し皮膚ガンや白内障等の健康被害を増加させ、植物の成長障害や海洋生態系の基礎となる浅海域の動植物プランクトンの生育障害を引き起こすなどのおそれがある。我が国では、オゾンの減少による有害紫外線量の変化を監視するため1990年(平成2年)よりUV-Bの観測を行っており、1993年(5年)末までのUV-B観測値は推定平年値に対して著しく大きい値は見られない。しかし、1990年のつくばにおけるオゾンとUV-Bの観測結果に基づく解析によれば、オゾン以外の条件が変わらなければオゾンの減少に伴い、UV-Bの地上到達量が増加することが確認されており、今後も引続き監視を続けていく必要がある(第4-1-18図)。
一方、オゾン層破壊の原因となっているCFC等の大気中濃度については、我が国では北半球中緯度地域(北海道、岩手県三陸町綾里)及び南極地域(南極昭和基地)等において観測が行われている。第4-1-19図に示すように、最近北半球中緯度においてCFC-11等の濃度の増加がほとんど停止しているが、依然として南極でオゾンホールが観測される以前の1970年代と比べるとかなり高い状況にある。
こうした状況を受けて、我が国では、新規規制物質の追加等を行う1992年(平成4年)のモントリオール議定書の改正等を踏まえた「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)の改正等により、オゾン層保護対策の推進のための制度の拡充強化を図る必要がある。
(8) 二酸化炭素その他の温室効果ガス
地球温暖化問題とは、人間の様々な活動に伴う排出により大気中の温室効果ガスの濃度が増加することによって、地球上の平均気温が上昇して海面水位の上昇や降水パターンの変化及び自然生態系の変化などの各種の影響が生じる問題のことである。
大気中の二酸化炭素(CO2)・メタン(CH4)・一酸化二窒素(N2O)・クロロフルオロカーボン(CFC)などの温室効果ガスは、太陽放射により暖まった地表から放射される赤外線を吸収し再び放射することにより、地表と大気を暖めて熱を宇宙に逃しにくくしている。これにより、大気と地表は温室効果ガスがない場合より暖かくなり生物の生存に適した気温が保たれているが、大気中の温室効果ガス濃度の増大は人類が今までに経験しなかったような早さで気温を上昇させると知られている。また、火山噴火によるものなど大気中のエアロゾルも放射を反射したり吸収したりすることにより気候に影響を与える。
1988年(昭和63年)に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)の共催により設置された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告書によれば、1980年代において二酸化炭素の寄与度は各種温室効果ガス全体の約55%を占めるとみられている。これは一定量当りの地球温暖化能力はメタンなどの方がかなり高いものの、二酸化炭素は排出量が膨大であるため結果として地球温暖化への寄与が大きいと考えられていることによる(第4-1-20図)。
大気中の二酸化炭素濃度は産業革命以前には280ppm程度であったが、現在では350ppmを超えており、さらに年0.5%の割合で増加していると推測されている(第4-1-21図)。産業革命以前の1000年間は温室効果ガスの総量は比較的一定であったが、世界の人口が増加して世界の産業や農業が発展するにつれて温室効果ガスの総量は著しく増加し、化石燃料の燃焼や森林の減少により大気中の二酸化炭素濃度は26%増加したとされる。なお、国内では岩手県三陸町綾里などで観測を行っており、平成5年の年平均濃度は359.3ppmであった。
こうした温室効果ガスの増加により、何も対策をとらなかった場合の地球全体の平均気温は2025年(平成37年)には現在に比べて約1度、21世紀末以前には約3度上昇し、海面水位は2030年(平成42年)には現在に比べて約20cm、21世紀末までには約65cm(最大1m)上昇するであろうと報告されている。また、こうした気候の変動に伴い、地域によっては乾燥化の進行等の懸念があることが指摘されている(第4-1-22図)。
メタンについては、100年程度のタイムスケールでみると同じ量の二酸化炭素の約21倍の温室効果を持っていると考えられ、その発生源としては、湿原や湖沼などの自然発生源と天然ガスの漏出や家畜・水田・廃棄物埋立等の人為的発生源がある。大気中のメタン濃度は、過去3000年間の古大気の分析によると250年前まではほぼ一定であったが、この200年ほどの間に2倍以上に増加しているものと推測されている。国内では岩手県三陸町綾里で観測を行っており、平成5年の年平均濃度は1.82ppmであった。また、シベリア上空の大気中のメタン濃度は高濃度で観測されており、シベリアの湿地がメタンの大規模な貯蔵地域となっているなどの点が注目されている。
一酸化二窒素は、メタンと同じく100年程度のタイムスケールで見ると同じ量であれば二酸化炭素の約290倍の温室効果を持っていると考えられており、自然発生源である海洋や土壤などのほか、人為的発生源である化石燃料や薪等のバイオマスの燃焼・施肥農地などがある。一酸化二窒素は大気中の寿命が150年程度と長いことが分かっているものの、地球規模での動態などには不明な点も多い。IPCC報告書によると平成2年(1990年)の一酸化二窒素の平均濃度は約310ppb(ppmの千分の一)であり、国内の岩手県三陸町綾里での観測では、5年の年平均濃度は308ppbであった。
対流圏オゾンは二酸化炭素に比較してかなりの温室効果を持つと考えられ、自動車や工場などから排出される窒素酸化物や非メタン炭化水素が光化学反応を起こして生成されることが知られているが、現在の観測からその変化を定量化するのは難しく、今後科学的知見を蓄積していく必要がある。また、二酸化炭素やメタンのようにそれ自身が地球からの赤外放射に対して直接的に温室効果がある気体ばかりでなく、温室効果気体の寿命に影響を与えたり、対流圏オゾンや硫酸エアロゾル等の温室効果物質を生成することにより間接的に大気の温室効果の大きさを支配している気体も地球の温暖化に大きな役割を果たしている可能性がある。
我が国では、第3章第1節で見たように「地球温暖化防止行動計画」に基づき各種の対策が進められているところである。また、温暖化防止のための国際的取組として、1992年(平成4年)5月に「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、同条約は1994年(6年)3月21日に発効した。
(9) 酸性雨
酸性雨とは、工場や自動車など人類による化石燃料の大量使用から排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で硫酸・硝酸等へ変化し、それぞれがイオンとして雨に取り込まれて降下するpH5.6以下の降雨のことであり、酸性を示す降雨は大気の状態により酸性雪及び酸性霧となることもある。酸性雨は、欧米等において早くから森林や湖沼などの生態系への影響や文化財等の人工物への被害を与え、地球規模の環境問題の1つとして国際的に関心を集めているところである。
こうした酸性雨による影響は、ヨーロッパを始め北米・中国等世界的な規模で発生しており、湖沼のpHの低下を招いて湖底から有害な金属を溶出させて魚を死滅させるなど生態系を破壊し、湖沼を「死の湖」と化す。例えば、スウェーデンの約4,500の湖沼やノルウェーの約2,650の湖沼では魚が死滅し、カナダの約4,000の湖沼は死の湖と化している。アメリカのロッキー山脈地帯などの湖沼の3分の2以上は酸性化するおそれがあるとされ、日本でも酸性雨の影響を受けやすいと考えられる湖沼があることが分かっている。
森林への影響はドイツのシュバルツバルト(黒い森)やアルプスに代表されるヨーロッパに多く、中国の四川省の我眉山では冷杉が衰退して87%が被害を受けている(第4-1-23図)。森林の被害は必ずしも酸性雨のみによって生じるものではなく、硫黄酸化物・窒素酸化物・オゾンなどの大気汚染物質等が複合的に作用していると考えられている。このほか、アテネのパルテノン神殿やローマの遺跡など貴重な文化財に影響が出ているといわれている。
我が国では酸性雨の現状と影響を調査するため、昭和58年度から62年度までの第1次酸性雨対策調査と63年度から平成4年度までの第2次酸性雨対策調査を実施した。第2次の調査結果によると、降水のpHについては第1次の調査と比較しても顕著な変動はみられないものの、降雨のpHの年平均値は4.5〜5.8の範囲内であり、また、欧米とほぼ同程度の酸性降下物が観測されている(第4-1-24図)。また、平成5年度には14か所の国設酸性雨測定所を整備し、酸性雨モニタリング体制の整備・充実が図られた。現在のような酸性雨が今後も降り続けるとすれば、将来、生態系への影響を及ぼすことも懸念されるが、酸性雨による陸水、土壤・植生等に対する長期的影響については未解明な点も多く、さらなる調査・研究や監視が必要であり、5年度から第3次酸性雨対策調査を実施している。
こうした酸性雨問題は、大気を経由し国境を越えて移送される酸性物質が他国に大きな被害を与えるように多国間にまたがる広域的な環境問題でもあり、欧州及び北米では先に見たように「長距離越境大気汚染条約(ウィーン条約)」に基づくモニタリングネットワークが実施されている。また、東アジア地域特に中国においては化石燃料の使用量が著しく増加しており、将来酸性雨による影響が懸念されるようになってきたため、我が国では平成5年(1993年)10月に東アジア諸国での第1回専門家会合を行うなど、東アジア酸性雨モニタリングネットワークの構想の策定を進めている。