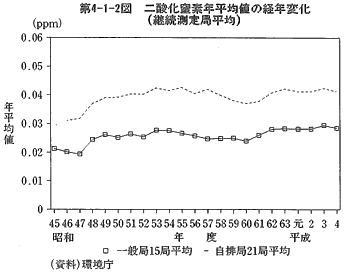
1 大気環境の現状
大都市地域では、自動車交通量やディーゼル車の増加を背景に窒素酸化物による大気汚染の改善がはかばかしくない。また、浮遊粒子状物質(SPM)と光化学オキシダントについても依然として改善が進んでいない。さらに、新たな有害大気汚染物質による汚染の可能性が懸念される。
環境への負荷について見ると、かつては生産活動に起因する負荷が特に著しかったが、今日では交通に起因する負荷が重要となっている。
このため、生産活動に係る環境保全対策とともに、交通に係る環境保全対策を総合的に推進する必要がある。窒素酸化物については、自動車NOx法が平成5年12月から全面施行されており、同法に基づく諸施策のほか、平成元年中公審答申に沿った自動車単体規制の強化、各種の助成措置等による低公害車の普及促進を進めている。また、自動車交通騒音については、総合的な対策のあり方について中央環境審議会で審議が行われている。
また、SPMと光化学オキシダントについては、これまでの対策に加えて総合的な対策を策定するため、汚染機構等に係る調査・検討を進めている。特にSPMの中でも寄与割合が大きいディーゼル排気微粒子(DEP)については自動車排出ガス規制を強化し、粒子状物質全体に対する規制を導入したところであり、今後とも平成元年の中公審答申に沿い、一層の規制強化を行うこととしている。
新たな有害大気汚染物質については、トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンについて「大気環境指針」を策定するとともに、「暫定対策ガイドライン」を取りまとめ、汚染状況を調査している。さらに、多種多様な物質に対する体系的・総合的な取組を行う必要があるため、健康影響や環境濃度の把握などの調査を総合的に進めている。
(1) 窒素酸化物
一酸化窒素(NO)・二酸化窒素(NO2)などの窒素酸化物(NOx)は物の燃焼一般にともなって発生し、その発生源としては工場のボイラーなどの固定発生源と自動車などの移動発生源がある。二酸化窒素は高濃度で呼吸器に好ましくない影響を及ぼすほか、窒素酸化物は酸性雨及び光化学大気汚染の原因物質となる。
我が国では、窒素酸化物のうち二酸化窒素について対策の目標となる環境中の汚染物質濃度を示す環境基準(人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準)を「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること」(ppmは体積百万分率)と定めている。
平成4年度における二酸化窒素の濃度については、一般的な大気汚染状況を把握するために設置された一般環境大気測定局(以下、「一般局」と言う。)のうち昭和45年度以降の継続測定局15局における年平均値で0.028ppm、道路周辺における状況を把握するために沿道に設置された自動車排出ガス測定局(以下、「自排局」と言う。)のうち昭和46年度以降の継続測定局21局では同じく0.041ppmであり、これらは3年度と比べてほぼ横ばいであった(第4-1-2図)。また、昭和53年に基準値が改定された二酸化窒素の環境基準の達成期限は原則として60年であったが、平成4年度においても大都市を中心に環境基準の達成率は依然低い水準で推移している。
全国の環境基準達成状況をみると、全国の有効測定局(年間6,000時間以上測定を行った測定局)のうち環境基準のゾーンの上限である0.06ppmを超えた環境基準非達成局の割合は、一般局では平成3年度の5.9%(1,378局中81局)が4年度では2.6%(1,406局中37局)、自排局では37.2%(325局中121局)が28.6%(336局中96局)といずれも減少している(第4-1-3図)。また、工場等の固定発生源について総量規制制度が導入されている3地域(東京都特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域)における環境基準達成状況をみると、非達成局の割合は一般局では3年度の52.7%(112局中59局)が4年度では29.7%(118局中35局)、自排局では93.1%(72局中67局)が73.6%(72局中53局)といずれも減少している。後述の自動車NOx法の特定地域の環境基準達成状況では、環境基準非達成局数は一般局では3年度の26.6%(305局中81局)が11.5%(313局中36局)、自排局では3年度の72.0%(150局中108局)が53.9%(152局中82局)といずれの局においても減少している。全測定局(一般局と自排局)でも3年度の41.5%(455局中189局)が25.4%(465局中118局)となっている。
このため、工場や個々の自動車などの発生源に対する各種の規制、汚染の著しい地域に限った工場・事業場の総排出量の規制、排出量の削減に資する各種の事業など、諸外国に先駆けた強力な対策を行っている。排出規制については、工場などの固定発生源に対して窒素酸化物を排出する施設の種類及び規模ごとに排出基準を設定し規制が行われている。さらに、工場などが集合し排出規制のみでは環境基準達成が困難と認められる3地域(東京都特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域)について工場ごとに許容排出量を割り当てる総量規制が行われている。
一方、自動車から排出される窒素酸化物については、平成4年6月に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)」が制定され、自動車の交通が集中してこれまでの措置では環境基準の達成が困難な地域(首都圏及び大阪・兵庫圏の特定地域)を特定地域に指定している。特定地域では国が策定した総量削減基本方針に基づき、関係都府県知事により、総量削減計画が策定され、自動車から排出される窒素酸化物の総量の削減を図っていくこととしている。
そのほか、特定地域内を使用の本拠とする自動車について特定自動車排出基準を定め、より窒素酸化物の排出量の少ない車種への代替を促す使用車種規制を行うとともに、各事業を所管する大臣から事業者に対して自動車使用の合理化等に係る指針が定められ、それに基づく指導等が実施されている。
諸外国についてみると、先進国主要各都市の窒素酸化物による大気汚染はフランスのダンケルク、オランダのアムステルダム、イギリスのロンドンで1985年(昭和60年)以降1990年代にかけて若干悪化しており、依然として窒素酸化物の汚染防止対策が進んでいないことが分かる(第4-1-4図)。
(2) 二酸化硫黄
二酸化硫黄(SO2)は、硫黄分を含む石油や石炭等が燃焼することにより生じるが、呼吸器に悪影響を及ぼし、四日市ぜんそくなどのいわゆる公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼などに影響を与えると言われている酸性雨の原因物質ともなる。
我が国では、二酸化硫黄についての環境基準を「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること」と設定している。平成4年度における二酸化硫黄の濃度は、一般局のうち昭和40年度以降の継続測定局15局における年平均値で0.009ppm、自排局のうち48年度以降の継続測定局16局では同0.009ppmとさらに改善されている。また、環境基準の達成率は、一般局では3年度の99.7%(5局で非達成)が4年度で99.6%(6局で非達成)、自排局では98.6%(1局で非達成)が98.7%(1局で非達成)であった。
二酸化硫黄による大気汚染は経済の高度成長下における化石燃料の大量消費により急速に拡大したため、昭和44年2月にはじめて環境基準を設定し、燃料中の硫黄分の規制、ばい煙発生施設ごとの排出規制(K値規制)及び全国24地域における工場ごとの総量規制の実施・強化など環境基準の達成に向けた様々な対策が行われてきた。こうした硫黄酸化物低減対策を受け、企業等による低硫黄原油の輸入の増加と重油の脱硫などの燃料の低硫黄化及び排煙脱硫装置の設置等の諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度(一般局)は昭和42年度のピーク値0.059ppm以降年々減少し、61年度には0.010ppmと著しい改善をみた(第4-1-5図)。
諸外国では、二酸化硫黄の排出量削減の効果により西ベルリン・アムステルダムなどの先進国主要各都市で1985年(昭和60年)以降大幅な改善がみられるものの、一部の都市では汚染状況が悪化している(第4-1-6図)。また、1993年(平成5年)の国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の報告によると、世界保健機構(WHO)の二酸化硫黄濃度の大気質ガイドライン(150μg/cubic meter)を超えた1年間の日数は、先進国に比べ開発途上国では多く、特に、中国・イラン・韓国の各都市では汚染が激しくなっている。地球モニタリングシステムによると世界の都市の約3分の2の住民がWHOの定めた環境SO2濃度の規制値を超える都市に住んでいる(第4-1-7図)。
(3) 浮遊粒子状物質等
大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉じん・エアロゾルなど)のうち粒径が10ミクロン以下のものを浮遊粒子状物質(SuspendedParticulate Matter、SPM)と呼ぶ。浮遊粒子状物質は微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響がある。その発生源は、工場などから物の燃焼等に伴い排出されるばい煙中のばいじんやディーゼル自動車排出ガスに含まれる黒煙などの人為発生源によるものと、土壤の飛散や巻き上げなどの自然発生源によるものがあり、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と硫黄酸化物・窒素酸化物などのガス状物質として放出されたものが大気中で粒子状物質に変化した二次粒子とがある。
我が国では環境基準を「1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下であること。」と昭和47年1月に定めており、環境基準達成に向けて工場・事業場からのばいじん・粉じんや自動車からの黒煙の排出規制などが行われている。
平成4年度における浮遊粒子状物質の濃度は、一般局のうち昭和49年度以降の継続測定局39局における年平均値で0.038mg/m
3
、自排局のうち50年度以降の継続測定局6局では同0.048mg/m
3
であった(第4-1-8図)。環境基準の達成率は、一般局では平成3年度の49.7%(1,348局中670局)が57.6%(1,408局中597局)、自排局では30.1%(166局中50局)が33.5%(182局中61局)といずれの局においても増加したものの、依然低い水準で推移している。
大気中のすす・粉じん(物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積にともない飛散する物質)などの粒子状物質のうち、主として比較的粒子の大きい沈降しやすい粒子は降下ばいじんと呼ばれ、平成4年度における状況は長期間継続して測定を実施している測定点(16測定点)における年平均値の平均で3.5トン/km
2
/月と3年度の3.5トン/km
2
/月に比べて横ばいとなっている。
スパイクタイヤ粉じんに係る降下ばいじんについては、昭和50年代初期頃から、北海道・東北・北陸などの積雪・寒冷地域に普及したスパイクタイヤにより都市部を中心に道路が削られて発生する粉じんが身体・衣服・洗濯物の汚れや不快感をもたらすなどの大きな社会問題となったが、環境庁では、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」に基づきスパイクタイヤの使用が禁止される地域の指定を平成6年3月までに実施しており、指定が必要な市町村の98%以上の指定を終了している。札幌市や盛岡市などの各都市においては、第4-1-9図に見られるように降下ばいじん量は著しい改善を示している。また、国設測定局では浮遊粉じん中の硝酸イオンや硫酸イオンなどの成分測定を行っており、これらの測定結果においては際だった変化は見られていない(第4-1-10図)。
SPMの発生源は多様であるが、その2〜4割を占めるディーゼル排気微粒子(DEP)は、健康影響の面から特に注目されている。DEPについては、ヒトに対する発がん性や気管支ぜん息・花粉症等のアレルギー性疾患等の健康影響との関連性が懸念されるため、現在その研究・調査が進められている。
環境庁では、従来よりDEP対策として黒煙の自動車単体規制を実施してきたところであるが、平成5年度から黒煙に加え粒子状物質排出量全体の規制を開始しており、また粒子状物質排出量をさらに6割以上削減することを求める長期目標に対し、早期達成に向けてディーゼル車から排出される粒子状物質について総合的な低減施策を検討していくこととしている。
諸外国をみると、先進国主要各都市の浮遊粒子状物質の濃度は1985年(昭和60年)以降OECD諸国のほとんどの各都市で減少している(第4-1-11図)。また、1993年(平成5年)の国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の報告によると世界保健機構(WHO)の浮遊粒子状物質の大気質ガイドライン(230μg/cubic meter)を超えた1年間の日数は中国・インド・インドネシア・イランなどの各都市では際だって多く、開発途上国の大都市における汚染状況が依然深刻な状況にあることが分かる。地球環境モニタリングシステム(GEMS)によると1987年(昭和62年)には世界の都市人口の7割がWHOのガイドラインよりも高い粒子状物質レベルの都市に暮らしていると報告されている(第4-1-12図)。
(4) 光化学オキシダントと非メタン炭化水素
光化学オキシダントは、窒素酸化物(NOx)と炭化水素類(HCs)とが太陽光の作用により反応(光化学反応)して二次的に生成されるオゾンなどの強い酸化力を持った物質である。光化学オキシダントは、いわゆる光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響など人間の健康に悪影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。また、オゾンは二酸化炭素よりもはるかに強力な温室効果を持っていると考えられている。
光化学オキシダントについては、昭和48年5月に環境基準が「1時間値が0.06ppm以下であること」と設定されており、「光化学オキシダント濃度が1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合」に光化学オキシダント注意報を発令し、屋外での運動を避けるなど健康障害の未然防止ための各種措置を講じることとなっている。平成4年度の注意報レベル以上の濃度が出現した1局当りの平均日数についてみると、一般局では3年度の1.6日が1.7日、自排局では0.2日が0.5日といずれの局においても増加しており(第4-1-13図)、首都圏地域及び近畿圏地域に多く出現しているなど依然として厳しい状況で推移している。
炭化水素類において光化学オキダントの原因となるのは光化学反応性の乏しいメタンを除いた大気中の非メタン炭化水素(NMHC)であり、非メタン炭化水素の濃度は、一般局で昭和53年度以降の継続測定局(6局)での午前6時〜9時における年平均値の単純平均値は近年横ばいで推移してきたが、平成4年度は0.49ppmCで3年度の0.53ppmCに比べ減少しており、自排局では52年度以降の継続測定局(9局)での午前6時〜9時における年平均値の単純平均値は4年度は0.046ppmCと3年度の0.51ppmCに比べ同じく減少している。
非メタン炭化水素については、環境基準は設けられておらず、光化学スモッグの発生を防止するための濃度の指針(午前6時〜9時の3時間平均値が0.20ppmC〜0.31ppmC、ppmCとは各種の炭化水素に含まれる炭素量で換算した濃度)を定めており、二酸化窒素と同様に自動車から排出されるほか、炭化水素類を成分とする溶剤を使用する塗装・印刷等の工場・事業所からも排出されるため、自動車に対する排出規制や排出抑制に向けた工場等への指導等が行われ、指針を確保するよう各種の対策を実施している。
(5) 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素(CO)は燃料の不完全燃焼により生じるもので、主として自動車がその発生源と考えられる。一酸化炭素は血液中のヘモクロビンと結合して酸素を運搬する機能を阻害するなど人の健康に影響を与えるほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。
我が国では、昭和45年2月に環境基準を「1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること」と設定するとともに、自動車の排出ガスの規制を行っている。
平成4年度における濃度は一般局のうち昭和46年度以降の継続測定局5局における年平均値で0.66ppm、自排局のうち46年度以降の継続測定局14局では同じく2.0ppmであり、40年代後半から50年代後半にかけて大幅に改善した後はほぼ横ばいで推移している(第4-1-14図)。また、環境基準の達成率は一般局・自排局ともに3年度に引き続き全局(534局)で達成している。
(6) その他の大気汚染物質
カドミウムや塩素など大気汚染防止法で有害物質として規制されている物質については、発生源の工場や事業場に対し排出基準を設けて排出規制などの様々な対策を実施している。一方、未規制の大気汚染物質については直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではなくても将来的には問題となることが懸念され、その濃度の推移を把握していく必要があるため、環境庁では未規制大気汚染物質モニタリング調査を昭和60年度から実施している。平成2年度と4年度ではホルムアルデヒド・ダイオキシン類について実施し、5年度では3年度と同様に石綿(アスベスト)・水銀・有機塩素化合物(トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン等)について実施している(第4-1-1表)。
平成4年度の調査結果では、フェノール樹脂・防かび剤・殺菌剤等を用途とする無色の可燃性の刺激性気体であるホルムアルデヒド及び化学物質の合成過程・燃焼過程などで非意図的に生成されて毒性をもつダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾ−p−ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF))の一般的な環境における濃度レベルは特に問題となるレベルではないが、今後とも引続きモニタリングを実施するとともに各種発生源からの実態把握等に努めるなどの汚染の未然防止のために必要な調査を推進していくこととしている。
化学物質はその用途・種類が多種多様であり、現在工業的に生産されているだけでも数万点に及ぶといわれ、これらの化学物質の環境安全性を点検するため、環境調査を行うべき物質を計画的に選定して各種調査を行っている。一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした大気に関する平成4年度の化学物質環境調査では調査対象8物質のうち2物質が大気から検出されたが、検出頻度はいずれも低く特に新たな問題点を示唆するものではないと考えられる。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく指定化学物質及び第2種特定化学物質計9物質について環境残留性の調査を実施しており、うち6物質については日常生活において人がさらされている媒体別の化学物質量に関する暴露経路調査を実施しているが、これまでの調査結果と比較して汚染状況に大きな変化は認められなかった。
有機塩素系溶剤等の有害大気汚染物質については、一般環境におけるモニタリング調査によれば直ちに問題となるレベルではないが、健康影響の懸念から注目されている。金属脱脂洗浄剤・溶剤等を用途とするトリクロロエチレン及びドライクリーニング溶剤・金属脱脂洗浄剤・フロンの原料等を用途とするテトラクロロエチレンについては、我が国の大気において低濃度ながら広い範囲で検出されているほか、環境庁が行った未規制大気汚染物質規制基準検討調査等によると、その発生源の周辺では局所的ではあるものの比較的高い濃度が検出される事例があることが判明している。環境庁では、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについて人の健康を保護する上で維持されることが望ましい指針として大気環境指針(暫定値)を平成5年4月に定め、また、その2物質の大気中への排出に係る暫定対策ガイドラインについて取りまとめて都道府県知事・政令指定都市市長に対して実態の把握・濃度測定・排出の抑制等を要請している。
諸外国では、アメリカで大気清浄法が1990年(平成2年)11月に改正され、有害物質を現行の9物質から189物質へと大幅に拡大するなど規制の強化が図られているほか、各国際機関においても化学物質のリスク評価及びリスク削減の取り組みが行われてきている。環境庁としては、未規制の有害大気汚染物質に関して国際的な取り組みの動向にも留意しつつ、優先的に取り組むべき物質について健康影響及び発生源に係る情報の収集・モニタリング事業の充実などの取り組みの拡充・強化に努めることとしている。