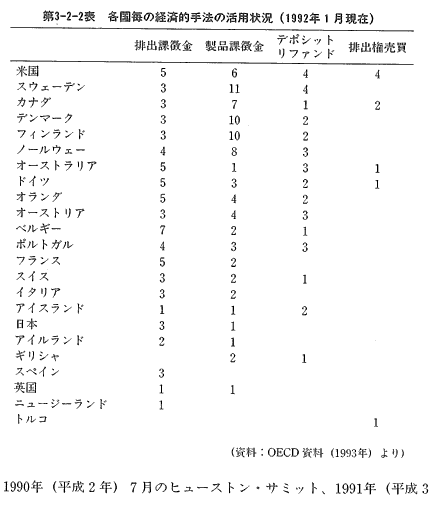
2 経済的手法
(1) 経済的手法を巡る内外の状況
今日、生産・消費・廃棄を通じた人の社会経済活動は、われわれを取り巻く環境に大きな負荷を与えている。特に、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題は、将来世代を含めた人類の生存基盤を脅かしつつある。このような問題が生じた大きな要因は、人間の活動に伴う環境への負荷に係る費用が把握困難であり、経済の中に適切に内部化されてこなかったために、いわば社会的なコストが生じたままこれらの活動が続けられてきたことなどがあげられる。このため、環境への負荷活動を行う者に対し、市場メカニズムの活用を通じて、政策的に適正かつ公平な経済的負担を課すことによりその者が自らその負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるよう誘導すること、あるいは負荷活動を行う者に対し、必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずることによりその者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長すること等の新たな施策の導入が必要であるとの認識が世界的に広まってきている。環境問題の多様化・グローバル化を背景に、従来の規制的手法等に限界があるとの認識の下、新たな対策手法として注目されてきたのが経済的手法であるといえよう。
経済的手法は直接規制に比較して以下の長所を有すると言われている。まず、第一に、広範な主体を対象とする二酸化炭素等の排出を削減する場合、規制的手段では、個別企業や産業に対する適切な削減量の割当を定めることが困難であり、結果的に過大な削減コストを招来しがちである。これに対し、経済的手法は、市場のメカニズムを通じて、それぞれの主体が最も経済的な行動を自主的に選択することにより、少ないコストで最適な努力の配分がなされる可能性がある。第二に、規制的手段では、規制値を超える汚染量削減に対するインセンティブが欠如するが、経済的手法は、汚染量の削減が経済的な利益に結びつくため継続的なインセンティブ効果がある場合がある。また、近年の規制緩和の動きの中で、各種の規制は必要最小限度の規制内容とし、その透明な運用を行うことが望ましいとの指摘がある。この根底には自己責任原則を重視した社会の構築という考え方が存在するものと考えられるが、経済的手法は各主体に対し費用と便益に基づく自主的な判断を求めることになるため、直接規制に比べ、より自己責任型社会の形成にも資するものといえよう。なお、そのような自己責任型社会が環境負荷の低減に役立つか否かについては、国民意識の中に環境負荷の低減が主要な行動基準となっている必要がある。
次に、経済的手法を巡る国際的な動向を見てみよう。近年、環境税あるいは課徴金をはじめとする経済的手法の導入の議論が高まりを見せており、既に多くの国々で課徴金等の活用が見られる。(第3-2-2表)
1990年(平成2年)7月のヒューストン・サミット、1991年(平成3年)7月のロンドン・サミット、あるいは1992年(平成4年)7月のミュンヘン・サミット等の国際政治の場において、経済的手法は、地球環境保全のための重要な環境政策手段として位置付けられた。
OECDでは、1991年(平成3年)1月の環境委員会閣僚会議において、環境政策と経済政策の統合を軸とした基本的な方向が合意され、さらに、加盟各国が経済的手法をより効率的に、かつより広範囲に活用できるように「環境政策における経済的手法の利用に関するOECD理事会勧告」を採択、承認した。この中で、経済的手法を、?課徴金及び税、?排出権の市場での売買、?デポジット(預り金)制度及び?資金援助(補助金等)を挙げ、各国の社会経済的状況を考慮しつつ利用することを勧告した。その後、OECDの「税制と環境に関する作業部会」は、1993年(平成5年)3月に環境税の導入に当たっての様々な論点を整理し、問題点への対応策を示す内容の報告書を公表した。一方、EC委員会においては、燃料の炭素分とエネルギー分とに着目した炭素・エネルギー税(car-bon/energytax)の導入に関するEC指令案がEC委員会で1992年(平成4年)5月に採択され、現在、理事会で審査が継続されている。
スウェーデン、ノールウェー、フィンランド、デンマークの北欧諸国やオランダでは、地球温暖化の主因となっている二酸化炭素の削減を目的とした炭素税をはじめとする各種の環境税等を1990年代に導入している。なお、導入後、産業・エネルギー分野の税率変更や減免措置の導入など試行錯誤を繰り返している。米国では、1993年(平成5年)の一般教書において、英国熱量単位(BTU)に応じた広範囲なエネルギー税の創設を提案していたが、最終的には、BTU税の導入には至らずガソリン1ガロンにつき4.3セント(1lにつき約1セント)の輸送燃料税の引き上げにとどまった。また、地球サミットで採択されたリオ宣言の原則16では、「各国当局は、汚染者負担原則を考慮にいれつつ、公益に対し適切な考慮を払い、かつ、国際貿易や国際投資を歪曲することなく、環境コストの内部化及び経済的措置の利用を促進するよう努力しなければならない」としている。
一方、我が国においては、中央公害対策審議会及び自然環境保全審議会の答申(平成4年10月20日、「環境基本法制のあり方について」)で、今日の環境問題への対処に関して以下のような認識が示された。「国、地方公共団体、事業者及び国民すべての主体が自主的、積極的に取り組む必要があり、あらゆる経済社会活動に環境への配慮を組込んでいくことが重要である。経済社会活動に環境配慮を組み込むに当たっては、汚染物質の排出規制等の規制的手法や各種の経済的手法の活用、環境影響評価の活用、所要の社会資本の整備、事業者や国民の積極的取組への支援等多様な手法が考えられる。」
また、政府税制調査会は、平成5年11月「今後の税制のあり方についての答申」(−「公正で活力ある高齢化社会」を目指して−)を細川総理に提出した。その中で、環境関連税制については、国内外の動向・議論を踏まえ、「環境問題に係る税制についての議論を大別すると、?環境汚染抑制のための「経済的手法」としての税制の活用の側面と、?国内外の環境対策のため「財源調達手段」としての税制の活用の側面の二つの議論がなされているところであるが、いずれにせよ、環境問題に係る税制については、国内外での議論の進展を注視しつつ、更に調査及び研究を進めていく必要がある。」ことを指摘している。
さらに、OECD環境保全成果審査(Environmental Performance Review)においても適切な調査と相談を行った上で経済的手法を一層活用することが望ましい旨指摘されている。
現在、我が国においては、経済的手法の活用としては国レベルでは、航空機騒音に係る賦課金制度などが、また、地方レベルでの取組として廃棄物収集の有料化などの事例がある。
このような状況の中で、平成5年11月に制定された環境基本法では、その第22条に必要かつ適正な経済的助成措置を環境の保全上の支障を防止するための経済的措置の一つとして位置付けるとともに、新たに、経済的負担措置について規定している。経済的負担措置については、まず、このような施策が、有効性を期待され、国際的にも推奨されているという認識を明らかにしている。次に、税、課徴金、デポジットなどの個別の措置が国民に負担を与えるものであることから、その措置の効果、経済に与える影響等を適切に調査し及び研究する必要があるとしている。そして、そうした調査・研究を踏まえ、個別の措置の必要がある時には、経済的な負担を課す施策を活用して環境の保全上の支障を防止することについて、国民の理解と協力を得るように努めるとしている。さらに、その措置が地球環境保全のためのものである時は、その効果が適切に確保されるようにするため、国際的な連携に配慮して行うとしている。
以上のような基本法の趣旨に沿って、今後とも、内外の研究成果や実例等を参考に調査研究を行っていくことが必要である。
(2) 世界の経済的手法活用の現状
経済的手法には、先にも見たようにOECDの整理によれば、?課徴金及び税、?排出権の市場での売買、?デポジット(預り金)制度及び?資金援助(補助金等)が挙げられている。ここでは、OECDによる調査等をもとに、課徴金及び税、排出権売買、デポジット(預り金)制度及び資金援助(補助金等)についてその内容及び諸外国における導入例について見てみたい。
ア 税・課徴金
環境へ直接・間接に悪影響を与えるもの、環境汚染物質の排出を削減する狙いを持つ多様な税を環境税と総称することがある。諸外国において環境税に関連する税制としては、例えばCO2の排出を抑制するための炭素税、より硫黄分の少ない燃料に転換することをめざした硫黄税、廃棄物処理費用を汚染者に負担させ、再利用システムの確立を狙った使い捨て飲料容器に対する税など各種の税が存在する。
また、課徴金にも、様々な形態がある。まず、不用物を排出する際にその排出量や質に応じた金員を徴収することにより、環境への負荷をもたらす不用物の排出を抑制しようとする排出課徴金がある。また、不用物処理のための公共の施設又はサービスを利用する際に、その利用に応じて金員を徴収するユーザー課徴金、廃棄物の最終処分を行う際に、その量や質に応じた金員を徴収する最終処分課徴金がある。さらに、製品の生産、輸入等に際し、その量や質に応じた金員を徴収することにより消費後の不用物の発生が少ない製品を優遇する製品課徴金、再生資源以外の原材料の使用、採取、輸入等に際し、その量や質に応じた金員を徴収する天然資源課徴金がある。
? 水質保全
まず、水質保全の分野は、OECD諸国で従来から経済的手法が比較的重要な役割を演じてきた数少ない環境政策の分野である。排水の処理等のための課徴金制度はほとんどのOECD諸国において採用されている。公有水面に排水を直接排出する者に課徴金を課す例も見られる。特に(生物)化学酸素要求量に関わる分野で直接規制と経済的手法を組み合わせることによって成果が得られている。また窒素、重金属及び他の有害物質が多くの国々で共通の課題となっている。水質汚濁に係る課徴金の目的は、排水の収集と処理に必要な施策に係る費用を賄うためである場合と、排水からの汚濁負荷の低減のための経済的なインセンティブを与える場合であることがある。
フランスでは、1964年(昭和39年)の「水質汚濁防止法」に基づいて各種の排水行為が規制されている。全国を6区域に区分し、各流域では、流域委員会及び流域財政公社を設立することを定めるとともに、一定の場合に、各流域の財政公社は、排水課徴金を徴収し、その収入を水質汚濁防止対策に支出することができるとしている。賦課ベースは、個々の事業者から排出される汚染物質の種類毎に決められる料率と排出汚染物質量の積とされており、料率の算定根拠は、外部不経済をなくす対策に要する費用に置かれている。また、ドイツの排水課徴金は、排水の水質改善のインセンティブを与えることを目的として1976年(昭和51年)に導入された。連邦により課徴金制度が営まれ、課徴金の対象となるのは、CODや重金属である。企業が排出源において基準を満たすものであることを証明した際には、課徴金の料率が最大75%まで引き下げられる。オランダでは、排水課徴金の額は水質の改善及び下水処理に必要となる歳入額により決定される。課徴金制度の実施主体は、独立の機関である水質委員会である。BODと多くの場合重金属を対象としている。直接、間接を問わず課されている。家計と小企業は定額を支払う。また、大企業に対して実際に排水抑制効果がみられるとされている。(第3-2-3表)
? 大気保全
大気保全の分野では、伝統的に規制的手法が主要な役割を担ってきたが、経済的手法は規制的手法の補完としても機能する。多くの国々では、主として財源調達目的ではあるが、様々な形態の燃料課徴金が適用されてきている。最近では、特に製品やエネルギー使用による大気汚染を対象としてより広範な経済的手法を導入することが考えられている。スウェーデンでは、1995年(平成7年)の窒素酸化物の新たな排出ガイドラインの早期達成を目的として、1992年(平成4年)より窒素酸化物排出課徴金制度が導入された。ボイラー等の固定発生源からの窒素酸化物の排出を抑制するため、10MW以上の投入により50GWh以上のエネルギーを生産する者に課せられ、スウェーデンの総窒素酸化物排出量の6.5%が対象となる。1992年(平成4年)には、20-25%の削減を予想していたが、実際には予測を大きく上回る30-40%の削減が達成された。フランスでは、1980年(昭和55年)に大気汚染の監視や大気汚染防除技術の開発等を目的とする「大気質公社」が設立され、同公社の事業のために、政府に対して特別課徴金を設ける権限が与えられた。課徴金の使途は、賦課対象事業者を含む委員会によって決められるが、全体の75%が賦課対象者における大気汚染防止施設の設置にあたっての補助及び大気汚染対策技術の研究開発に、残りの25%は大気汚染監視網の整備等に充てられている。1985年からの5年間の補助により、フランス全土の硫黄酸化物総排出量比で約8%にあたる量の硫黄酸化物が削減されたといわれる。(第3-2-4表)
? 廃棄物
OECDでは、廃棄物に係る課徴金等を、?廃棄物の収集及び処理に係る費用を賄う使用者課徴金、?廃棄物処理税、?有害廃棄物の処理に係る費用を賄う有害廃棄物課徴金に分類して調査している。英国では、廃棄物の収集及び処分は、地方税で賄われている。また、フィンランドのいくつかの自治体では、家庭及び事業場からの廃棄物の収集は民営化されている。スウェーデンにおいては、廃棄物となる乾電池の対策として、水銀とカドミニウムの合計含有量が重量の0.025%を越える乾電池に対して1987年(昭和62年)より課徴金が課されている。アルカリ電池、水銀電池の課徴金による収入は、全額、電池の回収費用、最終処分費用、広報費用に充てられている。また、使用後の容器・包装材といった廃棄物の減量化を目的とした課税が多くの国々で見られる。イタリアでは、1983年から1988年にかけてプラスチックの買い物袋の消費が37%増加したが、1988年にこれに課税したところ、その消費量が20-30%減少している。(第3-2-5表、第3-2-6表)
? 騒音
経済的手法は、騒音の分野ではより効果的な機能が発揮できるものと考えられるが、航空機の分野を除きほとんど適用されていない。OECDによる経済的手法の活用に関するガイドライン(1991年(平成3年))では、騒音に関する政策の進展は遅々としており、経済的手法の適用状況も芳しくないとされた。諸外国においても、航空機の重量及び騒音レベルに応じた着陸料を課している例がある。ノールウェーでは、2つの空港において、騒音レベルに応じた課徴金制度を実施しており、歳入はノールウェー民間航空機関に属するとされる。また、ドイツのように、航空機に対する課徴金の額がその騒音レベルに応じて著しく差別化されており、結果的に比較的低騒音の航空機が増加したという例も見られる。(第3-2-7表)
? 運輸部門
運輸部門では、これまで、環境に負荷を与える行為に対して、規制的手法と許認可による対応が主たるものであり、環境保全を目的とした経済的手法はそれほど活用されていない。OECDのガイドラインによれば、政府が環境保全に係る費用の内部化などを十分に考慮せずに地域、産業、社会その他の政策目的を達成しようとすると環境への負荷が発生するとされた。スウェーデンでは、1989年(平成元年)より航空機からの排気ガスの減少を目的として、国内航空機に対して環境税を課している。これにより、航空機の燃焼室の交換が進み、炭化水素の排出量が90%減少したとの報告がなされている。(第3-2-8表)
? エネルギー部門
エネルギーの分野では、これまでにも、エネルギー税、優遇措置、補助金などの適用例が見られる。
EC委員会においては、1991年(平成3年)9月、燃料の炭素分とエネルギー分とに着目した炭素・エネルギー税(carbon/energytax)を提案した。その後、具体的な検討を経て、1992年(平成4年)5月にこの新税(炭素税分50%、エネルギー分50%)導入に関するEC指令案がEC委員会で採択されたものの依然として理事会では合意できない状況である。また、米国ではBTU税の導入に至らず、輸送燃料税の引き上げにとどまった。
スウェーデン、ノールウェー、フィンランド、デンマークの北欧諸国やオランダでは、地球温暖化の主因となっているCO2の削減を目的とした炭素税をはじめとする各種の環境税等を1990年代に導入している。
? 農業部門
農業分野では、健康に影響のある農薬の使用禁止などを除いて規制が難しいとされ、また、これまで環境保全目的を明らかにした経済的手法の活用は限られていた。OECDのガイドラインでは、従来の政策が長い間に農産物の価格を歪め、過剰生産に加え環境に負荷を与えるような土地の過剰利用、汚染源となる化学品の過度な使用、そして個別農場のみならず地域全体に及ぶ特定作物への特化をもたらしたとしている。OECDによれば、多くの国が、汚染者負担の原則の考え方を農業セクターに適用することに注目しつつも、汚染者及び汚染行為の特定、モニタリングと管理の費用問題などによりその適用が困難であることを認識し、この原則を適用するための努力を行っていないとしている。さらにこの他の誘導策として投入財に対する課税などの経済的手法の導入が見られるとした。例えば、ノールウェーでは、1988年(昭和63年)に農業における環境改善施策の財源確保と肥料使用の削減を目的として人工肥料税を導入している。フィンランド、オランダ等においても同様の趣旨からこのような経済的手法を活用しており、肥料による環境負荷の低減に有効に機能している例がある。(第3-2-10表)
イ 排出権売買
排出権売買とは、個々の主体に定められた廃棄物の排出量等をあらかじめ割当て、その排出の権利の売買を許すものである。排出権売買にも様々なものがあり、例えば、米国では、1990年(平成2年)の大気清浄法の改正により、酸性雨の防止を目的とした排出許可量の売買制度が導入されている。これは、全米の発電所の各ユニットを対象に、二酸化硫黄の排出量を2000年(平成12年)までに1980年(昭和55年)の排出量に比べて1000万トン減の年間890万トンとすることを目標としている。各発電ユニットに配分される排出許可量は売買可能である。米国環境庁は、その実効性を高めるために排出量のモニタリングを行っており、割当てられた排出許可量を超えた場合には課徴金が課される。また、米国には、オゾン層破壊物質の製造と消費の低減を目的としたCFC、ハロンの製造権及び消費権に係る売買制度が見られる。製造権は、1986年(昭和61年)の製造量に基づいてこれらの製造者に付与され、消費権は、製造者及び輸入業者に割当てられている。(第3-2-11表)
ウ デポジット(預り金)制度
デポジット・リファンド制度とは、潜在的に環境への負荷を有する製品などにデポジット(預かり金)を課し、当該製品ないしその廃棄物が適切に返却されたことにより環境への負荷が回避された時に払い戻し金を支払う制度である。OECD諸国の例では、飲料容器の分野が多く見受けられ、その平均的な回収率は、概ね80%程度であるとされる。また、この他にも使捨て電池やプラスチック、農薬など様々な導入例がある。スウェーデンでは、1970年代前半より自動車の廃棄が目立つようになったため、その対策として制度整備が行われた。まず廃車証明委託制度を導入し、正規の廃車手続きをとるまで、「自動車税」の支払要求がくることとされた。次いで、「廃車課徴金」を利用したPantシステム(デポジット・システム)を採用し、これにより自動車の不法な廃棄を抑制している。これは購入者が新車購入時に基金に対して一定額を支払い、定められた手続きに従って廃車を行うとその際に基金から払い戻しが行われる仕組みである。払い戻しの額は、廃車に要する費用を上回るように設定され、制度の有効性を高めている。また、ギリシャの廃車に係るデポジット制度では、ECの排ガス基準を満たした新車を購入する場合に限り預かり金が払い戻される仕組みとなっている。(第3-2-12表)
エ 資金援助(補助金)等
環境基本法では、環境に対する負荷活動を行う者による公害防止のための施設の整備その他の自ら環境への負荷を低減するための措置に対し、経済的な助成を行うことを規定している。経済的な助成の意義としては、?各主体の環境対策への努力を効率的に引き出し得る?産業活動自体への影響が少ない?各国における個別対応が可能である等が指摘てきる。補助金は、資金援助によって対策実施の経済的インセンティブを与えるという意味で、負の税又は課徴金であると考えることもできる。このため、汚染の社会的費用の内部化にあたって、政策的な観点から補助金が適用されることがある。各国でも産業公害対策の促進策として利用されている事例が見られる。
我が国では、クリーンエネルギーの導入、省エネルギーの推進等のために様々な助成措置が講じられており、特に前通常国会では「エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律」及び「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」が成立し、助成措置が拡充されたところである。